

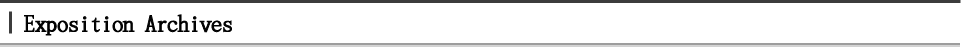











油彩画の様々な技法を訪ねるうちに戸嶋靖昌《アルバイシンの男―ミゲールの像》(1990年)には驚嘆させられた。スペインで戸嶋が実際出会ったことのある鴨居玲の画風への近似を想起させる方も多いかもしれない。筆者にはこの両者には根本的な違いがあるように思われてならない。単色の背景に人物が描かれている点では確かに共通している。しかしその違いといえば、鴨居は何事かを明らかに描き出そうとしているのである。人物の性格や表情を、鑑賞者の感情を喚起しつつ、濃厚にモデルの個性をこちらに押し出してくる。
これに対し戸嶋は、何も描くまいとしているように思えるのである。背景色はほぼ黒一色に塗りつぶされている。分厚いマントのような漆黒の、そして暖かな闇が、霧のような事物にまとわりつき、闇の向こうにモデルを引き戻し、呑み込んでしまおうとしている。人物に与えられたほんのわずかな光によって頭蓋骨から首、胸部へつらなる人体の体型を表現する技術は並みではない。しかし、技法に優れる戸嶋はこの人物の何ものも、あえて説明しようとはしていないようである。「ミゲール」という名前の男から、ほとんど全てが剥ぎ取られ惨たらしくも、そこにある(存在する)だけである。これは、いわゆる絵画でなく、反絵画(反表現)とでもいうべきかもしれない。ただの土塊、石塊があるだけである。そこに土塊、石塊があると信じる人のためだけにそれがある。美しくもなく、醜くもなく。ただそこにあることを示している。このような悲劇(宿命)をキャンバスの中で実現できようとは。まさにこの点において、驚いたわけであった。
モデルから人としての性格を剥ぎとってしまうというのは、あまりに不遜であろう。しかし、《黒と静物》ではどうか。同じように背後の闇に姿をくらませてしまおうとするその刹那、腐りつつ薫るカリンという果実たちが、この世と決別し、去りゆく最後の決別の姿を描いている。気になる戸嶋の言表が残されている。「カリンは、色気があり腐り方が素晴らしい」という。やはり、最後の姿に美を感じているのである。筆で描いたものか、布で拭き取ったのか、ナイフで押し付け剥ぎ取ったものか知らない。けれども事物からほぼ全てを奪い、捨て去り、それでもなお「ここに、まだ存在(あ)る」と主張する存在の実体のみが、戸嶋の写心機によってかろうじて映し出されているのである。この作品は恐らくは、どのようなフィルム感度であっても、拾い上げることのできない、存在の沼底の闇に、本当にわずかな光を放ち、あっという間に再び闇に消えてしまうような「炎」にも人体を描くに肉体を焼き、遺された魂だけを照らし出すような「炎」にも思われる。
 「武蔵府中 炎の油画家5人」展 チラシ
「武蔵府中 炎の油画家5人」展 チラシ 〈図録付属資料:戸嶋作品の一覧〉
〈図録付属資料:戸嶋作品の一覧〉