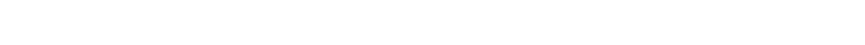
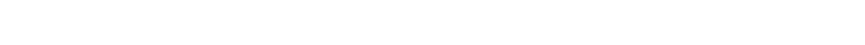
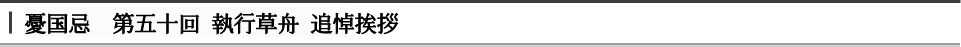
――(司会者)最初にご登壇いただきますのは、実業家であり思想家でもあられます、執行草舟先生です。先生は中学生時代から三島先生と激論を戦わせた貴重な経験をお持ちです。それでは、執行先生お願いいたします。
今、ご紹介に与りました執行草舟です。宜しくお願いいたします。僕は今、会社経営と、それから自分が後援している画家の記念館、それから色々な著作物を書いて、自分の事業と思想を世の中に広めようとしています。
今日、本当にこの没後五十年の「憂国忌」に招かれ、またこういう話す機会を与えられたことに対しては、もの凄く僕は誇りに感じています。僕のような者がこのような所で話すのは本当に場違いなんですが、そういう機会を与えて下さったので、少々自分の考えを述べたいと思います。
僕は、今七十歳なんですけれども、今日まで自分が生きて来るためにひとつの誇りをもって、その誇りだけで自分の人生を築き、思想を築いて来たと思っているのです。その誇りを与えてくれた方が三島由紀夫先生なんです。僕は小学生や中学生の頃から凄く文学とか哲学が好きで、本を読み漁っていたのです。そして丁度僕の両親が偶然三島先生と知り合いだったので、そういう関係で僕は十六歳の時に三島先生とお会いする機会を与えられました。僕はその時、三島先生の作品は全て読んでいましたので、それで自分の三島文学論というのですかね。そういうものをすでに持っていましたので、その場で三島先生にそれをぶつけて色々な話をさせて頂いたというか、特に文学論をさせてもらったのです。
それに対して三島先生というのは、中学生の最後から高校生一杯なんですけれども、短い時で三時間とか四時間、長い時で五、六時間、僕のようなまだ高校生を相手に本当に熱心に文学論をやって下さった。そういう恩義が今でも毎日、僕の誇りになっているのです。そういう時間を持てたということをですね。そういうことが今日こんにちを築いているということを感じているのです。
もちろん三島文学だけではなくて、僕はその当時、日本だと埴谷雄高とか高橋和巳、それから西洋文学だとドストエフスキーだとかロマン・ロラン、ヘルマン・ヘッセ。そういう色々な作家を自分なりには徹底的に研究していたわけです。それで文学の研究もあるのですけれども、それ以外に僕は小学生の時から武士道が好きで、特に『葉隠』という武士道の本が好きで、それを暗記するほどに何百回も読み込んでいたんですね。それで僕は少年のころから葉隠の精神で生き、そしてそれだけで死にたいと思って生きていたのです。だから自分なりには葉隠思想というものを中心に持っていましたので、すでに全ての文学を葉隠的な考え方で自分なりに読んでいたんですね。その葉隠的な思想で文学を読んでいると、一番その葉隠と共振する文学が、僕にとっては三島先生の文学とドストエフスキーの文学だったんです。その他だと埴谷雄高。埴谷雄高の『死霊』という文学がありますが、それがやはり大好きでいつも読んでいました。
先ほど言いましたように十六歳から十九歳まで、僕は三島先生と縁があって、それは丁度あの事件のちょっと前までの期間ですね。本当に十ヶ月くらい前まで縁があって、七回にわたって先生とお会いする機会をいただき、文学論をさせていただいていたわけです。その中で今日は没後五十年ということなので、それを記念して本当に先生と色々なことを話して、その話した内容自体が僕の全ての誇りの基本を作り上げているのですが、その中の一つだけを話したいと思います。
僕は三島文学の中でも特に好きなのが『美しい星』という文学なんです。この『美しい星』というのは、主人公たちが自分たちを宇宙人だと思って活動し生きる物語なのですけれども、そういう「宇宙人」に三島先生が自己のロマンと思想を仮託することによって、三島先生の本当の真心、それから思想の根源、そういうものが一番表われている作品だと思うのです。だから僕自身としては三島先生のこの作品が、三島文学の思想のすべての予言であり、それから人類への本当の遺言だと思っているのです。その当時の、青年の頃からそう思っていましたし、七十歳になった今日こんにちも思っています。もう五十年以上経過しましたが、その信念が揺らいだことは無いです。
こういう本なんですけれども、これは僕が持っている中の一冊なのですが、この本の主人公は大杉重一郎という人とその家族であり、自分たちを宇宙人だと思っているということなんですね。その人たちが、地球人たちに対して色々と考え方を言うわけです。その内容と質が僕は三島由紀夫先生の最大の遺言であり予言だということを先ほど言ったわけです。その人たち、大杉重一郎とその家族が最後に自分たちの理想とか夢とか、そういうものに向かって家族全員で突進して行く場面がある。実際には死に向かって突進するのですが、そこでこの作品は終わるんです。その最後の言葉が僕の全ての思想の根源を創り上げたということを申し上げたいんですね。
その言葉は『美しい星』の最後に出て来る言葉です。「人間の肉体でそこに到達できなくとも、どうしてそこへ到達できないはずがあろうか」。もう一度言います。「人間の肉体でそこに到達できなくとも、どうしてそこへ到達できないはずがあろうか」。こういう三島文学最大の思想で締めくくられている本が『美しい星』という作品なのです。これはどういうことかと言うと、読んで字のごとく、魂のために肉体を擲つ生き方こそが、我々人類の生き方なのだということを三島先生が言っているのだと僕は思うのです。
そういう三島文学の中枢の柱となる思想が、この『美しい星』の全体を支えていると感じます。全ての三島文学を貫いている思想だということですね。この思想を中心に僕は五十年以上にわたって自分自身の人生と自分の生き方、それから自分の色々なできることを積み重ねて来たのですね。そして自己の思想というものを築き上げて来ました。だから僕が築き上げたものは、もう三島文学の思想と、それから先ほども申し上げた武士道の葉隠と、これだけだと自分でも思っています。それ以外のものは何もないと自分でも思っているし、またそういう生き方を自分では誇りとしています。
この『美しい星』の文学論を三島先生にぶつけた日のことが思い出されるのです。それを言いたいと思います。先ほどの「人間の肉体でそこに到達できなくとも、どうしてそこへ到達できないはずがあろうか」という言葉を僕は三島先生に、三島文学の中枢じゃないかということで、高校生の時ですけども、ぶつけたんです。そうしたら三島先生が言われた言葉が本当に忘れられないんです。プライベートなことですが、ここで言うことを先生も許して下さると思います。先生はこういう風に言われたんですね。「魂のために命を投げ捨てることができる生き物こそが人間なんだ」と、こう先生は言われたんですね。続けて「私はそのことだけを自分の文学に書き残したいと思って生きてきた」。そのように先生がおっしゃったのです。この言葉自体が僕のその後の五十年の生き方を創った言葉だと思っています。
その日に先生と色々な『美しい星』の文学論をしていまして、それではこの世の中でそういう魂のために肉体を投げ捨てる生き方をどうやってやって行くのかという、そういう細かいことを話したんですね。その時に先生が「それはね、『美しい星』の中にも僕が書いているんだよ」。そういうことをおっしゃった。それでその個所を教えて頂いたんですが、その言葉が僕は三島先生の本当の生き方の中心じゃないかと思っているんですね。その言葉というのがですね、この文学の中にある言葉です。「愚かしさの中で、敗北の中で、苦痛の中で、みじめさの中で、聖性を夢みる」ことによって、それは成立するということが語られているのです。
聖性というのは「ひじり」という聖なるという意味です。自分の聖なる心というものについて、先生はそのようにおっしゃっていた。この本の中にある思想です。三島思想の中核だと僕は思っています。「愚かしさの中で、敗北の中で、苦痛の中で、みじめさの中で、聖性を夢みる」こと。それによって、憧れというか、自分の肉体を投げ捨ててでも到達したい憧れに行くことができるのだということを先生は高校生だった僕に言ったのです。それがもの凄く僕の魂の奥底に入っていまして、それ以降五十年以上ですけれども、それだけによって僕は全てのことを乗り超えることができたのです。凄く良く言えば、何と言いますか、この世の中で苦しかったこととか嫌なことが何も無かったのです、それ以降の五十年の生涯でね。つまり三島先生ほどの人がこういう思いで生き、そして自分の信念を貫いていたのだということに確信を持てたのです。
三島先生と比べれば僕なんかはまったく取るに足らない人間ですから、そんな人間が人生で色々な苦労をするとか嫌なことに遭遇するのは当たり前のことだと思えるようになったのです。自分では本当にそういう青春時代に三島先生から受けた恩を強く感じているんです。
このエピソードは、三島先生と七回行なった文学論の中の、僕が高校三年の時の最後になった文学論なんです。それから十ヶ月くらいしてあの事件が起こったのです。この最後の文学論は先生もやはり喜んで下さったと思うんです、内心は。それで二、三日後に電話がかかって来て、「君にあげたいものがあるのでちょっと会えないか」ということで、僕の家が目白だったもので、目白駅で会ったんです。それでその時に先生が先日の文学論の記念にということで、この「書」をくれたんですね。この「魂」という書なんです。これはレプリカです。本物は額に入れて飾ってあるんで。これはレプリカなんですけども、ほとんど同じです。この書は、それから五十年の僕の人生を支配し、今は僕が自分の信念で立てた会社と美術館、その社長室に額に入れて飾られています。この「魂」という三島先生の書がですね、僕の昨日も今日も支配しているんです。そういう素晴らしいものなので、今日は是非レプリカだけどお見せしたいと思って持って来ました。
この最後の文学論が終わりまして、十ヶ月後に先生のあの「事件」が起きたんです。僕は文学で先生といつも会っていて、政治向きのことというのはほとんど喋ったことが無かったので、本当に三島先生のあの事件は驚いたんですね。ただ僕は三島先生の政治向きのことをほとんど知らなかったので、却って何かあの事件の本質を一つ自分なりに摑んでいるように思うんです。それは、僕にとってあの事件というのはですね、やはり三島先生が最初のこの昭和三十七年に書いたこの本の中に書いてある、人類に対する「予言」、それから我々人類が何であるかということを知れという「遺言」ですね。そういう三島文学の思想の実現だと僕は取ったんです。政治のことを知らなかった分だけ、余計に僕は核心に迫っていると自分では思っています。
だから僕から見るとあの事件というのは、『美しい星』のロマンティシズムの地上的な実行、地上的実現なのです。この地上で先生が実現したひとつのロマンティシズムだと思っているんですね。僕はどうも政治だと思えない。ロマンティシズムだと見えるんです。それでロマンティシズムであるということは、三島先生の「文学」だということなのです。だから僕はあの事件そのものが「本」になっていない「三島文学」だと思っています。先生が最後に最大の文学作品としてあの行動を実行されたという風に僕は捉えているんですね。三島先生の魂が宇宙空間へ飛翔していくための、一番重要な儀式だったんじゃないかと僕は思っています。
僕は政治のことは知らなかったからこそ、だから全く違う角度から、三島先生のロマンティシズム、それから三島先生が抱えていた思想を三島先生が最後の作品として実行されたということを感じているのです。このことを没後五十周年を記念して皆様にお伝えできる機会を得られたことは、非常に幸運だったと思い喜んでいます。三島先生も喜んでくれているのではないかと思います。ありがとうございました。
――(司会者)執行草舟先生、ありがとうございました。