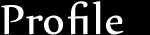
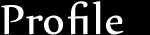
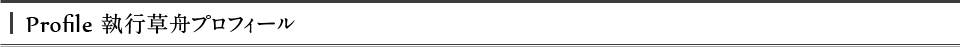
昭和25(1950)年、東京生まれ。立教大学法学部卒。実業家、著述家、歌人。生命の燃焼を軸とした生き方を実践・提唱している生命論研究者。
著書に人生論『生くる』、詩歌随想集『友よ』、哲学・思想エッセー『根源へ』(以上、講談社刊)、戸嶋靖昌の芸術作品とその生涯を紹介した決定版『孤高のリアリズム』、独自の芸術思想が語られた『憂国の芸術』、様々なテーマから「生命の燃焼」論を語り尽した『生命の理念』、若き現役医学生と文学・哲学・宗教・生命論等を真正面から語り合った対談本『夏日烈烈』(以上、講談社エディトリアル刊)、本のソムリエ・清水克衛氏との対談本『魂の燃焼へ』(イースト・プレス刊)、人間の老いについて語った共著『耆に学ぶ』(エイチエス刊)、「憧れ」への果てしない想いがこめられた渾身の一冊『「憧れ」の思想』、自身の波瀾に満ちた半生を語った『おゝポポイ!-その日々へ還らむ-』、臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師と禅と武士道の真髄を語った対談本『風の彼方へ ―禅と武士道の生き方―』、松下幸之助の思想と人間的経営の核心に迫る『悲願へ ―松下幸之助と現代―』、PHP研究所内で一年以上に亘って行なわれた講演会をもとにした816頁に及ぶ一大著作『現代の考察―ただ独りで生きる―』(以上、PHP研究所刊)、また『見よ銀幕に―草舟推奨映画―』(戸嶋靖昌記念館刊)がある。日本菌学会終身会員。
◆ 出版活動を詳しく知りたい方はこちら
◆ 事業活動を詳しく知りたい方はこちら
◆ プロフィールを詳しく知りたい方はこちら
◆ 草舟思想を導き出した根源公理、葉隠十戒はこちら
また独自の美術事業を展開しており、執行草舟コレクションを主宰、戸嶋靖昌記念館 館長を務める。草舟の蒐集する美術品には、安田靫彦、白隠、東郷平八郎、南天棒、山口長男、平野遼等がある。魂の画家・戸嶋靖昌とは深い親交を結び、画伯亡きあと全作品を譲り受け、戸嶋靖昌の遺志を継いで記念館を設立した。その画業を保存・顕彰し、千代田区麹町の展示室で公開している。

「夢の草舟」
油彩 戸嶋靖昌 2003年
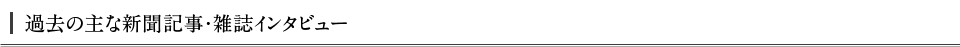
表題にも掲げられるこの書物の著者、マリアーノ・ホセ・デ・ラーラとは何者か。
例えば学生時代にでも、スペイン文学やスペイン史にいくらか触れる機会があれば、ロマン主義の台頭する19世紀初頭に活躍した反骨のジャーナリストとして、ラーラの名前をきっと見聞きしただろう。だが知ることができるその仕事は、文学史や文化事典などのレファレンスが伝えることくらいで、それ以上の事情に通じようとすれば原著をひもとかねばならなかった。
この『ラーラ―愛と死の狭間に』の刊行は、批評記事だけではなく戯曲や詩を手がけ、政治の世界にも足を踏み入れた多才な文筆家が培ったものだが、スペイン近代における批評精神の芽生えを直接にのぞき見ることを日本の読者にも可能にしてくれた。巷間にはびこる蒙昧をいましめ時代錯誤の迷信をいさめることで、ブルボン朝へと移行した18世紀にフランスから伝わった啓蒙主義思想を、次の世紀の終盤にスペイン的なものの本質を国家の危機に直面して問うた《98年の世代》の哲学的な思索へとつないだ才物の全貌を、一冊の書巻で明らかにしようという意欲的な作物である。
1808年、皇帝ナポレオンがイベリア半島の隣国に侵攻して実兄を治者としたのに対してマドリード市民が反乱を起こした様子は、不世出の画家ゴヤが残した2枚の絵がよく伝えている。ラーラはその独立戦争勃発に続く短い時間―28年にわずかに及ばない―を苛烈に生きた。本書の第一部では、文学史家アルボルグがラーラの業績をつまびらかにしていく。親仏派の父に連れられての亡命、不幸な結婚生活、政治上の挫折などそれはそれで興味深い伝記をまずは簡略にたどり、その後、100ページを超える紙幅を割いて、自由を求めてさまざまなジャンルの文章を綴りつづけた孤高の作家の活動を丁寧に振り返っている。
ラーラの著述の中心をなすのは、初期には「いたずら好きの小悪魔」の意を持つ《ドゥエンデ》の、そして後にはボーマルシェの戯曲に由来する《フィガロ》の筆名を用いて「エル・エスパニョール」紙などの新聞に寄せられた記事である。横行する厳しい検閲にもかかわらず世相をよく写して社会の諸相を鋭くえぐり出すそうした玉稿は、すでに生前に書き手自らの手でまとめられて当時から高評を得ていた。劇評や文芸評、あるいは政治的な論説とテーマが多岐にわたるなかで、ことに風俗写生の趣の強い記事がスペイン思想史に与えた影響の大きさは特筆に値する。
スペイン語でコストゥムブリスモと呼ばれる《風俗写生》は一般に土地の慣習や風景を描き出すことを目的とするが、習俗の単なる描写を超えて地代と社会を記録する重要な行為だと捉えたラーラは、考察に普遍的な価値を与えることでこの時代に流行した同種のものとは一線を画することに成功している。本書には「カフェ」や「古き良きスペイン人」のような代表的な記事の数々が載るが、一編ごとに役者の安倍三﨑氏が解説を付している。そこでも指摘されているようにラーラの筆は、社交や食事の場の情景を提供して《ピレネーを超えた向こう側》であるスペインの往時の様子をわたしたちに垣間見せてくれるだけでなく、時に人々の習性を明るみにさらし、意識の深層に根付く悪癖を巧みに暴きだしている。
このようなジャーナリストとしての資質だけでも興味深いが、併せて収められた戯曲『マシーアス』は、ラーラのもう一つの顔を浮き彫りにしている。つまり、ロマン主義者としてのそれである。
人妻ドロレスとの恋愛に破れてピストルによる自死を遂げるという自身の悲劇的な最期こそがラーラを、スペインでは比較的に遅れて流行したこの芸術思潮の最大の体現者であったように見せている。しかし、彼のロマン主義者としての資質は、ローペやカルデロンらの古典演劇が重視した名誉や信仰よりもひとりの女性への愛をひたすら行動原理として動く主人公の姿を通して鮮明になる。確かにラーラの評価は、時として厭世的な気分に支配される同時代の社会に向けた風刺記事があってこそのものだ。けれども、『マシーアス』の基調となっている激しい愛の感情もまた、二世紀近い時間を経てなおもわたしたちがラーラの作品を読むべきもう一つの大切な理由にしている。
本書はまぎれもなく、あとがきでその恩恵が語られる佐々木孝氏をはじめとする先達の研究者たちが尽くしてきたスペイン哲学の紹介の系譜に連なるものである。そのことは執行草舟氏が巻頭に寄せた短い、しかし熱のこもった序文からも明らかだ。ラーラという近代社会が生んだ風刺の異才に触れられるばかりでなく、そこからやがてウナムーノらへと至るスペインの近代思想の変遷を汲むこともできる。そのような資料としての価値がきわめて高い労作だと言えよう。(関西大学外国語学部教授)
×神が想像し給うたといわれている森羅万象の中で、最も偉大な被造物は「人間」だと思っていた。
太古の昔からすぐれた精神文化を創り、その土台の上に文明を開化させた生き物は、我々ホモ・サピエンス以外にいない。人間が「万物の霊長」といわれる所以である。
しかし、その考えを改めなければならないような話を聞いた。
その「偉大な」とか「万物の霊長」といわれている人間を存在たらしめ、その生命を支配している生物がいる。
それこそが神が想像し給うた、一番偉大な被造物なのではないか。そういう考えに至った。
その生物とは、すなわち「菌」である。
㈱日本菌学研究所の社長で、文筆家の執行草舟さんは言う。
「菌とは宇宙的存在であり、地球上の生物はすべて菌に支配されている。菌こそが地球の主人公であり、主流である」(YouTube執行草舟チャンネル「菌のはたらき」より)
つまり、植物や動物、延いては人間の生命の根源を菌が支えているというより、菌が生きていくために動植物をはじめ、すべての自然界の生命がそれぞれの役割をもって存在し、繁殖しているというのだ。
人間は、自分で自分のことを「万物の霊長」と豪語しているが、考えてみればそれは人間中心の見方であることは否めない。生物学的に大先輩である菌に対して、人間は自分たちに有益なものを「善玉菌」と呼んで重宝し、有害なものを「悪玉菌」と名付けて悪モノのように思っている。
確かに悪玉菌は、腸内で分解されたんぱく質を腐敗させて発がん物質や有害物質を作り出すという働きをする。しかしその悪玉菌もある一定数「いなければならない」存在だというのが、今の生物学の常識だ。
腸内の悪玉菌は、腸内で分解されたたんぱく質を腐敗させて発がん物質や有害物質を作り出すという働きをする。しかしその悪玉菌もある一定数「いなければならない」存在だというのが、今の生物学の常識だ。
腸内の善玉菌と悪玉菌の理想的な割合は2対1で、善玉菌が全体の20%、悪玉菌は10%、そのどちらでもない日和見菌が70%。
このバランスが崩れ、たとえば悪玉菌がいなくなってしまうと、善玉菌が全く働かなくなってしまう。すると食べ物の消化・吸収力が激減し、健康維持に必要な栄養分が吸収できないなどの不具合が生じる。
言ってみれば、悪玉菌がいてこそ、善玉菌が正しく働き、我々の健康を維持している。
執行さんは言う。
「要はバランスなんだ。悪玉菌が多過ぎると病気になるし、少なすぎると体調を崩す。ちょうどよくバランスが取れている状態を健康というんだ」
「数十年前から『抗菌』という名のもとに抗菌グッズが売れに売れ、ばい菌を生活の中から排除している。抗菌思想は人類滅亡の考え方だ。これがコロナ禍でさらに加速した」
腸内菌のバランスが取れていないのが赤ん坊である。生まれたばかりの赤ん坊の腸内環境は100%善玉菌の状態だ。しかし、ばい菌だらけのこの地球に生まれた以上、ばい菌に対する免疫力がないと生きていけない。
だからスキンシップなどを通して、家族みんなからばい菌を貰い、免疫力を獲得する。その過程で何度も病気になり、小児科への駆け込みを繰り返す。それは乳児期の宿命である。
また、赤ん坊の体は結核菌もゼロなので、生後6か月以降にBCGワクチンをハンコ注射して、わざわざ結核菌を摂取させる。そのことで結核菌に対する免疫力をつける。
ここから執行さんの話はさらに一歩進んで「心にも毒が必要だ」という話題に及ぶ。
たとえば、現代人が感じるストレスの大半は、自分の思い通りにならないことに対する精神の免疫力の低さに由来する。だから、肉体にばい菌のような毒が必要なように、精神的な毒も同じ理由で必要なのだ。
「その毒は昔、家庭の中にたくさんあった」と執行さんは言う。怖い親父とか厳しい祖母とか。自分の思い通りにならないなんて当たり前だった。嫌なことは大概我慢するしかなかった。
そうやって大人になると、自分と合わない人や自分を嫌う人がいて当たり前だと思えるし、そんなことでいちいちイライラしない。
クオリティの高い人生に「嫌なこと」という毒は必要悪なのだ。突然降ってくることもあるし、毒が足りなかったら誰もやりたがらない「役」を引き受けてでも経験するのがいい。
何事もバランスである。
×令和五年(2023)1月30日(月曜日)通巻第7611号<前日発行>
☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆
書評 しょひょう BOOKREVIEW 書評 BOOKREVIEW
はじめに言葉ありき、魂が言葉を求めた
そして言葉が氏の魂、武士道の信念を一層強くした
執行草舟『人生のロゴス 私を創った言葉たち』(東洋経済新報社)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
著者の執行草舟氏は現代日本人が顧みない武士道(それも『葉隠』)に生きる思想家であり、美術コレクターであり、たぐいまれな批評家である。
氏は実業家でもあるが、最近の連続的著作に惹かれ、氏の謦咳に接しようと、全国から講演会に人が集まる。爆発的な熱情をもって氏は武士道を語るからだ。
その氏が六十年以上にわたる思索の過程において、呻吟し、慟哭し続けた言葉があった。葉隠武士道に通じる魂の感動があった。
まだ高校生の頃に三島由紀夫に哲学的な質問をぶつけた早熟な青年だった。別荘が近く、毎年、氏は三島と顔合わせをした。
本書に引用される箴言の数々は思想家、哲学者から小説家、禅師、宗教家と古今東西を問わず、また左右のイデオロギーを超越している点が、じつに、じつに独創的独特的思考の産物である。
小林秀雄、三浦義一、亀井勝一郎、川端康成、中河与一、福田恆存、三島由紀夫、竹本忠雄から箴言の引用と解説は、この人脈が伝統を尊ぶ保守系の人々ゆえ、おのずと了解できるが、他方で安部公房、高橋和巳、丸山真男、サルトル、堀田善衛、吉本隆明が並ぶのである。人生論、愛情を論じ、情熱を沸かせ魂をかき立てた箴言に、執行氏は左右を超えて感動し、そのひとつひとつに何故、感動し、いかに解釈したかを触れてゆく。
いくつかの例を拾う。
早熟の天才作家ランボーは「我々は聖霊に向かって行くのだ」という言葉を残した。ランボーといえば、わかき日の三島由紀夫が憧れた。
執行氏は「武士道の不合理に哭き、その矛盾と格闘してきた」ので、「無頼にはあこがれがある。不良には不良の名誉というものがあるのだ。それが、ランボーの「聖霊と溶け合っている。私はランボーによって、武士道の中に聖霊を見いだすことが出来るようになった」(中略)「その聖霊と出会った頃から現世には興味が無くなった。現世を作り上げた何者かと向かい合いたいと思った」(38p)
アンドレ・ジードが言った。
「人間は幸福になるためにうまれてきたのではない」。
執行氏。「私の青春は、恋の苦悩とともに始まり、その悲痛とともに去った」。
ジードの『狭き門』は「私の人生に一つの革命をもたらすものだった」。すなわち「純愛のもつ高貴性がそれを乗り越えて到達する生命の実存」であり、『葉隠』がいう「忍ぶ恋」とは何かを掴んだのだと言う。中河与一の『天の夕顔』も同様な主題である。
ドストエフスキーは「どんなでたらめをやっても、心さえ歪んでいなければ、最後には必ず正しい満ちに到達する」
執行氏はこの「言葉に因って、自己の命をすくわれ」、そして「無限の荒野に向かう勇気を得たのである」(85p)
トルストイは『復活』のなかで言う。
「春は、やっぱり春であった」
執行氏は「どうにもならぬ人間の性(さが)の中に、私は人間の愛おしさを感じていた」。そして「否定の真っ只中に、真の希望をみだすことだけが自己を立てることだと感じていたのだ」(104p)
福田恆存は『人間、この劇的なるもの』のなかで、「私たちが欲しているのは、自己の自由ではない。自己の宿命である」
執行氏はこの言葉を座右の銘として、初読の中学一年のときに「深い喜びを感じた」のだが、六十年後に「深い悲しみを見るのだ。ただただ涙が滲む」。なぜなら「私は現代が最も失った考え方が、この言葉にあると思う。そして自分たちの生命がもっと必要とする思想が、やはりこの言葉の中にあると考えるのである」(207p)
航海王エンリケ王子の碑銘には「航海をすることが必要なのだ。生きるとは必要ではない」
ヘミングウェイは『老人と海』で老漁師を描いた。「彼は決意にみなぎっていたが、殆ど希望は持っていなかった」
執行氏はこのような箴言に感動し、人生を武士道を基軸に航海してきた。
さて評者、この本を読みながら、しきりと対極にあると想定される藤原道長の人生を考えていた。
平安時代は武士道の影も形もない、光と闇のなかで宮廷人は和歌を詠んだ。道長は「この世をば我が世とぞ思う望月の 欠けたることもなしとおもへば」という傲慢な和歌で知られる。
現世では天皇の側近として権力状況を醸成しつつ、その権力を巧妙に行使して絶頂を極めた政治家ながら、同時に若き日から執拗な出家願望があり、極楽浄土の実現を目指して壮大な伽藍の法成寺を建立し、写経に熱中して金峯山寺に埋経した。最後には阿弥陀党で死んだ。彼の人生は、ここに挙げた箴言とはまったく無縁に見えて、じつは近似があることに気がついて、評者は愕然となったのである。
(付記)執行草舟公式YouTubeチャンネルがあります。
公式チャンネル:https://youtu.be/d7TXh6FNQIY
「二十一世紀は霊性の時代となるであろう。さもなくば二十一世紀は存在しないであろう」。このように、あの文豪アンドレ・マルローが語ったと、竹本忠雄はその『マルローとの対話』の中で伝えている。文豪にして美と行動の巨人、そして何よりも魂の形而上学を現代人に愬え続けた人物の言葉である。私はこの思想を、自己の信ずる『葉隠』の武士道に取り込みながら、考え続けて生きて来た。その煩悶と葛藤が、私に人間の未来を指し示してくれている。
二十世紀において、すでに神を失ってしまった我々現代人は、自らの魂に宿る「霊性」を発動させなければならないのだ。それ以外に、多分、我々がこの地上で生き延びる道はないだろう。我々の未来は、我々自身のもつ霊性の発現にかかっている。その霊性を引き寄せるのに一番大切な事柄は何か。私はそれを考え続けているのだ。「聖性」こそがそれだと、私は年を経るごとに確信を深めて来た。聖なるものを仰ぎ見る。その我々の純心を取り戻さなければならない。
我々が現代文明の中において、最も激しく失ったものが聖性なのではないか。聖なるものとは、我々の心の奥深くに潜む人間存在の真実である。人間が人間として生きる、その存在理由ですらあるだろう。聖なるものを仰ぎ見る生き方。そして、その下に死する生涯。我々は、そのような信念を取り戻さなければならないのだ。まさに霊性とは、聖性を仰ぐ生き方を取り戻した人間の心の性と言えよう。
我々人類は、何を聖なるものと感じていたのか。私の歴史探求は、その一点に尽きるだろう。私は自分なりに、それを摑んだと思えるときがあった。それは自己の命の深淵に触れるときだった。自己を生かす「何ものか」に畏れおののいた日だった。その恐怖によって、自分なりに美しく気高いと思うものを摑み取ったのだ。真の「崇高」を感ずる心である。大いなるものを畏れる心とも言える。神ではない。宇宙と生命を貫く、恐ろしい深淵のエネルギーに違いない。
それを神と感ずる時代があったことは間違いない。しかし、それは現代においては決して神ではないのだ。神なら、我々はそれを自己都合にしか使わないだろう。我々はすでに神を失っている。そうではなく、我々の心が純粋に畏れを抱くもの。それが崇高なのだ。美しいだけではない。立派でもない。正義ですらない。それらすべてを超越する「力」である、仰ぎ見ることしか出来ない力。神としか呼べなかった力。その力こそが、我々の心に聖性を呼び戻す。
G・K・チェスタートンは、その力によってヨーロッパの中世文化が生まれたのだと『英国小史』の中で言っていた。そしてそれをMystical materialism(神秘的物質主義)と名付けた。この思想の中に、崇高を仰ぎ見る生き方の秘密がある。中世人は、神秘と物質の融合に成功していた。その力によって、気高い崇高な人類文明を築き上げたのだ。ノートル・ダム、シャルトル、アミアン等の大聖堂が、そのゆえに聳立った。現在に至る、偉大なヨーロッパの魂と文化が、この地上に出現したのである。
ヨーロッパの価値は、現代でもそれらの上にしか成り立っていない。そして今でも、科学文明に汚染され切った我々現代人は、それらの建造物が人間の真心と神秘の上に成立した真の物質文明だということに気付いていない。中世の大伽藍と修道院のすべてが、聖性を仰ぎ見る神秘によって出来上がったことを忘れてしまった。それらの「偉大さ」はすべて、聖人の骨片や聖遺物の片らの上に建った。人間の畏れと崇高を仰ぐ純心がこの文明を推進したのだ。その力を我々も取り戻さなければならない。
このような、神秘と物質の融合による「霊性文明」の奇蹟の力は、日本の中世においても同じだった。平安の延喜式に示された二千八百の聖域に立つ社は、中世の六百年を経て八万八千に増えた。神社の建立が、日本の根源的文化を支えていたことは誰もが知るところだ。それらは、伝説上の「聖なるもの」、そして歴史に名を刻む偉大な人物の遺物の上に成り立っているのだ。聖なるものが、一国の文明を築き上げた。それも大宇宙と大自然を包み込む真の人間の文明を、である。
聖なるものを取り戻さなければならない。そして、その上に物質の文明を築くのだ。そうでなければ、我々人類の未来はない。聖なるものが、我々に真の「霊性文明」を指し示してくれるだろう。我々は中世において、限り無く霊性文明に近づいた。そのとき、我々の祖先が自分の命よりも大切にしていたものは、現代人から見れば「ガラクタ」だった。しかし、その中に崇高を見ていたのだ。その純心を取り戻す。
人間の影と涙の価値を、我々の祖先は崇高なものとして認識していた。三島由紀夫は、その『美しい星』において、聖性についてこう書いている。「愚かしさの中で、敗北のなかで、苦痛のなかで、みじめさの中で、聖性を夢みていた」そう聖性について語ったのだ。これらに含まれる価値は、現代の我々が失ってしまった価値である。我々にとっては、不幸とガラクタは何の価値もない。人間の影と涙の真の価値を取り戻す。実は現代の我々にとって、最も価値のないものが、最も聖性に近いものなのだ。
その聖性の力によって、我々は新しい文明を築かなければならない。そうしなければ、本当に人類の未来は空しく寂しいものとなってしまうだろう。
執行 草舟 記
×令和四年七月八日、我々は日本を支え続けた清らかな「良識」を喪った。言うまでもなく、元総理・安倍晋三のことである。私もまた、多くの日本人と共に、この喪失感に苛まれる日々を送っている。いま日本は、ひとつの歴史的運命の転換点に来たと私は考えている。安倍元総理の政治的業績について、私は口を挟む立場にはない。ただ、その政権の日々に、我々国民の一人ひとりに向けられた無垢としか言いようのない、その笑顔の印象が忘れられないのだ。その笑顔は、安倍元総理の「人間生命」の全体から醸し出される真実だった。その笑顔が、強く私の脳裏に焼き付けられている。美しい笑顔は、人間的品格からのみ生み出される。だから、そこから出発した政治思想は、美しいものに決まっているのだ。政治とは所詮、人間が行なうものだからだ。いかなる政策も、人間が行なっている。私はあの人間的温かさを湛えた美しい笑顔の「原点」を信じている。その原点は、歴史的な「正統」が創り上げているものに違いない。
安倍元総理は、その正統を担い続けて来た人物だと思っている。だから、いかなる時も「洗練」の姿勢を失わなかった。いかなる時にも、日本の「中心軸」を失わなかった。そして、日本人が日本人らしく生きることだけを願い続けていたのだろう。そういう当たり前のことが、正統の持つ真の力なのだ。いまはただ、日本の正統のために殉じた、その生命の尊さを偲びたい。その魂の誠を仰ぎたい。
令和四年七月二十六日 執行 草舟 記
×人間は死者を慕い敬うその心によって真の人間と成る。「恩」を担うことで人は自己を築き上げることができるのだ。恩が人間を創り、民族を育て上げてきた。その意味で靖國神社は恩の生命的系譜といえるだろう――
春たけなわの靖國を凌ぐものが、この世にあるだろうか。いま私は、その靖國神社に佇んでいるのだ。いつものように、深い生命の安らぎが私を包み込んでくれる。その力は、遠い過去から来る時間の堆積がもたらす「何ものか」である。過去の日本人の涙と躍動が、私の周囲を埋め尽くしている。この靖國に鎮もれる祖先の魂こそが、私に自己の生命の本源を分からせてくれるのだ。私は民族の魂に抱かれ、いま死者との交感を始めようとしている。
この国に生まれ、この国を愛し、そしてこの国で死んだすべての人々を私は祖霊だと思っている。その中でも特に、国を守るために戦って死んだ人々の霊魂ほど、我々の生きる力を鼓舞してくれるものはない。現代に生きる我々は、死者の存在に支えられている。そして、死者と共に生きる時、我々は本当の生命を生きることが出来る。我々は現代を考えるに当たって、常にすべての死者と共に考え続けなければならないのだ。
我々の生は、死者と交わらなければ燃えることはない。それと同じで、現代の問題は、歴史を繙かなければ分かるわけがないのだ。繙くとは、我々の魂を過去に参入せしめることに他ならない。歴史は、戦争と平和の弁証法的展開である。善悪を超越した、人間の涙そのものと言えよう。平和の価値は、戦争の悲惨を受け止めた魂にしか宿らない。つまり、死者と共に生きる魂にしか感応しないのだ。現世だけに生きる者は、平和の氾濫に押し流されて終わるだろう。
元々、我々人間が真の人間と成ったのは、死者を慕い敬うその心によって成された。その心こそが、現世を生きる自己の運命に愛の力を与え続けてくれているのだ。死者を慕うことが文化を育て、英霊を敬うことが平和の真の力を養ってきた。それを忘れた時、我々は人間として終わり、民族として崩壊していくだろう。死滅した過去から降り注ぐ力によって、我々は初めて生命の本源たる「恩」というものに覚醒めることが出来る。
靖國には、それを思い起こさせる力がある。そこに靖國の生命があるのだろう。死者たちの働きの上に、いまの文明と生活が存在しているのだ。我々が真の人間と成った時から、我々の生命は自己以外の「何ものか」に捧げるためにある。それが人間生命の価値を創り出してきた。真の生き甲斐とは、自己の生命が敬い慕うもののために燃え尽きることである。その生命がもつ真の夢を、昔の人たちは恩と呼んだ。恩の堆積が、民族を愛し、国を敬い、親を慕う文明を築き上げたのだ。
恩を現代に打ち込む社こそが靖國神社である。それが靖國の原点だ。我々日本人は、祖国と他者のために死んだすべての人々に恩を感じなければならない。そうしなければ、現世の何ものにも本当の恩を感じることが出来ないのだ。しかし我々の祖先は、恩について何も言挙げをしていない。我々はそういう民族なのだ。だから私は、日本的霊性を深くもつフランスの哲学者ポール・ヴァレリーの思想をもって、恩について語りたい。
ヴァレリーは、自己の本質について「私の担う、私自身にも未知なるもの、それが私を創っているのだ」とその『ムッシュー・テスト』の中で言っている。私はこの言葉に触れた時、骨髄の中に電撃が走るのを感じた。私の中で、過去に存する恩こそが、自分自身の運命を創っているのだと直感できたのである。恩は担うものだ。だから、それは自分を鍛えるものと成り得る。恩に生きれば、未知へ向かう人生となる。だからこそ、その断行には不断の勇気を必要とするのだろう。
重荷と勇気が、自己を築き上げる。その重荷と、未知なる人生へ向かう勇気だけが、自分の運命を創っていく。つまり自己固有の人生とは、恩の認識とその実行に他ならないと言える。過去の重荷と、未知なる人生を抱き締めるとき、我々の生命の奥底に恩が生まれ出づる。自己に最も近い恩の現前が親なのだ。親への恩は、そのまま国と民族に広がっていくだろう。恩に生きる者だけが、自己の本質と交わり、民族の淵源を担うことに成っていく。
この恩という運命に、真正面から対峙した人々が「英霊」と成っている。自己の本質から逃げずに、それに立ち向かった人たちである。我々が死者や英霊と交わるとは、その運命を承け継ぐことと言える。その継承の中に、民族を打ち立ててきた恩の思想が鎮もれているのだ。靖國に鎮もれる「恩の霊魂」を仰ぎ見ることが、自己の運命を生き切ることに繋がって来る。そして我々の死が、新しい恩をこの世に伝えるだろう。
靖國の存在意義は、恩の生命的系譜にある。まさに靖國とは、恩の牙城なのだ。恩が人間を創り、民族を育て上げてきた。恩が人間生命の淵源を支えている。我々死すべき者の心の故郷は、遠くにはない。それは間近にあるのだ。我々の故郷は、親の中にあり、国の中にあり、また民族の哀歓の中にこそある。靖國の歴史は、人間の運命としての恩を祈り続けている。それこそが、永遠を仰ぎ見ることに繋がっていくのだ。
令和四年五月三十日 執行 草舟 記
×令和五年(2023)7月19日(水曜日)通巻第7826号
☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆⌒☆
書評 しょひょう BOOKREVIEW 書評 BOOKREVIEW
生命が大事で魂は死んでも良いのか」。三島由紀夫は檄文で叫んだ
歴史とは民族の魂を謳う詩である
執行草舟『草舟言行録2 人間の運命』(実業の日本社)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
葉隠的な運命論の決定版である。「武士とは死ぬることと見つけたり」とは人生における運命の悟りであって、切腹のすすめではない。戦後は葉隠をあまりにも短絡的に解釈しすぎた。
つねに執行氏の口をついて出てくるのは「葉隠」と「忍ぶ恋」であり、三島由紀夫の『美しき星』であり、そしてドンキホーテ、ヤマトタケル、神武天皇、聖徳太子と定番が続くのだが、しかも内容は前作を殆ど変わらないことを唱えているにも拘わらず、新作ごとに感動するのはなぜなのか?
機械には喜怒哀楽がない。涙を流すことがない。しかし魂は人の心を揺さぶる。文学は天地(あまつち)を動かすと藤原定家が言った。
AIの時代、鉄腕アトムの夢の世界がまもなく現実になろうとしている時代にこそ「精神世界」の深さを考察するべきではないか。つまりAI時代にこそ思想と哲学は発展しなければならない。
でないと、本当に人類は滅亡へ向かうしかない。
昭和四十九年に小林秀雄は国民文化研究会が毎年有為の学生や若者を集めての合宿勉強会に講演におもむき、「信じることと知ること」と題して次のように言われた。
「僕らがいきてゆくための智恵というものは、どれだけ進歩していますか。たとえば論語以上の知性が現代人にありますか。これは疑問です。僕らの行動の上における、実生活上の便利さは科学が人間の精神を非常に狭い道に、抽象的な道に導いたおかげだと言えるでしょう。そういうことを諸君はいつも気をつけていなければいけないのです(『国民同胞』、令和五年七月十日号から重引)。
AIが人間の知恵を越えると、人類はAIロボットに従う奴隷になるのだ。
執行氏はこう説かれる。
ルネッサンス以後、「ヒューマニズムが始まってから、人間は確実に神から離れ始めた。それでも神から離れる葛藤があった。この葛藤は、十九世紀までつづきます。また、その葛藤がヨーロッパ人の偉大な文明を生み出す原動力になりました。」
「これは神から離れようとするヒューマニズムと、それをまだ全面的には受け入れられない思想の壮絶な衝突のエネルギーなのです。つまり呻吟です。だから良いとか悪いとかではない。呻吟して行くことこそが、本来的な人間を生み出すことになる」
AIには精神の呻吟が出来ない。
この思想状況に英国の詩人ジョ・ンダンが言い放つ。
「死よ、おまえは死ぬのだ」!
則ち『死というものは神がいなければ出来ない。人間の死は神と繋がっている。宇宙と一体化する死が人間の死である』。しかしヒューマニズムが発展し、人間が神から離れたがゆえに「人間の死というものが死ぬのだ」
そして二十一世紀。生命は地球より重くなって、防衛方針も「国民の生命と財産を守る」だけとなった。防衛白書のどこにも「わが国の伝統・文化、そして日本の精神を守る」とは書かれていない。生命が大事で魂は死んでも良いのかと三島由紀夫は最後の檄文で叫んだのだが、そのことさえ現代人は気にも留めていない。
だから執行氏は次の慨嘆の言葉を続ける。
「ただ肉体が朽ちただけの動物の死です。多くの死が人間の死ではなくなってしまった」、 「葉隠の精神とは「死ぬ日まで体当たりをして未完で挫折して死ねばよい」。それが『生命燃焼』であると執行氏は力説する。
真の道徳とは『魂の永久革命だ』とする氏はこうも言われる。
自己の運命に内在する美しさは各民族ともそれぞれに歴史上の共感する人物の魂にこそ見いだせる」
「だから歴史は詩」である。
一行一行の言葉に活力と真実と詩がある。
×ロシアがウクライナへの侵攻を開始する1週間前、AFP(フランス通信社)が2月17日に配信したあるニュースに心が少し揺さぶられた。
ウクライナ南東部マリウポリ近郊の村チェルボネで、ペンテコステ派教会の牧師が運営する施設で暮らす、問題ある家庭出身のおよそ40人の少年たちが塹壕を掘り始めたというのだ。そのひとり15歳のミハイロ・アノパさんは誇らしげにこう語ったという。
「ロシアが攻撃してくるかもしれないと牧師から聞き、悪夢を見るようになった。今はウクライナ兵を助けるために塹壕を掘っている。僕たちの使命になった」そんな少年たちを見て、牧師は「ただ心の奥には強い恐怖が宿っている。少年たちは生きてきた大半の時間を兵士の背中を見て過ごしてきた。そして窓の外に広がっているのは前線なのだ」と話す。
戦い方にもいろいろある。少年たちは悪夢を振り払うかのように、誇りを胸に自分の持ち場で戦っている。まぶしく感じた。いざというときに、戦う覚悟のない国家や個人に、神が与えるのは「隷従」だけだ。ひるがえって、平和憲法と日米安全保障条約の下に、自ら戦うことを想像することもなく過ごしてきた私たち日本人はどうか。同じような状況に遭遇したとき、少年たちのように塹壕を掘ることが果たしてできるのだろうか。
周知のこととは思うが、塹壕とは敵の銃砲撃から身を守るために陣地の周りに掘る溝のことだ。リアルに知りたければ、1999年に制作された英国映画「ザ・トレンチ 塹壕」(ウィリアム・ボイド監督)を見るがよい。第一次世界大戦最大の会戦といわれる「ソンムの戦い」の塹壕戦を描いた作品で、極限状況に置かれた若い兵士たちの緊張と不安と絶望の入り交じった感情が、残酷なまで冷徹に描き出されている。
このニュースが配信されてから1カ月が経過した。少年たちの暮らすウクライナ南東部はロシアに制圧されてしまった。アノパさんたちの無事を心から祈る。
一夜でおよそ10万人もの非戦闘員が殺戮された東京大空襲から77年の3月10日、靖国神社を参拝し、次いで境内にある靖国会館に足を運んだ。「戦う僕ら小国民」顕彰鎮魂祭に出席して玉串をささげるためだ。斎主は、フランスのドゴール政権下で長く文化相を務めた作家のアンドレ・マルローの研究で知られる仏文学者・評論家の竹本忠雄さんである。竹本さんは国民学校6年生のときに、下町の深川で大空襲を経験し、多くの級友を失っている。
昨年のこと、戦後の日本を憂い自刃した作家、三島由紀夫を追悼する憂国忌(11月25日)の集いで、思索家・実業家の執行草舟さんと初めて顔を合わせた竹本さんはこう語りかけた。
「私と友人たちは、みな子供でしたが、兵隊さんと一緒に戦っていたのです。だからこそ、あらゆる困苦に耐えることができた。私たちは犠牲者ではありません」
この言葉に魂を震わせた執行さんは、発起人代表となって、顕彰鎮魂祭の実現に奔走してこの日を迎えたのだ。
大東亜戦争末期、「一億総玉砕」が叫ばれ、学校の校庭で女子生徒たちはたすき掛けで一斉に薙刀(なぎなた)を振るい、男子生徒たちは竹やりを手に「鬼畜米英」に見立てたわら人形に突撃する。「後の世から見れば、狂気の沙汰に違いありません」と竹本さんはいう。だが、小国民は幼いからこそ、より純粋に日本の勝利を信じ、戦地の兵士と一体となって銃後で懸命に戦い、困苦欠乏に耐えていた。
「かわいそうに、気の毒に」と、悲惨な犠牲者として憐れみの対象とするのではなく、「よく戦った、よく耐え抜いた」とたたえることこそが、真の鎮魂になるのではないか、と竹本さんは戦後ずっと思い続けてきたのだった。
もちろん体験者の思いはそれぞれで、竹本さんの考えに反発する人もいるだろう。国の犠牲となったと、国を恨みながら生きてゆくのも人生ではあろう。それは仕方ない。
斎主の竹本さんは祭文をこう締めくくった。
《その多くを焼き亡ぼした猛火の中から、猛火よりも強く、いま、彼らの殉国の歌声が聞こえてきます。/神とまします英霊に願い上げ奉ります-/たとえ戦死者と呼ばるること適わぬとも、/せめて今日、/ここ九段の大鳥居の空に、/「戦う僕ら小国民」の精霊を迎え、/親しく照覧したまわらんことを!》
この顕彰鎮魂祭が、今後も継続されることを願う。
話を変えよう。ロシアによるウクライナ侵攻の報道についてだ。わが国の報道の多くは「ウクライナの人々が気の毒だ」と、読者・視聴者の情緒を刺激したがってはいないか。けっして悪いことではないが、野蛮な大国に立ち向かう人々の勇気(もちろんそこには悲劇もともなうだろう)を称賛する報道がもっとあってよいのではないか。それができないのは、大東亜戦争時に戦争をあおったという反省、そして「戦うこと=悪」という、戦後日本特有の思い込みがあるからだろう。
モンテーニュは第1巻第1章「人さまざまの方法によって同じ結果に達すること」に面白いことを書いている。人に対して憐れみの感情を持ちやすい、と自分の傾向を分析する彼は、反省をこめてストア学者の言葉を紹介する。
《彼らは言う。「悲しんでいる人たちは助けてやらなければならないが、一緒になってくずおれたり嘆いたりしてはならない」と》
なるほど、一緒になって崩れ落ちてしまったら、助けることなどできるはずもない。私自身について語れば、一連の報道を見ながら、ウクライナの人々に同情し、プーチン大統領への憎悪を煮えたぎらせる。それで完結だ。恥ずかしいことに一ミリも踏み出していない。ところが、塹壕を掘る少年たちの報道は、私を少しだけ動かした。塹壕を掘れない代わりに、自分のできること、すなわちこのコラムを書いている。「だから何なんだ」と言われたら返す言葉もないが。
※モンテーニュの引用は関根秀雄訳『モンテーニュ随想録』(国書刊行会)による。
×執行草舟(しぎょう そうしゅう)氏
プロフィール:昭和25年(1950年)生まれ。立教大学法学部卒。生命の燃焼を軸とした生き方を実践・提唱している生命論・人間論研究者。菌酵素食品の研究・製造・販売の事業である(株)日本生物科学、(株)日本菌学研究所を経営。また独自の美術事業を展開しており、執行草舟コレクションを主宰、戸嶋靖昌記念館館長を務める。
インタビュアー:どんな夢・ビジョンをお持ちですか?
執行草舟氏(以下、敬称略):私は夢とかビジョンとかはありません。いつも基本的に話していることですが、現世の人が言う夢やビジョンは持ったことはないのです。私は小学生の頃から『葉隠(はがくれ)』という武士道の基本書物の哲学が好きで、葉隠のように生きたいと思って生きているだけで、葉隠に書かれてる通りに死にたいと思っています。
つまり、武士道の貫徹です。武士道を貫徹する人生を送りたいと思っているだけなので、他のことは何もない。武士道の貫徹に対して、言葉としては絶対に到達不能の憧れを持たなければならない。そうしなければ武士道に向かうことができないということです。
魂というのは無限成長しなければダメだから。「魂の無限成長に向かうということは、到達不能の憧れを持たなければならない」のです。到達不能の憧れということは、普通の人がいう夢とかビジョンとか、そういうものとは違います。到達不能の憧れは持っていますが、それは言葉にはできない。
「宇宙の根源に向かう魂の無限成長」、言葉としてはそんなようなことになってしまいます。要するに、「人間として生まれたということは、魂が無限成長に向かう義務がある」ということで、私はそれを、人類の「宇宙的使命」だと思っているので、そこに向かうということです。それを文化に表したものが西洋の騎士道と日本の武士道だと思っている。
その武士道の中で一番私が気に入ったというか、好きな書物が『葉隠』です。それは私が書いた本にも沢山書かれていますが。その『葉隠』に書かれた通りの生き方をしたい、それだけが私の人生の目標。あとは金も地位も名誉も何もいりません。今も、今後もそうだし、過去からずっとそうなのです。人に好かれたいと思ったことも、小学生の頃から一度もない。だから聞かれてもちょっと困る。シンプルだけど、現代人には割とわかりにくいのでしょう。
先ほど少し触れましたように、夢やビジョンはありませんが、私には到達不能に向かう理想というものがあります。理想というのは重要なのですが、誰と話しても「理想」というのはそれこそ理想に過ぎないと考えているので、現実は違うという話になると、もう理想の話はできないのです。
しかし人類というのは、「理想の貫徹のために神からつくられた」という思想を私は信念として持っていて、そこが動物との違いだと考えています。だから「理想の貫徹のために生きるのが、人類の人間としての使命だ」ということです。
その貫徹の一つの形として、文化で残っているのが武士道であり騎士道。騎士道はキリスト教から出てきた、キリスト教が生み出した武士道みたいなものです。日本の武士道というのは、天皇制と大家族主義が生み出したものです。そういう違いがありますが、「人類文明が生み出した、最も人間として生きる宇宙的使命を体現している文化だ」と私は思っている。
つまり「自分の命を何に捧げるか」ということだけが人生の課題と言えます。命がけの生き方ということですね。これは愛に捧げるのか、友情なのか真理なのか、まあ色々あると思いますが。だから人生というのは、自分の命と、この人生そのものを何かに捧げるために生きているわけで、それを苦悩し考え、また何かを求めて体当たりを敢行し、繰り返すのが人間だということをずっと言っています。
インタビュアー:ご著書の『脱人間論』というタイトルに惹かれました。
執行:これは「人間がダメだ」ということを言っているわけではありません。『脱人言論』という題名を考えたのは、現代人が人間だと思っているものは既に間違いで、動物のことを言っていて、本当の人間ではないのです。肉体は大切です。しかし肉体を中心に生きたら動物になってしまう。その「一番大切であるはずの肉体を捧げるものを探すのが、人間の人生だ」ということです。
人間に与えられた魂、これは言葉としては「神から与えられた宇宙的使命だ」と私は思っています。それを模索するために生まれた文化が元々武士道だとも言える。だから武士道や騎士道が好きなんだと思います。色んな文化があるけれど、文化の中で人間の宇宙的使命というのを体現するのに最も成功している文化が、武士道と騎士道だと思っているということです。
インタビュアー:武士道の葉隠をご自身の人生でも貫徹されているということでしょうか?
執行:葉隠の思想を生きるのが私の人生そのものと言えます。葉隠は、そういう何かの価値観のために死ぬことだけを思想として説いているわけだから、死に場所を探している人生だということになります。ここまで生きてしまっていることも不思議なのですが。若い頃から私は死に場所を求めています。しかし、なかなか死ねないね、人間というのは(笑)。
インタビュアー:葉隠を貫徹するための目標・計画についてお伺いしたいのですが。
執行:それはないです、体当たりのみ。私は葉隠が好きなので、この葉隠の中に自分の運命を見ているということなのです。人間には生まれた時から、宇宙から与えられた使命とか運命があると思っている。その運命を生き切るのが人生だと思っているから。運命というのは自分固有のもので、親にも兄弟にも誰にもわからない。もちろん恋人ができても恋人にも運命はわからないのです。
宇宙と己、神と自分、宇宙と自分、我と汝。それを生きるのが人生というわけです。だから体当たりしかない。だって教えてくれる人がいないのです。運命は全員違うわけだから、自分の人生を理解するのが人生だとして、全ての人が体当たりをして知るしかない。自分の生きる価値を知るために人間は生きているのだと、私は若者でも講演で言っているわけです。
つまり自分の運命というのは体当たりして失敗を繰り返すしか、悟る道はないわけです。
私は70過ぎるまで、その人生の連続を送っているということで、この位の年になると、何となく自分の運命というのがわかるようになるけれど、若い頃なんかは何もわからない。
とにかく来た運命に、真正面からぶち当たることを繰り返して来た。
だからさっきちょっと出た恋愛の話は、出会った女性に惚れたとしたら、「死ぬほど惚れる」ということです。死のうと思ったけど死ねなかったというだけで、私の場合は。それは結果論です。私の恋愛については本にも書いてありますが。『おゝポポイ!—その日々へ還らむ—』(PHP研究所刊)というインタビュー形式の自伝に詳しい。恋愛は一つの例で、自分の運命を悟るというのは、恋愛で言えば自分が恋をした人のために命を捧げる以外に、自分の運命は何なのかわからないのです。
そこで死んだとして、それでいいわけなのです。死んだらダメだとかそういうことではない。
私は天命なのでしょう、こうやって70まで生きてしまったけれど、二十歳で死んでも三十歳で死んでも、四十歳で死んでも、その人の運命に体当たりしているなら、自分の人生の価値は同じだと思っている。常にそうで、私がやる使命が他にあるのかわからないけれど、ここまで生きてきてしまったというだけです。私にだって自分の運命はわからないのですから。
どんな運命であれ、葉隠に示された武士道の人生を死ぬ日まで送りたいというのが願いと言えば願いです。送れると思ってはいるのだけれど、これは死ぬ日まではわからない。本当に死ぬ瞬間までわからない。葉隠の思想通りに生きてそのままで死ぬということだから。何とかやり通せると思っているのですが。そのためには、ある程度、健康を維持しなければならないと思っている。意識不明になってしまうとダメなんでね。
インタビュアー: 執行さんの普段はどういった活動をなさっているかについて聞かせてください。
執行:一言で言うと、活動などないのです。自分の仕事をして読書をして研究する。例えばお客さんが来たら話して、商売して。私が自分で独立して事業を立ち上げたので、うちの会社を信用してくれる人には、商売的な意味では全力投球しています。その人の人生に寄与するためにです。そういう商売の仕事と、あとは家に帰ったら読書して研究しかない。
私は、うちの製品も全部自分で研究して自分で開発して、自分の工場で作って、それを売る仕事なので、それ以外の人生はないのです。
独立して38年経ちますが、会社にいるか家にいるかの往復しかない。私は旅行も嫌いだし、遊びも全部嫌いなので、ゴルフもしたことないし、酒も飲めないので飲みに行ったこともない。一般的にいうカラオケとかの遊びは全部嫌いです。
サラリーマンの時に付き合いでやらされたことあるけど、もう死ぬほどのストレスだった。カラオケに1回付き合わされたことはありましたが、造船所に勤めている時で、もう3、4日立ち上がれなかった、余りの疲労で。
だから遊ばないというのではなくて、そういう一般の人のする遊びが大っ嫌い。私にとっては文学書や哲学書を読むのが気晴らしといえば気晴らしです。それが私にとっての遊び、そういうことだろうと思う。例えばカントとかニーチェとか、ああいう哲学書を家に帰って読むと、仕事上すごく嫌なことがあったとしても、すーっと下りていく。だからそれが私にとっての遊びなのでしょう。
インタビュアー:執行さんのなさっている芸術活動についてもお伺いしたいのですが。
執行:芸術は好きですし、芸術の一環である、文学も好きなので読書ももちろん毎日している。絵画や彫刻、書画などの芸術は、後世に残すために色々集めて、勉強したり研究したりしています。これは私の宇宙的使命の一つで、仕事と言えば仕事です。
現世で見捨てられている芸術を、後世に残すのが使命だと思っています。本当に魂を燃やした日本人が、現世で報われないとしても、これが日本人の魂だということを後世に残せば、それを見て感動する人が後の世に必ずいるから。そういう未来的な価値に寄与しようと思って今これをやっているのです。
芸術作品というのは、魂の系譜を継承する力がある。系譜というのは繋ぐということ。人間は芸術作品には、その芸術を生み出すための魂というものがあるではないですか。この魂は何百年経っていても、受け取ることが出来る人は、その芸術作品を見ると受け取れる。いわばチャンネルが合うわけです。私は日本の文化は滅びると思っているのです。特に今の経済構造では。
そうなった暁に、世の中が荒廃してしまうわけだから、その時に正しい日本の魂を、将来の日本人に受け継いでもらうためには、今本当に魂が燃焼している人たちの芸術作品を残す必要があると思っているわけです。未来の人々に向かってね。その活動が執行草舟コレクションであり、戸嶋靖昌(としまやすまさ)記念館です。
これを全部纏めて「憂国の芸術」という題名を付けている。それが私のコレクションです。憂国ということは国を憂うことです。だから「憂国の芸術」という題名を付けているわけです。これが私の芸術活動だから、純粋芸術ではない。魂の系譜です。
私は物質主義の現代人が嫌いなので、特に学校でも先生のいうことを聞いたことがないし、親の言うことも聞かない、何も聞かない。要は、優れた魂の直接教育しか受けたことがない。小学校の頃から、日本の古典で言うと、万葉集が好きだった。万葉集の歌が好きでずっと勉強していたのだけれど、学問が嫌いなので、学者の意見なんかが全部嫌なので、辞書も引いたこともないし、解説書も読んだことがない、ずっと。
インタビュアー:学校の試験はどうされていたのですか?
執行:試験は関係ない。そんなのどうでもいいことだ。だから、古代人が書いた万葉集の歌と対峙していたわけです、それで何十年か暮らしていた。それで私は古代人と自分の中では対話できるようになった、ある時期に。柿本人麻呂とか大伴家持(おおとものやかもち)とか。それは28、9歳の頃かな。それではたと気付いたのは、本当に好きで、何の科学的要素や学問的要素も入れないでやっていると、心というのは1,300年前の人間と通じることができるということを実感した。
私の人生に役に立った歌は、全部そうやって得たものなのです。その体験から「憂国の芸術」を思いついたわけです。だから、本当の魂が燃焼した芸術作品があると、好きでそれと対峙している人は、1,000年経とうが2,000年経とうが、わかり合えるということなのです。自己の魂を燃焼させるために使ってほしいと思って、絵とか、彫刻とか、色んな芸術作品を今集めているわけです。
だから条件は、命を芸術に捧げた人たちの生き方が入っている芸術作品であることです。私が好きな洋画家・戸嶋靖昌(としまやすまさ)も、死ぬ日まで、お金もない、食えなかった人だけれども、死ぬその日まで、芸術にその身を捧げていた人なのです。だから芸術が優れているのと、生き方の両方が揃って執行(しぎょう)草舟コレクションなのです。
100年後の人も、戸嶋靖昌の作品を見れば、秀れた価値観のために命を捧げた人の生き方がわかるということです。絶対にそうなるということに自信があるので、集めている。
今、宗教はもう死んだので、人間の魂を復活するには芸術しかないと思っているのです。本当は宗教なのです、人間にとって重要なのは。本当はそうなのですが、もうこれは無理です。今の人間には昔の人みたいに神を信じることはできないので無理です。それこそ原始キリスト教みたいに、見つかったらみんな殉教したわけだから。そういうことは現代人にはもう無理なんだ。これは見ていてわかるので。宗教はもう死んだと思っているので、その宗教の一段下となると、芸術を残さなければならないと思ったのです。
インタビュアー:宗教の一段下なのですね?
執行:そう、宗教というのは神の問題だから。哲学はもっとそれより下だよ、芸術のまた一段下。魂には階層があるのです。今の人が有り難がっているものは一番下にあるものと言えましょう。現代人が素晴らしいと言っているものは、最も低いものである、もうボトムだよ。だから人間であることをもうそろそろ辞めるしかない、ということです。
ボトムが今の価値ですが、芸術はもうちょっと上。そのもっと上には神とか宗教があるわけです。私はキリスト教とか仏教とか宗教も好きなので、散々研究してきたけれど、やっぱり昔の人の宗教心は本当に清らかなものだから、これはもう現代の人は無理です。私も含めて現代の汚染を受けているから。それくらい自分でもわかっています。
インタビュアー:葉隠の思想を生きるようになったきっかけについて教えてください。
執行:きっかけなんかないです。魂がそれを求めたとしか言えない。やっぱりカッコいいってということでしょう。私は男だから、男に生まれたからには、こういう生き方をしたい、こういう死に方がしたいと、小学生で思った。内容なんて関係なくて、文章がカッコいい。命をかけるだけのカッコよさがある文なのです。有名な「武士道というは死ぬことと見つけたり」とか。ジーンとくるじゃないですか。その感動がそのまま、武士道の信奉になったというわけです。
私の心は小学生から全然変わってない。その証拠に、小学生からあらゆる文学を読んできたのだけれども、例えば小学4年生の時に、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』を読んだのです。私は本にあまり線を引かないのだけれども。珍しくその本は、線を引いたのです、赤線を。これ珍しく引いてあるので、ずっと記念に持っていたのですが。60歳を超えてから、もう一回読んでみようと思って、『若きウェルテルの悩み』を読んでみたわけです。別途に本を買ってきてまた赤線引いた。それで照合したら、97%一緒だった。
だから小学校4年の時に自分が感じたゲーテの文章と、65歳位になって感じたゲーテの文章は、同じものだったということです。これは魂の不動を表すのだと思う。要は感性だから。だから年令を越えて持っている価値観が同じなのだということになるでしょう。
インタビュアー: 葉隠に出会ってカッコいいと思われた、その出会いについてもう少し聞かせてください。
執行:親父の本箱に入った本を取って、本自体がカッコよかったのでしょう。私が入院していて、奇跡的に病気から命が助かって、病院から家に戻ってきたときに、親父のその本を取って読みたくなったのです。漢字は全然読めなかったのですが。小学校1年だったからね。お袋に全部仮名を振ってもらって、それで読んだのです。なぜかそれを読みたいと思った、理由はないです。これは運命だと思う。
インタビュアー:お父様も武士道に関心を持たれていたのですか?
執行:親父は武士道とかには興味がなかった。それでも佐賀の武士の家系なので、本だけは持っていたのですね。親父は私が武士道好きだということに一番腹が立っていて、「お前みたいな時代錯誤な奴はダメだ」といつも言われて、その後勘当されてしまったんです。親父はエリートなので、そういうものは嫌いなのです。
インタビュアー:お母様はどんな方だったのですか?
執行:お袋のことは大好きでした。私はお袋っ子なのですが、葉隠とも比べようがないくらい、お袋も好きだった。お袋は面白くて、世間話が大好きな人で。お袋が話すと面白くて、他の人が話すとダメですが私はお袋の世間話を全部聞いたものです。お袋がそういう人だったから、私は世間に強いんだと思う。世の中のことをよく知っている。
死ぬまでお袋と同居していたので、死んだ時は泣きに泣いた。ボケていても可愛かった。
ちょうど戸嶋靖昌の芸術について纏めた『孤高のリアリズム』(講談社エディトリアル刊)の本を書いている時が、お袋のボケが一番酷くて、死ぬ前だった時です。
あれを書いている時が、ちょうどお袋の最後を看取ってるようなものでした。ボケたお袋を抱きかかえて執筆していた時期なのです。だからすごく思い出深い。お袋はすべての人から好かれていた。
インタビュアー:お母様から特に言われていた言葉などはあるのでしょうか?
執行:特別はないですが、とにかく人は信用するなとか、人に親切にするなとか。そういう昔の人がいうことです。昔の人は全員そうです。親切にしろというのは、現代の影響を受けている。本音を言う人は違う。それでいてお袋は他人に親切だった。だから嫌な思いを沢山していたのです。
人生というのは辛いもんだ、自分の思い通りになることは一つもないと、昔の人が言っていたことです。だから私なんかこの歳までやってきて、何ともない。嫌なことがあったとしても、親からずっと人生なんて嫌なことの連続だから、死ぬまで大変なのだと言い聞かされていましたからね。
昔の言葉で言えば、「死ぬまで自分の力でおまんま食うのは大変なことなんだ」と言っていたから、そうなのだと思って育っている。もちろん、今もそう思っています。人生なんて楽しいものと思っていないから、もともと。くだらないものだと思っているので、くだらないことが起こっても、ほうほう、なるほどと思うだけです。くだらない所なのだから。もともと現世ってそうなのです。
これは別に、さっき言った哲学の研究でも、哲学者もみんなそう言っている。現世などというのはドロドロで、もともと汚い所なのです。そこをどう自分の心を清く高く美しく保って生き抜くかが人生論であり、宗教なのです。
世の中が綺麗なところだと思っている人はおかしい。多分、自分自身が汚いのだと思う。だから世の中と一致しすぎて保護色でわからないのでしょう。お袋はそういう正直なありのままをバンと言う人でした。
インタビュアー:「絶対負」について聞かせてもらえますか?
執行:「絶対負」というのは、私の人生全部で作り上げた、人生観をまとめた、執行(しぎょう)哲学の中枢課題です。だから、葉隠も全部入っている。現代の価値観は全部、「正のエネルギーだ」ということです。全ての人が話していることは、「全部正」。私が話す話は「全部負」ということです。現代は、プラスにしか価値を感じていないということです。
私が話しているのは負のエネルギーだけで、負の価値を言っているのです。現代人はみんな数字で表されるような正のエネルギーだけを語っている。食べ物なら栄養が好きなのです。私が話しているのは、栄養を支えているものは目に見えない、もっと尊いエネルギーが栄養物を支えているのだという話をしている。それも絶対負の一つです。だから商売も全部私は「絶対負」なのです。
栄養素としては何の価値もない「菌食」と言って、菌の活動エネルギーを日々取り入れるという健康食品を推奨しているわけ。だから研究も全てその思想から出ているということ。
うちの製品は、好きになってくれた人は、みんな創業以来30年40年愛飲している人ばかりです。その思想とは生命の根源を支え生かすものということです。
生命を生かすということは、長生きでもないし健康でもないし、病気とも関係ないということです。自分の運命に沿った自分らしい人生を送れるかどうかというだけの話でこの事業をやっています。それを応援するのがうちの菌食だと思ってくれたらいい。
インタビュアー:「死」はどういう概念でしょうか?
執行:死というのは永遠に繋がる全てのことです。死ぬために生きているのが人間であり、死というのは人間そのものなのです。人間以外で死を認識できるのは、生物も無機物もない。
人間である証。人間というのは死ぬために生まれ、死ぬために生きているということです。
それを文化にしたのが武士道です。だから武士道が大事だと言っているのです。
生というのは死ぬための準備だというだけです。だから死は特別なものではない、死が宇宙なのです。我々は死ぬために生まれ、そして生きている。どう死ぬかが問題なのです。それをあからめるのが武士道ですが、私は死生観をよく話すけど、そのためでしょう。
だから今の人は死を忌み嫌っているので、真の人生がない。腐れゆく肉として生きるのみで、これは動物ということです。人間の人生は動物とは違うということ。死を認識して死に向かって魂の無限成長のために生きている。肉体は魂を乗せているだけの価値なのです。
私はいつ死んでもいい覚悟で今も生きている。全精力を日本が滅びてから魂を立て直すためのものに、全てを捧げるつもりでいる。事業も全部そうなのです。私の本は現世の人に向けて書いたものではないのです。これから世の中が滅びて本当の日本人として立ち直る時の心の支えになるように、今書いているわけです。
だから現世の人の評判なんて聞きたくないし、気にもしていない。後の時代に残すために私は本を書いているだけだから。やはり立ち直るにはきっかけがいるので文化遺産が必要なのです。だから書いている時から文化遺産のつもりで書いているのです。
以上
×人生には、忘れ得ぬ出会いというものがある。私にとって、その最も大きいものの一つが井口潔先生との出会いと言えるだろう。
それは二〇一八年八月の突然の出来事だった。私の親しい人が、是非紹介したい人物がいるので、これからすぐに伺いたいと言ってきたのだ。場所は私の経営する会社の社長室である。そしてその日、九十七才になられる井口潔先生を、私は初めて仰ぎ見ることになった。その令名はかねてから聞いてはいた。しかし直接お会いするのは初めてだった。井口先生を紹介して下さった人の言によると、先生は元々から私の著作をいくつか読まれ、その内容を高く評価して下さっていると伝え聞かされていた。
それに引き換え私のほうは、自分が「井口理論」をまだ勉強したことがない不精を、いたく恥入ったままでの初対面だった。仰ぎ見るべき業績を重ねられた人が、私の著作を読んでくれている。それにも拘わらず、私は不勉強だったのだ。目下も目下、能力も実績も年齢さえもかなり下の私が、井口先生の業績は知っていたが、内容をよく理解していなかった。多分、その時の私の不甲斐ない、情ない気持は、多くの人に分かっていただけるに違いない。
しかし、それらの心配は、先生に会った瞬間に吹き飛んだ。それは先生のもつ無限に近いほどの深い慈愛の姿勢と、それを湛えている深度の厚いその笑顔のゆえと言っていい。九十七才であることは聞いていた。しかし眼前に立つ先生は「青春」を生きる青年のような熱情を発散しておられたのだ。失礼とは分かっているが、言葉には言い尽くせぬ「かわいらしい笑顔」だった。私はすっかり「安心」して、いつもの「くだけた」感じに成り下がってしまった。そのような私を、最後まで先生は包み込んで下さった。あの先生の温かさが、今でも瞼の裏に焼き付いている。
私は先生と出会うまで、自分自身が長生きをしたいと思ったことはなかった。長生きに何の価値も感じていなかったのだ。私は生命の真の燃焼と、砕け散ることを前提とした体当たりの生き方だけを尊いものと信じていた。その私の人生観に激震をもたらしたのが、先生との出会いだった。「矍鑠」という古い言葉が、最も正確な描写となろう。美しく崇高な「老い」を私はそこに見出したのである。
現に生きている美しい老人を、私はそれまであまり見たことがなかった。私は、そういう時代を生きて来たのだろう。昔の人が語っていた崇高で高貴なる「老い」を私は先生の中に見た。人間が真に老いるとは、かくも偉大なものなのかと実感した。この実感が、私自身に「長生き」の真の尊さを教えてくれたのだ。私は出会いの中で、すでに長生きに憧れるようになった自己を見出していた。
昔の人は、このような人生を矍鑠と名付けたのだろう。矍鑠とは、死ぬ日まで「青春」を生きようとする老人のことを言うのだ。私もそう成りたい。先生との出会いは、私の人生に革命をもたらした。そして先生は、青年の如く語り続けたのである。ヘルマン・ヘッセの言葉を引用しておられた。「人は成熟するにつれて若くなる」。文学において、青春を教えてくれたのはヘッセだった。私の青春が甦った。そして先生はその言葉をその場でドイツ語の原文で話されたのだ。
好きな言葉を原文で語るには大いなる記憶力と気力が必要となる。日々の努力がいるのだ。先生の日常に対する畏敬の念が沸き上がって来るのを押さえられなかった。九十七才にして、青春文学の巨人ヘッセの言葉を人生の中枢に据える人を目の前に見た幸福は、測り知れないものがある。
話は弾み、放って置けば徹夜になりかねない勢いとなった。さすがに、周りにいた人たちが心配して声をかけてきた。仕方がない。こうなったら最後の話をしようということになった。先生はその時、先生自身の理論である「生物学的人間教育論」の核心と思われる思想を述べられたのだ。私はその言葉を、一生忘れることはないだろう。「自分の脳は、自分で創る」という思想だ。深い思想である。人間生命の「根源的実在」を把握している言葉と私は受け取った。
現代の物質文明を超越する理論と考えている。先生の理論は、人間存在の「実存」を問うているのだ。人間生命のもつ真の「独立自尊」と「自己責任」ということを、これほど見事に表現する言葉に出会ったことはない。先生のもつ人間生命に対する真の愛と、その本質を抉る凄絶な科学的精神に私は舌を巻いた。そして何よりも、それを世に問うその真の勇気に心が震えた。先生が提唱される理論は、現代の物質偏重文明に対抗している。だから不断の勇気がなければ、その実行は成せる業ではない。
そのような思想を、先生は易々と語られる。その魂の純粋に、私は敬慕の念を抱くのである。そして先生は最後に、私の思想である「自己の運命を愛する」という考え方を讃えて下さった。私の思想などは、勿論、先生の足下にも及ばないが、そのような思想でも先生は摑み取って下さったのだ。今、先生はこの世には居ない。しかし私は、この日のこの出会いから受けた「恩」を忘れることは決してない。
令和三年十一月二十八日 執行 草舟 記
×異形の思想家である。武士道(葉隠)の精神とキリスト教を核にした西洋思想を止揚した独自の思想から、人間と人間社会の在り方を厳しく問い続ける。本書は若いビジネスパーソンを念頭に、Q&A方式で自身の思想を平易に述べたものだ。
タイトルが示すように、常識を覆すメッセージが満載されている。読めば分かるが、けっしてこけおどしではない。核になる思想は次の言葉に凝縮されている。
≪何をおいても命が一番大切だというのなら、それは動物です。そうではなく、わが命よりも大切なものがあるから、人間なのです≫
この言葉は現代においては、「時代錯誤」「滅私奉公の思想」といった感じ方をする人も多いはずだ。
命を軽んじろと言っているわけではありません。命に代えても守りたいものが自分にはあるのか、と問い続けることが人間の人間たるゆえんだと考えます」
執行さんはフランスの哲学者、アランの≪魂とは、肉体を拒絶する何ものかである≫や、スペインの哲学者、ウナムーノの≪人間以上のものたらんと欲するときにだけ、人間は本来的な人間になる≫という言葉を紹介しながら、その真意を読者に伝えようとする。
執行さんは現代の日本人の多くが動物、それも飼い慣らされた家畜になっていると考える。
「欲望のみに従った生き方は、欲望の堂々巡り、無間地獄に陥るだけです。戦後日本で当たり前とされてきた物質至上主義という常識が覆されない限り、私たちに未来はありません」と言い切る。
平易な叙述ながら、そこには祈りにも似たメッセージが込められている。
本書で興味を持った読者に、次の一冊として勧めたいものを問うと、『超葉隠論』(実業之日本社)との答えが返ってきた。
×存命中、画家としてほとんど無名のまま生涯を終えたと言われる戸嶋靖昌(1934-2006)だが、秋田の地で展覧会が行われたことを一番に喜び誇りに思ったのは、泉下の母ミツヱではなかったろうか。
会場入り口に、冬の坊沢(北秋田市)の屋敷前で撮った家族写真があった。右から二人目に長身のミツヱ、左端が靖昌だ。妹、弟、ほかの二人は友人だろうか。うりざね顔で美形のミツヱはほほ笑んでいる。
師走に入り、私は高松から卒寿の母が一人住む秋田市を訪ねた。コロナ禍で国内の移動さえ気づまりな状態が続いていたが、母をずっと訪ねないなど、あり得ないと心に決めた。幸い母は元気であった。翌日「戸嶋靖昌の絵を観に行こう」と二人で出かけた。
山を背負うように伸びる坊沢、羽集街道沿いの小さな集落。曹洞宗永安寺の下で私は生まれた。家の窓には、向かいの家のうっそうと茂る樹木の影がいつもあった。その家は「かどの家」と呼ばれる大きな屋敷で、そこに「かどのおがはん」は住んでいた。おがはんには、庄屋である戸嶋家の「奥様」という尊称の意味が込められている。
小学校に上がる前の私は、街道を渡り、かどの家のイチイの実を食べた。赤い実をつまみ口に入れると、つかの間の甘い汁が心を満たす。黒い種を吹き出しまた口に入れる。そうして夕暮れまでの時間を過ごしたのだ。
数年前、母が「かどの家の息子さんは有名な画家なんだど」と電話口で話していた。わが家はすでに秋田市に転居していたが、長く住んだ坊沢の地はなつかしい。NHK「日曜美術館」で「グラナダ 魂の画譜 戸嶋靖昌 孤高のリアリズム」の放送を観たのである。画面には代表作「クリスティーヌの像」が映し出された。灰色の濃淡を背景に、白っぽい衣服をまとう存在感のある女性。まなざしは遠くへ伸びている。瞬間、「この絵は、かどのおがはんだ」と思った。
スペイン・グラナダで30年近くを過ごした戸嶋が現地で出会った女性を描いたものではあるが、その瞳は私が幼い時から知っている戸嶋の母、そのものだった。
「目は描かないで描く」と、戸嶋の画業をたどる著作「孤高のリアリズム」(執行草舟・著)に本人の言葉が記されている。戸嶋にとって描くこととは、もどること、いのちへの回帰ではなかっただろうか。ゆえに「母のまなざし」はあまねく戸嶋の魂に宿っていたのではないか。
美術館の展示室は薄暗く、奥へ奥へと導かれるように歩を進めた。初期の作品には色彩の原初ともいうべきものにあふれていた。「名づけえぬもの」「森と抽象」「雑木林」「赤のある森」など。「縄文の焔と闇」という展覧会のテーゼが、私自身の記憶をも呼び覚ます。
戸嶋は鉱山技師の父の赴任先栃木で生まれたが、父を亡くし母と共に5歳の時、父祖の地坊沢へ戻る。大館鳳鳴高校卒業後、代用教員をした。母の強い反対を押し切って絵を描くために上京したのは1953(昭和28)年、私が生まれる4年前であった。
あの写真の、雪を解かすようなミツヱのほほ笑みを、幼い私は見たことがなかった。母を置いてでも絵の道に進もうとしたことが、母を寂しい顔つきの人にしてしまったのだろうか。屋敷全体から漂うざわざわと揺れる樹木の陰りとも重なり、誰もが踏み込めない雰囲気の中で母は暮らし続けたのだ。
土の色、緑陰、落ち葉の朽ち色、熾火のような赤、晩秋、雪の気配。一連の絵の前に立つと、私が幼少期、記憶の底に残していたものに呼びもどされてゆく。芽吹きの春はいったいどれだけのものを孕んでいるのだろう。命の春を得るために、戸嶋はどれだけの腐蝕の色を作品に注ぎ込んだのだろうか。戸嶋靖昌は故郷秋田の地へ還り、命の源へ深く問いかけていく。
×秋田県立美術館で開催中の「戸嶋靖昌展―縄文の焔と闇」を見てきた。日本人にあまり馴染みがない画家であろう。どういう画家かということも含めて、わたしは断想的紀行として以下を書く。
「肉体は朽ち果てるものであって本質的には存在していない。腐っていく過程こそが肉体なのだ。だからこそ愛情がなければ見つめることはできない。しかし、愛を捨てなければキャンバスの上では形にならない」
戸嶋靖昌(1934-2006年)が語った言葉のなかでも、これはもっとも端的に戸嶋芸術の要諦をなす言葉であろう。愛するものへの愛を描ききるには愛を捨てなければならないとは、リルケがセザンヌの芸術に見て取った洞察を想起させる言葉である。
セザンヌは朽ち果てるものを描いたのではなかったし、かれの愛したリンゴは堅固な存在感と永遠性を感じさせる。これに対して戸嶋の描く果実はメンブリージョつまり花梨であるが、その果実に肉体が仮託される。グラナダで戸嶋は友が庭からもいで持ってきてくれたこの果実がひと目で好きになった。ある日その友が死んだ。
時間とともに朽ち果てる果実。戸嶋の場合、それは朽ち果てる果実。戸嶋の場合、それは朽ち果てる肉体であった。瞬間よ、止まれ、おまえは美しいから、とファウストは呼びかける。現実の時間はけっしてとどまらない。刻々移りゆく時間の悲哀のなかに、この世のすべてのものが生きている。
一九七七年、戸嶋靖昌はグラナダでかれのモデルとなるベルタと出会った。すでに八十歳を越えていたベルタを描こうとして苦心を重ねる戸嶋の言葉に、その後ミゲールやマヌエルやバルバラといった人物像を描く戸嶋の心意をうかがうことが出来る。
「老女の背後にある時間の重さが欲しい。単に時間を経ているという説明的なものに終わるのではなく、その人間の歴史的人生の荘厳さといったものが描出できなければ、真の目標は達せられない」
戸嶋が自分の絵に欲した「時間の重さ」。果実や樹木や林、街並みや家々のあいだを延びる道についてもおそらく同じであった。
わたしに想起される英国の美術史家ジョン・ラスキンの言葉がある。風景画の巨匠とされるターナーの描く風景は、実際の景観とは似ていないという同時代の人の非難を受け、ラスキンはこう反論した。ターナーの風景画は美化された一枚の静止画のように見えるがそうではない。画家は目指す風景に出会うまで、何時間または何日、険しい道を登り続けた。濁流が渦巻く川の傍らを危険を冒して歩いた。刻々移り変わる景観のなかを画家の足が歩いた道程そのものが、その風景画には描き込まれているのだ、と。
戸嶋が描こうとしたのも、年老いた人間が歩いてきた長い時間と人生そのものである。生きられた時間が自から放つ高貴さ、荘厳さを画家は描こうとした。そのために対象を凝視し続ける画家のまなざしもまた膨大な時間の奥を見通さなくてはならなかった。
秋田の展覧会場で、わたしは一人の見学者として自分の風土との対応を考えないわけにはいかなかった。対応する風土とはここでは秋田と岩手である。どちらも東北だが、いっぽうは日本海側、他方は太平洋側というちがいがある。秋田は豪雪地帯であるが、岩手は雪より寒気の厳しいところである。しかし、東北という風土にはらまれる厳しさの人間精神へのはたらきかけにおいて、秋田と岩手は共通し合う。風土の過酷さが人間の魂にどういう影響をもたらすのか。秋田の冬をわたしは同じ東北人として想像することが出来る。
いっぽう、風土をスペインということで言えば、とくにグラナダでの日々である。そのグラナダと故郷・秋田での戸嶋の生活。二つの風土の冬の日々がどういうものであったか。戸嶋は長年グラナダに暮らしたから、この地の冬というものを体感的に知悉していたはずである。その体感がかれに秋田の冬を想起させなかったはずはない。
十数年前、アンダルシアを旅したおり、グラナダにもわたしは滞在した。真冬のちょうど大晦日、グラナダの寒気の酷烈さを身をもって経験する機会となった。岩手のわたしの郷里・遠野は秋田のような豪雪地帯には属していない。だが、一月中旬から二月いっぱいと三月初旬にかけて、すさまじい寒気と冷え込みが襲う。人々を文字どおり縮み上がらせ、屋内に閉じ込めてしまう。よく知られている南部の曲り家というものが遠野に発達したのも風土的必然からだった。
したがって、グラナダで寒さにふるえていたわたしは、けっして異郷の地に自分がいるとは思わなかった。自分の感覚に刻み込まれた冬の記憶が戸嶋に秋田の冬を想起させたであろうように、わたしに遠野の寒気を想起させたのである。
自分のからだの奥深いところに埋め込まれた辺境の記憶は、ところによって風土的としか言いようのない奇妙に濃密な共振を内部に促さずにはいない。同じ記憶が戸嶋の描く風景のなかにも感じられるのだ。それがわたしのなかの抜きがたい風土の記憶に向かって呼びかける。
しかし、風景以上にむずかしいのは人像であると戸嶋は嘆息する。とくに老いた人の顔面だ。芸術家として描かなくてはならないのは老いた顔自体ではない。描かれるべきは時間の重さそのものなのだ。モデルになったミゲールにしても、ベルタにしても、またはバレリーやクリスティーナにしても、それから帰国後の晩年に描いた執行草舟の像にしても、表情にどことなく共通したものがある。民族、性別、個性を超えて似かようものがある。つぶさに見ればもちろんちがっていよう。しかし一見したところでは相互に似ている。それは表情の奥、または向こうにあるもの、つまり人間によって生きられた時間というものの本然のかたちが帯びる普遍性のゆえであろう。
老いを老いとして感じさせるのではなく、時間つまり生きられた時間を肖像に現前させる。それが戸嶋の目指したるものだった。老いの説明としての絵にとどまってはならない。その人間によって生きられた時間を現前させなければならない。人間は老いる。老いて醜くなる。だが、生きられた老いの時間とは、ツヴァイクふうに言うならば「星の時間」である。芸術家が表現しなくてはならないのは、その人間によって生きられた現前する存在としての「星の時間」なのだ。
秋田の深い雪について戸嶋はよく語っていたという。豪雪に閉じ込められ、人は耐えること、我慢することを鍛錬させられるという。
わたしに思い出されるのは英語でいうエンデュアランスまたはフォーティテュードという言葉だ。風土や環境といった人間を取り囲む条件の苛烈さに人間はどのように対処するのか。右の英語はいずれも「堅忍不抜」という意味に近いが、語感として印象づけられるのは、厳しい風土と生活に立ち向かう人間の品位または高貴さの感覚である。
ジョン・ラスキンのゴシック論を初めて読んだときの感銘をわたしはいまだに忘れない。辺境である北方の荒々しさと野蛮を含意する侮辱後としてのゴート的すなわち中世ゴシック、そのゴシック様式の本質。それはまずもって風土との人間の果敢な対峙に要約される。すなわち厳しい自然、過酷な気候と生活条件に打ち負けない強さ。それが北方の人々の人生観に高貴さの感覚をかたちづくる基礎となった。
戸嶋の秋田について豪雪に閉ざされる東北の辺境ということが強調されるなら、遠野は風土の自然は雪よりも寒気である。盆地特融の凍てつく寒気は地元の言葉で「しばれる」である。同じ岩手でも三陸沿岸部の気候とは全然異なる。地形自体が冬の気候そのものを変え、四囲をいっそう狭め、押し込めるような圧迫感をもって人間を抑圧せずにいない。
一九六〇年代の戸嶋の絵を今回の展示会場で何点も見たが、武蔵野美術学校時代、くる日もくる日も画家はおのれの内なる風土と激しいたたかいを続行していたことが如実にうかがわれた。
そして六〇年代も後半となると時代環境と社会条件という諸要因が加わる。それらが外的・内的風土と化し、抑圧する閉塞感となって戸嶋を追い詰めた。武蔵のの雑木林を描いた息苦しいまでの混沌図からもそれがはっきりとうかがわれる。
そして、この時代の抑圧を象徴する社会的事件は、七〇年十一月、三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊駐屯地で自決を遂げたことである。その衝撃を戸嶋はどう受けとめたか。
自己の芸術はなにを目指すのか。その根本的な問いに戸嶋は直面していた。三島事件が起きたのは、ちょうど戸嶋の葛藤が頂点に達していたときであった。戸嶋のなかにも名声や名誉や経済的豊かさを求める気持ちが全然なかったわけではなかった。世俗的な欲求を投げ捨てて顧みない生き方を戸嶋は貫いていたと誰の目にも見えていた。戸嶋自身もそう思っていた。実際はどうだったか。執行が戸嶋の述懐をつぶさに聞いている。三島の自決という衝撃の激しさが戸嶋に自分の内部を抉り出させるきっかけとなったという。天才に恵まれた作家として頂点をきわめたとはいえ、それに安住しきれないものが人間として三島のなかにはあった。四十代半ばにしてノーベル賞候補となった。のちに編まれた全集は三六巻にもおよぶ。にもかかわらず、世の度肝を抜くような壮絶な方法で死ぬことを選択した。それまでのあらゆる名声は、自決を思いとどまる上でなんの意味も持たなかった。このことに深い衝撃を受けた戸嶋は、顧みて自分の内部に依然として世俗的な栄達を求める野心の残滓がわだかまっていたという不甲斐ない事実に愕然として気づく。
その事実を自分に認めさせるには勇気が要った。だが戸嶋という人間の稀有なところは、その認識への勇気を失わなかったことだと執行は語る。沈思した挙句生涯無名に徹し、探求一途に生きることを自身に要求したのもその勇気だった。こうしてヨーロッパの「辺境」であるスペイン生きを企図した。四年後の一九七四年、戸嶋は旅立った。
およそ三〇年におよぶ長いスペイン滞在から帰国して、戸嶋靖昌の最後のモデルとなったのは実業家・執行草舟であった。絶筆となったのも執行の肖像だった。印象的な次の言葉が執行の著書である戸嶋靖昌論『孤高のリアリズム』に記されている。
「絶筆の中で、戸嶋は何かを待っている。そこに描かれた私も、また何かを待っているのだ。それが何なのか、誰にも分からない。分からないが、確実に何かを待っている」
絶筆とは二〇〇六年の執行草舟を描いた『魅せられたる魂』である。そこに込められた「待つ」という姿勢にわたしは感銘を受け、畏怖を感じずにはいられなかった。はるか古代の人間がそなえていたであろう緊張と激しさがそこにあった。
なにかを待つ、とは現代のわれわれからすればもっぱら受動的な姿勢のように思われよう。現代人は待つことを忘れて生きている。近代以降、待つことの深い意味が忘れられている。だが「待つ」とは、語の根源においては二重性を帯びた身がまえを意味した。燃えるようななにものかを内部に蔵して肉薄してゆく魂が、「待つ」のである。たとえて言えばそれは獲物の出現を固唾を飲んで待ち受けるマタギという猟師の身がまえである。あるいは、高空を遊弋しつつまなこを光らせて機をうかがう猛禽のような面影を失わなかった戸嶋のまなざしをわたしは想起する。徹底的な探求性を秘めた人間のみが持つまなざしである。未到のなにものかの到来をあえて促すような、内側に起爆力を秘めて「待ちかまえる」人間のまなざしである。立野正裕(付記 戸嶋靖昌展は秋田県立美術館で一月十日まで開催)
×~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
令和2年(2020)12月15日(火曜日) 通巻第6731号
●随筆
「縄文の焔と闇を描いた孤高の画家、戸嶋靖昌」 宮崎正弘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲「縄文の焔と闇」を描いた孤高の画家、戸嶋靖昌
米国のノーベル文学賞作家ウィリアム・フォークナーに次の箴言がある。
「過去は死んでいない。過去は通り過ぎてもいない」。
この言葉は、霊魂は不滅、魂は輪廻するという意味だろう。
三島由紀夫、森田必勝の「楯の会事件」(昭和四十五年十一月二十五日)は日本のみかわ全世界に驚天動地の衝撃を運んだ。人生が変わった人もいれば、後追い自殺の若者が事件後に相次いだ。いま後期高齢者となった世代の誰にでも、「あなたはあの日どこで何をしていましたか?」と問うと記憶が鮮明に甦る人が殆どである。
筆者自身は楯の会成立時に学生運動の渦中にあって、森田必勝とは三年同じ釜の飯をたべた経験があり、その体験と経過は拙著『三島由紀夫「以後」』、『三島由紀夫の現場』(ともに並木書房)に書いたので、ここでは繰り返さない。
日本画壇で活躍していた戸嶋靖昌も、その一人だった。大きな衝撃を受けた戸嶋は、名声もカネも求めず純粋に芸術を完成させようと決断し、日本での生活を畳み、スペインへ移り住んだ。そして三十年近くをスペインで創作活動を続けた。
こうなれば日本の画壇は戸嶋の存在を忘れかけた。
同じ外国へ移住した画家に藤田嗣治がいるが、かれは戦争画を書いたという理由だけで、風当たりが強くなり、外国へ移住した。藤田嗣治はパリで水を得た魚のように自由は創作を続け、その画風はフランスで広く受け入れられた。日本の評価とは異なり、またそのユーモラスな画風は人気を得たが、画風が明るく、分かりやすく、或る意味で漫画的であり、戦前の作風とはどことなくことなる。
藤田は最後には仏蘭西国籍を取得した。
一方、戸嶋靖昌はマドリッドの安宿を根城にブラド美術館などに足繁く通いつめ、それからグレナダへ、スペインのあちこちを移住しながらも似顔絵、風景画などの創作に没頭した。
それにしても何故スペインか?
スペインはピカソやダリも産んだが、歴史的にみると、スペイン各地にはケルトの痕跡がある。ケルトと縄文は地域を超えた精神世界で通底している。祭祀のスタイルが酷似している。ケルトの炎と闇は縄文の焰と闇と通底するのだ。
戸嶋は三十年を閲してスペインを切り上げ日本に帰国してから遭遇したのが実業家で思想家でもある執行草舟だった。
執行草舟をモデルの絵画や彫刻をつづける裡に二人は共鳴し合い、執行は八百点にも及ぶ戸嶋の殆どの作品を得て、戸嶋絵画館を作ったほど熱を入れた。
根になる共通点は三島由紀夫の魂ではなかったのか。
戸嶋は三島事件に衝撃を受けてスペインのケルトの足跡を追った。
執行は中学生から高校にかけて毎年夏に避暑にやってきた三島由紀夫と知り合い、若さを顧みずに文学論哲学論をふっかけたという。三島もきちんと応対し、また何枚かの色紙を執行のために書いた。筆者も実物を見せて貰ったことがある。
戸嶋は秋田生まれで、武蔵野美大で学び、武蔵野神社付近を散策しながら、若き日々には暗鬱ななかの十年を描く風景画を描き続けた。
その頃の作品に「森の呻き」がある。
筆者は秋田県立美術館(二階は藤田嗣治常設館)で開催された戸嶋靖昌展を見に行った折に、およそ200点の作品のなかでも、この「森の呻き」の前に立って、じっと眺めていた。
そうだ、これは古代人と神々の呻吟が、深奥な森の構図の中から聞こえてくる。森厳のなかに古代人の雄叫びを聞くような幻覚を覚えた。全体が暗い、その戸嶋のあまりに暗鬱な基調は、縄文時代には日光と月光のほか、光がなく、それだからこそ天然自然、森羅万象が澄明に見えた。神々の声が聞こえたのだ。その縄文の炎と情念、その灼熱と熱狂が伝わってきた。これぞ全身を揺らすパワースポット的な絵画だ。
弥生時代から飛鳥、平城、平安にかけて、日本の美はわびさびへと比重が移り、日本庭園に茶室が設えられ、物静かな文化が重視された。静謐の中の庭園は、人を和ませ、その優雅にして壮麗な造園の建設思想は日本文化の独自性を発揮している。
名城や名刹を飾る彫刻は唐風も多いが、屏風絵などは狩野派、尾形派が独占し、画壇主流に挑戦した長谷川等伯などは斥けられた。
近代の日本画壇は、唐突に西洋絵画に暴走し、伝統的日本画家は大変な苦労を強いられた。
目利きの西欧人らは江戸の日本文化の絶頂期に書かれた美人画、浮世絵、写楽、北斎、そして春画を買い求め、せっせと外国へ運んだ。いま名作の浮世絵を鑑賞したいと思えばルーブルやNYのメトロポリタン美術館に行かなければいけなくなった。
絵画は、音楽も文学もそうであったように西洋にかぶれ、日本が誇る伝統的な骨董、芸術品、鎧兜に日本刀も、打ち捨てられた。
たとえば日本企業の社長室や役員室を飾る絵画を見よ。およそが西洋画であり、セザンヌ、ルノアール、モネ。。。。それも複製が多い。欧米では富裕階級の豪邸には大概が絵画で飾られ、インテリアは中世風であり、絨毯はペルシャ。。。。
ゴッホもゴーギャンも生前は評価されず画商から相手にされず、貧困に喘ぎながらもゴッホは弟に助けられた。ゴーギャンを助けたのはタヒチの僅かの友人だった。しかし、目利きは収集家のなかにいるのだ。ゴッホをこつこつと買い集めた富豪がいた。
多くのゴッホ作品を集めるのはオランダのアムステルダムのゴッホ美術館と、ドイツ国境に近いクレラー・ミューラー美術館である。
筆者も両方を見に行ったが、後者は山の中の自然林に囲まれた森に開かれていて『箱根の森美術館』の設計のモデルとなった。
フェルメールは死後二百年間、誰も相手にしなかった。作品がすくなく37点とされるが、筆者が見たのはオランダ、ベルギー、ドイツで半分ほどである。令和元年に上野の森美術館でフェルメール展が開かれたときは、雨の中、見に行ったが入場制限があり、展示場は立錐の余地のないほど超満員だった。
この価値の変遷は、いったい何だろうか。
そうだ、フェルメールは空に浮かぶエンジェルやキリストを描かず、当時の教会が主流の宗教画には興味を抱かずに、世俗の生き方に背を向けて、富豪の肖像画も引き受けず、ひたすら孤高に、ひたすら光をモチーフとした作品を描き続けた。門弟二千を誇り多くの教会の絵画をあたかも創作工房のように引き受けたレンブラントと、その生き方が対照的だった。
日本でも伊藤若沖も長谷川等伯もながく世に埋もれたように、戸嶋靖昌への評価はこれからである。
秋田県立美術館において開催された戸嶋靖昌展は、三階のフロアにスペイン時代の作品が並んでいた。縄文の炎はスペイン時代にも灯り続けたが、明るさがでて、とくに風景画は寂しさの光りの中に曙光が射している。
肖像画も無名の近所のおばさんらを描きながら、人生を紳士に見つめる姿勢が漂う画風となっている。
(編集部から。戸嶋靖昌展は、秋田県立美術館で令和三年1月11日まで)。
×現代日本の軽佻浮薄な風潮に対する大胆な叛旗である。
「脱人間」とは「新しい旅立ち」を意味すると著者は言う。
「いま世を覆っている人間中心のヒューマニズムは、すでに行き過ぎて腐臭を放っている」
確かにそうだがなぜそうなったのか。それは人間が神を創造したのではなく神が人間を造ったことを否定したからだと戦後日本人の忘れ物を衝く。
著者のいう三大毒素とは民主主義、ヒューマニズム、科学文明である。
この「ウイルスに遺伝子と脳の特定部位が侵されて」しまった。だからこそ『脱人間』の手術が必要だと言い切る。
さらに大胆になってヒューマニズムは西洋の近代化が生んだ真のリヴァイアサンであり、物質至上主義は「魂の進化」ということを忘れてしまった。魂は永遠であり、肉体は現世における単なる容れ物でしかない。
「魂のために肉体を捨てることは、いまの世の中に受け入れられるものではない。そこには、現代的な綺麗事や優しさと抵触する本来的な厳しさがあるからに他ならない」
現代日本人は「去勢状態」にあり、学校の「イジメ撲滅」などは却って子供の去勢化を促す危険を内包している。子供の感情を合理的に作ることなどできる相談ではない。
古代の人間は、なぜあれほど動的で挑戦的だったのか?
「原初の人々は、人間を神の分霊と言っていた。神の分霊として、宇宙の霊魂は地球に降り注いでいた。そして、その分霊の一部が、後に人間の魂となり、地球上に棲息していた類人猿に入ることによって、肉体を持つ人類が生まれた。だから、まず魂となったものの原型は、全体的な存在である神の分霊だと言える。その分霊がまた分離して一人ひとりの人間に入ることによって、個々の人間が生まれた」からだ。
三島由紀夫は戦後民主主義を憎み、偽善のバチルス(細菌)と言った(「果たし得ていない約束」、昭和45年7月7日付サンケイ新聞夕刊)。この三島と著者の訴えは爆発的に通底している。読了後、スサノオの荒ぶる魂、ヤマトタケルの絶叫、そして三島由紀夫の雄叫びを聞いたような気がした。
×肖像画や風景画を中心に、日本国内やスペインを拠点として活動した画家、戸嶋靖昌(1934~2006年)の芸術の全貌と生涯を伝える展覧会が、父祖の地である秋田県立美術館(秋田市)で開かれている(2021年1月10日まで)。透徹したまなざしで生命の根源を見つめた作品とともに、衰えぬ探求心の淵源となった若き日々の遍歴も紹介し、見応えのある展示となっている。
戸嶋は幼少時に父を亡くし、秋田県坊沢村(現北秋田市)で育った。周辺には大湯環状列石など縄文時代の遺跡があり、戸嶋も狩猟・採集を主とした時代への関心を深めたようだ。展覧会は副題で「縄文の焔と闇」とうたっており、作品にも原始の魂に触発されたごとき活力をふるって、存在や死への不安を克服しようとする格闘の跡が生々しい。
とりわけ、武蔵野美術学校(現武蔵野美術大学)時代から卒業後に描いた裸婦像や森の絵には、抽象と具象、混沌と秩序といった対立を昇華させようとする葛藤が感じられる。血肉を画布にたたきつけたような作品の数々には見る者を圧倒する迫力がある。
1970年の三島由紀夫の自決を機に、戸嶋は名声を得ることのむなしさを感じ、より純粋に芸術を追求しようと、画業の場をスペインへと転じた。慣れ親しんだ秋田や武蔵野とは対照的な風土ながら、歴史の奥行きを感じさせる街のたたずまいや人々の容貌にひかれ、精力的に制作へ打ち込んでいく。背景に沈みこむような曖昧な輪郭を特徴とし、刻々と姿を変える時空の位相の中で、事物が存在することそのものへの哀歓が漂う。
積極的に自らの作品を世に問うたことがほとんどなく、多くの絵画はこれまで一般の目に触れる機会が少なかった。今回は油彩画や彫刻作品約120点のほか、写真や遺品など計200点以上の資料を展示する。本展をきっかけに生涯が広く知られ、孤高の画家への理解が深まることを期待したい。
(毛糠秀樹)
画面の右下から左上に向かってゆるやかな坂道が続き、道の右側には家屋が立ち並ぶ。日の光が差し込み、道を明るく照らしている。「秋田原景」と題されたこの作品を描いたのは、北秋田郡坊沢村(現北秋田市坊沢)を父祖の地とする洋画家 戸嶋靖昌(1934~2006)である。
戸嶋は父の赴任先である栃木県塩谷郡で生まれた。5歳の時に父を亡くし、母、弟、妹とともに坊沢村へと転居する。大館鳳鳴高校に進み、1953年に武蔵野美術学校へ入学するまで、幼少年期を村で過ごした。
「戸嶋は秋田で育ったことも誇りに思っていたし、それが縄文の土壌だということから、自分の血に縄文があると言っていた」。晩年の戸嶋を支援し、絶筆のモデルとなった戸嶋靖昌記念館(東京)の執行草舟館長によると、戸嶋は縄文土器やその生命観について、たびたび語っていたという。
戸嶋が暮らした県北部では、伊勢堂岱遺跡(北秋田市)や大湯環状列石(鹿角市)など、縄文時代の遺跡が多く発見されている。また、縄文土器に芸術的価値を見いだし、その造形は縄文時代の人々の生命力の表現であることを指摘した芸術家岡本太郎(1911~1996)の著書を、戸嶋は愛読していた。縄文の土壌に育ったと語る戸嶋は、縄文時代の人々の生命力を秋田の地で感じていたのだろう。
「秋田原景」を描いたのは65年。武蔵野美術大学彫刻科助手として働いていた戸嶋が、故郷に帰った際の作品である。暖かい日の光が降り注ぐ場所には、白の絵の具が用いられている。強い筆致で描かれ、画面の中で光を放っている。この白色は自然の中の生命力を表わす色として、後年、スペインの風景を描いた作品にたびたび登場することとなる。
戸嶋が初めてスペインを訪れたのは74年、40歳の時だった。スペイン各地を旅しながら、戸嶋は多くの肖像画を制作するが、そのほとんどが名も無き庶民をモデルにしたものであった。「アルバイシンの男―ミゲールの像―」も、その一つである。
闇の中から浮かび上がってくる男性の姿。輪郭線は黒い焔となって揺らめき、顔や首もと、手といった肌が露出している部分だけが淡く光を放っている。少し首を傾けた男性のまなざしは優しげで、手のひらを上に向けたしぐさは、対峙する者を温かく迎え入れてくれるかのようである。
戸嶋がスペイン・グラナダのアルバイシン地区の住むミゲールを描き始めたのは、83年の頃。戸嶋が「実に奥底に無欲のエレガンスを持っている」と語ったように、ミゲールは貧しいながらも気品を失わない人物だったという。外面ではない、ミゲールの内奥にある人間性に魅力を感じた戸嶋は、10年以上もの間、彼をモデルにした作品を描き続けた。
2000年に日本に帰国した戸嶋は、東京都稲城市の自宅で制作を続け、晩年は執行氏が提供した虎ノ門のアトリエでも制作を行うようになる。末期がんを宣告された後も制作意欲は衰えず、肉体はやせ細りながらも絶筆となる作品を完成させた。それからわずか半年後、その命を燃やし尽くしたかのように生涯を閉じた。
開催中の展覧会では、秋田で描いた作品から絶筆に至るまでの作品を展示している。戸嶋靖昌の画業と、戸嶋作品が持つ力強さを、会場で堪能していただきたい。
(公益財団法人平野政吉美術財団学芸員・佐々木佳苗)
×現在の日本は、歴史の様々な過程によって「人間とは本来どういうものか」という大前提を誤解して成立している社会です。
我々は人間ですから人間として生きるのは当然ですし、生活の中心にあるのが「人間を大切に扱う」ということであるべきです。
そして皆さんは人間として正しく生きるのがいいと思っているでしょうし、人間としての価値を発揮したいと思っているはずです。しかし、その人間の解釈の仕方をある時期から誤ってしまったのです。
僕は「真の人間とは何か」ということを長年研究してきました。
有史以来、文学において「真の人間」を目指す代表的な物語の一つに『ドン・キホーテ』があります。
その『ドン・キホーテ』をこよなく愛したスペインの哲学者にミゲル・デ・ウナムーノという人がいます。
彼は自身の著書『ドン・キホーテとサンチョの生涯』の中で、「本来の人間」というのについて定義しています。この定義が僕はものすごく好きなんです。この定義以上の本来の人間の定義はないんじゃないかと思っているんです。
それは「人間以上のものたらんと欲するときにだけ、人間は本来的な人間となる」というものです。
つまり、「人間でありたい」とか「人間として生きたい」では、人間にはなれない。人間は「不可能と思われることに挑戦し、人間には無理だと思うようなことに挑むのが人間なんだ」ということです。
これは歴史上の優れた人の人生を見ると本当にそう思います。
人間以上のもの、たとえば不可能を目指して不可能を成し遂げたいと思って死に物狂いで修行し、勉強し、そういう人たちの人生からポロっと出たものを、他者から見て「偉大だ」と言っている歴史があります。
例えば、ニュートンという人を我々は数学者、物理学者という側面で理解していると思いますが、実は彼は偉大な宗教家であり、熱心なキリスト教徒であり、錬金術師でもありました。
ニュートンはケンブリッジ大学の教授をしていたのですが、大学のチャペルに毎日1日一〇時間、祈っていたといわれています。
あれほどの物理学者が1日の大半を費やしていたのは祈りだったのです。そういう宗教的な生活の中から、ちょっとだけ出たのが「ニュートン力学」なのです。
実際に全著作を読むと、八〇%ぐらいは宗教関係の著作です。科学者としての著作は1割から2割あるかないか、そのぐらいです。
僕が言いたいことは、そういう過去の人たちが呻吟した魂が残したものを我々は利用して現代文明を築いているということなんです。それに気付いて欲しい。
最初に「人間の解釈の仕方をある時期から誤ってしまった」と言ったのは、偉大な発明や発見という成果だけで人間が解釈されているということです。本当は、苦しみ、慟哭し、呻吟するのが真の人間なんです。
現代で言うと、「生命の本質とは何か」とか「真の愛とは何か」とか、こんなことを考え出したら本当に苦しみます。
僕は文学青年でしたから、子どもの頃からそういう人生の根源的な悩みを抱えていました。でも、そういう苦しみを抱きながら生きていくことに、価値があると僕は思っているのです。
真の人間とは、現世の人間にはなかなかできないことを志向する人間です。永遠を志向し、愛を断行し、自己の肉体を何ものかに捧げ尽くさなければならないんです。これは「宇宙の神秘を解き明かすために生きる」ということです。
昔の人は信仰というものがあったので、今言った「呻吟する人生」を生きることができました。そういう人たちは本当に素晴らしい人生を送っています。
ただ現代人は、ある意味、神を失っているので苦しみ、もがく人生に何の意味も見出してません。
従ってその次元に到達するには、もっと深く宇宙のことや生命のことを勉強して、自分の生命の深源に突き進もうと思う気持ちがないと、真の人間にはほど遠いわけです。それをやることが現代科学の本来的な使命だと思うのです。これが僕の本来的な人間の捉え方です。
だから、今の時代は何が重要かというと、「青春の苦悩」です。これがやっぱり1人の人間をつくり上げていく原点じゃないかと僕は思うんです。
一言で言うと、「自分の命を捧げ尽くすものを追い求める」ということです。これ以外の悩みは「青春の苦悩」じゃありません。ただの自己固執、エゴイズムです。
「自分が認められない」とか「自分のしたいことができない」とか、そういう悩みは自分の欲望が達成されていないだけです。
悩みとは何か。呻吟とは何か。苦悩とは何か。それは「自分の命を捧げ尽くすものを探し求める」ということなんです。
そしてさらに大事なことは、その「苦悩」や「呻吟」の先にある「自分の命を捨てるに値するものを見つける」ということです。それが真の人間のやるべきことなのです。
これが見つからなかったら本当の人生ではないんです。本当の人生を送らないということは本当の死を全うできないということです。
「自分の生命よりも大切なものは何かを追求する」、これが真の人間の悩みということです。
(令和元年、福岡市で開催された「ヒトの教育フォーラム」での招待講演より/
取材・編集~水谷謹人)
僕には、小学生の頃から死ぬほど愛読してきた本があります。『葉隠』です。
8歳の頃にこの本と出会い、武士道に憧れ、そのまま大人になりました。今、六十八歳ですが、六〇年間、この本は僕の人生の最高位にある本です。
武士道を愛し、武士の生き方に憧れ、武士道で死のうと、若い頃から決めています。これができたら僕は自分の人生を成功だと思っています。
『葉隠』に触れると、現代人の「どうした、こうした」という話がみんな物質主義に見えます。我々はもっと世のため人のために自分の命をなげうって苦しんだ先人のことを学ぶべきです。
『葉隠』には三つの思想があります。
第一に「死に狂い」です。生きている限り目の前の現実に対して徹底的に体当たりするという思想です。将来のことなんか考えない。僕は会社の将来も、僕個人の将来も、家族の将来も考えたことはありません。どんなことが起きても全て僕の運命だと思って受け止める覚悟はできています。
キリスト教の言葉で「明日のことを思い煩うな」という、『葉隠』から取ったような言葉があるんですが(笑)、要するにキリストも同じ考えなんです。
二つ目は「忍ぶ恋」です。「到達不能の憧れ」のことです。到達できる憧れはただの欲望です。人間は、絶対に到達できないほど高貴で崇高なものに憧れなきゃ駄目です。現世的な例えで言うと、絶対に手の届かない異性に恋焦がれることです。
「忍ふ恋」は絶対に他人に理解できません。理解できるのは自分だけです。たとえ家族でも命の根源は絶対に分かり合うことはできないのです。自分が宇宙の根源と繋がるしかないです。それが「忍ぶ恋」の本意です。
これに近い思想は、パスカルが『パンセ』の中で言っている「ただ独りで生き、ただ独りで死ぬ」という思想です。
この覚悟がなければ「忍ぶ恋」は達成できません。
三つ目は「未完」です。みんな何かを成し遂げようとするから弱くなるんです。僕もそうでした。自分の志を成し遂げようとしていた時は精神が弱くなってました。
「未完」、すなわち「犬死にでもいい」と決断しなければならないんです。先ほど言った「他人に理解されない」というのも、「自分がしていることは他人から認められなくてもいい」と覚悟を決めないと、葉隠的な「未完に向かう本当の挑戦」はできないということです。
僕は埴谷雄高の『死霊』という文学が死ぬほど好きです。埴谷雄高の作品は、文学では絶対に表現できないものを描こうと決意して書いた文学です。
それは埴谷雄高も分かっているんです。分かっていて、その文学に若い頃から死ぬまで挑戦し続け、未完のまま死にました。ここに僕は痺れたんです。
埴谷雄高の『死霊』は難しいとよくいわれます。僕はそうは思いません。内容を分かろうと思ったことがないからです。内容なんかどうでもいいんです。僕は内容なんか興味ないです。
埴谷雄高は絶対に描けないと分かっているものに挑戦した、その文学者の心意気と毎日一緒に居たいんです。僕の文学への愛とはそういうものです。
(令和元年、福岡市で開催された「ヒトの教育フォーラム」での招待講演より/
取材・編集~水谷謹人~前号1面の続編です)
自分の人生を振り返って運がよかったと思うのは、子どもの時に「葉隠」という思想と出会い、それを信仰して生きてくることができたことです。
僕は、この世にある文学作品で読んだことがないものはないと言っていいほど文学に触れ、研究してきました。その結果、日本の武士道が人類最高の文化であり、これこそ真の人間を引き出せるものだと確信しています。
モーリス・パンゲというフランスの哲学者は日本の大ファンで、特に武士道のことを「運命への愛」という言葉で表現しています。武士道を研究してきたパンゲは「武士はどうしてあんなことができたんだろう」ということも含めて、「武士とは自分の運命を愛した人たちだ」と言っているんです。
つまり、「運命への愛」とは「自分の運命を生き切る」ということです。これは全ての人間の人生にとって一番重要だと僕は思っています。
皆さんは「武士」と言うと、「刀」とか「侍」をイメージするかもしれませんが、「葉隠」のいう武士道というのは問答無用に「自己固有の運命を生き切るということ」、「自分の運命に体当たりをして死ぬ」ということです。私もそのように生きたいと思っています。現代的武士道です。
僕は小学校の頃から、『葉隠』の中にある「毎朝毎夕、改めては死に改めては死ぬ」という言葉を毎日唱えていました。この言葉が大好きなんです。
この言葉を唱えていると「体当たりの人生」が面白くなってくるんです。体当たりをするとしくじることもあります。でも「毎日死ぬために生きているんだ」と思うと、「体当たり」のしがいがあるんですね。
僕の会社に創業から三十五年経ちますが、僕は今まで体当たりしかしていませんでした。その日の会社の問題も、その日に来たお客さんの接待も全力で体当たりしてきました。
売り上げを気にしたこともないし、いくら儲かったとかも一切考えたことがありません。それでも会社は順調に成長してきました。
毎日体当たりを繰り返していると、自分の運命が好きになります。不幸なことが起きてもそれを丸ごと受け止められます。だって自分の運命ですから愛おしいんです。
これからもし不幸のどん底に落ちることがあっても一向に構わないと思っています。それも僕の運命ですから。だからその現実を存分に味わいたいと思って日々を生きています。
そういう人生を死ぬまで続けられたら真の人間の最低レベルはクリアできるのではないかと思っているのです。
僕は、そんな生き方を貫いた真の人間の典型として三島由紀夫を挙げたいと思います。三島は、独自の文学と独自の死を築き上げた作家で、同時にすごく誤解された天才でした。
三島が一番優れていたところは誤解を全く恐れてなかったことです。それは三島が自分の運命を貫いていたからです。いかに不評であろうと、全ての批評を超越して、その最後にあのような死に方に向かっていった。その死も世間から批判されましたが、僕にはよく分かるんです。
独自の人生を貫いてきた人じゃないと、三島の死は絶対に分からないんです。
(令和元年、福岡市で開催された「ヒトの教育フォーラム」での招待講演より/
取材・編集~水谷謹人~前号1面の続編です)
三島由紀夫の作品の中で僕が一番好きな本が『美しい星』です。
「美しい星」とは当然地球のことです。これは昭和三十四年、まだ原発もなく、原子力が人類を破壊に導くという実感がない時代に書かれた幻想的なSF小説なのですが、ものすごいロマンティシズムに満ちた本です。僕はこの本の中に『葉隠』の「忍ぶ恋」を感じるんです。
この本の最後から5、6行にこんな言葉があります。「人間の肉体で、そこに到達できなくとも、どうしてそこへ到達できないはずがあろうか」
この言葉に出会った時、僕は『葉隠』がまた自分の腹にドーンと落ちました。人間というのは「あれは駄目だ、これは駄目だ」といろんなことをぶつぶつ言っている人は、肉体ばかり気にしている人です。
人間の理想というのは、やっぱり肉体を捨てる覚悟がなきゃ駄目だと思っています。
そもそも人間というのは魂が躍動している存在なので、肉体を捨てる覚悟ができると、その魂の中にある高貴なもの、美しいもの、清いものが輝き始めます。この魂の躍動を感じることができないのはなぜかというと肉体ばかり気にするからなんです。
肉体はいずれ捨てるものですから、諦めたほうがいいです。先ほどの三島の言葉はそれを現しています。
もっと深く説明すると、「そこ」というのは、これは僕の解釈なんですが、フランスの哲学者で、カトリックの司祭でもあるテイヤール・ド・シャルダンの言う「オメガ点」のことではないかと思っています。「オメガ点」というのは、人間の魂が最後に行き着き、それだけで一つの天体を創ると言われている宇宙の終末点です。
その宇宙の終末点が星であるかどうかは僕にも分からないんですが、天体になるだろうと言われているんです。それを「オメガ点」と言って、このオメガ点が三島由紀夫の言う「そこ」なんです。「そこに到達できなくとも」ということなんです。
「人間の肉体でそこに到達できなくても、どうしてそこへ到達できないはずがあろうか」と。
僕自身は、当然自分の肉体はいつでも捨てる覚悟はできていますから、肉体のことは考えたことがありません。
肉体をいつまでも生き長らえさせようとか、肉体をこうすればいいとかああすればいいとか考えたことがないんです。肉体が自分の意識の中から去っていくと、魂の中から宇宙的なもの、生命的なものが出てきます。それこそが愛の本質です。
三島もそういう人だったと僕は思うんです。この「人間の肉体で到達できなくとも」というところがやっぱり一番重要です。
そういう本当に高貴で、清く、美しいところに肉体を伴って行きたいと思っている人は一人も辿り着けないということなんです。それつまり現世的な成功を目指して生きているということです。または現世的な幸福ですね。
そんなことばかりを考えている人というのは崇高なもの、つまり人間の本質に到達できない。だから、それをいつでも捨てられる覚悟を持って生きなければならないということです。
(令和元年、福岡市で開催された「ヒトの教育フォーラム」での招待講演より/
取材・編集~水谷謹人~終わり)
人の精神的健康や心の健康問題にかかわるとき、援助職は、対象となる人の人生の文脈をとらえる必要があり、ぶれることのない対応が求められる。援助職としてぶれないためには自分の軸が大切となるが、この軸づくりは一筋縄ではいかず、究極のところ、人生とは何か、人間とは何かという哲学的な問いに直面していく。その答えも、自分でつかもうとしなければわからない難問だ。人生に試練や苦悩はつきものだとわかっていても、災害や思いもよらない困難に遭遇して、これまでの拠り所を失い、将来に希望を見いだせないことが、だれにでも一度ならず訪れるのではないだろうか。あるいは、平穏に暮らしていても、何の変哲もない日常に空虚感を抱くこともあるかもしれない。目まぐるしく変転する世の中で秩序が崩壊し、信仰が失われつつある現代社会に、生きづらさを感じない人のほうがまれなのかもしれない。
そのようなとき、何らかの大いなる力や働きの存在を信じることで、救われることがあるのではないだろうか。人生の意味を感じられない苦悩をスピリチュアルペインとよぶが、人のスピリチュアリティに焦点をあてたケアは、肉体的な死に臨む人だけでなく、精神的な危機状態のなかで日常生活を送っている人にも必要なのだと思う。市井の人々が困難に遭遇したときの支えとなるような、普遍的なスピリュアリティを共有できる新たな人間観は存在するのだろうか。
今から約50年前に提唱されたある人間観を見てみたい。一部抜粋すると「人間は、たえず生成発展する宇宙に君臨し、宇宙にひそむ偉大な力を開発し、万物に与えられたるそれぞれの本質を見出しながら、これを生かし活用することによって、物心一如の真の繁栄を生み出すことができる」というものだ。
これは、かつて日本の津々浦々にまで“家電”を普及させた松下幸之助(パナソニック創業者)により提唱されたものだが、物と心が調和したスピリチュアリティの豊かさが彷彿とされ、未来が開けていくような壮大さと、人間という生命のもつ潜在的能力を呼び覚まされるように感じる。半世紀を経てまったく古びないどころか、物質的に何不自由なく暮らしている現代人が、高次の生命的幸福を得るためのメルクマールとしての存在価値があるように思う。この国に暮らす多くの人が恩恵を受ける電化製品も、元はといえば松下幸之助が宇宙に潜む偉大な力を開発して、無から有を生み出した実例であろう。敗戦後の焼け野原から今日までの国家の繁栄を牽引してきた偉大な成果の根底に、このような人間観があったことは示唆に富んでいる。
本書では、思索家執行草舟による新たな幸之助像に迫ることができる。徹底した顧客主義から滲み出る「相手の幸せを願う真心」には崇高さが漂い、対人援助職として、この人の真の姿に触れることで得るものは大きい。国家的一大ブランドを築き、わが国に繁栄をもたらした松下幸之助だが、その晩年、物質的に満たされた日本を見て苦悩を深める様子も浮き彫りにされる。当時すでに物質的な豊かさだけが先行し、本当に築きたかった物心一如の繁栄は現実から遠いものとなっていた。地球規模の環境破壊が止まらない文明の袋小路に立たされている私たちは、憂国の思いから政経塾を立ち上げた実業家の打ち立てた人間観を吟味してみることで、何か立ち直るための突破口が見えるのではないだろうか。
物心一如の状態がこの世に現出した時、本当に豊かな社会が現出するという。そして、もし、松下幸之助が現代に生きていれば、物ではなく心を豊かにする商売をすると執行草舟は喝破する。自然の法則で与えられた「天命」は、物心一如の真の繁栄を生み出すことであり、それが「宇宙的使命」であるという。このような松下思想を考えることは、人がスピリチュアリティを志向することと関係が深いように思えるのだ。
著者の執行草舟は、仏教用語である「物心一如」について、物と心の平衡をとる要諦は、心が常に中心にあることだと説明しているが、ここでいう“物質”とは、目に見える財産や金銭的なものだけでなく、名声など世間で評価されるものをすべて含むとされている。この物質的なものに飲み込まれると、生命的な幸福が失われていくのだ。物質とは、それについて考えないようにしても、つい考えてしまうほど強いもので、私たちは物質のない世界のことは考えられないし、生活も物質抜きには成り立たないが、物質に心を奪われがちな弱さも自覚しなければならないだろう。
人間は幸せを追い求めるが、人間だけが味わうことのできる生命的幸福は、目に見えないものに気づき、スピリチュアリティを発露することであり、物心一如の調和した豊かさは、与えられた宇宙的使命に生きるなかでつかむものである。松下幸之助の悲願とその真心から提唱された人間観は、次の文明で新しい人間になる人類へ希望を与える。真の生命的幸福は、物質では得られないことに、現代人は少しずつ気づき始めている。物質的価値に侵された精神が、心の空虚さを埋める何かを欲しているからに違いない。
幸せの定義は人によって異なるが、人間の生命的幸福は、利他の営みでしか得られない。人類が築きあげてきた崇高な価値のうち、何に自己を投じるのかを定め、投じられる自己を築かねばならない。そして、人として生かされてきた私たちが、人生の終焉を迎えるとき、自己に与えられた役目を果たし得たという実感だけが、宇宙に還元されていく魂を癒すのだろう。私たちは、先の見えない社会に生きる現代人の生命的な幸福をとらえ直し、人間観を再考する時期にきている。真の人間の幸せとは何か、あまたの哲学書にはない日本的心性に基づく松下思想に、ぜひ触れていただきたい。
×先日参加したビジネスセミナーでのこと。開始時間になっても参加予定者のうち2人がまだ到着していなかった。1人からは「遅れます」というメールが来たが、もう1人からは連絡なしとのことだった。
その時、「昔はどうしてたんだろう?」という話になった。昔というのは携帯電話やスマホがなかった時代のことだ。
たとえば、駅で待ち合わせをする。何かの事情でどうしてもその時間に大幅に遅れるなんてことは誰しもが経験したことがあるのではないだろうか。そんな時、待つ側も待たせる側も平常心ではいられなかったはずだ。
「昔は駅構内に『伝言板』があった」という話も出た。そこにチョークで「先に行きます」とか「駅前の喫茶店にいます」などと書く。ただ遅れてきた人がそれを見てくれたらいいが、見なかったら悲劇である。
さらに言うと、「渋谷ハチ公前」のように連絡手段のない待ち合わせ場所の時はどうだったか。デートの約束なら1時間でも待つだろうが、ビジネスの約束だと信頼を失うだろう。
待ち時間も自分の人生の一部、貴重な「自分の時間」である。何分くらい待てばいいのか分かれば、その時間を有意義に使うこともできるが、分からないと、ただイライラするだけの時間になる。
「自分の時間」を何にどう使うかは人生における極めて重大な問題だ。
女性アニメーターの草分け、奥山玲子(故人)をモデルにしたNHKの朝ドラ『なつぞら』が佳境に入ってきた。主人公なつが仕事と家庭の両立に向けて奮闘中である。
かつて女性は、結婚や出産を機に退職するのが通例であった。ドラマの中でも妊娠したなつに、「契約社員になれば時間が自由になり、子育てがやりやすくなる」と提案する社長に対して、「正社員として仕事を続けたい」と迫るなつ。仲間の応援もあってなつの主張は認められるが、産休明け早々、なつは長編アニメの作画監督を任せられる。
「自分が、後に続く女性たちの道を拓くんだ」と奮起した以上、後には引けない。それまでの「仕事か家庭か」ではなく、「仕事も家庭も」を選択するなつである。
時代背景は昭和40年代だが、今日の「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」という時代の流れとうまく嚙み合わせているようにも思える。
文筆家・執行草舟さん(69)の著書『生くる』(講談社)に「自分の時間」を考察する章がある。こんな言葉で始まる。
「現代人は『自分の時間』を誤解している。それにより多くの人が何よりも尊い、自分に与えられた生命の燃焼に支障をきたしている」と。
どういうことかと言うと、たとえば「仕事が忙しくて自分の時間がない」とか、「人生を時間単位で売り買いする」という発想がとんでもない誤解であるという。
執行さんは菌酵素食品の研究・製造・販売を手掛ける㈱日本生物科学および㈱日本菌学研究所の社長である。33歳でこの事業を興した。創業の少し前に子どもが生まれ、その3か月後に妻を亡くした。
多くの人は「小さな子どもを抱えながら仕事をしていくのは大変だろう」と思う。しかし執行さんは「逆だ」と言う。
「子どもがいたから事業もやってこれた。家で子どもの世話をしたり、寝顔を見たりして気力を取り戻していた。自分の時間がないと考えたことは一度だになかった」と当時を振り返る。
「事業は私の時間が社会に役立っている喜びを与えてくれた。子どもの存在は私が一人の人間として生きている実感を与えてくれた。事業や子育ては、自分の時間を奪うものではなく、自分の時間を有意義たらしめてくれるものであった」
そしてこう断言する。「仕事や家族との時間は『自分の時間』の代表的なものだ。人生における有意義な時間の過ごし方とは、仕事と家族に多くの時間を当てることである」と。
×北秋田市出身の画家戸嶋靖昌さん(1934-2006)の作品が中心の絵画・彫刻展「内なる力―火と土と」が、東京・麴町の食品会社「バイオテック」本社ビル内にある戸嶋靖昌記念館分館で開かれている。戸嶋さんと親交が深かった同社社長で、記念館の執行草舟館長(69)のコレクションの中から選ばれた約50点が並ぶ。
会場には、戸嶋さんの油彩画と彫刻30点に加え、戸嶋さんの大学時代の恩師である画家山口長男の抽象画7点が並ぶ。このほか岡本太郎さん(1911~96)作の焼き物や、サルバドル・ダリ(1904~89)のリトグラフなど、世界的に著名な芸術家の作品も展示している。
戸嶋さんは坊沢村(現北秋田市)生まれで、大館鳳鳴高を経て武蔵野美大を卒業。1974年からスペインを拠点に制作に打ち込んだ。
帰国後の2000年に執行館長と出会い、絶筆となった肖像画のモデルにするほど親交を深めた。執行館長は「戸嶋の作品には、秋田や東北に今も残る日本人の根源的な魂、情熱が感じられる。それが人を引きつける」と話している。
回帰は9月28日まで。入場無料。鑑賞希望の場合は事前連絡が必要。予約、問い合わせは同館03-3511-8162(小松田直嗣)
×日本人なら、武士の生き様をかっこいいと思われる方は多いのではないだろうか。精神看護学を専門として大学で教育研究に携わる中で「人間の精神の健康とは」という問いを考えていくと、究極のところ“人間とは何か” “人はどう生きるべきか”という哲学や宗教に答えを求めざるを得なくなる。日本人の健全な精神性を育むために欠かせない日本文化の精華として“武士道”に着目していたが、本書に触れ、それは確信へと変わりつつある。臨済宗円覚寺派の横田南嶺管長と実業家で著述家でもある執行草舟氏が、禅と武士道をテーマに語り合った対談本は、現代日本において歴史的価値のある書物だ。日本の伝統文化に一家言をもつお二人の言葉は、いちいち為になり、かつ味わいがある。我が身が武士らしく生きているかといえば、「死ぬことと見つけたり」の実践は容易ならざるものだが、それでも、本来のあるべき姿を知っておくことは、精神の健康に資するものと感じる。
例えば、わからないことを強いるという意地悪さが禅の本質で、この「精神の毒」も人間には必要なのだそうだ。深みのある人生を送るために必要な薬が禅なのだと知ると、俄然、禅に親しみたいという意欲が湧く。そして、清濁併せ吞む度量の大きな禅僧のエピソードは、実に豪快であり、私たちの気持ちを強くしてくれる力があるように思う。ある弟子が「悟りとは何ですか」と尋ねると、師匠が「わしは耳が遠い。何を言っているか聞こえん。もっと大きい声で言え」と応じる。それではと、「悟りとは何ですかっ!」と大きな声で再度尋ねる弟子に「うるさい」と一言で片付ける。これで終わりである。このような禅問答の意地悪さは、現代の教育界では受け入れられないだろう。趙州という有名な禅僧と修行僧の問答の実話である。他にも多くの実例が紹介されており、このような否定の体験を幾度となく繰り返しながら、合理や理性を突き破り、その上の生き方を掴み取っていくのが人生の醍醐味だと感じられる。
武士道と禅は、交錯しながら日本民族の精神性を練磨してきた。平和な現代社会で、“武士道とは、死と隣合わせで生きること”という情報を大脳新皮質に与えてみても、精神にさほどの変化は訪れないだろう。便利な情報社会を生きる我々が、“日々死を思う”という理想論を掲げようとしても、聞き流すか、あきらめるか、二の足を踏むかで、所詮は損得勘定から抜け出すことすら難しいのかもしれない。しかし、真理を知りたいという欲求や、自分の運命を生きたいという願いは、誰もが抱いているのではなかろうか。運を拓くには、物質科学で考えられる正解を求めるより、目前に来たことに向き合い、結果の是非に囚われないで体当たりでぶつかる武士道精神こそが重要なのだ。かつて、中国の皇帝が、鉄製の牛を作って川底に沈め、黄河の氾濫を防いだという。横田管長は、この話から“禅の心は鉄牛のような働き”だと教えてくれる。そして、執行草舟の思想を、世の中の流れに全く乗らないものであり、底に沈んだ鉄牛のように微動だにしないことで、今日の時代の激流の中で間違った流れを正していくと称している。本書は読者に禅と武士道という羅針盤を与え、現代に翻弄されない鉄牛の精神を導く一期となるに違いない。
×日頃よりご指導戴いている執行草舟先生より「革命家・予言者」としての松下幸之助という全く新しい解釈についてご示唆を戴いた。彼が『繁栄を通しての平和と幸福』というPHP理念を唱えたのは一九四六年で、日本は敗戦により貧しさの只中にいた時期だった。おそらく当時の日本人にとっては、お伽話や夢物語にしか思えなかったはずだ。このような時代にあって、繁栄に向かう決意と希望を掲げ、それを実践した彼は、もはや「革命家」として捉えることができる。また、この時代の誰の目にも映らなかった日本の繁栄の姿を見据えていたという意味では「予言者」としても捉えることができる。
さらに、PHP理念の提唱から三十年余が経過した一九七九年、松下政経塾設立時に起草された趣意書の中にも、その当時の日本の現状を憂うこんな一節がある。
《日本の現状は、まだまだ決して理想的な姿に近づきつつあるとは考えられない。(略)物的繁栄の裏側では、かえって国民の精神は混乱に陥りつつあるのではないかとの指摘もなされている。》
この趣意書は、バブル景気の絶頂期が始まる前に書かれたにもかかわらず、幸之助は、まるで平成末の日本の混迷の理由を言い当てるかのように、日本が物的繁栄を成し遂げた後の精神の混乱を憂いている。まさに「現在に生きる予言」であり、彼の「革命家・予言者」としての側面を垣間見ることができる。
では、なぜ幸之助は、「革命家・予言者」に成り得たのか。これは、彼の魂の中に高貴性と不良性の両輪が存在していたことが非常に大きいと思う。
まず、高貴性については、幸之助が反自己の人であったことが深く関与したと思う。彼は、自己観照を怠らず、決して自己に満足せず、常に渇望感を持ち、絶えず求め続ける人であった。
また、丁稚時代や大阪商人として鍛えられた頃に、石門心学を通じて会得した武士道精神が、彼の高貴性と不良性の根源にある。武士道精神の本質とは、他者のための自己犠牲のことである。
さらに、彼が二十歳までに家族のほとんどを亡くしているという不幸な境遇や、丁稚時代から、非常に厳しい大阪商人の世界を生き抜いてきた経験、そして戦後、GHQから理不尽な財閥指定を受けた際の公への怒り(公憤)などのように、呻吟と悲哀を味わい尽くしたことで、たたき上げの反骨精神ともいえる不良性は生み出された。
私が初めて幸之助に出会った時の率直な印象は、「笑顔の中でも目が笑っていない。なんという怖さと迫力だろう」というものだった。しかし、今思えばあの怖さの背景には、日本の将来に対する強烈な憂国心があったのだと感じる。
現代の日本では、良いものと酷いものとを極端に分ける傾向がある。しかし、この二つの交錯なしには、物事の本質を捉えたり、事を成すことはできない。崇高で気高い理念は、清濁併せ呑むことによってそそり立つ。彼が、高貴性と不良性という両義的な精神性の中で、善悪をこね合わせ、そこから光輝くものを作り出す力を持った稀代の人物であったからこそ、「革命家・予言者」に成り得たのではないか。
私は、「革命家・予言者」としての松下幸之助という解釈に強烈な示唆を受け、松下政経塾の副理事長として、次に迎えるであろう大変革の時代に、立ち向かうことができる真のリーダーの育成に微力ながら尽力する所存である。
×看護系大学で教員をしているが、入試の面接時に高校生の読書傾向を聞いてはいけないことに違和感を感じて久しい。そのようななか、この『夏日烈烈』という白熱の対談本は、古今東西の名著を読破する若き医学生佐堀氏と、知識層の間で知られる思索家執行草舟が、本音でぶつかりあった真実の書として存在感を放つ。医療人にとっての読書の意義を実践的に示す類いまれな良書と感じる。看護者はそれぞれの看護観をもち、看護を実践する。その人間性を支える豊かな土壌を育むのが読書ではないだろうか。500ページを超える対話のどこを切り取っても価値ある内容ばかりだが、独断と偏見で一部をあげるとしたら次の箇所だろうか。
(執)今の人は、生命って、肉体だと思ってるんだよ。(佐)そうですね。(執)もちろん魂も入ってるけども、魂だけですらない。今僕が喋っている言葉も、それ単独で生命を持っている。そういうものがわからないと、「人間の実存」というのは把握することはできないというかな……(中略)実存というのはこういうことですよ、と言ったら、何を言おうが間違いなの。(佐)生命というのは無限変転、流動だから、言った瞬間に間違いになってしまう……。(執)そうなんだよ。だから、無限流動の文章の中から、その場その場で自分なりに掴むしかないわけなんだ。禅でいう「寥々たる天地の間、独立して何の極まりか有らん」ということだよ。全ての事象・現象にそれ固有の生命があるんだ。生命とは、その独立した一回性の燃焼なんだよ。
看護を志す学生との出会いも、臨床実習での学生と受持ち患者との出会いも、すべてが一回性であり、看護実践も一人の看護師と一人の患者との関係性のなかで繰り広げられる唯一無二の無限変転する流動的なものである。今ここで、生命を育む気持ちで目前の仕事に打ち込むことが、自身に与えられた生命を最大限に生かすことにつながることに気づかされる。しかし、何かに向き合えば必然的に葛藤が生じる。これを乗り越える自身の軸の確立には、過去からの文明を引き継ぐことが欠かせない。そのような読書をしてきた日本人の魂から紡がれた「生命」「人生」「文明」への透徹した思索に、対話という身近な形で触れることのできる魅力的な一冊である。
×真の文明とは何か、それを問いかける一冊である。著書はその核心に「義」を据えているのだ。義に生きた人々と、著者の魂が語り続ける。その魂の躍動が、読む者の胸に突き刺さってくる。久々に読み応えのある本を読んだ。びっしりと詰められた重力が伝わってくる。実際に、この世を生きた日本人たちが生み出した義の重力が、我々の魂に迫ってくるのだ。日本人の心に沈潜する清冽な悲しみが喚起されてくるに違いない。
著者の愛する歴史上の人々には共通項がある。それは、不遇を一顧だにしないということに尽きる。不幸を厭わぬ勇気と言い換えてもいい。文明社会の中にあって、自分が義だと信ずるもののために、人生を捧げた人物たちが本を狭しと舞っているのだ。義によって、文明を支えた人たちの悲哀を著者は追悼しているのだろう。その人々が味わった不幸に、切ないほどの共感を著者は抱いている。義を貫くとは、不幸を抱き締めることである。我々は、それを思い起こさねばならない。
貫くべき義は、情の上に成り立っている。いや、情を克服したところに存在しているのだろう。私は本書を読みながら、日本的情愛というものを強く感じ続けた。情愛に泣き、情愛の悲しみに沈む者にして、初めて義を貫くことが出来るのだ。切なさと不幸に寄り添うことによって、初めて義が文明の中を貫徹するのである。日本的情愛をどう超克するのか。それが、本書を著した著者の目的の一つではないだろうか。本当の情愛に裏打ちされた義こそが、文明の将来を担うのだ。
著者は28年前、その『内村鑑三』によって文壇に登場した。それ以来、私の最も愛する文芸批評家であり続けた。著者を貫く精神には、確固たる「良心」がある。その良心は、歴史を貫徹する民族の雄渾な精神にあると感じている。そしてその精神をこそ、著者は「義」と呼んでいるのだろう。著者の愛する人たちが連なる本書は、そういう意味で著者自身の分身なのではないか。著者のもつ「義」が、日本の歴史を貫く「良心」として煌めいている。
×東京・六本木のスペイン大使館で12日から開かれている企画展「いま、ウナムーノを問う」で、スペインで長く活動した坊沢村(後の鷹巣町、現北秋田市)出身の画家戸嶋靖昌さん(1934~2006年)の作品28点が展示されている。
同展は、スペインを代表する思想家ミゲール・デ・ウナムーノ(1864~1936年)の功績をたたえる資料を展示。98年まで24年間同国に住み、ウナムーノの思想に影響されたという戸嶋さんの代表作の油彩「ロペスの像」「老女ベルタ」「街・三つの塔―グラナダ遠望」なども出展された。同じ趣向の企画展は5月中旬から1か月、スペインのサラマンカ大学内の日西文化センターでも開かれており、今回はその日本版。
11日夜に開かれた式典では、ゴンサーロ・デ・ベニート駐日スペイン大使や田中克之元駐スペイン大使のあいさつに続き、戸嶋さんの作品を所蔵する「戸嶋靖昌記念館」(東京・麹町)の執行草舟館長が「戸嶋はウナムーノの思想で自らの芸術を支えた」と紹介した。
式典に招かれた戸嶋さんのめい、横浜市の廣瀬美穂子さん(53)=旧姓戸嶋、北秋田市坊沢出身=は「たまにスペインから帰省する伯父が絵描きだとは知っていたが、素晴らしい絵を描いていたことは亡くなるまで知らなかった。伯父の作品を広めてくれた執行館長に感謝したい」と話した。
戸嶋さんの作品はF50号(117センチ、91センチ)級の大作を中心に展示。暗い絵の中から訴えるような視線を向けた肖像画が注目を集めていた。
同展は10月9日まで。入場無料。月―金曜日は午前10時~午後5時、土曜日は午前10時~午後2時。日曜日と9月17日は休館。(中田貴彦)
×スペイン文学におけるもっとも偉大な宗教詩の扉を開くにあたり、読者にはまず、扉前に付された絵画「十字架上のキリスト」をじっと見つめて欲しい。1913年、ミゲール・デ・ウナムーノ(1864-1936)が詩作をはじめた当初、本書のタイトルは「ベラスケスのキリストを前にして」だったからだ。
スペインの宮廷画家、ディエゴ・ベラスケス(1599-1660)の磔刑画を見て一番に覚えるのはその浮遊感ではないだろうか。黒一色に塗りつぶされた背景のせいで、白く輝くイエスの身体が十字架とともに画から浮き上がって見える。同時代のルーベンス(1577-1640)の、たとえば「フランダースの犬」のネロ少年が最後に見たアントウェルペン大聖堂の祭壇画と見較べると違いは明らか。ベラスケスの画からは、一切の背景が、人物も地上物も排除されている。そのため、磔刑のシーンが時空間を超えて我々にせまってくる。
さらにベラスケスのキリストには、ルーベンスの画に際立つ身体のよじれがまったく見られない。伝わってくるのは磔刑の苦しみより、美しいまでの静謐さである。対してスペインの教会内を飾るバロック時代の磔刑像では、キリストの苦しみが、傷口や流れ出る血まで生々しく再現され、目をそむけたくなるほど迫真的に表現されている。ウナムーノ自身、同郷の画家イグナシオ・スロアガの「血のキリスト」(1911)を「スペインに典型的な」、「土気色で、血まみれの」、「最後の一滴まで流血しきった」キリスト画だと讃えている。
ではなぜウナムーノは、この、スペイン美術において異質とも言えるベラスケスのキリスト画を選んだのか?その鍵は、詩作を始めた前年(1912)に発表された哲学的エッセイ『生の悲劇的感情』に見出せる。プロテスタンティズムにとってバッハの音楽がもっとも強烈な芸術表現となっているという見解に対し、ウナムーノは、「カトリシズムの、少なくともスペインのカトリシズムの最高の芸術的表現は、[……]ベラスケスの『十字架上のキリスト』に、あの、われわれに生命を与えんがために、常に死につつありながら、決して死にたえることのないキリストに見られる」と述べているのだ。
つまり、ウナムーノが本詩集で意図したのは、キリストの苦悩を描いて、憐れみを喚起し、読者の信仰心を煽ることではなかった。彼はベラスケスのキリストこそ、「死につつありながら、決して死にたえることのない」という不条理、還元するなら、永遠に死滅しないことへの渇望、不滅性への信仰を「我々」に呼び覚ますことができると考えたのだ。キリストの美しい磔刑画を愛でることによって、「我々」が終わりのない生を信じるよう、ウナムーノは思索/詩作をめぐらしていく ―
[ベラスケスの]この筆によって我々は今、肉体となった汝を見ることが出来る
汝は永遠の「人」であり、我々を新しい人間へと生まれ変わらせてくれる
[……]
私の悲劇的な民は、ここに線と色彩で語る
この沈黙の白い言葉の中に生を吹きこまれ、その信仰を告げ知らせる(Ⅰ、一)
全八九編の詩は、四部から構成され、第Ⅰ部 神を啓示するイエスの生の素描、第Ⅱ部 イエスの死の劇性、第Ⅲ部、ベラスケスのキリストを(冠、頭、髪から脇腹の傷、膝、足まで)見つめながら、復活について思索、第Ⅳ部 人間の救済や神の王国といった概念についての考察へと至り、ウナムーノ自身の絶唱で終わる ―
私を愛してくださる汝よ、
見てください
私がどれほど病に苦しんでいるかを
汝は復活である。そして生そのものと成ったのだ
ラザロを呼び寄せたように、汝の友たる私を呼び寄せてください
(Ⅳ、最後の祈り)
本作の価値は、もちろん、霊魂の不滅性についての思索にとどまらない。詩として、カスティーリャの荒野(メセータ)を謳い上げたウナムーノの詩才も是非、感得していただきたい。まず第一に、白/黒、光/闇、生/死、言/沈黙、精神/物質、魂/肉体といった、二つの対立する概念によって劇性を高め、最後にその二元性を解消する存在イエスを登場させる ―
汝は、死から蘇った最初の人間である(Ⅳ、一)
汝の沈黙は、天国を満たす承認の言葉となっている(Ⅳ、三)
さらに、ベラスケスの画に際立つ<白>が同系の<銀>とともに全編、とくに第Ⅰ部を覆いつくす ― 白い「夜明け」、イエスの「白い身体」(十二)、「五つの白い花弁をもつ薔薇」(十三)、「神の白い子羊」(十六)、砂漠の畝に稔った小麦で作られた「白い聖体」(十七)、「白い鷲」(二十)、砂漠の「白い獅子」(二十二)、「暗黒の中を流れる、生きた銀色の血管」(十四)「太陽に照らされ剣のように煌めいている……白い焔」(二十七)。すなわち、白という色彩を介して、さらなるシンボルを引き寄せ、すべてのシンボルを連鎖させていく。まるで「アレゴリーの織物」を編んでいくかのごとく。このように、対義語と色彩的白さを介して象徴体系を造りあげていく手法は見事としか言いようがない。
ところで、この詩集を読み終え、私はひとつの疑問を抱いた。果たして、当時のスペイン読者に彼のメッセージは届いたのだろうか?なぜなら、『ベラスケスのキリスト』を解するには、聖書やキリスト教の伝統、その上、スペイン各地の伝説や習俗に関する膨大な知識を要するからである。そういう意味で、単なる翻訳者ではない、博学多才かつ緻密な解釈者を得た日本の読者は、幸いだと言えよう。 (明治大学法学部教授)
×人間の本質は、“憧れ”に向かって生命を燃焼させることにあると語る著者。喜怒哀楽の感情を超えた先にある“魂”―― つまり、「命よりも大切なものがある」などの人間特有の精神性が、人間を人間たらしめるのだと言う。そして、その思惟こそが憧れの概念である。
本書では、『葉隠』をはじめとする日本古来の武士道や、初期キリスト教の殉教者など、古今東西様々な人物や話をもとにそれを説いていく。
世の中には自分の力で解決できないことが多々ある。たとえば、母が子を思う気持ち、PK戦でチームメイトが祈る気持ち―― これらは、自分の力が及ばないと無意識に悟ったときに、人間の心の中に自然に生まれる祈りの心、自己を超越する何者かへの想いに他ならない。これも一つの憧れである。そこに身を委ねる謙虚さを持った“生き方”を今後も目指したい。
×これは美術書ではない。17世紀スペインの画家ベラスケスが描いた傑作「十字架上のキリスト」(プラド美術館蔵)に触発されて、19世紀末から20世紀前半に活躍したスペインの詩人ミゲール・デ・ウナムーノが、1920年に著した壮大な長編詩の待望の日本語訳である。
本編は全4部からなるが、第3部では、頭、髪、額、目、耳など磔刑のキリスト像の細部が丹念にかつ克明に言葉で描写される。そこに頻出するのが色彩の白。例えば「聖体のように白い汝の身体」や「汝は天国の白い門」といった表現に代表されるように、白を表す言葉が本書の底流にある。
この白はたしかに迫真のリアリズムでキリストの肉体を描いたベラスケスの絵画に発している。だが絵画を見れば腰布の方がより白く描かれていることは明白だ。つまりウナムーノの発話する白は、単なる色彩としての意味を超え、ベラスケスが描いた肉体が生と死を超えた超越的なものであることを示している。
こうしてウナムーノは、この静謐な磔刑像が秘めている痛み、苦しみ、喘ぎ、乾きなどを言語のリアリズムで執拗に積み重ねながら、いつしか読者をも生と死の彼岸へと誘っていく。
随所に聖書の引用がちりばめられており、一見難解にも思える。しかし、個別の宗教を超えた、より普遍的な人間の本質に迫ることが詩人の真の狙いであろう。
日本から遠いスペイン、そして日本人から遠いキリスト教についての知識を持たなくても、この詩は肉体的な受難を超えたところにある心の救済に、全ての人々を誘う力にあふれている。あたかも、宗教についての知識を一切持ち合わせていなくても、宗教画の持つ造形的魅力を味わうことができるのと同じように。
この長大で深淵な詩は一読して味わい尽くせるものではない。口絵として掲げられた色刷り図版との対話を繰り返しながら、時間をかけて味わい尽くしたい本である。
評・山本和弘
美術評論家(東根市出身)
スペインで長く活動した坊沢村(後の鷹巣町、現北秋田市)出身の画家故戸嶋靖昌さん(1934~2006年)の作品展が15日まで、スペイン西部のサラマンカ大学・日西文化センターで開かれている。戸嶋靖昌記念館(東京・麹町)の安倍三﨑学芸員は「肖像画は『人間の内面や情熱が表現されている』と好評だ」としている。
サラマンカ大はスペイン最古の大学で、作品展は創立800周年を記念して先月17日に開幕。大学総長を務めた思想家ミゲール・デ・ウナムーノ(1864~1936)の文章と並べ、記念館所蔵の肖像画や風景画など油彩約50点を展示している。戸嶋さんは98年まで24年間スペインに住み、ウナムーノの思想の影響を受けたという。記念館によると、スペインでの戸嶋作品の公開は始めて。
スペイン政府が東京・六番町に設立した文化施設「セルバンテス文化センター東京」で昨年5月に戸嶋さんの作品展を開いた際、在日スペイン大使館員が戸嶋さんとウナムーノの関係性を知り、記念館に開催を持ち掛けた。
作品展は地元紙でも取り上げられ、関心を集めている。とりわけ肖像画は、暗く粗い画調から見る者に訴えるような視線を向けており、人気が高い。地元紙ではベラスケスやゴヤら現地の画家に筆致を例え、「『自分とは何者か』というウナムーノの問いを反映」「素朴な人の魂を模索」と報じた。現地の市井の人を描いた「ロペスの像」「老女ベルタ」「子供を抱く女」なども好評という。
安倍さんによると、日西文化センターは1999年開場以来、1か月の催しの最多来場者が1200人だったが、今回の作品展は開幕21日目の今月6日までに1531人を集め、過去最多を更新した。
東京・六本木の在日スペイン大使館は9月に日スペイン国交150周年を記念したウナムーノ展を開催予定で、その際も戸嶋さんの作品が展示される見込み。(中田貴彦)
×今年は日本とスペインの外交関係が樹立されて150周年。さらに、スペイン最古の大学であるサラマンカ大学創立800周年にあたる。これを記念してさまざまな文化事業が繰り広げられている。目玉は東京・上野公園の国立西洋美術館で開催中の「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」だろう(5月27日まで。次いで神戸市の兵庫県立美術館で6月13日から10月14日まで開催)。
サラマンカ大学の総長を務めた思想家・詩人、ミゲール・デ・ウナムーノ(1864-1936年)の哲学を読み解いた佐々木孝さんの『情熱の哲学 ウナムーノと「生」の闘い』を今年復刊した法政大学出版局は、新たにウナムーノの長編詩『ベラスケスのキリスト』(執行草舟監訳、安倍三﨑訳、2700円+税)を刊行した。
スペイン黄金時代を代表する画家、ディエゴ・ベラスケス(1599-1660年)の「十字架上のキリスト」に感応したウナムーノが言葉を紡いだこの長編詩は、ヨーロッパの古典的教養抜きにとても理解しうる作品ではないため、誰も完訳をこころみることがなかった。
「ヨーロッパの古典的教養を備えた本物の文化人の最も重要な長編詩の日本語訳が、訳者たちの並々ならぬ努力で初めて実現した」と同出版局の郷間雅俊さんがいうように、本書400ページのうち、3分の1が丁寧このうえない注釈と引用聖句に費やされている。「なんとしてもこの作品を現代の日本人に紹介しなければならぬ」という監訳者と訳者の強い執念が感じられる。
米西戦争(1898年)の敗北で完璧に打ちのめされたスペインにおいて、「スペインとは何か」「人間存在とは何か」と問い続けたウナムーノはこの長編詩で、死から永遠の生に向かう道を歌う。「スペイン同様に後発の文明国である日本の読者にとっても、共感できるところが多いのでは」と郷間さん。
イエズス会のホアン・マシア神父による解題を読んだうえで船出し、注釈をコンパスに風を帆にはらませれば、難破から免れられるかもしれない。航海を終えたとき、読者は新たな世界観を手にしているはずだ。
×ミゲル・デ・ウナムーノとは何者か? 1864年に生まれ、1936年に亡くなったスペインの哲学者・詩人である。スペイン最古のサラマンカ大学の総長も務めた。
1588年に無敵艦隊がイギリスに敗れ、凋落の一途をたどっていたスペインは、1898年にアメリカとの戦争に敗北して海外植民地のほとんどを失う。近代化の遅れが原因なのは明らかだった。当然のように国内では近代化論争が起こる。誰もが「バスに乗り遅れるな」と叫ぶ中で、彼は「発明は彼らにまかせておけ!」と言い放つ。「彼ら」とは科学文明の進んだ英米独仏のことだ。自分たちにはそれより大切な使命があると彼は考えた。「使命」とは、人間本来の生について思索することだ。神の代わりに理性を信仰する近代人は科学文明を生み出し、生活を快適にしていったが、まもなく科学文明が人間の生を支配するようになる。彼はこれに徹底的にあらがうのである。
本書はそんなウナムーノの最高の入門書である。41年前に講談社現代新書の一冊として世に出たが、まもなく絶版となった。ウナムーノの思想が自身の血となり肉となったと信ずる著述家の執行草舟氏が、著者の佐々木孝氏と「ウナムーノ著作集」全5巻を出していた法政大学出版局にかけあって復刊にこぎ着けた。
スペインの哲学者というとわれわれはすぐに、『大衆の反逆』を著したオルテガを思い浮かべる。オルテガの精緻な論理は、合理主義に骨の髄まで侵されたわれわれに理解しやすいからだろう。ところがウナムーノの著作は日本人にとってはかなり手ごわい。なぜならパッションがほとばしるあまり論理が飛躍することがしばしばあるうえに、スペイン神秘思想につながるところもあるからだ。
若いころ神に仕えようとした佐々木氏は、ウナムーノのパッションを愛を持って受け止め、その思想の核を日本人に分かりやすく伝えていく。
世界は乾いている。その原因は理性信仰の蔓延にある。本書をきっかけに、一人でも多くの日本人がウナムーノ思想に関心を持つことを願う。
×現代版「生命論」のバイブル
~1,000ページにわたる重厚な大書から響く生命の実存~
執行氏の目指す「生命の理念」は、自らが自己の生命力を高めていく躍動的なものである。科学偏重主義の精神への影響に警鐘を鳴らさんとする祈りが通底している本書は、文明の潮流を俯瞰しつつ、矛盾撞着を生きる人間生命の発露を論理的哲学的に解明した百科事典のようでもある。
人間の生命を西洋医学一辺倒ではなく、東洋医学にも偏りすぎずに見事に捉え、膨大な知識体系と実体験に裏付けされた理論が展開されている。
とくに「生命エネルギー」と称す概念は、宇宙に生かされる生命の神秘を見事に喝破する。生命エネルギーとは「物質を集め、凝縮させ、それを動かす力」の総称で、この世で唯一無二の存在である自分を自分らしくたらしめる力であり、人はまるで磁石のように宇宙に遍満する生命エネルギーをキャッチできるという。我欲に生きれば邪なものが引き寄せられ、無心に使命に生きれば高貴なものが引き寄せられるのだろう。「生命の理念」から見れば、奥底の魂は、崇高な生命エネルギーを凝集させ、価値ある使命に身を投じることを望んでいるのだ。本書を通して、生命の神秘に触れ続けたい。
×― 執行先生、三枝先生、本日はよろしくお願いします。
平成30年の幕開けですね。二月には冬季オリンピックが開催され、各国のアスリートが自らの限界に挑む姿を見られることと思います。
「限界」と言いますと、達成する毎に更新されることを考えると、完成形はない、つまり「未完」と置き換えられるかと思います。
未完に挑む姿には気品も感じられるかと思うのですが、気品ということからお聞かせいただけますか。
執行 気品は子供のころからずっと考えている中心課題なんですが、気品の中で一番大切なものは「野蛮性」だと僕は思っています。
「野蛮性」というと言葉は悪いかもしれないですが「野生」ですね。人間の最も根源的な生きる力です。こういう野生の裏打ちがある気品が重要ですね。
三枝 野生の裏打ちがある気品
執行 そうです。だから平安貴族的な雅な気品は、僕は気品だと思わないんです。
気品というのは、武士の持っている気品。つまり、いつでも命をかけて戦う覚悟がある、そういう気が出ていることを真の気品だと思うのです。
今は女性の時代と言われますが、今の女性よりも昔の女性のほうが遥かに強いと思います。昔の女性がなぜ強かったかというと、気品の本質を知っていたからだと思うのです。
昔の女性は自分を主張しないけれども、一生懸命に家族を支えていた。母親の愛情と言えるかもしれない。僕の母も家族とか自分の子供がよくなる、つまり幸福になるために、自分の生命を全部注ぎ込んでいた。そうやっておふくろが僕を作ったと思っています。おふくろの愛情だけが僕の支えというとおかしいかもしれないですが、僕自身を創ったんですよね。
今、若い人と話すと母親によって作られた男らしい男というのは少ない印象がありますね。母親に頼っている男は多いですが。
― 気品について、そして女性について出てきましたが、三枝先生はいかがですか。
三枝 私はまだ未熟ですが、作法をお伝えしておりまして、その中で気品は精神性や教養が、立ち居振る舞いに表れたものだと思っております。
ただ、気品と上品は違うと思っています。気品は「気」「品」ですので、執行先生がおっしゃるように、その人から出ている「気の品格」だと思うのです。
いかに人のために生きられるか、といった生き方が気品だと思っています。
執行先生のお話から、気品というのは勇ましくて高尚なるもののように受け止めました。
気品があるからそう振る舞えるというよりは、そう振る舞えるから気品がある人なのかなと感じました。
執行 そうですよね。自分から出すよりも、何かに対する受け答えに気品って出ますよね、やっぱり。僕はそう思います。
三枝 はい。型ではございませんよね。
執行 僕は気品や生き方には、男も女もないと考えます。
たとえば、よく女性は男性に仕えると言いますが、本当に愛している男性に何もかも捧げ尽くしている女性というのは美しいでしょ。
男性だって同じ。愛の根源というのは、自分の生命を捧げる対象への気持ちだから。それが国、文化、家族、奥さんと違いはあれど、これらは全部等しいと思っているんです。
三枝 執行先生は犠牲イコール愛とおっしゃっていますよね。
執行 もちろん、愛というのは犠牲的精神のことしか言わないから、それ以外の愛は全部愛を騙っているだけなんですよ。
三枝 さきほど、執行先生のお母様のお話が出ましたが、本来、女性って辛抱強く、調和力があると思うんですけれど、現代では、その力は弱くなったと思います。女性の方が男性よりも我慢強いとずっと思っていたのですが。
執行 その通りだと思います。
しかも最近は女性が自身を全部捧げる対象を見つけにくいようにも思えます。
元来、女性は自分が愛する男性に対してすべてを捧げるやり方には慣れているはずですが。
三枝 今はすべてを捧げることができる、犠牲になってもいいと思える男性が少なくなってきたということですね。
執行先生みたいな、勇ましく潔い方はお会いしたことがないです。
執行 僕はやりたいように生きてきた男だから、そこだけがいいところであり欠点でもある。
やりたいように生きるその中で、後世へ残す遺物として僕が人生を捧げていることの一つに、芸術作品があります。
芸術とは何かというと生命が燃えた証。その時代の人たちが生命を燃やしてぶつけた対象が、僕は芸術だと思っています。
芸術の中で本当に優れたものを後世になるべくいい状態で残していくことが、いつの時代の人間にとっても一番大切なことだと思っている。
三枝 魂が燃焼したものがその作品として表れる。芸術品であり、そういう生き方ですよね。
執行 そう、生き方。
三枝 それは希望だったり歓喜だったり、自分の好きなように生きるという「わがまま」ではなくて、好きなように生きるという「生き方」ですかね。
執行 僕は好きに生きるのが一番正しいと思うけれど、やったことが人の幸福とか健康とかに貢献できれば、それはすばらしいことだと思っている。
三枝 人の役に立つこと、人を喜ばせることで自分も喜びを感じますし。
執行 生命というのはがむしゃらに好き勝手にやらないと燃えない。でも、人の役にたつようになるには、一番最初に言った野生に裏打ちされた気品みたいなものがその人物の中にないとだめなんだと思います。そういう意味では親の役目は重大ですよね。
親とのコミュニケーション、簡単に言えば、親が愛情を注いだかどうか、子が親の愛情を受けたか、そのようなことかもしれないですね。
三枝 親と子、先生が著書で説かれている“縦”ですね。
執行 縦のラインですね。親にはまた親がいて、そのまた親がいる。綿々と受け継がれた親の愛情。今自分がいるこの環境を考えると、親だけに留まらないですね。自分の祖先や、自分の国、自分の関わるものすべてと言ってもいい。
三枝 好き勝手やるには、つまり生命を燃やすには縦をしっかり持っていないといけないということですね。
執行 僕はそういう理論を持っている。僕は自分の国が好きで、自分の家系が好きで、自分の出た学校も好きで、自分に関わるものは全部好き。
なぜかと言うと、これらはすべて縦だから。自分の運命に対して来たものだから。人間にとって一番大切なのは縦だと思う。縦が立つということです。
三枝 垂直ですね。
執行 そう。この対談は「未完に挑む」という題名だけど、未完というのは縦なんですよ。
だから未完に向わなければダメだってことを僕は本に書いている。自分の縦に向かうってことを僕は本に書いている。自分の縦に向かうってことは自分の親を愛することであり、親のまた根源を愛すること。だから親の親の親の親のと辿っていけば、宇宙の果てまで行くわけで、僕はそれを縦と言っている。縦を求める考え方というのは、永遠につながるということ。完成はないということです。
三枝 未完に挑む、命の燃焼と申しますとなかなか難しく思われるのですが。
執行 どちらも初心があるかどうかということが重要ですね。
何がこの世で美しいかというと、いろんな人が持った初心が最もきれいで崇高で美しいと思う。
誰でも経験があると思います。志望の学校に受かった喜びとか、結婚とか。でも、みんなだいたい三日目で忘れてしまう。
僕の女房は結婚して子供を産んですぐに亡くなったけれども、女房と結婚できたときの喜びっていうのは毎日思い出します。死ぬほど好きだった。だから再婚もしてないし、ただ一度の結婚で、あれ以上の幸福はないと思っている。だから僕には初心しかない。
三枝 日々、「初心」を振り返っていらっしゃるということですね。
そうするといろんなことに初心がありますから、わくわくしどうしになりますね。
執行 全部に初心が必ずある。
要するに、僕は初心を自分に与えられた運命と呼んでいます。誰にでもあることですよね。
だから文句を言っている人は自分の運命を受け取っていないんですよ。自分に与えられたものをありがたいって思っていないから文句が出てくる。
三枝 文句を言う人は「運命」を受け入れていないということですか。
執行 初心っていう言葉が自分独特の運命だと思うと、何かつかめるようになると思いますよ。
三枝 初心というと、世間では最初に立てた目標くらいに軽く受け取られますけど、そうではないのですね。
執行先生は初めてお会いしたときに運命に従って、目の前にあることに体当たりするというお話をされて、私にとって一番印象に残っていました。
先生とお会いしてから、目の前に来たことをぶつかってもいいからやろうと思うようになりました。そこが変わったと思うんですね。
私自身、格好つけのところとか、痛みを避けるみたいなことが多かったものですから。
今日もまた、新たな気づきがありました。運命イコール初心ということですね。たくさんの初心がありますから、それを思い返して自分に問うことをしたいと思います。
― 執行先生、三枝先生ありがとうございました。
×ことしNHKの日曜美術館で戸嶋靖昌という画家の絵を見て衝撃をうけた。スペイン滞在が長いので、これまで日本ではほとんど無名の画家である。モチーフは人物像、風景、静物であるが、なかでも人物像は圧倒的な迫力である。
描かれているのは、画家が長く滞在したスペインで出会った人々である。例えば「アルバイシン男 -ミゲールの像-」である。アルバイシンは画家が住んだグラナダの地域名で、ミゲールは男の名前である。作品のまえに立つと視点は一直線に顔に向う。やや顔を傾げている。筆を重ねた皮膚の質感がすごい。長い歳月、風雨にさらされ、紫外線に傷めつけられ、内からの懊悩に襲われてきた皮膚である。そして視線は男の眼差しに釘づけになる。眼裂が狭い。左目がかすかに光る。この男はいまなにを考えているのだろうか。絵の前にたたずみ思いをめぐらす。ミゲールの眼差しには優しさと寂寥がただよう。むかし兵役にいたころを懐かしみ、制作中に涙を流すことがあったという。
戸嶋が好んで描いたモデルのひとりがベルタである。彼女は80歳を超えていた。「老女ベルタ」の眼差しは奥が深い。結んだ口と大きな鼻が意志のつよさや頑固さを想像させる。老女はたくましく、そしてしなやかに生きてきた。顔のしみが人生の年輪を語る。
会場には30号から50号の作品がならぶ。人物像の誰もがステージ中央に座る名優のようだ。着衣のディテールは描かれていない。基調の褐色系を黒が被覆し、そこにペインティングナイフを使って、ホワイトが島嶼のように点在する。顔が迫ってくる。瞳にさした極微のハイライトが、いのちの光を放っている。白の使い方が絶妙である。
裸婦像「裸 -Ra-」がある。黒く暗い画面から横臥した骨太の裸婦が浮かび上がる。重量感のある裸婦像である。両手を頭のうえに長く伸ばし、物憂い面持ちで視線の先は遠くにある。絵を離れても裸婦の残像がついてくる。
若いころ描いた裸婦のデッサンを見ると、陽炎がゆらゆら揺れているような繊細な線で画かれている。飽きない線である。
高台にあるアトリエから、「グラナダの幾何学」「街・三つの塔 -グラナダ遠望-」などグラナダの街の眺望を描いている。画面の左手前に大きなカテドラルが描かれ、右上方には縦長の四角い建物が遠望できる。絵の中心部は立て込む街並みが埋めている。しっとりとした空気が街を包む。画家がアトリエの窓からグラナダの街並みを撮った写真をみると、単なる写生ではないのがよくわかる。戸嶋のグラナダである。写真が好きでライカ、ニコンF、ハッセルブラッドなど高級カメラを愛用していた。グラナダのアルバイシンにアトリエを構え1977年から30年近くを過ごしている。
マドリッド滞在時の戸嶋がバイクと一緒に写った写真がある。バイクに凭れて立つ画家は長髪で短めのコートをはおり、バイク用の靴を履いて、なかなかの伊達である。旧家の御曹司のおもかげがある。「よくもてた」と本人自ら語っていたようである。側車に積まれた荷物からイーゼルがあたまを出している。今川一郎先生にこのバイクについて尋ねたら「イタリア製のVespaのサイドカーです。映画ローマの休日で、オードリー・ペップバーンとグレゴリー・ペックがローマの街を乗り回していたスクーターです」と返信があった。
マドリッドからアンダルシアの田舎村アスナルカサルに居を移す際には、この愛車に大きな荷物を積んで550キロの道程を南下している。当時この村にいた作家佐伯泰英は、サイドカーでやってきた戸嶋を見て「出で立ちはまるで神風特攻隊のようで殺気に満ちた風姿と風貌」と記している。平穏な村に突如現れた戸嶋の風体と面容に出会い、とっさに特攻隊が連想されたのであろう。
アスナルカサルには1年間住みついて「アスナルカサルよ」「アスナルカサルの家」などを画いている。白壁の家の陽射しと影のコントラストが美しい。構図が堅牢でゆるぎがない。崩れかかった土壁などに魅せられたようだ。
制作に疲れると愛用のバイクに画材と愛用のカメラをつんで、アンダルシア地方マラガ、オルベーラ、カジスなどへ旅に出た。「マラガにて -El paisaje en Málaga-」は3号の小品であるが、旅先でリラックスしていたときの制作なのか自由で闊達な線が奔る。具象であるが固有の形象は判然としない。しかし、眺めていると、雲が奔り、潮風が頬をなでる。土や砂の感触が伝わる。
城塞都市クエンカを見上げて描いた「クエンカ風景」がある。そそり立つ断崖や崖上の城塞の白と木々の濃い緑の対比、その上にごく薄く青を刷いた透明感のある画面である。
カリン(メンブリージョ)の絵が多い。凹凸のあるカリンの実が横一列に並べられている。カリンの腐れてゆく過程に魅かれるという。描かれたカリンのひとつひとつが、哀歓を抱える人物像にみえる。日本に帰国後も、モチーフのカリンを求め諏訪まで出向いている。
「花の季節」は小品であるが、赤がすばらしい。大輪の花の中心はコクのある濃いくれない色で、外側の花びらは淡いピンクとなる。その周りをブルーが包む。葉には鮮やかな緑を使っている。花はまもなく枯れて朽ちる。いま束の間の盛装である。暗い設定の照明のなかで光彩を放つ珠玉の逸品である。
肖像、風景、静物のいずれの作品も、おもねるところが微塵もみられない。画家の息遣いと呻きと咆哮だけが聞こえてくる。
1967年、恩師麻生三郎の推薦により超一流の銀座・サヱグサ画廊で個展を開く。将来を嘱望されてのことである。しかし戸嶋はそれから7年後(1974年)スペインに渡ってしまう。
スペイン移住の動機として、4年前の1970年、戸嶋が36歳のときに起きた三島由紀夫の自決事件が影響を与えたという指摘がある。
戸嶋はこの時期、人生に悩み精神的危機にあったという。そこに高名な作家三島由紀夫の自決という驚愕の事件が起る。三島が自身で結成した盾の会の会員4名とともに市ヶ谷の自衛隊駐屯地をおとずれ、2階バルコニーから自衛隊の国軍化を訴える演説をする。そのあと総監室で会員のひとりとともに割腹し、残った会員が介錯をした。遺体が床に横たわる現場写真が新聞に載り、事件のショックがひろがる。戸嶋は事件のあと「名声を求めることのむなしさを痛切に感じた」と語っている。この事件が精神的に追い詰められていた彼の背中をつよく押した。そう推察すると渡欧は必然であった。
事件後に描かれた「冬の庭」は、黒い絵具のかたまりのような重たく陰鬱な画面である。「この作品は、三島事件のショックに触発されて描いたものである。悲しみの極北が埋葬されているのだ」と述べている。三島事件のあと「回る森」「逆光の森」「杜の中で」など森をテーマにした一連の作品があるが、いずれも暗くて重い。心のうちを投影した心象の森である。Schwarzwald(黒い森)という言葉が浮かぶ。
当時32歳の自分は群馬大学内分泌研究所の助手(いまの助教)で、電子顕微鏡を使って皮膚細胞の研究をしていた。その日、1970年11月25日の昼過ぎ、「鈴木さん、いま三島由紀夫が自衛隊で切腹自殺した」と同僚の瓦井康之助手(後に金沢医大教授)が興奮して研究室に駆け込んできた。夕方、テレビで事件の詳報を知る。七生報国と記した鉢巻をしめ、会の制服で身をかため拳をかざし演説する三島、バルコニーの三島にむかって怒号を発する自衛隊員たち、演説の内容は聞き取れない。そのあと三島が若い会員とともに割腹自殺したという報道。この一連の場面が繰り返し放映された。戸嶋もこのテレビ画面を見ていたであろう。
突然起きた三島の自衛隊立てこもり、そして割腹自殺という結末は大きなショックであるが、加えて「なぜ三島由紀夫が!」「どうして?」とわからないことが多く、こころの整理がつかないまま困惑の時間が長く続いた。
事件の2年ぐらい前から、ベトナム反戦デモが激しくなり、日大闘争、明大闘争、東大安田講堂事件など大学紛争が拡大する。朝、駿河台病院のポリクリ実習で御茶ノ水駅の改札口を出ると、過激化した学生デモの鎮圧に機動隊が放った催涙ガスで目が痛かった。講堂の窓から道路を見下ろしていると、逮捕されたデモ学生が首根っこをつかまれて連行されてきた。三島事件の後には、連合赤軍による迦葉山総括リンチ殺人事件や浅間山荘事件など世間を驚愕させる事件が相次いだ。1970年前後は大きな事件や紛争が相次ぎ、なんとなく社会全体が落ち着かない不安な時代であった。そして戸嶋は事件の4年後、1974年にスペインに渡る。
スペインに渡った戸嶋は、日本の画壇を離れ、作品の発表も疎遠となり、名声への道を自ら閉ざす。本質をいかに表現するかにすべてをそそぎ、ただひとりで助けのない孤立の道を一途に進む。この決意を実践した童心のような純粋さは、旧家に生まれた血筋と育ちが関わっているように思える。
「制作することは僕にとっては苦しみ以外の何物でもないのです」と言いながら描き続ける。絵は売らない。埃をかぶってアトリエに溜まっていく。キャンバスにサインはない。すべてが未完成で、ひとまず筆を置いたに過ぎないからだ。
戸嶋の生活費は日本に残った曰子夫人が支援を続けてきたようだ。この仕送りによって己の志に専念できたとすれば、まことに仕合わせなひとである。
1999年に妻曰子を亡くす。看病のため帰国していた戸嶋は夫人の没後も日本に留まる。そのころ著述家であり実業家の執行草舟(バイオテック)は美術雑誌に載った戸嶋の絵に感動し、自画像の制作を依頼する。「断られると思って出向いた」ところ、ふたりはたちまち意気投合し、戸嶋は「一丁やるか」と制作を応諾する。2003年から執行が社屋内に設けたアトリエで制作をはじめ、「黒の草舟」など次々と絵画制作する。
執行の回想である。「戸嶋は下書きをまったく描かずに、絵画をキャンバスに塗りはじめます。なにを描いているのかさっぱりわかりません。キャンバス全体に絵具をのせていきます。せっかく画いたところを惜しげもなく消してしまいます。『心配するな!』とよく大きな声を出すのです。わたくしのまわりにも絵具が飛び散ってきます。」
「やがてキャンバスに顔らしきものがうかんできます。目を入れてくれるように頼んだが聞き入れられません。目は描いてはならぬ。目は描かないで描くのだ、と言っていました。」目は描いているなかから自然に生まれてくるのであろう。目が生まれてこないばかりに、数十回の描きなおしはざらであったという。戸嶋のモデルをつとめた日本人は稀有であり、この体験談は興味深い。
制作の時間が過ぎると、ふたりはビールを飲みながら文学や絵画について熱く議論を交わす。充実した至福の時間であった。このころ画家の長髪はすっかり白くなっていた。
2005年4月に外遊するが、この頃から体調不良の日が続く。10月に末期の直腸がんと診断され虎ノ門病院に入院する。抗がん剤治療は拒み制作をつづける。入院中も外出許可をもらってアトリエに通った。2005年11月に50号の執行像を描きはじめる。翌2006年1月「魅せられたる魂 -執行草舟の像-」というタイトルをつけ、「この絵は俺の出発だ」と言って筆を止めた。7月に入ると病状が悪化して、20日の夜に息を引きとる(享年72)。志を高くかかげ、それを一途に貫いたもののふが逝った。スペイン時代の友人磯江毅がデスマスクを描く。端麗な容貌である。
戸嶋の死後、執行は遺作800点と遺品のすべてを譲りうけ、保存のために戸嶋靖昌記念館を設立する。こうして画家のいのちは散逸をまぬがれる。執行の戸嶋に抱く熱いこころと彼の事業家としての器量がこれを成した。いまは新社屋(東京・麹町)の4階に設けられた戸嶋靖昌記念館で作品は常設展示されている。
友よ、朝が来たら記念館のミゲールやベルタに会いに行こうではないか。アンダルシアの風はきっと心地よい。バイクを駆る画家に会えるかもしれない。
スペインのグラナダ25年近く、人間の魂を描き続けた孤高の画家、戸嶋靖昌(1934-2006年)が注目を集めている。絵の具を塗り重ねた彫刻的な絵画。暗闇のようなキャンバスに、人間の生命と崇高な魂の輝きが浮き上がってくるようだ。
今年初め、NHKテレビ「日曜美術館」で取り上げられたほか、5月12日からは1ヶ月間、東京・千代田区のスペイン国営セルバンテス文化センター東京で「戸嶋靖昌の見たスペイン」展が開催された。同展には、カトリックの神父や上智大学・学芸員課程の学生たちなど、多数が訪れたという。
戸嶋は、故郷の秋田県から東京・武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)に進学し、優れた才能で将来を嘱望される。しかし、商業ベースの「売れる絵画」の制作を拒み、1970年に起きた作家・三島由紀夫の自決事件に衝撃を受け、「名声を求めることのむなしさを痛切に感じ」る(執行草舟著『孤高のリアリズム―戸嶋靖昌の芸術―』)。自己の芸術を高めていくことだけに人生をささげる決意をした戸嶋は、絵画のリアリズムを求めてスペインへ渡る。
戸嶋がスペインを選んだ理由は二つある。一つはベラスケスの絵画群に表現される崇高さ(生命の神秘と悲哀)に魅せられたこと。もう一つはマドリードのカプチン・フランシスコ修道会にある木彫《死にゆくキリスト》(グレゴリオ・フェルナンデス作)に象徴される「見えない神を出現させるキリスト教美術」(小池寿子・國學院大學教授談)に魅了されたことだ。
戸嶋は、グラナダ大聖堂に通い創作の疲れを癒やした。また聖母巡礼などの行事に参加し、人々と交わりながら深く地域社会になじんでいった。そんな戸嶋が求めるリアリズムとは何だったのか。戸嶋靖昌記念館の副館長で、カトリック信者でもある執行真由美さんはこう語る。「キリスト教の美術や彫刻は、人々の信仰に役立つように、目の前に神が現前するように感じさせることが重要です。戸嶋の肖像画の描き方も宗教画と同じで、表面的に容姿や形を忠実に描くのではなく、人間の生死、内奥をむき出しに描きます。人間の内的な精神性や超越性を現前させるリアリズムなのです。戸嶋の生き方は、信者に限らずとも『超越』と真摯に向き合う人生があるということを気付かせてくれます」
戸嶋が、富や名声に見向きもせずにグラナダで描いたのは、没落貴族や社会から見捨てられた人など“貧しい人々”の光輝く人間性や「無欲のエレガンス」、内面の力強さだった。
日本から妻が送ってくれる資金で清貧生活を送り、その後、妻の看病のため帰国するが、記念館で所有する絵画は約800枚。戸嶋はそれらを売ろうとはしなかった。記念館では、戸嶋の死後、数々の絵を修復して、よみがえらせ、随時入れ替えながら公開している。
執行副館長によれば、イエズス会のホアン・マシア神父は、戸嶋の絶筆《魅せられたる魂―執行草舟の像―》に深い宗教性を感じるという。「超越した神に向かう光(カトリック的精神)と、自分を“無”にする“空”の境地(仏教的精神)が見事に表現されている」と。
×東京・六番町のスペイン国営施設・セルバンテス文化センター東京で「戸嶋靖昌の見たスペイン展」が開かれている。坊沢村(現北秋田市)出身の画家戸嶋靖昌さん(1934~2006年)が現地に住んだ24年間で描いた油絵約50点を展示。近年脚光を浴びる戸嶋さんの絵を見るため遠くから足を運ぶ愛好者も多い。
同展は、センターが戸嶋靖昌記念館(執行草舟館長、東京・麹町)に持ち掛け実現。主に同館で展示した2~50号の作品を並べた。戸嶋さんが写した写真も初公開。40歳からのスペイン滞在で戸嶋さんが達した筆致と対象へのまなざしを感じさせる構成とした。
同館は戸嶋さんが生涯に描いた約千点の8割を所有。センター展期間中、同館では、スペイン以前の戸嶋さんの作品を中心に展示している。
13日に訪れた京都府京丹波町の会社員中村穰子さん(60)と東京・台東区の同篠田麻理子さん(60)は、戸嶋さんの母校・大館鳳鳴高の出身。中村さんは「昨年初めて見て魂を堀り起こすようなタッチに引き込まれた。再会できて感動」、篠田さんは「芸術を追求した生き方が表れた筆致と、描かれた人物の存在感に驚く」と話した。
執行館長は「戸嶋ファンが増えたと感じる。彼が願ったスペインでの展覧会と秋田での展覧会も実現させたい」と話した。展覧会は21日にNHK教育テレビ「日曜美術館」アートシーンで紹介される。
両展は6月10日まで。ともに午前11時~午後6時で鑑賞無料、日曜休館。バイオテック社内にある同館は予約(03・3511・8162)が必要。(中田貴彦)
×2015年に開催された回顧展が大きな話題を呼んだ戸嶋靖昌(1934-2006)。以来、急激に注目度が上がっている戸嶋の人となり、スペインでの活動に着目する展覧会が、スペイン国営の文化施設、セルバンテス文化センター東京で開かれる。戸嶋はグラナダを拠点に、スペインで26年間に亘って活動。本展では同地の風土や人びとを追った画家の視点を主題に、戸嶋自身が撮影した写真も出品。スペインならではの作品として、たびたび描いていた花梨の絵も見逃せない。NHK「日曜美術館」(1月22日放送)で取り上げられた作品も展示される。さらに愛用していたカメラやスペインと関連した遺品をあわせ、約70点(一部展示替えあり)での展観だ。
本展を記念して、スペインを代表するヴァイオリニスト、リナ・トゥール・ボネが、スペイン大使館内のオーディトリアムでのコンサート(5月19日)のために来日。戸嶋が好んだバッハのバイオリンそなた、パルティータ、グラナダにちなんだプーランクの楽曲などを演奏する。当日は演奏会場と大使館内のギャラリーに戸嶋の作品が並び、音楽を聴きながら絵画鑑賞が楽しめる。詳細はスペイン大使館のホームページのニュース欄、またはフェイスブックを参照。
×スペインと東京を拠点にキャンバスと向き合い、生きることの意味や生命の本質とは何かを問い続けた。坊沢村(現北秋田市)出身の画家戸嶋靖昌(1934~2006年)。生前は脚光を浴びることがなかったが近年、美術雑誌などで取り上げられ、知名度が高まっている。
1974年~98年にスペインに滞在、そこで出会った人物や風景の油彩画を残した。いずれの作品も暗い色を何度も重ねており、重々しい雰囲気が漂う。気軽に鑑賞できる作風とはいえないかもしれないが、見る者を引き付ける独特の迫力がある。
代表作の一つ「ノルディンの顔」は、政争の果てにイスラム圏の国からスペイン・グラナダに移住してきたノルディンという男性がモデル。戸嶋が63歳の時に描いた。スペイン生活も終わりにさしかかり、画家として円熟期を迎えた時の作品と言える。
ノルディンの背景の闇は暗く、タッチは粗い。顔の輪郭ははっきりとしないが、どことなく憂いを帯びた表情のようにも見える。
2015年に戸嶋を含む油彩画家5人の作品集を開いた府中市美術館(東京)の学芸係長・志賀秀孝さん(57)は「本来、絵は人物の存在をあぶり出すもの。しかし、戸嶋はモデルの存在を否定し、心の中で『おまえなんかいないんだ』と唱え続けた上でもなお感じる生の残滓を描いている」と解説する。
志賀さんは、戸嶋の作品に描かれる人物は出自や個性がそぎ落とされた人間そのものだとし、「絵を見る人に、あるがままの姿で生きればいいんだと思わせる」とも語る。
カリンを描いた1996年の作品「シャコンヌ -乾いたメンブリージョ-」も人物画と同様に、否定してもしきれないカリンの本質を表した。戸嶋は子どもの頃から絵が好きで、中学校で美術部に入り、本格的に絵画に取り組み始めた。大館鳳鳴高校卒業後に上京し武蔵野美術大学に進み、助手として残った。40歳の時にスペインに渡り、画業に磨きをかけた。
帰国後の2000年、秋田魁新報社の取材に対しスペイン行きについて「バロック時代の教会に付属した彫刻の写真を美術本で見て生々しい表現力に魅了されたのがきっかけだった」と語っている。
戸嶋が渡った当時のスペインは、1975年にフランコ総統が死去し、独裁体制に終止符が打たれた激動の時代。現世で戸嶋は民衆の悲哀に共鳴したという。戸嶋の大館鳳鳴高校時代の同級生・三沢盛夫さん(83)=北秋田市=は「自分の信じるものと純粋に向き合い、突き詰める男だった。難しい絵を描くので、本人には冗談半分で、死後100年たたないと認められないだろうと話していた」と振り返る。
高校時代、戸嶋がサバの絵を描いて級友に見せたところ「まるで死んでいるようだ」とからかわれ、「そんなことない」と食ってかかったことを鮮明に覚えているという。「若い頃から自分の絵に誇りを持っていた。」と話す。
戸嶋と親交があり、2012年に戸嶋靖昌記念館(東京・麹町)を開設した実業家の執行草舟さん(66)は、戸嶋作品の人気の高まりは時代の要請とみる。「物質的な豊かさを実現した日本社会が求めているのは、人間性や魂の復活だ。そこに生命の本質をえぐり出した戸嶋の絵が合致しているのだろう」
戸嶋が20年余りにわたりスペインで絵を描き続けたことは現地で評価されている。日本との友好の懸け橋を担う存在として捉えられており、今年5月には、スペイン政府設立の文化施設「セルバンテス文化センター東京」(東京・六番町)で作品展が開かれる。
×近年、高齢化社会を迎えた我が国では、終活と題した活動が盛んです。一方で老人問題に目を向けると、認知症などの介護問題に始まり、高齢者の軽犯罪の増加、農業の後継者不在など、希望を見出しにくい現状もあります。老いや死のイメージは概ね否定的なものかもしれません。人はさまざまな出来事に翻弄されながら、いつしか夢を諦めて人生の終焉を迎えるのでしょうか。
しかし結局、全ての人は老いて死に向かうわけで、「老いをどう生きるか」が人生の一大問題であることに相違ありません。上智大学グリーフケア研究所の高木慶子先生によれば、ターミナル期にある人に「この世に残っている人々へのメッセージは?」と聞くと、ほとんどの方が「死については、若い時から、また、高齢者は元気な時から考えておくことを勧めます」と話されるそうです。ただ漫然と生きるだけでは理想とする老いは訪れないことを知りながら、「どのように老いに向かうか」という問いへの哲学を持つ人は少ないかもしれません。
人間としての魅力を増していく老い方とはどのようなものでしょう。少々手荒く感じるかもしれませんが、「毒を食らえ」という執行草舟氏による生命論(『耆に学ぶ』エイチエス。2016)は、華麗なる老いへの希望を見出す示唆を与えてくれます。本質を突く強力なエネルギーにより、従来の固定観念が次々と打破され、神経が活性化されるようです。毒は一般的に、“体に悪いもの”、“避けるべきもの”というのが生命を守るための考えですが、執行氏は、その毒から逃げることなく、あえて食らえと言うのです。人の肉体、精神、そして文明という“人間と人間を取り巻く環境”に関わる毒を取り入れることが、美しい老いに向かわせるのだそうです。(一部抜粋)
×文明論か宗教論か、いや人生論としても読める。音楽、文学、絵画と広範に芸術が論じられているが、本書は強固な思想書なのである。
人生の骨格をなすのは「憧れ」にあり垂直な生き方を重視する。「人間は宇宙の意思である」「人間だけが精神を志向することが出来るからだ。精神のために死することが出来るからだ。命より大切なものがあるからだ」。それが著者のいう「憧れ」の概念である。
執行氏の人生の信念が本書に叩きつけられている。しかし「人間中心といいながら、人間の精神的な崇高や恩に基づく真の絆を一切捨て去った思想のもとでは、生命が発展する術もない」という文章など左翼的ヒューマニズムの偽善を暴く一方でAI(人工知能)とかの技術革新に狂奔する文明社会を非情な目で見通し、やがて「社会は乱れ」「人間の文明は破綻してしまう」と警告するのである。
なぜなら中世では人間の心を憧れが支配していたからこそ、中世を経過した日本が真の近代化と工業化をなしえた。中世は躍動的で「不合理と不幸を、中世人はその身に受け続けた」。だからダビンチが出た。ミケランジェロが出た。日本では鎌倉に仏教が高みに達した。
執行氏が深く惹かれたのは日本古来の武士道、それも『葉隠』だった。とくに「武士とは死ぬること」であり、恋愛は「偲ぶ恋」にこそ崇高さが宿るとする。この箇所では文章に熱が籠もり、行間からも情念があふれ出てくる。強力な磁性、その強烈な個性が随所に配された箴言に論が集約されていく。
「垂直を仰ぎ続ける」憧れを自己に引きつけ、与えられた「知性や精神、そして自己の存在をより燃焼させたいという、根源的な欲求が憧れを生む」。「人間とは精神であっても肉体ではない」。執行氏は三島由紀夫の思想と行動にたどり着く。「人間は肉体を忘れなければならない」
これほど強烈な思想書は久しく手にしたことがなかった。3日がかりで読み終えたが余韻のなかにまだ浸っている。
×執行草舟氏は、今日の日本における、いわば「知る人ぞ知る」著述家である。『生くる』『友よ』『根源へ』などの著作によって、その孤高の精神世界を表現してきた。それは「根源」的に反時代的であり、その精神の在り方も表現様式も極めてユニークである。そのユニークさは、氏が近代以降の制度化された「文芸評論家」とか「美術評論家」あるいは「詩人」などといった存在ではなく、「芸術」の「根源」というものに深く根差していることから来るのである。
氏は、独自の美意識で集めている書画のコレクションを所有しているが、本書は、その一部を紹介するとともにそれについての批評分を付しているものである。掲載されている作品も素晴らしいが、この批評文がいわば「画賛」ともいうべきものとなっていて、作者と氏の魂の見事な共鳴が聴こえる。これは、美術評論というようなものではなく、いわば散文詩の高みに達している。しかし、今日の日本の常識では、これを詩とは認めまい。執行氏が、孤高な存在である所以である。
氏は、自分が「世界の美術愛好家」ではないと強調している。なぜ、本書を『憂国の芸術』と題したか。いわゆる芸術好きの「美術コレクター」と捉えられては困るからだという。氏は、趣味で集めているのではない、芸術だけが民族の魂を未来につなぐことのできる、唯一の「神話」と考えているからなのである。
コレクションの中で、特に取り上げられているのは、洋画家の戸嶋靖昌と日本画家の安田靫彦である。本書の第3部「安田靫彦の心」は、氏が深く敬愛している安田靫彦の傑作に付して、賛歌のような美しさを持った散文詩が書かれているもので、この強い個性に貫かれた著作の白眉をなしている。巻末の「靫彦との対話」には、「靫彦の描く画はあくまでも美しく、また切々として悲しい。美しいとは悲しいということである」とある。こういう「切々」たる声を現代人は耳にしなくなって久しいのである。
×2020年度から小学校高学年で英語が正式教科になる。そのことに小学校教員の半数近くが反対していると、先週毎日新聞が1面トップで報じていた。
とは言っても、調査した対象者はわずか100人で、そのうち反対は45人、賛成は29人だった。1面トップを飾るにはあまりにも調査規模が小さ過ぎる気がした。
反対の理由は「他の授業時間は減らないので教員の負担が増す」「小学校教員の多くは発音などのスキル(技術)がない」など。今、小学校高学年では「外国語活動」といって、テスト評価がなく楽しみながら外国語を学ぶ時間があるそうだ。それを引き合いに出して、「正式教科になると楽しむ英語から勉強のための英語になる」という反対意見もあった。
計画を進めているのは文科省だ。この程度の反対意見など想定内のことだろう。何か新しいことを始めようとするときには、必ず反対意見は出るものである。その時大事なのは、反対理由がそれを推進する人たちの信念を凌駕するほどの崇高さがあるか、ということではないだろうか。
そういう意味で、文筆家の執行草舟氏が著書『根源へ』の中で述べている考え方に度肝を抜かれた。
「人間はまず母国語によって思考の軸を創り上げる。だから外国語教育は『自分』を創り上げてから始めるべきである」とか、「日本人は日本語で思考する。日本語は他の言語と言語構造が大きく異なる。だから子どもの頃に違う構造を持った言語を押し付けられると脳の思考軸が定まらず、母国語である日本語で深く考えることが困難になる」とか。
執行氏は「言葉は人間の魂そのもの。国語は民族の魂である。外国語は国語力あっての話である」と言う。
だから、「今小学校から英語教育が始まっているが、あんなことをしたら日本人はますます軽薄になる。口先が達者なだけのキャビンボーイのような人間では国家枢要の役には立たない」と手厳しい。
「キャビンボーイ」とは、船上で使用人として仕事をする青年のこと。世界中を航海しているので外国語はできるが、自分の考えがなく、ただ与えられた仕事をするだけの若者を総称している。
とにかくコミュニケーション言語としての英語を学ぶ前に、思考言語としての母国語にどっぷり浸ることが重要なのだ。
「どっぷり浸る」とは、子どもを理屈抜きに日本語の「大海原」に放り込むことだ。そこは野蛮な世界だから、子どもは溺れるかもしれない。溺れたら「大海原」が嫌いになるだろう。その「大海原」を泳ぐ技術と泳ぐことの楽しさを教えるのが国語教育なのである。
その「大海原」とは古典文学。執行氏の場合、それは「万葉集」なのだそうだ。
「古代から引きずっている唯一の『生き物』が言葉である。古典にどっぷりと理屈抜きに浸ることが、野生を取り戻し、言葉を取り戻す道だ」と執行氏。
古典は、「難しい」「意味が分からない」ということで敬遠されがちだが、「日本語である限り必ず分かる日が来る」と言う。
そのためには神社に行く。お墓参りをする。中秋に月を見上げる。祖母が口ずさんでいた歌を歌う。和歌や短歌をたしなむなど、昔の人と同じ体験をすることで、私たちは時代を超え、祖先と魂を交わすことができる。そして古典に浸ることで昔の日本人の哀愁をも味わうことができる。
執行氏は言う。「現代の言葉に対する姿勢では、言葉は単なるコミュニケーションの道具でしか理解されない。これでは思考が深まらず、若者はますます軽薄になっていく」と。
我々が中学・高校の時、国語教育というと、文章を読み取る力など受験対策としての国語力を養うものだった。今思うと、もっと日本語の美しさや言葉の持つ力などを教えてほしかった。
英語教育についてとやかく言うつもりはないが、「国語教育とは母国語教育である」、この視点は大切にしたい。
×私は、「出会い」だけによって出来上がった人間だと思っている。その出会いも、そのすべてが書物に依っているのだ。本が、私を創った。そう自分では思っている。確かに、人との出会いもあった。しかし、そのほとんどは、書物で得た信念を生身の上に確認するだけだったように感ずる。私にとって、本は神であった。
秀れた本を読むことの方が、自分が生きることよりも大切であったことを、よく覚えている。子供の頃から、死に直面していたことが、そのような生き方を生んだのかもしれない。宇宙と生命の真実に迫りたいという欲求が、自己の人生を忘れさせるほどに大きかったのだ。本の中に、それを求め続けた。
私は『葉隠』という書物によって日本の精神を知った。その武士道の中から、私のすべてが創られた。もちろん、解っているのではない。そうありたいと、心底から願っているのだ。これが、私の本との出会いの始まりである。始まりが、『葉隠』だったことが、不合理を愛する人生を創り上げることに成ったと思っている。
『葉隠』に始まった読書は、苦悩の青春を築き上げた。それは、この世の不合理と不幸を自分が招き寄せたからに他ならない。私の読書は、哲学と文学の深淵を彷徨い続けた。遠い憧れを目指して、魂は日々咆哮していた。ドストエフスキーにのめり込み、埴谷雄高の精神に震撼したのだ。出口の無い苦悩に、ベートーベンの音楽がのしかかっていた。
私は、精神の苦悩と青春の肉体がもたらす苦痛に苛まれ続けた。悶え苦しんでいたという表現が、最も適切かもしれない。しかし、そのゆえにと言うよりも、そうだからこそ出会う書物に私は出会ったのだ。その幸福を、以後の50年近くかみ締めている。悶え苦しむことによってのみ、解り合える本がこの世にはあるのだ。
それが、『生の悲劇的感情』である。『葉隠』以来の「出会い」と成った。生命の苦痛が、この出会いを促した。そういう思想が、この本には充満している。本の中に苦痛を突破して進み行く「力」が充溢しているのだ。著者のことは、高校生であった私は、その時初めて知った。スペインの哲学者ミゲル・デ・ウナムーノである。反骨の哲学者であり、苦悩の詩人であった。
ウナムーノの魂は、私を囚えて放さなかった。永遠を目指す苦悩の魂を知って、私は小さな自己を恥じる思いであった。ウナムーノの哲学は、理論ではない。これは、血であり涙であった。苦痛と苦悩を抱えた魂だけが目指すことのできる「希望」であった。
ウナムーノは自己の哲学を、生まれ苦悩し死ぬ「肉と骨の人間」のためのものだと言った。これこそが、わが哲学だと直観した。
「絶望こそが、不可能なことを行う原動力である」という言葉に直面したとき、私は生命の奥底からの慰めを得た。私の魂は、『葉隠』に始まり『生の悲劇的感情』の中に、その結論を得たのだ。
×スペインを拠点に長く自己の信じる芸術に打ち込み、ほとんど無名のまま世を去った日本人画家がいた。戸嶋靖昌だ。その孤高の生きざまと作品にほれ込み、日本で過ごした晩年の彼と交流。作品を譲り受けて「戸嶋靖昌記念館」を開設した。
戸嶋は1934年、栃木県生まれ。武蔵野美術学校(現武蔵野美術大学)の西洋画科と彫刻科に学び、40歳で単身スペインに渡った。グラナダに落ち着き、市井の人々の肖像や腐りゆく果実、部屋の窓から見える風景などを描き、66歳で帰国するまで絵画の「原点」をそこで追求した。
私が戸嶋を知ったのは2002年。ある美術雑誌に載った小さな肖像画を見て、体に戦慄が走った。幾層にも塗り重ねた深みのある暗色が、まるで画面奥底に穿った彫刻のように空間を圧していた。体の奥から湧き上がる祈りや音楽のような崇高さがそこにはあった。
作品に一目ぼれした私は、すぐに自分の肖像を依頼しようと彼に接触した。当時68歳。総白髪、高いワシ鼻の知的な風貌だったが、性格は気さくで明るかった。私より16歳上だったが、すぐに意気投合した。
戸嶋は他人に頼まれて作品を描いたことがなく、私に会ったのも直接断るためだった。私は「似ているかどうかはどうでもいい。私の魂を描いてほしい。キャンバスの真ん中に点を打って『これがおまえだ』というのならそれでいい」と訴えた。情熱が通じたのか、戸嶋は「そうか、わかった。よし、一丁やるか」と言った。そこから私たちの関係が始まった。
食品会社を経営する私は、当時、東京・虎ノ門にあった社屋の一室に戸嶋専用のアトリエを作った。彼は都内の自宅からここに通い、制作に没頭した。夜になると私の肖像画に取り掛かる、その仕事ぶりはすさまじかった。鍛え抜いた強い腕で画布に絵筆をたたきつける。まるで苦痛の中にしか真の創造はないという姿だった。
「肖像画は描く人間と描かれる人間の生命のやり取りだ。どちらかが倒れるまでやるぞ」と戸嶋は言った。1時間もすると本当に倒れるかというぐらいに消耗した。回を重ねるごとに肖像は塗り重ねられ、顔が次々と変わった。写真で見ただけの私の先祖が次々と現れた。私の遺伝子の動きを見ているのではないか。そんな畏怖さえ抱いた。
私の注文は一切聞かなかった。「あなたは自分の横顔がいいと思っている、だから死んでも描かない」。粘土で私の頭部を制作した折など、「この耳の形いいな」とほめた瞬間、ばっさりと耳を切り落とした。「本人がいいと思っているのはダメだ。不均衡の中に魅力がある」と戸嶋は語った。
一仕事終えると酒盛りとなり、芸術や哲学談義に花を咲かせた。戸嶋は「柔らかいベッドで寝たがる奴と、うまいものを食いたがる奴を俺は信用しない」と言った。安楽は独立自尊の精神や真の芸術の妨げになる。私は「泉の傍らに立ちて、喉の渇きに私は死ぬ」というヴィヨンの一節を引いて応えた。戸嶋が我が意を得たりと少年のような笑顔を浮かべたのが今も忘れられない。
05年10月、末期がんで余命半年を宣告された戸嶋は、「俺は死ぬまで画家でいたい」と治療を拒み、そこから50号もの大作の肖像画に取りかかった。残る命のすべてをぶつけるように筆をふるい、作品は最後まで変幻を繰り返した。これが絶筆となり、06年7月20日死去。72歳だった。
死後、戸嶋を敬愛する多くの人たちが追悼した。画家の磯江毅は彼のデスマスクを描き、韓国の写真家チョン・セヨンは撮りためた戸嶋の写真集「TOSHIMA」を4ヶ国語で出版。私も8年がかりで生涯を調べ、評伝『孤高のリアリズム』(講談社エディトリアル)をこの春出版した。
自宅に残る800点余りの作品をすべて譲り受け、麹町の新社屋に記念館を開設した。重い画面の作品ばかりだが、なぜか若者を中心に来訪者が絶えない。戸嶋は生前だれにも絵を売らず、スペインでは妻からの少ない仕送りで極貧生活を送った。そんな彼が「マエストロ」と呼ばれ、尊敬を集めていた。芸術に命を賭けた男の魂が、国境を越えて多くの人々の心に共鳴していたのだろう。
×「本の出会いと人との出会いで人生は変わる」という言葉を私は信じています。この本、この人と出会っていなければ、自分自身がどうなっていたかわからない。このような出会いは、もう過去には戻れないほどの経験、体験となるものです。逆に言えば、そのような強烈な出会いであるからこそ本物の出会いといえるのでしょう。
「あの時、あの場所でカミさんと出会っていなければ…」とどんなに悔やんだって、もうどうにも後には戻れないのと同じですね。
さて、後戻りできないほどの強烈な本との出会いといえば、この本しか私には思い当たりません。執行草舟著『生くる』です。私と同じくこの本と出会って、強烈に人生の方向を変えた方も多いだろうと思います。この本と出会うまでは、当たり前だと思っていた常識や、誰かから与えられたモノや社会の仕組みについて疑ったことがありませんでした。東日本大震災が起きるまで、電気はあって当たり前だと思っていました。ところがそうではなかったという事実を多くの都会人は感じたことと思います。
それと同等の衝撃を、この本は読んですぐに受け取らざるをえなくなるのです。この本には「似非民主主義」という言葉が頻繁にでてまいります。あまり普段聞いたことのないこの言葉は本文の中にこんな感じで登場します。
「悲しむべきことだが、人類の歴史は各時代とも身心ともに秀でた人は少数しかおらず、大多数の人間は私利私欲の虜となり物質万能、拝金主義で生きてきたと見受けられる。したがって、読書人は過去の読書人とつながることによって、環境により愚劣化される自己と戦わなければならない。そのための最大の武器は、何と言っても良書を読むことに尽きる。これは戦後、似非民主主義の嵐が吹き荒れるなか、私自身が自己の存在理由、つまりレゾン・デートルを確認していく過程で痛感したことでもある。すべての伝統を否定した、軽率な物質万能の消費文化から自己を守ってくれたのは過去の先人であった。(中略)先人につらなり、伝統につらなる生き方以外のものは、すべて自己都合と呼ばれる屁理屈となる。屁理屈が個人の枠をはずれて、時代の潮流となったものを、私は似非民主主義と呼ぶ」
この本に出会ってからは、当店では「縦糸の読書」と「横糸の読書」という言い方で本を分けています。縦糸の読書とは、時代が変わっても変わらない知恵であり、横糸の読書とは、その時代の流行りだったりその時代にしか通用しない道徳であったり、時代が変わったら善であったモノが簡単に悪になってしまうような知恵のことです。今の日本は、いろいろなことが大きな矛盾に蔽われる時代になったのは明らかです。その問題の解決をすっきりと片づけるためには、縦糸の読書はこれからますます注目しなければならないと強く感じる次第です。その筆頭がこの『生くる』という本だといっていいでしょう。
×北秋田市育ちの画家・戸嶋靖昌さん
知人が本を執筆し紹介
北秋田市育ちの画家戸嶋靖昌さん(1934~2006年)の作品や生涯を紹介する書籍『孤高のリアリズム -戸嶋靖昌の芸術-』(講談社エディトリアル)が刊行された。戸嶋さんと親交のあった会社社長執行草舟(本名・祐輔)さん(65)が執筆。書店の人気ランキングで上位に入ったこともあり、没後10年のタイミングで戸嶋さんの作品に改めて光が当たっている。
書籍は4部構成で、1部は戸嶋さんが活動拠点としていたスペイン、東京で描いた風景画や肖像画など約140点を収録。2部には、絶筆のモデルにもなった執行さんが戸嶋作品の解説や肖像画を描いてもらった際のエピソードをつづっている。3部は国学院大学の小池寿子教授(西洋美術史)の寄稿文、4部では戸嶋さんの経歴を紹介している。
執行さんは02年に戸嶋さんと知り合った。自らが経営する都内の食品会社「バイオテック」の本社ビル内に戸嶋さんのアトリエを設け、創作活動を支援。12年には戸嶋さんの遺族から譲り受けた絵画を展示するギャラリー「戸嶋靖昌記念館」を本社ビル内に開設。画業を後世に伝えようと一般公開している。
戸嶋さんは栃木県生まれで、5歳から父の実家がある北秋田市で生活した。大館鳳鳴高から武蔵野美術大に進み、卒業後はスペインを拠点に活動。海外生活が長いこともあり、日本国内での知名度は決して高くないものの、重厚感のある色使いやタッチを特徴とした作品が注目され、近年ファンが増えているという。
執行さんは、戸嶋作品について「哲学性が強い。自宅に飾って気軽に楽しむタイプの作品ではないが、生命が持つ悲哀や苦しみを描ききっている点が魅力だ。書籍は20~30代の若い世代が購入している」と説明。戸嶋さんは生前、作品を大々的に発表する機会が少なかったとし「これから秋田を代表する作家になるだろう」と話している。
×ただ一人で生き、深淵な芸術を残して逝った戸嶋。その遺志を受け「戸嶋靖昌記念館」を設立した執行草舟氏から敬愛に満ちた寄稿が本誌へ
東京鳳鳴会の会報に、私の拙い文を掲載していただけることを感謝します。この文を認める私自身は、鳳鳴高校を卒業した人間ではありません。しかし、多くの卒業生の方々にも負けず、大舘鳳鳴高校を愛する人間であることに関しては引けを取る者ではありません。なぜなら、私がその記念館を設立運営するほどに尊敬している画家、戸嶋靖昌が鳳鳴高校の卒業生であるからです。
戸嶋靖昌は、1934年に秋田県鷹巣町の旧家に生まれ、1952年に鳳鳴高校を卒業しました。その後、親の反対を押し切り画家として立つために、東京に出奔、武蔵野美術大学を卒業したのです。戸嶋は、若き日より天才の名をほしいままにしましたが、金銭や名声を一顧だにせず、己れの芸術の道だけを貫き通しました。その72年の生涯は、まさに壮烈であり凄絶を極めたと言えましょう。
私は、この戸嶋芸術に対して、「孤高のリアリズム」という名称を付与しています。その名称で展覧会を行ない、著作物も著しています。そして、自分の経営する会社に1フロアの展示場と1フロアの保管美術庫を有し、戸嶋靖昌の顕彰を行っているのです。戸嶋は、現世には一切の妥協をせず、ただ独りの道を歩みそして死にました。多くの人に誤解されていた人生でしたが、死後、その芸術的価値は広く世に浸透を始めてきたと思っています。
私が、戸嶋靖昌の死と共に、本人とその遺族の方々の意向によって「戸嶋靖昌記念館」を設立してから、早や八年の歳月が流れました。去年は、駐日スペイン大使館の主催による「孤高のリアリズム -戸嶋靖昌の芸術- 」展が一ヶ月に亘り催されました。スペイン大使館の催しとしては、大使館創立以来の大成功を収め、これによって数年後には、スペイン国家の後援による展覧会が、戸嶋の長く住んだグラナダで開かれる予定も立ちました。
また、今年に入り三月には、戸嶋芸術の決定版とすべき本が『孤高のリアリズム』という題名のもとに出版されたのです。不肖、私が戸嶋絵画を説明し、戸嶋との対話のエッセー、そして八年に亘り克明に調べた略年譜が載っています。他に、日本における西洋美術史の第一人者であり、國學院大學教授の小池寿子氏が、本書のために戸嶋絵画の論文を寄稿して下さったのです。この美術史界の泰斗は、戸嶋の良き理解者であり私の友人でもあるのです。このような経緯で、戸嶋芸術を世に問う準備が着々と整いつつあります。
さて、戸嶋靖昌と私の出会いは2002年に遡ります。戸嶋にぞっこん惚れ込んだ私が、肖像画を依頼することによって関係が築かれました。そして三年強の月日を共に過ごしたのです。出会ってしばらくした時に戸嶋に癌が発見され、七十二歳にして他界したのです。私は、戸嶋と共に、私が経営する会社の中に作ったアトリエで、毎日のように議論をたたかわせました。その三年間の思い出は、何にも代え難い美しい思い出として私の心にいまでも鮮明に残っています。
それは私の人生における焔(ほのお)のような時間であり、私の宝物として最後の日まで心の中に大切に抱き締めておきたいと思っているのです。戸嶋もそう思っていたに違いありません。そう思っていたからこそ、死後の自分の業績を扱うすべてを私に委任してくれたのだと思います。戸嶋の「死に水」を取った人間として、私は戸嶋の人生と芸術を後世に伝える義務があると思っているのです。
その戸嶋が、芸術以外のことで懐かしむものが二つありました。その一つが母親のことでした。もう一つが、鳳鳴高校の頃の話なのです。戸嶋は、画家であるにも拘らず美大のことよりも高校生の頃のことの方が話の中心となっていたのです。死の床で、最後の日々に口にしていたことは、母親の思い出と鳳鳴高校の同級生とのいたずらの思い出話ばかりでした。悪友とのいたずらは、昔の高校生たちの大人びた「教養」が感じられて、現代ではすっかり失われてしまった「男らしさ」のようなものをいつでも感じていました。
また、戸嶋は自分が生涯を芸術家として全う出来た基礎を、すべて鳳鳴高校の美術教育のおかげだと断定していたのです。その恩を戸嶋は私に語り続けました。そのため、私は昭和二十年代の鳳鳴高校、特に美術教育については、多分、卒業生の皆様よりも大いに詳しいだろうと自信を持っています。栗盛大地先生、そして伊藤彌太先生たちの人間性や芸術について随分と聞かされたものです。
戸嶋は、死ぬ日まで大館鳳鳴高校の卒業生であることを誇りにしていました。それは、信じられないくらい強く、私が鳳鳴高校の有する価値を実感するのに充分なほどでした。しかし、戸嶋は死ぬまで「執行は、まあいい男だが、鳳鳴高校の価値がいまひとつわかってない」というのが口ぐせだったのです。
思い出す度に、目頭が熱くなります。
×昨年11月、スペイン大使館のホールである画家の個展が開催され、反時代的とも言うべき暗く重い作品の数々は、足を運んだ美術関係者に強い衝撃を与えた。「こんなすごい画家がいたのか!」と。画家の名は戸嶋靖昌(1934~2006年)。武蔵野美術学校(現武蔵野美術大学)で絵画と彫刻を学び、67年に麻生三郎の推薦で銀座のサヱグサ画廊で個展を開き将来を大いに嘱望された。しかし、70年の三島由紀夫自決事件に魂を揺さぶられるような衝撃を受けた戸嶋は74年、商業的成功の可能性を捨ててスペインに渡る。以後何度かの一時帰国をはさみながら98年までグラナダを拠点に周辺の人物や風景を描き続けた。
本書は、これまでほとんど顧みられることのなかった戸嶋芸術に捧げられたオマージュであり、同時に戸嶋研究の土台を提供する試みである。著者の執行草舟氏は、妻の死をきっかけに帰国した戸嶋にアトリエを提供して創作活動を支援。友として肖像画のモデルにもなり、没後はすべての作品を譲り受けて戸嶋靖昌記念館を創設した人物だ。
4部構成の本書の第1部では読者が戸嶋芸術の本質を直観につかめるよう、作品138点をカラーで掲載、それぞれに戸嶋の言葉や執行氏の詩歌や短文を付す。第2部では晩年の戸嶋の言葉を踏まえた執行氏の渾身の戸嶋芸術論が展開される。いわく、≪「目は、描かないで描く」と戸嶋は言っていた。生命の奥にある「存在としての目」が戸嶋の描こうとする目なのだ≫≪「芸術とは、深淵との対話である」と戸嶋は言っていた。深淵とは、生命の悲哀を言っている≫≪戸嶋は、いつでも生命の悲哀から発せられる、幽かな揺らぎを見つめ続けていた。それが戸嶋芸術を特別な「供物」に仕立て上げているのだろう≫…。戸嶋のリアリズムとは、対象を見つめ、その奥にある高貴な魂を探し出し描くことなのだ。
第3部は正統の美術史の文脈に戸嶋を位置づける、小池寿子氏の精緻な論考、第4部は徹底した調査に基づいた詳細な年譜となっている。紛れもない労作である。
×昨年11月、駐日スペイン大使館で戸嶋靖昌(1934~2006)の回顧展が開催された。グラナダでの活動期間が長かったこともあり、日本では決して知名度が高くない画家だ。にも拘らず、多数の動員を記録。重々しく、生命感みなぎる肖像画や風景画の数々が来場者を魅了した。
その戸嶋靖昌の作品集が刊行される。派閥に属することも派閥を作ることもなく、ただ独り絵画と向き合った画家の人生も解説。著者は、絵のモデルとして、また友として晩年の戸嶋と親交深かった執行草舟氏だ。<戸嶋は、「柔らかいベッドで寝たがる奴と、旨いものを食いたがる奴、俺は信用しない」と私に言った>。<戸嶋は、キャンパス面のすべての個所を愛している>。身近で接した者のみが知る素顔から、画家の制作に対する凄まじい覚悟が伝わってくる。また小誌でもおなじみの小池寿子氏も寄稿。スペインの歴史的背景とともに、同地が戸嶋の作品に与えた影響を考察している。
地位も名声も、生活のための金銭すらも求めず、「リアリズムとは何か」を問い続けた戸嶋。作品のみならず、その生涯を通して知られざる姿を伝える決定版だ。
×人が生きていくためには、「ことば」が必要となる。
そんなことは当たり前、と言われるような自明のことでもある。
ただ、その言葉を日々どれだけ大切にして、生活することができているかを振り返ってみると、自身の課題というものが、明らめられるかもしれない。
たとえば、今日という一日を、自分がどのようなことばを発したかを振り返ると、どうだろうか。家族とどう話したか、挨拶はきちんとしていたか、友人とどんな言葉を交わしたか、友人とどんな言葉を交わしたか、など、どこまで思い出せるだろうか。それは習慣的であったり、相手への甘えから礼儀を欠くものであったり、自分の気持ちを一方的に押し付けるものあったり、また単なる情報であったりするかもしれない。一歩立ち止まり、相手との対話ができていたのかを考えると、あまり価値のない内容や音声を発していただけといったことはないだろうか。
もちろん、誰かと何かを楽しくおしゃべりをする一時は、人生の中でかけがえのない時間に違いない。家族との語らいは、美しき思い出ともなるだろう。しかし、どれだけ他者に意味のあることばを伝えられているか、他者を思いやることばを発しているかを考えると、心許なさを感じるところがあるかもしれない。
そのように考え、「ことば」を大切にしようとすると、「沈黙」ということの意味がみえてくる。我々は普段、やみくもにことばを発しているわけではないけれど、沈黙への苦手意識や気まずさから、つい何か話をしようと無理をすることもある。
「ことば」の原始をたどり、ことばとともに「沈黙」がそこに存在していたことを、美しく、荘厳に表現した詩歌がある。
長田弘の「はじめに……」は、多くの詩歌を生きる糧としてきた執行草舟氏の詩歌集に、紹介されている。執行氏は長田氏との出会いを「生というものを、根源的なところから考え抜き、その響きを感じ取っている、詩人の偉大な感性と知性に驚嘆する」「人間の生を大切にし、また信じ切っている詩人の誠実さがひしひしと私に迫って来る」「この宇宙にあって、我々人間の本当の生とは何かを問いかけるこの詩人は、まさに私の心の友としか言えない」と語る。
はじめに……
長田弘
星があった。光があった。
空があり、深い闇があった。
終りなきものがあった。
水、そして、岩があり、
見えないもの、大気があった。
雲の下に、緑の樹があった。
樹の下に、息するものらがいた。
息するものらは、心をもち、
生きるものは死ぬことを知った。
一滴の涙から、ことばがそだった。
こうして、
われわれの物語がそだった。
土とともに。微生物とともに。
人間とは何だろうかという問いとともに。
沈黙があった。
宇宙のすみっこに。
また、この詩を賛して、「在る」ことの重要さを、これほど飾り気なく、簡単に美しく表現している詩句はめずらしく、削り取ることによって、芸術を生み出す彫刻家を思い起こす、とも述べている。そして、「在る」ものは、宇宙、自然が初めで、人間が初めではなく、その順番がしっかりとわからなければ、我々は本当に生きることはできないのだと言う。永遠と呼ばれるものが元々あり、その永遠の中から自然が生まれ、自然の中から、我々が創り上げられた。そして、我々は死を深く認識する生き物であること、人間の物語りは涙を知ることによって生まれ、人間とは何かを問い続けることが人間の人間たる理由となるのだそうだ。
この詩は、このような根源的な重要事項を、私たちの心に、優しく静かに語りかけてくるようだ。宇宙の原始を認識する心は、微生物とともに土に還ることを定められた身体に宿るが故に、悲哀を感じているのだ。悲哀は生命の摂理であり、そして恩寵でもあるのだ。そこから目をそらしてはいけないのだろう。悲哀を抱きしめる生命の紡ぐことばは、宇宙の中でたしかに生かされている存在として、人間とは何かという問いと沈黙の響きとなって、心に染み渡るのだろう。
長田弘氏は、多くの詩歌を残して、2015年、亡くなられた。『黙された言葉(みすず書房)』に本詩歌は掲載されている。執行氏の『友よ』の解説とあわせて味読したい。
引用文献
長田弘:黙された言葉、みすず書房、1997
執行草舟:友よ、講談社、2010
スペインを愛した異色の日本人画家を紹介する「孤高のリアリズム - 戸嶋靖昌の芸術」展が、港区六本木の駐日スペイン大使館で開催されている。
暗色を塗り重ねた底から、確かな命の存在を響かせる人物像。塔がそびえるグラナダの空に浮かぶ悲しみ。繰り返し描いたメンブリージョ(カリンの実)があらわす生命の変容- 。人間存在の本源に迫る作品約100点(期間中展示替えあり)が展示されている。
昭和9年、秋田県に生まれた戸嶋は、武蔵野美術学校(現・武蔵野美大)で麻生三郎、山口長男らに師事。画壇に交わることなく自己の芸術性のみと向き合い、名利と無縁の生涯を送った。芸術上の危機に陥った49年、スペインに渡り26年間を過ごす。グラナダに居を構え、人々の暮らしに溶け込みながらふ風景や身近な人物の肖像を描いた。
帰国後の戸嶋と出会い、平成18年に没するまで深い親交を結んだ執行草舟・戸嶋靖昌記念館館長は、「彼の絵の重さや暗さは、物質や生命の持つ宿命そのもの」と話す。
28日まで(日曜閉館)。入場無料。
問い合わせは戸嶋靖昌記念館事務局 03・3511・8162
駐日スペイン大使館の主催により、東京・六本木の同大使館内ギャラリーで「孤高のリアリズム」―戸嶋靖昌の芸術―展が始まった。戸嶋靖昌記念館(東京都千代田区麹町)が収蔵する作品のうち100点近くが展示されている。そこからはスペインを愛し、それが作品に色濃くあらわれた戸嶋靖昌(1934~2006)の生きざま、思想、創作への熱情が伝わってくる。
展覧会が始まる前日の11月4日、展覧会場では、駐日スペイン大使館や、戸嶋作品を収蔵する戸嶋靖昌記念館の関係者、来賓など約200名が集まり、前夜祭が行われた。「生命の根源」を探求し、それを絵画や彫刻として表現した戸嶋靖昌の作品群に、出席者からは次々と賞賛の声があがった。
17世紀にスペインで活躍した画家、ベラスケスの作品を思わせる、深く暗い、しかし迫力に満ちた油絵の数々が濃密な空間を生み出している。
戸嶋は72年の生涯のうち30年近くをスペインで暮らした。そのことが縁となり、今回の展覧会につながった。亡くなって9年。今回、総数で100点以上の作品が一挙に公開されることになった。
駐日スペイン大使、ゴンサロ・デ・ベニート氏は開会の挨拶で、「戸嶋がいかにスペインを愛し、どれほど大きな影響を受けたかは作品を見ればわかる。作品を通して、日本とスペインがより共感し合い、ますます友交が深まるのではないかと思う」と話した。
また、スペインから日本に帰国した戸嶋を支援し、その死後、すべての作品を買い取って「戸嶋靖昌記念館」を創設した執行草舟氏は、「戸嶋靖昌は、いつも『見捨てられたものの中に美しいものがある』と言っていた。彼は名声も富も求めず、ただひたすら自分が目指す芸術を死ぬまで求め続けた。体を動かすだけの最低限の食物をとり、睡眠も短かった。一般の人の日常とはかけ離れたところで生き、死んでいった人だった」と懐かしそうに語った。
戸嶋は生前、公的な個展を全く開いていない。有名になることには興味がなく、そのほぼすべての時間を創作に当てた。帰国後も、年に数ヶ月はスペインにいたため、中には修復の必要な作品も多くあった。戸嶋靖昌記念館ではそれらを丹念に修復していたため、今日まで9年の歳月を要した。
戸嶋靖昌の長男で、戸嶋靖昌記念館の名誉館長でもある朋嗣氏は、「父が生きていたら、こういう華やかな場に照れていたかもしれない。父は特に、恩を感じて感謝の気持ちを表すことを大事にする人だった。私は父と離れて暮らすことが多く、一緒にいた時間は短かったが、会うと、『とことんやれ』とか『徹頭徹尾』とかいう言葉で激励された。あれば自身に言い聞かせていたのかもしれない。真っ直ぐでエネルギーのある人だった」と語った。
日本を愛し、スペインを愛し、生命の真の意味とは何かを表現し続けた孤高の画家、戸嶋靖昌。彼の作品はいま、人はなぜ人として生きているのか―を我々に問いかける。
戸嶋靖昌は1934年に生まれ、秋田県で育った。中学生のころから絵を描き始め、武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)西洋画科入学。のちに彫刻科へ転科。
卒業後は、教授陣の勧めで彫刻科助手となるが、67年、画業に専念するために退任する。妻の曰子は生涯、戸嶋の芸術の理解者であり、経済的にも支え続けた。
70年、戸嶋は三島由紀夫の自決に激しいショックを受けた。地位も名誉もある芸術家の死は、彼の生き方を定めたのかもしれない。その心情は、「冬の庭」という作品に表れている。自然の森に鬱然とした心を投影したのか、あるいは微かに洩れる光に希望を見出そうとしたのか。もともとバロック芸術に関心の深かった氏は、ついに74年スペインへ渡る。76年からはグラナダに転居し、2000年まで過ごした。
グラナダでの彼は、地域に溶け込み、街の人に愛されていた。身近な人々を描いた人物がも増えていく。近所の老女をモデルに描いたとき、彼は「老女の背後にある“時の重さ”を表現したい」と語っている。また、「グラナダには内向的な一つの悲しみがある」とも記している。常に眼の前にあるものの奥底を表現することに、全神経を注いでいたのだろう。
99年、妻が逝去。定年退職したらスペインで一緒に暮らすのを楽しみにしていたが、59歳で世を去った。戸嶋は激しいショックを受け、それを機に翌年帰国した。2年後、美術雑誌に載った小さな絵に、執行しが感銘を受けて戸嶋を訪ね、肖像画を依頼。芸術への思い、生命の根源などについて話すうち、ふたりの心が触れあい、執行氏は経営する会社内にアトリエを設けた。戸嶋はアトリエに通って制作を続け、作業が終わると執行氏と芸術、文学から音楽まで語り合った。ふたりが心から楽しみにしている時間だった。「柔らかいベッドを欲し、うまいものを食べたがる人間を信用しない」。戸嶋はよくそう言っていたという。どこまでもピュアで孤高の精神を持ち続けたまま、彼はものごとの本質、生命の根源を見つめ、それを作品へと昇華させていった。
執行氏は、戸嶋に向けてグラナダにまつわる聖人、十字架のヨハネの言葉を贈った。「お前の知らぬものに到達するために、お前の知らぬ道を行かねばならない」
戸嶋は、芸術の世界においてひとりで生き、ひとりで逝った。生命の根源を探求した彼の作品は、後世に生きる我々に残された。
2006年に彼が亡くなったとき、ニュースを知ったグラナダの友人たちは深く悲しみ、戸嶋が愛した日本映画を上映して彼を偲んだと言う。
×美達大和は、現代社会に突き刺さった一本の「棘」である。この棘は、飽食の時代に生きる我々に、鈍い痛みを伝え続けている。豊かさの上に、恥を忘れた我々に、真実という痛みを発信しているのだ。美達の思想が深刻なのはそのためである。
しかし、その思想を表す美達の言葉には、深い温かさがある。それは、美達が自分自身の人生をかけて語っているからだろう。つまり、美達は「血」で書いているのだ。人間として燃えたその血が、我々に何ものかを訴えている。私は、美達がもつその「生命の雄叫び」に魅了されていると言っていい。
本書は、その美達が著した最新刊である。一読して、この著者が何ものに憧れ、何ものに苦しみ、何ものを訴えたいのかが伝わってくる。この書には、人間の運命から滴る「涙」が見える。ひとりの男が、自分の生命に哭き、書物の中にそれを復活させているのを感ずる。
この著者は、自己の運命を本当の意味で愛している。自己の生命に正直に生き、読書を通してその成功と失敗のすべてをまっすぐに見つめ続けているのだ。その愛読書は、頭ではなく全生命で読み解かれている。それが勇気のいることだと誰が知ろう。
著者の読書体験は、自己の悲しみとの対面に違いない。それが伝わってくる。著者は、自己の運命を抱きしめているのだ。その始まりが本書の中にもある『ジャン・クリストフ』なのであろう。私はそこに深く共感する。若き日に、この書に親しんだ者を、私は友と感じてしまうのだ。
著者は古い人間である。つまり、真の「男」として生きた。だから、世間においては「敗北」したのかもしれない。しかし、その敗北は人間としての真の「勝利」に結び付いている。その敗北は、明らかに、あの保田與重郎が言った「偉大なる敗北」なのだ。それは、理想が俗世間に敗れたという意味に他ならない。
著者は、独力で真の人間的意識に到達している。そして「人はいくらでも変わり得る」という真実を、切々と語り続けているのだ
×武蔵野美術大学に学んだ後に渡西。スペインのグラナダで、26年間にわたって生命の源流を追求する絵画を描き続けた戸嶋靖昌の個展が開かれる。独立独歩を貫いた戸嶋。その晩年を支えたのは、作品と人物に惚れ込んだ実業家の執行草舟氏。著述家・歌人としても知られる氏は、800点以上の戸嶋作品を収集し、2008年に記念館を設立。この度、スペイン大使館で開催される展覧会には、草舟コレクションの戸嶋靖昌作品の初期から晩年までの100点以上が展示される予定だ。ここでは、展覧会図録収録のサンティアゴ・エレロ・アミーゴ氏(駐日スペイン大使館文化担当参事官)と執行氏の対談から主要部分を抜粋し、魅力を伝える。
執行 この度スペイン大使館のご協力で、戸嶋靖昌の展覧会を開けることを大変有り難く思っております。戸嶋がスペインという国と、スペインの芸術を、心の底から好きだったので、戸嶋靖昌の支援者としては大変光栄です。
サンティアゴ(以下SA) 私の見方では、日本よりもスペインを感じます。戸嶋は日本人的というよりも、とてもスペイン人的だと私は思いました。
執行 戸嶋の作品というのは、純粋な日本らしさはあまり無いかもしれませんね。例えば外国人の方が言う「日本らしさ」というのは、日本にある仏教的なものを指すことが多いのですが、その仏教的なものは、戸嶋の作品にはほとんど無いのです。まだスペインに行く前、日本にいた頃、戸嶋は「神道」の精神に共感していました。神道というのは、天を目指す垂直の精神とでも言いましょうか。仏教はこう、水平の精神を示すのですが、戸嶋は仏教的というよりは、神道的な思想家であり芸術家だった訳です。
SA 彼の作品を遠くから見ると、暗い印象があるのですが、その暗さの中に信じられないほどの光があって、スペインでいえば、ゴヤが根底にあるのでしょうか。暗闇の中の光を好むやり方は、ベラスケスやレンブラントなどを思い起こすのですが。
執行 戸嶋の暗さというのは、同じ暗さでも先ほど申し上げた神道とか、ヨーロッパでいうとキリスト教の根源的な生命の意味、つまり生命の神秘が持っている暗さが絵に出ているのです。戸嶋は、生命の神秘を描こうとしています。そこには生命の中から発せられる「人間の光」というものもあるのです。
SA よくわかります。確かにそうですね。戸嶋の作品が生きているというのは全面的に同意見です。
執行 戸嶋の作品はベラスケスの作品により似ているのではないかと思いますね。内面的にという意味です。ベラスケスは、戸嶋が一番尊敬していた偉大な画家の一人ですが。外面的な描き方は違うのだけれども、垂直というか、天を目指すような、キリスト教的な生命観がベラスケスにはあると僕は思っているのです。戸嶋もそういうものを目指していたということです。
SA 対談の準備をしているときに、まさにそのベラスケスのことも考えていたので、話題に出て良かったです。おっしゃるように、生命の奥底を至向する精神性と光の追求が、戸嶋をスペインへ向かわせたのではないかと思います。
礒江毅は、超具象の大家でしたが、画家の先輩として戸嶋を尊敬していたそうですね? そういえば大使館の展示で、礒江毅とフェルナンデスの現代リアリズム展を開いたときに、礒江によって描かれた戸嶋靖昌のデスマスクが飾られましたね。二人の友情が伝わってきました。
執行 戸嶋はリアリズムの原点になるもの、つまり物や生命の源流を描こうとしている、という点が戸嶋独自であり、他の画家と全然違うと感じていた。少し表現しにくいですが、いわゆる芸術ということではなくて、源流 —つまり「生命の痕跡」に向かっていったのが戸嶋芸術といえます。
SA 今回の大使館での展示は「孤高のリアリズム」というタイトルがつけられましたが、これは戸嶋が追求していたリアリズムのことでしょうか?
執行 リアリズムという言葉を使ったタイトルですが、「孤高のリアリズム」の意味は、リアリズムの様々な派閥や仲間がある中、戸嶋がただ一人で、そのような仲間も、派閥も知り合いも誰もいない中で、何が絵画なのかということを追求したいという意味です。ただ孤独ということではなく、そこには唯一人の存在が持つ高貴性があるのです。人間的には多くの人々に慕われていたから「孤独」ではなかった。しかし芸術に関しては、ただ一人で、宇宙に実在する生命の神秘を描こうとして戦い続けました。
SA このタイトルは大変興味深いですね。ある意味具象とも言えるかもしれませんが、戸嶋の目指したリアリズムによく結びついています。
SA もしお許し頂けたら、グラナダ市長とお会いして戸嶋のプロジェクトを話したいと思います。戸嶋は30年近くもグラナダに暮らしていたのですから、何か記念的なことができればいいですね。例えば、アルバイシンの通りに戸嶋靖昌の名前を付けたらどうでしょう。
執行 そういうことが出来たら、戸嶋を通じて日本でもアルバイシンが多くの人の関心をそそると思います。是非進めて頂けたら嬉しいですね。
SA 戸嶋が最後に描いた晩年の肖像(『魅せられたる魂 -執行草舟の像-』)は、ゴヤの肖像に外面的には似ているのですが、完全にデフォルメされ、徹底的に破壊され、おそらくは彼自身の内面を超え、絵画を通じて表現できる肖像ではなく、人物の探求 — つまりはその奥にあるものを表現していたのでしょう。
執行 戸嶋は現代人なのですが、その前の時代の人間に属しているということです。だから、言い方はおかしいですが、ゴヤは近代人で、戸嶋は中世人という感じがします。それ故、中世的なものを、現代人の目で描こうとして、誰からも理解されずに苦しんでいたのが戸嶋だったのだろうと思います。
SA 戸嶋の絵について多く語ってきましたが、何よりも執行さんが戸嶋と出会った証言者となられた以上、戸嶋の作品を世に広める使命を持っておられることを深く感じるということです。そして、私自身、ここで見られる作品群が素晴らしいという理由だけではなく、戸嶋の作品に多く触れてきて、全ての人に戸嶋を知って頂けるようにしなければならないという倫理的使命を感じています。
執行 僕もそれを使命だと思っていますし、また戸嶋の生き方や戸嶋靖昌自身を作品とともに広めていきたいと思っています。戸嶋は、スペインという国とその文化がなければ、40歳位で壁にぶつかって画業を諦めなければならなかった時期があったに違いありません。だから、スペインという国にも、僕は戸嶋に代わってぜひ御礼を申し上げたいのです。戸嶋をスペインが救った理由として一つ言えることは、スペインが非常に宗教的であったことが挙げられます。つまりキリスト教的な文化伝統が戸嶋を救ったということです。また、戸嶋が言っていたのですが、スペインは様々な人間を受け容れる度量をもっていて、多様な文化に対して門戸を開いてくれる。だから自分も受け入れてもらえたのだと言っていました。そして、戸嶋は新しくスペインで芸術家として生きる道を見出したのでしょう。
×子どもたちの“生きる力を育む”ことが求められている。かつて小林秀雄は、心の在処を問うことに意味がないことをベルクソンやフロイトを引き合いに述べたが、現代は、心はどこにあるかと問い、脳にあるとする時代である。このような物質文明のなかで失われつつある心を見詰め、“人生とは何か”“いかに生きるべきか”という問いに、大変やさしく答えてくれる本が登場した。『生くる』『友よ』『根源へ』などの著書で知られる思索家執行草舟氏と、独自に良書を広める“本のソムリエ”こと清水克衛氏との出会いは必然だったのだろう。本書は2人の対談集であり、次から次へと展開される話題は興味が尽きないが、現代社会の中で立ち止まって考えなければならない大切なことが語られている。
たとえば、清水氏は現代を「簡単、便利、サルでもわかる、という文化」と称する。たしかに、現代が追い求めているものの本質を言い表しているようにも思える。また、執行氏は、現代が喪った精神を掘り起こし、「未完」で終わるような壮大なものに向かうことの偉大さを語る。執行氏が愛して止まない作家、埴谷雄高は、“神や霊魂と言った事柄は、論理的に絶対解明できない”としたカントに抗して“詩とか文学ならできるのでは”と発奮し、「かつてなかったもの、また、決してありえぬもの」を目指して『死霊』という文学作品に挑んだのだという。便利さや保障を求める現代社会が、理想や憧れを求める心を霧散させ、人々の心から自己固有の運命を生きることを忘却させているのかもしれない。もしそうだとしたら、それは1つのスピリチュアルペインなのではないだろうか。彼らの語りは、そのような魂に、読者に自分の人生を何に向かわせるか、自分が求めるものは何なのかといった問いを投げかける。
対談では、2人の人生を築き上げてきた糧として、さまざまな契機における豊富な読書体験が語られている。本は単なる紙の物体ではなく「1冊の本というのは、1つの神秘」なのだという。イスラムの神学者ムハンマド・アル・ガザーリは、読書の根本の問いに答えて、コーランをなぜ読むかと言えば、それは知識ではなく“哭くために読んでいる”のだとの紹介がある。我々は、新たな知識を得るために本を開くことも多い。しかし、コーランは哭いたなら読んだ価値があるのだという。コーランという聖典を通して、心が震撼する時、民族の培ってきた魂に触れることになるのだろう。
日本にも日本人が心を動かされる物語、文学がある。なかでも魂に届くのは古い言葉で、日本では大和言葉なのだそうだ。“天地初めて発けし時、高天原に成りませる神の名は
”天之御中主神”とは古事記の冒頭の一節だ。
本書では、この宇宙の始まりと我々人間との関係について、“ビッグバンのエネルギーが天之御中主神なら、我々はその「わけみたま」”との壮大な話になる。自分の中にあるという“宇宙エネルギー”なる魂が、大和言葉に触れるうちに、日本人が連綿と価値を置いてきたものと共鳴できるように思えるから不思議だ。古来より言霊を大切にしてきた日本人の感性に、敬虔な気持ちを改めて抱く。
「矛盾」はあればあるほどいい、「得」をしたいと思うな、など、既成概念を覆すような言葉にも目を開かれる。“大切なものは目に見えない”という言い古された言葉があるが、本書は見えない大切なものに心で触れうることのできる「1つの神秘」なのかもしれない。手のひらサイズで鞄に入れて持ち歩けることも嬉しい。一度きりの人生を生ききり、かけがえのない大切な自己固有の運命を拓く必読書として、是非とも手に取っていただきたい。
×グラナダを拠点に、スペインで26年間にわたって画業をつづけた洋画家・戸嶋靖昌(1934~2006)の個展がスペイン大使館で開催される。
戸嶋は武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)を卒業後、同校助手を経て、1974年にスペインへ渡った。ベラスケスやエル・グレコ、スルバランなど巨匠たちへの憧れからの渡西だった。そして同地の風景や人びとを描き、戸嶋は自らの画業を切り拓いていく。派閥に属することなく、自ら派閥を作ることもない。地位や名声、生活のための金銭すら求めることなく、ただ独りで「リアリズムとは何か」を問いつづけ、絵画を追求したという。展覧会タイトル「孤高のリアリズム」はそんな戸嶋の生き方を反映したもので、重々しい絵画から生命の根源に迫ろうとする画家の姿勢が感じられる。
晩年を過ごした日本でも絵画との真摯な対峙は変わらず、加えて長らく離れていた彫刻の制作にも再挑戦した。
本展は初期から晩年まで、代表作を中心にした約100点の作品による展観。生涯を賭した数々の作品に出会える。
×北野武には、ひとつの深い印象がある。「誰よりも十戒を守った君は、誰よりも十戒を破った君だ…」という芥川龍之介のあの言葉である。
私は、ビートたけしこと北野武の中に、その重層構造を感じ続けているのだ。この芥川の言葉は、革命の精神に捧げられた詩と言えよう。私は北野武を見るたびに、現代社会における真の「革命」を感じていたに違いない。本書は、その北野武が著した最新刊である。それも『新しい道徳』と銘打たれている。やはり、革命の匂いがする。読む前に胸の鼓動が高鳴ってくるのを感ずる。この著者は、そういう伊吹を持っているのだ。私は本書を「一挙」に読み抜いた。一挙に、まず読む。その後に改めて、著者と自分の考え方のずれを問答として少しずつ租借していかなければならない。著者の語りに、魅力が溢れている分だけ、その人生の哀歓がほとばしる血しぶきとなって迫ってくるからである。
一読して、北野武という男の「覚悟」が展開されているのがわかる。著者の言葉は、その本物の覚悟によって裏打ちされているのだ。だから、面白い。思想の魅力が、著者の本音の生き方から生まれている。本物の生命が躍動する。それゆえに、著者は「不道徳」を恐れないのだ。不道徳が、真の道徳を支えていることを知っている。つまり、戦争が平和を生み、平和が戦争の準備をしているということだろう。自分の力で生きてきた者にだけ言える、真の思想が放射されていく。
「道徳は・正義ではない」 -そう著者は言いたいに違いない。権力者の自己都合によって道徳は生まれる。そんなものに簡単に騙されるようでは、本物の人生は歩めない。道徳は、時代精神によって、いとも簡単に変わっていく。それを見つめなければならない。民主主義が終われば、今の道徳は全て瓦解するのだ。
本書には、生命の雄叫びがある。その痛快さは、著者の人格が持つ「直接性」から生まれてくるのだ。本書によって本当の自己に出会えれば、それが「本当の道徳」を与えてくれることになるだろう。
×現在では、心は脳の働きによってつくりだされるものと多くの人が考えるだろう。かつて、文芸評論家の小林秀雄はフロイトを紐解き、無意識心理学では、心は脳の中に存在しておらず、どこにと問うことに意味はないと述べた。脳科学研究への期待が高まる現在では、そういった議論すら一笑に付されるかもしれないが、はたして唯物論的な見方、物質を中心とする考え方で、“生きる力”は育めるのだろうか。豊かさを求める物質文明や科学万能主義のなかで、私たちは大切な何かを見失いつつあるのではないか。人が有限の時間に気づき、人生をいかに生きるべきかを模索するとき、希望となりうるものはなんだろうか。それは、物やお金や科学の最新情報ではなく、この世の真理に触れられる一冊の書物なのではないだろうか。
これらの問いへの示唆を与えてくれるのが、思索家・執行草舟氏と“本のソムリエ”として著名な清水克衛氏の対談を収録した本書である。本書は、ひたすら経済成長を追い求める時代にあって“宇宙、生命、文明のことだけを考え、実践してきた”という事業家と、“世間で売れている本は死んでも売らない”という書店店長の出会いから生まれた。それぞれの道を切り拓いてきた2人の、仕事、愛、人生についての対談は、お金のことから宇宙の果てまで幅広く、実に面白い。それどころか、現代の既成概念を次々と塗り替えていくような迫力に圧倒されつつも、自然と自分に向き合わせてくれる不思議な力のある本なのだ。
たとえば、日ごろ何気なく使っている言葉について。清水氏は、巷で聞く“ウィンウィン”や“シェア”などの怪しい横文字に出会ったら、自身の言葉で訳してみると言う。それを受けて執行氏も、“昔の人が使っていた言葉を大切にすると、必ず本当のものがわかるようになる”と意気投合する。
本書では“恥をそそぐ”という言葉をめぐり、“そそぐというのは言葉の音の通り、身を削って反発エネルギーを出すこと”であり、“その言葉を知って、感覚的にでも「いいな」ととらえることができれば本当の生き方が必ずわかってくる”という。本当の生き方とは、魂を燃焼させ、自己固有の運命を掴む生き方と言い換えてもいいだろう。執行氏いわく、昔の人の言葉というのは、“人生を生ききること”に特化した言葉のつくりであって、テレビも情報も何もない時代に、生まれてから死ぬまで、どう生きるかだけが人生で、何もないからこそ、真実の言葉が生まれてくるのだそうだ。そこには、何かにつけて、理屈を考えたり、できない理由を探そうとする現代的な思考は存在しない。清水氏も、“「雪ぐ」と書いて、「そそぐ」と読む、なんてかっこいいんだろう”と語られているのだが、「恥をそそぐ」という言葉に魅力を感じるならば、それはその人の奥底の魂が本質を求めている証左ではないだろうか。
また、世の中の現象を「縦」と「横」の概念で仕分ける対話により、日ごろの違和感が氷解する。「縦」の概念は垂直、崇高なもの、個人として屹立すること、「横」の概念は水平、横並びと言えば伝わるだろうか。自己の「垂直」を立てて生きる人を“縦人間”と言い、横ばかり気にして生きている人を“横野郎”と呼べば、“人生を突き抜ける”には「縦の力」が必要なのは誰にもわかるだろう。しかし、自己の垂直を志向すれば、人から嫌われない人生を卒業しなければならない。そのためには勇気もいる。人生の選択は各々に委ねられているが、本書との出会いは、その勇気を引き出すきっかけになるかもしれない。
そして、「魂」の話は圧巻である。精神看護においても、とらえ方がそれぞれ異なる難しいテーマだが、本書では、執行氏の透徹した見解と清水氏の明晰な応答が見事に融合し、宗教色に偏ることなく、魂というものの実体を知り、概念への直感的な理解に到達することができる。
宗教で「魂」と呼ぶものを、科学的に「生命エネルギー」と言い換えてみると、この生命エネルギーは、もともと宇宙に遍満している。その微かな量のエネルギーの分霊が地球上の我々であり、清水氏は、これを、神道でいう「わけみたま」のことだと即座に解する。そして、執行氏は、我々の生命は銀河や星の生命と同じくビッグバンのエネルギーから出て来たものだと言い、話は我々の神話におよんでいく。
この宇宙の中や我々のなかにある生命エネルギーは、もちろん、目にみえないのだが、愛、献身などのエネルギーのことらしい。我々が美徳とする普遍的、かつもっとも崇高な価値は何かと問うならば、それは、時代や民族を超えて、永遠に「愛」であるということに異論を唱える人はいるだろうか。きっと、地球上の生命体は宇宙から降りそそぐ愛ゆえに生かされていて、生命の本質は、この宇宙に遍満するエネルギーとなんら矛盾することはないのだろう。つまり、宇宙の生命エネルギーの本質は、人類が営々と受け継いできた文化的価値がいかに築き上げられてきたか、また、多くの先人がその価値のために自己を投じてきた事実を考えれば、自ずと浮き彫りになるのではないだろうか。
自分という人間が宇宙のなかで生まれ、宇宙を構成する生命エネルギーの分霊であるという神秘は、唯物論的立場や科学では説明できない。しかし、自己の奥底にある魂は、宇宙の魂と共鳴することができ、生き方次第で、少しずつどこまでも成長させることができる。価値ある本や偉大な文学の魂と自己の魂を共振させ、憧れに向かって自己を投じる自由が、人間には与えられている。
まだまだ書ききれない数多の対話が本書の中にある。人生を生ききる2人の真実に触れた魂は、何かを感じ、反応を起こしていくだろう。1度きりの人生においてみずからの運命を生きたいと願う人に、ぜひとも手にとって読み続けていただきたい。
×『魂の燃焼へ』(イースト・プレス)が6月に発売され、増刷を重ねている。著述家で実業家の執行草舟氏と、「本のソムリエ」として雑誌、新聞への寄稿も多い清水克衛氏が、「読書」と「生命」について語り合い、思索を深める対談本。大型書店の中には、執行草舟専門コーナーを設け、大量に平置きしている所もある。執行氏は『生くる』『友よ』『根源へ』(いずれも講談社)などの思索書があり、現在、月刊「正論」で連載「憂国の芸術」を持つ。清水氏は、流行に左右されない良書を薦める書店「読書のすすめ」(東京都江戸川区)の代表で、NPO法人読書普及協会顧問も務めている。
―刊行後の反応は
執行 出してすぐ、大阪在住の大学生が読んだ勢いで、会いたいと東京まで訪ねてきた。その後も、同じように何人もの読書と良き出会いが続いており、十代から三十代が多い。人生観が変わったという声までいただいた。
清水 今回の本の中で取り上げた書籍が売れるという現象が続いている。埴谷雄高の大著『死霊』や、小林秀雄、福田恆存、森有正、森信三、安岡正篤らの著書。中には歴史学者、平泉澄の『少年日本史』など品切れになるものまである。
―読書の喜びを覚えた人や、読書を通じて思索をこれまで以上に深める人が増えた実感は
清水 店頭で多くの読者や来店者と接し、常連客になる人の顔を見ていると、本を読むことで顔つきも変わってくる。当店ではそれを冗談半分に「執行化現象」と呼んでいる。
執行 本の読み方が変わったという読者の声が多い。何かの答えを求めるために読むのではなく、問いをさがすために読むのが読書だと。過去の偉大な人たちの声に触れることで、何かに対する問題提起、疑問、考える材料がさらに増え、思索を深めることになる。
―問いをさがす本は、商売として厳しいのでは
清水 そんなことはない。当店は、答えだけを安易に提供する本や、置くだけで売れるような本は置かない。うちのような小さな書店には流行本がなかなか回らず、開店当初はくやしい思いをしたが、その反発から、本当に自分が良いと思った本を多く売るようになった。
執行 それこそ志のある仕事。お金や名誉にとらわれた商売ではなく、起業や経営には志がないといけない。私が経営している会社は健康や食に関わる分野で、私自身は禅の思想から、人々の体質を整えたいと願っており、食糧革命という志を掲げている。
―本書で取り上げられている本は、時代を超えて長く読み継がれている
清水 うちの店では「縦糸の読書」「横糸の読書」という言い方をしている。前者は、時代が変わってもずっと残る、普遍的なもの、つまり問いを見つける読書。後者は、時代が変わったらすぐに役に立たなくなる、いわば答えを安直に見つけようとする読書。
執行 清水さんが言う前者の中には、複雑で難解な本が少なくない。意味が分からなくても、とにかく読み進め、一行でも心に響けば、その本は読んだ価値がある。人間が人間たるゆえんは言葉にあるから。人類史を見ると、栄華を極めた古代文明の多くが、言語の簡略化と軌を一にして勢力も衰退した。私見だが、言葉は複雑であるほど、それだけ情感も多く、思索も深まる。
―読書によって思索を深めることは、現実を変える力になるか
執行 絶対的なものが世の中にあるか否かわからないが、だからこそ人は、自分の立ち位置を規定するために相対的に物事を捉えようとする。しかし、古くから読み継がれる普遍的なものに触れることは、その歴史の延長線上にいる自分の立ち位置を見出すことにつながる。私はそれを「垂直を立てる」と言っている。日本には『万葉集』『平家物語』『葉隠』など多くの古典がある。
清水 『葉隠』は、武士道とは何かを説いた江戸時代中期の書物。人間は生きている限り、いつでも死に直面している。だからこそ、どう生きるかと同じぐらい真剣に死にざまについて考えることは危険思想でも何でもない。死生観を封印する戦後教育を疑わずに育った私には衝撃だった。
執行 それこそまさに今回の本の題名『魂の燃焼へ』につながる。それぞれの生命が誰から生まれ、何がやりたいのか、このまま朽ち果てていいのか―。人間が自分の生命を燃焼させるために、燃焼させた先人の経験知を自分に注ぎ込む、読書はそのために有用で、その人の人生を自分らしく生きる劇薬となる。
×思索家・執行氏と「本のソムリエ」・清水氏。双方とも読書を通じて日常に疑問を抱き、その答えを経験の中で発見した読書家である。
本書はそんな二人の対話集であり、話題は読書を皮切りに仕事、愛、青春、そして人生へと移っていく。
語り合う中、清水氏が「難しくて本が読めない」という読者から寄せられた悩みを紹介すると、執行氏は「どんな本でもそうだけど。一行でも感動したらその本は読んだ価値がある」と応じ、読書の尊さを説く。
本書は読書の意味はもちろん、生きる意味をも考え直すきっかけとなるだろう。
×まず、帯に刷られた二人の写真を見て、「この人たち、普通じゃないな」と一目で思うだろう。執行氏は本誌「武士道への道」で壮大な“やんちゃ一代記”を連載中だが、実業家にして謎の思索家・執行草舟に、本のソムリエ・清水克衛氏が会いに行き、がっぷり四つに組んで、戦後の日本社会と日本人について、愛することについて、読書することの意味について…… つまり「生きるとは何か」を縦横無尽に語り合う。
インターネットとグローバル時代の到来により、人の心も世界全体も大きく変わっていく毎日。そこを突破する力は“根本哲理”にある。「時流に乗ろうなんて卑しいことを思うな」、「与えられた命をただ燃焼させることに専心せよ」、「楽しく生きることが人生の真の喜びではない」…… 発売直後からベストセラーにランクインしている本書。この本がそれほど多くの人に受け容れられるとは、いまの日本も捨てたものじゃない、か。
×浮世絵などに表現された市井の人びとの何気ない生活の美しさ、その構図や色彩は、モネ、ゴッホらの印象派の画家、ジャポニズムの絵画などに影響を与えた。それら印象派の絵画は、アメリカにフランスより多く収蔵されていると言われている。そのアメリカで活躍し、その浮世絵を始め陶磁器、掛物などの日本の美を世界に認めさせるために一翼を担い、他方色々な海外の万国博覧会、国内勧業博覧会などに関わり、日本美の創造による殖産興業と国立美術館の創設を願った明治・大正時代の「サムライ」の物語である。
執行弘道(1853-1927)
執行弘道は、佐賀藩士族出身、嘉永6年(1853)に生まれ。佐賀藩から推薦されて大学南校(東京帝國大学)に入学、米国に留学後に外務省に勤めている。清国(中国)厦門領事館勤務、明治10年(1877)香港、三井物産の初代支店長、明治13年(1880)に日本の工芸品の輸出振興を目的とする起立工商会社の新約克支店に転職した後に支店長になる。明治16年(1883)の米国ボストン万国産業博覧会ビジネスに執行は出展者座長代行として関わり、その後は数々の博覧会に参加した。起立工商会社は、明治24年(1891)に欧州の需要をつかめず、その影響を受けて解散することになる。
執行は、明治30年(1897)ニューヨーク5番街に美術商三笑堂を開業している。
その間に執行は、明治13年(1880)にニューヨークの画家、彫刻家、音楽家、建築家、芸術家などが集まるThe Tile Club、The Century Association 、The Aldine Club、倫敦日本協会、美術を普及するThe Caxton Clubに入会。The Grolier Clubで明治22年(1889)に米国で初の浮世絵の展示会を開いているが、明治29年(1896)の頒布会にはカタログに鈴木春信らの12人の浮世絵師の画に解説をつけ、ひと味違った浮世絵ビジネスをしている。
それは、多くのクラブで米国の芸術家たちとかかわり、彼らの美しさを極める姿に感化された様で、単なる工芸品から浮世絵、陶磁器、掛物などの美術に関心を生涯にわたって深めていった。一方でビジネスを通して万国博覧会、博覧会に国内外で関わり、日本の美、特に陶磁器などの殖産興業を目指して推進している。
その美への関心は、執行弘道自身が浮世絵の収集家でもあったことから分かる。浮世絵収集は日本浮世絵協会に所属し、後年に古今東西浮世絵数寄者総番付に東之方の「前頭」に列せられている。
その浮世絵への執行の見解は、大正4年(1915)の英文「日本の芸術」の中で書かれているが、卓越している。浮世絵の誕生は、「日本の上流階級の古い芸術に対する普通の人々の反発の結果であり、芸術的独立宣言と言えるだろう」。そして、浮世絵は「人々のために、歴史、小説、詩、恋愛、旅行などをイラストし、芸術的鑑賞力をひろめ、教育し、同時に色彩版画芸術を改良し、簾価な形式で絵を楽しむ喜びと方法を与えてくれている」と論じている。この様な浮世絵にフランスの印象派の画家たちは、直感的に新鮮な魅力を感じ、浮世絵の表現にある美を発見したのであろう。
浮世絵と言えば、旧帝国ホテルを設計したフランク・ロイド・ライト(1867-1959)の浮世絵収集は有名で、執行に依頼し、多くの浮世絵を集めた。その浮世絵はボストン美術館に今は所蔵されている。
執行は、早稲田大学に残る大隈重信(1838-1922)宛の手紙から住所は、明治31年(1898)頃から、麻布区飯倉町1-5(現麻布台1丁目) に晩年まで住んでいた。その執行邸の別棟(大正10年(1921)築)は、ライトと交友があり、さらに島崎藤村(1872-1943)が昭和5年(1930)の「飯倉附近」の中で、雁木坂に近く大師堂のならびにライトが残した意匠の家があると書いていることから、ライトの設計であったと伝えられている。飯倉町をたずねたが、残念ながら当時の写真を見つけることが出来なかった。
また、執行は古典本などの収集家でもあった。収集した古典本のために蔵書印を幾つか作っていたが、蔵書の表紙裏に貼る西洋のBookplate(蔵書票)も作っていた。蔵書票は蔵書印と同じであるが、その歴史が15世紀ごろにさかのぼり、ラテン語でExlibris「~の蔵書より」という意味らしい。蔵書票の特徴は、名前、好みの言葉、信念などが書き込まれ、銅版、木版、石版などの技法があり、芸術品との評価がある。執行は桜吹雪をあしらった和風の蔵書票を持っていた。
執行は、実に機知に富んでいて、蔵書票の特色を逆に蔵書印に引用した様である。明治31年(1898)頃に飯倉町に住んでいた執行は、その邸宅が前方の飯倉狸穴町、雁木坂上、後ろの緑の多い西久保八幡神社の三方から傾斜途中の地形にあり、それを意識してか、その印章の文言を「松下水流處」(松の下、水の流れる處)としている。だとしたら執行はユーモリストでもある。早稲田大学図書館に収蔵されている執行旧所蔵であった古典本に「松下水流處」、あるいは「松下水流處蔵書」の印が捺してある。
明治23年(1890)前後に、かつて東京帝國大学の教師であった、W.E.グリフィス(1843-1928)、哲学者E.F.フェノロサ(1853-1908)、日本研究家P.L.ハーン(1850-1904)、動物学者E.S.モース(1838-1925)らが、米国の雑誌に日本の日常生活や美術などの記事を書き、日本への興味が広がっていった。
日本の工芸美術品の輸出ビジネスが盛んになり、横浜のサムライ商会、米国で京都の古美術商山中商会、浮世絵の松木文恭、陶磁器の森村組、起立工商会社、パリの美術商林忠正らが活躍を始めている。後に日本美術品を流出させたとも言われるが、執行はビジネスをしながら国内外の博覧会に関わっていく。
執行弘道は、明治23年(1890)第三回内国勧業博覧会の工業、美術部門の審査官を始めてとして、第五回内国勧業博覧会事務官及び外事課長、さらに奏任官、高等官、大正博覧会で審査官に任じられる。明治26年(1893)から大正4年(1915)の間に、シカゴ閣竜博覧会美術審査官、同時に米国より絵と版画の美術国際審査員、仏国巴里万国博覧会の事務官、米国聖路易世界大博覧会の事務官、日英博覧会の美術部の金工、陶磁器、漆器の主席鑑査官、桑港市巴奈馬太平洋万国博覧会の理事官、米国からも芸術、彫刻部門審査員を嘱託されている。
万国博覧会などに関わりながら、執行は英文で、明治20年(1890)に米国の雑誌ʻThe Curio(骨董品)に「日本陶磁器の断章」、明治26年(1893)に米国の美術収集家の西洋の水彩画、油彩画や日本の陶磁器などの収集目録を編集し、その中で「日本陶磁器序論」を書いて評判を呼んでいる。明治43年(1910)英国の雑誌The Studioに「今日の日本の美術と芸術家―2-陶芸家」を大壺の写真を付けて書いている。執行は、佐賀出身だけに陶磁器などの普及に尽力をしている。また、明治32年(1899)頃、執行は圓山応挙の猛虎図などの掛物に画家、作品内容、所蔵者などの解説と写真を付けた日本美術帖(Japanese Art Folio)7帖を完成させ、後にTheCaxton Clubの美術本頒布会でも売り立ている。米国で日本の美を広めている。
国内にあって執行はデザインの重要性に着目し、明治35年(1902)に、社会の需要に応える美術、工芸作品のデザインは、全ての実物に応用することが出来る様に中学校、小学校から教えることが良いと「圖按普及の方法」を説いている。
そして、執行弘道は、市加古、巴里、聖路易万国博覧会、日英博覧会などの万国博覧会を回顧して博覧会が開催都市を発展させ、経済活動を活性化させ、友好を促進すると述べている。それらの日本の出展物を観て日本の文明の神髄を知り、自信を抱き、また、多くの出品物が自他の利便となる様に研究し、事業発展の好機となることを望んでいた。幻となった日本大博覧会が企画された際に、執行は「永久保存の目的を以て…美術館を建設し大博覧会閉会の後はこれを以て国立美術館」にと希望を述べている。日本美術の普及と保存を国内外で望み、勲五等瑞宝章を受章している。
執行弘道は、家庭内にあっては、外での善きこと、ありし事をも語ることがなく、こよなく猫を愛おしむ寡黙な人あったが、佐賀 葉隠誓願のひとつ、大慈悲心(励ましといたわりの愛)で人の為になる事を成した生涯であった。
×誰もが「楽をしたい」「得をしたい」「安定したい」と考え、そのためなら喜んで「家畜」にさえなろうという時代である。こんな風潮を憂い、半世紀以上にわたる古典との対話によって育んできた考えを、著書『生くる』『友よ』『根源へ』で日本人に真っすぐぶつけてきた思索家執行草舟氏が格好の相手を得て、「人間の本当の生き方」について激しくもおおらかに語る。その相手とは《世間で売れている本なんか売るものか》という情熱のもと、東京都江戸川区でユニークな品揃えの書店「読書のすすめ」を経営し、「本のソムリエ」としても活躍する清水克衛氏である。
執行氏の根本には、「何よりも命が大切」という戦後の風潮とは相容れない《人間を人間たらしめているものは、肉体よりも大切なものがあるという思想そのもの》とか《人間の最大の価値というのは、自分の生命よりも大切なもののために生きるということ》という考えがある。執行氏の考えに共感し、その境地にたどり着きたいと慣れる者に、本書はさまざまなヒントを与えてくれるはずだ。
冒頭、個性的な風貌をしている清水氏と顔を合わせるなり、執行氏はこんな言葉を吐く。《「自分の顔」をつくるのが読書の価値だということ。自分の生き方をつくると言い換えてもよい》。ここにすべてが言い尽くされている。周囲を見てほしい。読書をしない人間は、のっぺりとした馬鹿面をしているはずだ。
では、本とどのように付き合えばよいのか。《「わかろう」としないこと》と執行氏は言う。《わかるものを読んでいても、人間は成長しない。わからないものを読むから、そのうちわかるようになるんです》。そして《一行でも感動したらその本は読んだ価値があるんです》とも。また、読書は自己の独自性を築き上げる行為であると考える執行氏は、戦後日本の似非民主主義の「人から好かれなければいけない文化」と読書は、《すごく深いところで抵触するんだと思います》と分析(慧眼である)、《嫌われることを前提としない読書なんて、読書じゃない》と断言する。その通りだ。似非民主主義の中では、独自性を持つ人間はよくて「変人」、悪ければ「狂人」とみなされる。
さらに、暇さえあればインターネットの情報を集め、常にラインで「友だち」と繋がろうとする人間、つまり横ばかりを気にして生きている人間を《横野郎》と罵倒し、いまの日本人に求められるのは《縦の力》であると訴える。それは祖国の歴史や祖先の生き方を通じ、なぜ自分がいまここにいるのかを自覚することによって鍛えられるものであり、もちろんここでも読書が欠かせないのは言うまでもない。
執行節が炸裂する題名通りの熱い熱い本である。
×産経新聞の月間『正論』に「憂國の芸術」を連載する実業家で歌人の執行草舟氏と、「世間で売れている本は置かない」との信念で、全国から顧客を集める書店「読書のすすめ」の店主・清水氏の異色の対談。「答えではなく、問いを見つけるために読む」という読書論に始まる両氏の対話は、「人生」「仕事」「死」など多岐のテーマに及び、やがて「生命より大切なもののために生きること ― 魂を取り戻す」との命題に向かう。父祖の歴史から切り離され、「魂」を喪失して漂流を続ける戦後の日本人。国内外の情勢が激動の時代に突入する中、敗戦から70年の果てに行き着いたのが、老いも若きもスマホの画面に没頭する姿とすれば、行く末はいかに。最後の警鐘であり、決別の書である。
×日本の文化と言って思い浮かべるものは何だろうか。空気のように当たり前に日本文化を享受してきた我々は、その美しい文化をどれだけ次代へ伝えられているだろうか。日本文化の継承は、何もその道の師範や職人、名人だけの専売特許ではない。各々が与えられた持ち場で体現しようとすれば、自然とその風が漂うに違いない。では、何を受け継ぎ、何を伝えていくべきなのか。
本書は、古今東西の数多の先哲の言葉を紡ぎながら、日本の根源的な精神性を見事に蘇生させる。例えば、個性について。個性はどのように生まれるのか。「個性」とは人類文化の強靭な歴史と人間の葛藤の中から生まれるものであり、ヘーゲルが「民族の精神こそが真の個性である」と述べているように、民族の精神が個性を作るという。そして日本においては、世阿弥の「秘すれば花なり。秘せずば花なるべからず」の「花」こそが個性なのだと著者は説く。能の世界に日本的な美の凝縮を感じ、「花」を個性とする感じ方が腑に落ちるのは、祖霊により受け継ぐ遺伝子の記憶によるものだろうか。我々は誰に教わるともなく「秘すれば花」の醸しだす幽玄の世界に魅了される心を持つ。しかし、この深い精神性を養ってきた文化は今、閉塞感ただよう現代社会に覆われ、消えつつあるのではないだろうか。
有史以来の史実や偉人の言葉を縦横無尽に展開する著者の言説は、いわゆる宗教書や哲学書でないにも関わらず、人間はどこから来てどこに行くのかという深遠なるテーマを問いかけてくるようでもある。それはとりもなおさず、個々人の生を燃焼させ、生命(いのち)を輝かせるだろう。袋小路にある現代文明において未来に希望の灯を見出した人々の糧となる、新たな文明への壮大なる処方箋と言うべき一冊だと思う。
ד旅に病んで夢は枯野をかけ廻る”日本人なら、誰もが知る芭蕉辞世の句である。この句を聴くと、どこか心が広がりゆくようなロマンティシズムを感じないだろうか。思い描く情景は人それぞれかもしれないが、我々のなかにある原風景が各々の心に浮かび、日常から一瞬、心が解放されるのではないかと思う。
心に静寂の響きをもたらしてくれる芭蕉の句であるが、そもそも芭蕉は500年前に生きた西行に憧れ、西行のように旅の果てに野垂れ死にしたかったのだ。こうした死生観が、俳聖芭蕉を生むのだが、芭蕉は意に反して、畳の上で弟子に囲まれて息を引き取らなければならなかった。
かの芥川龍之介は、芭蕉の哀しみを解して、『枯野抄』において芭蕉の臨終場面をめぐる弟子達の心理を克明に描きだした。これらは本書のなかで取り上げられているのだが、西行、芭蕉、芥川といった天才達が憧れたある系譜をたどることによって、日本人が大切にしてきた何ものかに触れることができるのではないかと思う。
この『根源へ』は、古今東西の歴史に残る万書にもとづいた日本人のための形而上的宇宙論といえるものだ。
さて、旅の果てに野垂れ死にすることは、現代の価値観からすれば、およそ幸せとは言い難いのではないだろうか。家族に囲まれて畳の上で天寿をまっとうすることや、少しでも長くこの世を楽しむといった価値観のほうが、普通は受け入れやすいことと思う。しかし、本書によって、先哲の生き方を支える美意識や芸術作品を生み出す原動力などが紐解かれると、現代社会で是とされる偏った価値にとらわれることなく、これまで受け継がれてきた価値に気づかされるのである。
たとえば、一般に敬遠されがちな「老い」について、みなさんはどのようなイメージをもっておられるだろうか。多くの方は、若狭にこそ価値があり、いつまでも若くありたいと思われていないだろうか。若さが礼賛され、合理化が求められる現代社会のなかでは、できれば年をとりたくないと思うのはあたりまえかもしれない。
しかし、著者は“人生とは老いの道程であり、老いて成熟した人間にこそ価値がある”と断言している。つまり、人生の価値は、アンチエイジングではなく、人としての成熟にあるのであり、そうとらえれば、誰もが魂を持つ人間としての生命摂理にかなう目標をもつことができるのだ。もちろん、心の若さや健康を保つことは大切だが、それは、人生の目的のための必要条件であり、目的そのものでないことは言うまでもない。
与えられた生命を燃焼しつくして、一度きりの固有の人生に価値を与えるのは、他でもない自分でしかないことを、本書は真剣に考えさせてくれる。若さより老いに価値があるという、現代では逆説的ともいえる生命の法則を知り、そのことを実感できれば、漠然とした不安感は雲散霧消し、生の充実感が生まれてくる。
逆説的といえば、不自由のなかにこそ真の自由があるという理を知っておくことでも、いろいろな物事への向きあい方に差が生じると思う。平和で“自由”な時代に生きる私たちにとって、これは少し難しく感じるかもしれないが、著者によれば、とにかく自由というものは「制約」から生まれるものであり、いまどきの「自由」というのは、好き放題といった類の「放縦」なのだそうだ。
戦後の民主主義、消費社会文明のなかで、この「放縦」がまかりとおり、もののあはれを知る日本人の深い精神性の衰退を感じている人も少なからずおられることだろう。日本文化には、長く根づいてきた日本独自の「制約」があり、人々は、そのなかでこそ自由を味わうことができていたのだ。
本書では、精神科医の土居健郎が分析した「甘え」が強い日本社会の歴史的背景にも言及されている。土居は“父なき社会”の到来を指摘し、皆一様に子どものごとく甘えているわが国の現代社会を人類的な退行現象と言及している。このため、間接的にではあるが、精神看護においても示唆を得られる内容となっている。
本書は「別れ」を帰結としている。芭蕉は「自分だけでなく、木も石も空も時間もそれぞれが永遠の旅人」として接し、出会ったものすべてと別れながら旅をしたそうだ。そのように生きた芭蕉に思いを馳せて、名文“月日は百代の過客にして、行き交う年も又旅人也”を味わうとき、私はそれまで感じることのなかった日本人の根源的な魂へと回帰し、永遠に触れられた気がした。本書の「別れは復活のみずみずしい息吹を我々に与えてくれる」という言葉と相俟って『奥の細道』との新たな邂逅を果たせたのかもしれない。
読者の方々も「生命は未知なるものへ挑戦する」「情熱は不滅性への渇望から生まれる」「生きるとは呻吟する精神である」といった著者の透徹した言葉に触れ続けるうちに、自己が勇気づけられ、生命が躍動しはじめることを感じるだろう。本書を貫く明快で正々堂々たる主張は、何ものかを失った日本人の心に、不思議な安らぎを与えてくれるのである。
現在、大学では「国際人」なる人材育成が求められているが、わが国の分かの本質を知りたい方に強い味方となるのも本書の魅力である。死の半年前まで後進の指導にあたり、各界に影響を与え続けた土居健郎は、若き日のアメリカでの留学経験から「日本人の患者を診る以上は、日本語で記載し、日本語で物を考えるようにしよう」とかたく決心したと記している。そこから生み出された『甘えの構造』は、いまや世界8か国語に翻訳され、読み継がれるまでになった。日本文化を根底から理解した創造の価値が、今日の“グローバル化”する我が国において、一層その重要性を増しているように思われてならない。
日本の精神性を大切にした精神看護実践の底支えとして、日本の根源とのつながりを求めている方に、是非手に取っていただきたい1冊である。
×今年1月に日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)第5代チェアマンに就任した村井満さん。企業の執行役員などビジネスの第一線で活躍した経験を礎に、Jリーグのさらなる飛躍を目指している。多読家で、「本を通じて著者や登場人物と対話することで、自己の魂が磨かれ、情操が育まれる。読書の時間は何にも代え難い」と語る。
私はかつてリクルートで人事や人材紹介会社の経営に携わり、50歳を過ぎてから志願して香港に赴任し、多国籍の従業員を抱える現地法人の社長を務めました。さかのぼって大学時代は、達成はできなかったものの、中国大陸横断にチャレンジしました。外へと向かうそうした行動の原点といえるのが、高校1年の時に読んだ『竜馬がゆく』です。なぜこの物語に魅せられるのか自分でも不思議でしたが、「境界を越える」ことへのあこがれがあったのだと、人生における折々の衝動から自覚するようになりました。竜馬は、藩の境を越え、反目し合う政治勢力の境を越え、国の境をも越えんとし、異なる立場同士が共有できる「船中八策」のような価値を見つけました。同胞の結果は、悪くすると排他的、差別的な行動の引き金になります。越境して心を開けば本質的な価値にいきつくことを、竜馬から学びました。
『生くる』は、20代の頃に同僚を介してお会いして以来、心の師と仰ぐ執行草舟さんの著作です。歴史、哲学、科学、芸術など、その知識量は膨大で、知識のみならず、深い思考と体験に根ざした確固たる人生観の持ち主です。人の心の機微や葛藤をあらわにし、それへの向き合い方を示した本書は、私のバイブルです。「自信など必要ない。自信がないから日々精進できる」「作用反作用は自然の法則で、価値のある大きなことをしていれば、大きな反作用が壁のごとく出現するのは当然。壁が大きいほど生き甲斐もある」「読書の意義は、先達との魂の対話である」といった言葉を常々反芻しています。
その執行さんから立派な方だと教えていただいたのが、出光興産の創業者・出光佐三氏です。私が30代の頃で、早速出光氏に関する本を読み、なるほどと思いました。また近年、百田尚樹氏が『海賊とよばれた男』を発表し、出光氏の偉業が再注目されました。出光氏は、努力と苦労を重ねて石油の商いを広げ、国内外の商売敵や既得権益者に正々堂々と立ち向かい、戦後は本業以外の事業にも挑戦して雇用を守り、晩年は、大国による不当な油田支配に反発し、英国軍を向こうに回してイランからの石油輸送を成功させました。彼を突き動かしたのは、利益欲でも権利欲でもなく、「世のため、人のため」という強烈な社会的使命感です。Jリーグは、地域においてサッカーを中心としたスポーツ文化を育む「Jリーグ百年構想」を掲げています。出光氏のような気概をもって、この社会的な取り組みを推進していきたいと思います。
×唐招提寺の手前でタクシーを降り、少し歩くことにした。秋篠川の欄干にもたれ、ゆったりと流れる水面を眺める。時折上流から病葉が漂ってくる。流れゆく様を見つつ感慨に耽る。齢六〇半ば、生命の大河に還る身だ。この一瞬一瞬が珠玉のように尊く感じられる。
堅固な築地塀が見えてきた。丸瓦には唐招提寺の刻印が刻まれている。西の大寺に到着した。
伽藍に足を踏み入れると、清浄の気が立ちこめていた。掃き清められた参道には冬陽が斜めに射し、金堂の大屋根には松がその影を落としていた。吹き抜けになった八本の円柱も縞模様を描いている。陽光に照らされた円柱に掌を当てた。微かな温もりの中に、千数百年の蒼古とした歴史が伝わってきた。
薄闇に輝く黄金の廬舎那仏、薬師如来、観世音菩薩の三体を拝した。ふと脳裏に會津八一の歌が過った。
おほてら の まろき はしら の つきかげ を
つち に ふみつつ もの を こそ おもへ
暗誦している数少ない歌だ。友人の執行草舟は詩歌論『友よ』の中でこう読み解く。
唐招提寺を訪れて、まず考えるべきは鑑真和上の心だ。鑑真の心と、唐招提寺の歴史の重みを理解しなければならぬ。この歌が作られたのは大正時代、鑑真の名は忘れ去られていた。日本は西洋一辺倒の国是ゆえ、日本固有の歴史と文化に信じられぬほど粗略な扱いをした。その理不尽さに八一の憤りが込められているのだ。
なるほど、そういう側面があったか。執行の透徹した視点は、私の死角を照射してくれる。独自の視座に触れるのは楽しい。
初対面の時の印象は強烈だった。髪はオールバック、黒々とした瞳は好奇と快活を宿していた。高い鼻梁の下に髭をたくわえ、口元には一閃の含羞があった。安田靫彦が描く武士の姿だ。
執行と向かいあうと不思議な感慨を覚える。漆黒の宇宙に浮かぶ星雲を臨む感がする。万余の書籍に接して先哲との対話で磨きあげたせいか。無論考え方の相違はあり、時には違和感を抱く。だがそんな些事を超え、一個の思想的球体として敬意を払う。
現在、学門は極端に分化している。個々の事象は把握できても、全体を統べるのは稀である。そこを埋めるのが執行のような人物だ。学者ではなく実業家であることも好ましい。
執行は高校時代、八ヶ岳の麓に乗馬に行き、山荘で度々三島由紀夫と論じあった。時には仏教の根本哲理、唯識論にも及んだ。若くして三島と共有した時間は羨望の限りだ。輪廻転生を描いた「豊饒の海」、その第二作の「奔馬」の主人公、飯沼勲のモデルはお前だと、同級生たちは言ったそうだ。
佐賀鍋島藩士だった祖父、執行弘道はアメリカに留学した。海外に知己は多く、フランク・ロイド・ライトは弘道の親友だ。
晩年、弘道は枢密顧問官として天皇の美術顧問を務めた。執行草舟は美術品にも造詣が深い。安田靫彦、平野遼、禅宗の白隠や南天棒などの作品を蔵する。執行はコレクターという言葉を毛嫌いする。俺は単なる収集家ではない、真に良きものの継承者だ、後世に残す責務を負っていると語る。この点、川端と同様である。
洋画家の戸嶋靖昌と義兄弟の契りを結んだ。平成一四年秋に邂逅、戸嶋は執行の肖像画を描いた。濃密な交流の末、四年後の夏、戸嶋は冥府に旅立った。享年七二歳。その作風は重く、暗く、情念を抉りだす筆致は独自のものだ。
執行に先立つ一年前、私は吉祥寺のギャラリーで戸嶋に遭遇した。彫像的風貌に興味を覚え、こちらから話しかけた。俺はどんな巨匠にも劣らぬ絵を描くと戸嶋は豪語した。それなら証拠を見せてほしいと突っぱねると、古ぼけた鞄から美術雑誌を取り出してこちらに突きつけた。
五センチ四方の図版だった。瞬時に戸嶋の言が真実だと悟った。それが《バレリーの像》であった。これほどの画家が日本にいたのかと驚愕した。
稲城のアトリエを訪ね、《バレリーの像》を見た。いや見たのではない。私は見られたのだ。しかも描かれていたのは男ではなく女であった。私の常識は根底から覆された。
感動を口にしたが、戸嶋はさほど嬉しそうではなかった。まあ、いいから飲めと、ワインをふるまわれた。襲ってきた酩酊の底で私は戸嶋の声を聞いた。この絵をどう描いたか記憶はない、神が描かせたとしか思えないと。
もし、叶うものなら、川端康成に戸嶋の油彩を見せたかった。あの鷹さながらの眼で凝視するのか、一瞥するやいなや、足早に去って行くのか。
戸嶋は秋田県の鷹巣、今の北秋田市の名家に生まれた。
武蔵野美術大学に進み、師は麻生三郎、山口長男だった。卒業後、同校の彫刻科の助手をしていたが辞職し、スペインに渡った。四半世紀近くグラナダで暮らし、妻日子の死で帰国した。
執行は遺族から七〇〇点の油彩を譲り受け、数年前、英国大使館裏に新社屋を建てた。そのワンフロアーを戸嶋のギャラリーとした。無名のまま逝った画家の鎮魂の祭壇である。
ギャラリーはバイオテックに連絡すれば鑑賞可能だ。予約制の理由は少人数で作品に向き合わせたい。混雑が予想される展示会場に、私は足を運ぶ気にはなれない。鑑賞とはほど遠く、人の頭越しに見るなど論外だ。執行は展覧会のあるべき姿を示唆する。
平成二五年秋、執行は三冊目の著作『根源へ』を講談社から刊行した。表紙は菊池信義が装幀した《執行草舟の像》、戸嶋の絶筆である。『根源へ』は類稀な生命力を宿している。同書は人の胸を打ち、時代を超えて読み継がれるだろう。
×昨今、世の中は儲け方がうまい人だけが成功者、勝ち組と見なされている。そのような世の中に警鐘を鳴らし、著書『生くる』を執筆した執行草舟氏。真に生きるとはどういうことか、人生で真に成功することとはどういうことなのか。その人生哲学を伺いました。
―講談社から出された『生くる』『友よ』『根源へ』の三部作は、いずれも四百ページを超える大作ながら、大手書店の売上げベスト10に入るなどたいへん注目されています。好評の要因を著者としてどうご覧になりますか。
執行 売れる本を出そうと思って書いたつもりは毛頭ないので分かりませんが、一行の嘘もない、本当のことだけが書いてあるからではないですか。偉くなりたいとか、金儲けしたいなんて欲で本を書くから、ありもしないことが脚色され、読む価値のない本になるのです。今の日本には、本当のことを書く人が少なくなりました。
あの三冊には、執行草舟という一人の人間が、この授けられた生命をいかに燃焼させ、苦しみ、悩みながらもどう生ききってきたのか、それだけを書きました。そこには生きている限り、多かれ少なかれ誰にでも重なるものがあるはずです。自分の生命がボロボロに燃え尽きるまで、この人生を生ききりたい。そう願う人たちの生きる材料を提供するために書いた結果が、このような評価となり、光栄です。
―そうした著述家としての活動とともに、会社を経営する実業家としての一面もお持ちですね。
執行 三十三歳で酵素食品の会社を立ち上げ、以来三十年間、毎月の黒字経営です。個人の方々に利用いただく食品なのですが、私は「健康になるためではなく、正しく死ぬために飲んでください」と言っています。
―どういうことでしょうか。
執行 最近は、健康それ自体が目的であるかのように喧伝されていますが、あれこそ最低のエゴイズムです。健康とは、価値ある対象に己の生命を投げ捨て、燃焼して生ききるために必要なのであり、人間として正しく死ぬために整えておくべきものです。その信念で今日まで事業をやってきました。
私は七歳で胸の大病を患って死と直面し、その時に父の本棚から手に取って読みふけったのが『葉隠』です。その後、体は丈夫なのに、事故や原因不明の奇病に突然、見舞われることが三度四度と重なりました。
―自分の生命と向き合われて。
執行 生命とは何か、人生とは何か。万巻の書物、古今東西の芸術に光を求めました。その一つを挙げるとすれば、道元の『正法眼蔵』です。この中で道元は、人間は己の宿命を受け入れることで運命を自覚でき、生命を燃焼させ尽くすことが人の道であるということを喝破しています。私は『正法眼蔵』の真髄を、「火を噴く今」と捉えています。
―「宿命」や「運命」とは、どのように捉えたらよいのでしょうか。
執行 宿命とは、どこの国に生まれたのか、どういう両親の下に生まれたのかということ。運命とは、先祖や親から自分に与えられた宿命をあるがままに受け入れることによって初めて自覚でき、始まるものです。
例えば、黒人公民権活動の指導者だったアメリカのキング牧師。黒人として生まれた宿命に誇りを持ち、暗殺されはしましたが、見事に人生を生ききりました。あれこそ運命を自覚した生き方と言えるでしょう。
一方で、マイケル・ジャクソンのように、黒人としての宿命にコンプレックスを抱き続けると、宿命に囚われて自分の運命を生きる暇がなくなり、自分を潰す結果となります。そもそも私たちは、過去の先祖たちが築いた尊い文明に行かされている存在であって、与えられた宿命を否定したり、過去を貶める立場にないのです。宿命を素直に受け入れると、成功したいとか、有名になりたいとか、そういう雑念がなくなります。
―成功を求めて努力することは、運命を生きることにはならないと。
執行 自分が幸せになりたいとか成功したいなんて思っているうちは、自分の運命を本当に生かそうとしていません。文明のため他者のため、自分の生命を燃やし尽くすことが人生の本質であり、成功するかどうかという問題はあくまで結果論です。私が知っている成功者はみな「自分は運が良かった」と言っています。
―現代の資本主義社会は、多く儲けた者が勝ちという構図ですが。
執行 そこに根本的な誤りがあります。本来の資本主義は単なる金持ち主義ではありません。資本主義がヨーロッパで発達したのはプロテスタンティズムがあったからであり、日本では武士道があったためです。武士道とは、殿様に対して自分を投げ出す、自己犠牲の精神です。世のため、人のために、稼いだお金を事業の再生産につなげるのが、本来の資本主義です。
ところが今は、儲けたお金を、自分の贅沢のために浪費するのが資本主義を誤解されてしまった。こんな間違った資本主義から、真のリーダーが生まれるはずはありません。リーダーという考え方が生まれたのは十九世紀、商売の世界にプロテスタンティズムという封建主義的な考え方が入り、国のため、従業員のために組織を経営するという思想ができてからです。
―真のリーダーとして思い浮かぶ人は誰ですか。
執行 私は経営学も経済学も学んだことはないですが、出光佐三の書いたものだけは全部読みました。出光のモットーである「士魂商才」は資本主義の根本的な考え方と一致します。出光はきれいごとではなく、真に国家、社会の発展、人々の幸せのために事業を行いました。出光佐三以降、真に成功した人というのは見当たりません。
―出光佐三の経営の原点は、武士道と大家族主義といわれますが。
執行 大家族主義なくして、武士道は生まれません。血縁だけではなく、村社会や地域のつながりに価値を置くのが大家族主義です。今、世界でも日本に大家族主義が残っているのは皇室があるからです。天皇は権力を振りかざす支配者ではなく、すべての日本人の宗家であり、日本自体が大家族主義で結ばれた共同体なのです。
―そうした土壌から導き出されるリーダーの条件とはなんでしょう。
執行 リーダーか否かというのも結局は結果論であり、確実にそうなる条件はないというのが私の考えですが、それでは答えになりませんね(笑)。自分の運命を生ききる燃焼係数の高さ、それを感化力として、人を惹きつけるのがリーダーでしょう。あくまで惹きつけるもので、引っ張るものじゃない。人を引っ張るなどというのは傲慢です。近ごろは自分に対して「自信がある」とかないとか言いますが、本来は「あの人は自信があるように見える」などと他人を評して使う言葉なのです。ですから今流の「自信教育」は謙虚さを潰し、傲慢さを育てるもので、まったくの間違いです。
自信を持つと、成長しようという気持ちが失われます。最も顕著な例が豊臣秀吉ですね。天下人になるまでは、家柄も地位もなく、いつも謙虚で魅力的だった。だから成功したのです。それが天下人になったら、あのとおり、晩節を汚す結果になってしまった。人間というのは、謙虚さが最も重要です。それだけあれば、後はどんなことでも身に付けることができるのです。
―最後にご自身の人生の志を。
執行 人間が自分の生命を大切にし、生命を燃焼させ運命を生ききることの大切さを、これからも事業や著述を通じて示したい。また情熱を燃焼させた芸術家の作品を集め、その魂を形として後の世に残したいのです。それが私の運命であり志です。
×福田恆存は、小林秀雄の最期の大作『本居宣長』を論じた文章の冒頭に、「何年ぶりだらう、かういふ本を読んだのは。いや、生れて初めてかもしれない。その一言一句が滞りなく心の隅ゝに沁み渡り、日頃、とかく硬直しがちな筋を揉みほぐしてくれるような快さに私は陶然とした。」と書いたけれども、私も本書を読みながら「何年ぶりだらう、かういふ本を読んだのは」という思いに浸っていた。
数年前、『生くる』『友よ』の二作によって彗星のように登場した著者の最新作である本書は、一言でいえば「根源」からの反時代的考察と称すべき著作である。章の題名からして、もう只事ではない。
「我々は、どこに向って死ぬのか」「不合理を仰ぎ見なければならない」「不自由が真の自由を生む」「悲哀の彼方へと導け」「生きるとは、呻吟する精神である」「情熱は、不滅性への渇望から生まれる」「崇高を仰ぎ見なければならない」「復活の息吹きを愛しまなければならぬ」といった題名の下に、著者の該博な教養と深い魂から絞り出された刺激に満ちた言説は、今日の戦後的な価値観を、著者の言葉を借りれば「垂直の歴史観」によって打ち砕いているのである。その「根源」から打ち砕く言葉の力は、今日極めて稀なものであり、私が「何年ぶりだろう」と感じたのは、それ故である。
著者は、もし保田與重郎が生きていたならば、その『現代畸人伝』の中にとりあげたかも知れないと思われる人であろう。もちろん、この「畸人」とは、いい意味であって、単なる変人のことでない。少し卑俗な言い方で恐縮だが、野球の世界にたとえるならば、著者は、言説の世界に、ダッグアウトから出て来た選手ではない。外野のスタンドから、突如現れマウンドに立ち、驚異的な剛速球を投げて見せたような「畸人」である。ブルペンでコーチの指導を受けて練習することによって戦後的な価値観に泥んでしまうことを免れて、独学により人格形成の王道を一人で歩み続けたことによって、今日稀な筋金入りの教養を血肉化したのである。本格的な人物は、かえってこのようにしか登場できないのが、現代の不幸であろう。
だからこそ、著者の言説は「根源」的に反時代的であることができたのであり、今日の文明と人間の危機にとって、実に傾聴すべきものを持っているのである。本書の中に、ニーチェの『ツァラトゥストラかく語りき』が何回も引用されていることから連想するならば、本書は『執行草舟かく語りき』と題されてもいいのである。それは、戦後生まれの一人の日本人である筆者が、戦後民主主義の中に生きている人間として語っているというよりも、何か「ツァラトゥストラ」的存在として、世界、人間、神などについて「垂訓」しているからである。「耳ある者は聴くべし」。
×平成二十五年十二月号『正論』は、「神武天皇日向御進発」という絵画が表紙を飾っていた。いうまでもなく、宮崎神宮のご祭神・神日本磐余彦天皇が、日向美々津より大和橿原にご東征された際の様子を描いた作品で、作者は日本画家の巨匠安田靫彦である。船上中央には天皇が座しましたご鳳輦を描き、そして天皇に従った二十名程の皇軍兵士を配している。手前には楯が並び舳先には神籬が建てられ御鏡も描かれている。淡い色彩であるが実にバランスが良い。ただ不思議な事に兵の顔が描かれていない。国家の個性と成るべき〈ペルソナ〉(=人格)がないのだ。
その理由とはこれが下絵だからである(完成作は歌舞伎座所蔵)。執行草舟氏によると、「ここには、我が国の初心がある。靫彦の憧れが想う初国の偉業が見える」と解説する。そして、「ここには建国の涙がある。まだ穢れを知る前の、瑞々しい息吹きを感ずるのである。顔のない出発は、運命に向かう祈りを現している。だからこそ、我々がこの国のペルソナを創り出さなければならない。顔のない出発は、真の憧れに向う慟哭に他ならないのだ」と評している。
顔の話で思い起こすのは、哲学者和辻哲郎の「面とペルソナ」である。「顔が人格を現す」という単純な事実が西洋的教養を媒介する和辻の筆致によって特異な感覚で表現されている。和辻のこのキザな表現を苦笑し、それ以前の和辻の思想を追求すべきと論じたのが幡掛正浩(後の伊勢神宮少宮司)であった。幡掛は和辻に向こうを張って「面とミコト」を『理想日本』(昭和十八年十月号)に発表。玄洋社の頭山満の顔をして「頭山先生の顔はあたかも日本といふいのちの化貌」と論じ、日本主義による「面」を説いたのであった。
さて「顔のない出発」を我々はどう理解すべきか。
執行氏は「国のペルソナを創り出さなければならない」とする。その師表とすべきものは西洋的な「面」ではなく、日本的な「面」(神武建国精神)にこそ求めるべきだと思うのである。
×現代を覆う「物質文明」「経済至上主義」を根本から問い直し、先祖が築いてきた死生観に立脚した生き方を説く人生論集。著者は、佐賀にルーツを持つ実業家・著述家で、月刊論壇誌に2年間連載されたインタビュー記事に大幅に手を入れ、まとめた。<未来は過去の堆積のもとにある。そして現存する人間の判断力だけが、人類の未来を創り上げる。だからこそ我々は過去に学ばなくてはならない>と、西行、ゲーテら古今東西の人物の故事や思想を援用しつつ縦横に論じる。<思索の裏付けとしての読書の大切さを訴えたかった>という。
×千代田区麴町のビルに、無名の抽象画家を冠した展示室がある。
「戸嶋靖昌記念館」といい、ビルを所有する会社社長が本人と作品にほれ込み、2年前に開館した。看板もなく、目立った宣伝はしていないが、作品の評判が広がり、訪れる人が徐々に増えている。
同館は、加工食品会社「バイオテック」の1フロア、約210平方メートルの場所に設置されている。戸嶋の人物画や風景画などを中心に約50点を展示している。黒を基調に、重層的で重厚感のある作風が特徴だ。
戸嶋は1934年、秋田県鷹巣町(現・北秋田市)出身で、武蔵野美術学校(現・大学)西洋画科に入学し、日本抽象画家の第一人者山口長男や麻生三郎に師事して才能を認められた。だが、「描きたいものを描く」という姿勢を貫き、世に知られることはなかったという。
同社社長で館長の執行草舟さん(63)が2002年夏、美術雑誌に載っていた戸嶋作品を見つけた。直接会い、戸嶋の妥協を許さない姿勢に心を打たれ、当時虎ノ門にあった会社の一室をアトリエに改装した。戸嶋は肖像画などを描き、4年後に72歳でがんで死去。執行さんは遺族から全作品を譲り受け、同館を設立した。
作家としても活動する執行さんが、月刊誌のインタビューなどで戸嶋に触れてきた。その効果もあり、1日3人程度だった来場者は30人ほどに増えた。執行さんは「戸嶋作品は『生きるとは何か』を問いかけてくる。多くの人に見てほしい」と話している。
×400ページを超えるこの大著、文明論であり、芸術、文芸論であり、思想、哲学、宗教、歴史論である。それらが重層的にからまり合い、しかし究極に、人間いかに生きるべきか、死すべきか、というただ一つの問いに収斂する。
450人に及ぶ古今東西の古典、現代の著作者に言及するが、知識の広さを著者は問題にしない。厖大な古今の文献の読書遍歴を誇ってもいない。それらとの出会いの感動を率直に告白しているのだ。
いかに生き、死すべきか。この一点にむかう問いかけが、一本の垂直な太い線となって、この大著をつらぬいている。著者の態度は、素人に徹している。たとえば、「私自身の信念をまず言えば、文学を失えば、その民族は滅びる、ということです」「あらゆる分野で、古典と言われている作品の根本には文学があり、その意味では哲学、歴史、音楽、宗教、自然科学もすべて文学なのです」。
専門家はけっして、こんなことは言わない。専門という局部の隅々まで知っており、表と裏にも通じているという意識が、玄人のイリュージョンを生む。むかし夏目漱石は、玄人の陥る落とし穴を芥川龍之介ら後輩に警告した。文学を押すのではない、人間を押すのだと。つまり漱石は素人の初心に徹するという信念を抱いていた。
フルトヴェングラーの演奏したベートーヴェンが今日なお人の魂に触れるのは、その根底に「文学が」があるからだと著者は言う。文学とは「我々を崇高に向ける“何者か”を有している」ものだと言う。それは我々の魂に留まる」(ヘルダーリン)とも言う。
「日本は面白い国で、小説家がもっとも文学的ではありません」。これは著者の痛烈なイロニイである。
ひるがえって、「戦後民主主義」への批判は、激烈であり、そして正当である。その行文から悲しみと絶望の叫びがきこえる。しかし、悲しみと絶望のないところに希望も生まれない。「善人の無関心」こそ、絶望的なのだ。これが「戦後民主主義」を支えている。この弁証法も、本書の特徴である。
×北秋田市出身の画家・戸嶋靖昌さん(1934~2006)の作品が並ぶギャラリーが、東京・麴町開設された。戸嶋さんと親交が深く、絶筆のモデルにもなった会社社長 執行草舟さん(61)=本名・祐輔=が、昨年完成した新社屋の一室を活用し、一般公開している。執行さんは戸嶋さんを「日本美術史に名を残す人物」と高く評価。その画業に光を当てて後世に伝えたいと考えている。
ギャラリーは、執行さんが経営する食品会社「バイオテック」の本社ビル内の約200平方メートル。戸嶋さんが72歳で亡くなった後、遺族から譲り受けた絵画や彫刻など所有作品約800点の一部を展示。現在は、風景や人物を題材にした油絵など約50点が並ぶ。
このうち、1984年にスペインの街並みを描いた「街・三つの塔(グラナダ)」は、黒、白、褐色の絵の具を塗り重ねた重厚さを感じさせる作品。歌人でもある執行さんは、この作品から700年以上にわたり続いたキリスト教徒によるレコンキスタ(国土回復運動)を想起して詩をつくり、作品の隣にパネルを飾っている。
戸嶋さんは大館鳳鳴高—武蔵野美術大卒。74年からスペインに活動拠点を移し2000年に帰国した。執行さんと知り合ったのは02年。晩年は執行さんの会社ビル内にアトリエを構え、がんで余命宣告された後も制作に取り組んだという。
執行さんは「油絵の基礎がしっかりした正統派であると同時に、宗教的な重層構造(深さ)を備えている」と戸嶋作品の魅力を語り「粘り強く、深みを究める姿から『東北人』を感じた」と人柄をしのぶ。
ギャラリーは、戸嶋さんの自宅兼アトリエ(東京都稲城市)に08年に開設された記念館の分館という位置付け。鑑賞を希望する場合は事前に連絡が必要。問い合わせは、戸嶋靖昌記念館分館 03・3511・9711
×現代は「価値観の多様化」が許容される時代である。われわれは、戦後の平和で豊かな社会の中で、どのような職業に就いてどのように生きていくか、何を楽しみとし何を大切に生きていくか、1つひとつに限りない選択の自由を与えられてきた。
しかし、与えられた自由にかえって戸惑い、進むべき道を見出せずに悩む人もいる。かつての貧しい日本から想像もできないほどの発展を遂げた現在、毎年3万人を超える自殺者や300万人以上にまで増え続ける精神障害者数は何を示しているのだろう。医療機関で把握されない潜在的患者も相当な数であることが推測され、“うつ病は心の生活習慣病” “一億総うつ時代” というフレーズも、あながち誇張とは言えないほど現実味を帯びてきた。
富めるわが国において、かくも多くのこころの病が蔓延する現状をどう捉えればよいのだろうか。われわれは、人が人として生きていく上で一番大事なものを見失ったのかもしれない。これからの時代を、いかにして生きていけばよいのだろう。
筆者は精神看護学の教育研究に十数年携わるなかで、精神科医療は実にさまざまな思想が交錯する世界であると感じてきた。こころという目に見えない世界に対して、幼少期にまで遡って原因をさぐる精神分析的な見方があるかと思えば、精神内界には触れず、その人の固定的な「ものの見方」の幅を広げるといった見方がある。両者は相容れなかったり、バランスよく共存していたりする。近年は、どちらかというと、過去の犯人探し(原因追求)を行なわない認知行動療法が隆盛で、学会でもそのテーマのセッションは大盛況だ。
この療法は、対象の歪んだ内的規範に基づく不合理な思考や行動パターンに焦点をあてて、内的規範そのものの変容を目的とするものだ。詳細は成書に譲るとして、この場合、どのような内的規範の変容をめざすのかが重要になると思う。つまり、人はこころをどう用いるかで人生を良くも悪くもするのだから、人生を良くするこころの用い方をすれば、安定した精神的健康を得ることができるのではないだろうか。
これは、ケアを担う側の人にも全く当てはまる。コミュニケーションにおける種々の技法も、それを行なう人の人格力に支えられて初めて活かされるのであり、ケアをするその人自身の軸となる「こころ」を養わなければならない。では、こころを養うためには具体的にはどのようにしたらよいのか。これについて、とてもわかりやすく指針を示してくれる書籍を紹介したい。執行草舟著の『生くる』である。
例えば、現代の常識として、自信を持つこと、自分の時間を大切にすること、無償の愛を捧げることなどは是とされる。しかし、この本は、そういったこころの用い方をよしとしない。
例えば「自信とは何か」。現代は、学校でも職場でもあらゆる場で人々に自信を持たせようとする社会風潮がある。しかし、著者は、自信は持ってはならないという。自信を持てば、その人はそこで終わる。目の前に置かれた状況に全身全霊でぶつかった結果、周りからみて自信のある生き方に見える。著者はそう述べている。自信が慢心につながり、ひいては成長の芽を摘むのであれば、今流の子育てや教育のあり方を見直す必要があるだろう。
また、このご時世、仕事をとるか家庭をとるかとジレンマに陥る人は多いのではないだろうか。著者は、仕事と家庭のどちらも、その人固有の生命を燃焼させ、生き甲斐を与えてくれるものだと述べ、択一的な悩みのあり方に一石を投じている。もちろん、現実的な問題への対処は必要であることに違いないが、「自分の時間とは何か」の章を読み込めば、時間を物質的に捉えることから生じる悩みから解放され、より自由にこころを用いることができるだろう。今流行りのライフ・ワーク・バランスも、短時間労働者に優しい制度の裏でサポートする看護職の負担増を耳にする。何か大切な問題が置き去りにされているように思えてならない。
その他、現在は人に見返りを求めることはあさましいという考え方が一般的だと思う。しかし、著者は、見返りは求めなければならないという。それは、見返りを要求するとは、言葉を換えれば、何かを与えられた人間が、自分が何を返せばよいのかがわかるための行動規準を教えることにつながるからだ。そして、われわれは、絶えず他人からの見返りを要求されることによって成長していくのだ。つまり、見返りを求められない現代人は自分が大切なのであり、結果的に自分の大切な周囲の人を甘やかし、成長を阻害していることになる。
またボランティアなどの行為は、自己に満足感を与えるというメリットがあり、その意味で全くの無償の行為ではない。本来、全くの無償の愛などは神の世界にしか存在せず、人間になせる技ではないという。奉仕のこころを持ち、燃え尽き症候群になりやすい看護職にとって、深く考えさせられるテーマではないだろうか。
本書には1つの価値が貫かれている。著者は現代人が失った何ものかを取り戻してもらいたいと願っているのだと思う。一見、現代社会の常識を覆すかに見える著者の思想は、実は革新的なものではなく、民族の歴史と文化・伝統を礎とする確かな真理である。読者は、実生活で直面する根本的問題の氷解を感じ、著者の知識量に圧倒されつつ、知の世界へ誘われる。これは、人間の生命が大宇宙の中で燃焼するための法則を説いた他に類をみない人生論なのだ。
この本と向き合えば、自己固有の魂が燃焼できる。そして、それはそのまま一層深みのあるケアへとつながっていく。自己の生命を完全燃焼させ、価値ある一生をおくりたい人の座右の書としてお勧めする。
私がスペインにおいて、闘牛の取材を集中的になした時代は一九七〇年代前半だ。当時、現代闘牛の黄金期、闘牛が最後の輝きを放った時代かもしれない。動物愛護思想の高まりとともに「野蛮」の一語で糾弾されて、カタルーニャでは闘牛全面禁止になり、衰亡の道程を歩み始める。これはこれで時代の趨勢、致し方のない話だ。
まだ闘牛が光彩を放っていた時期、闘牛愛好家の洋画家鴨居玲から何度か連絡をもらった。
鴨居はスペイン在住の日本人画家の大親分のような存在であったが、私には鴨居の厚意に応える気持ちの余裕がなく、内に籠って、ついに稀代の画家と会う機会を失していた。
後に鴨居の作品、老残の闘牛士が古びた光の衣装の上着だけを羽織って酒場のカウンターに佇む背中を見たとき、ああ、会って話をしておけばと悔やんだものだ。静止した一瞬に闘牛の影の部分が、人間の哀しみが凝縮されて見えた。
真摯に抽象絵画と向き合ってきた、畏友にしてマドリードのエチェガライ通の住人の島真一(島家には、堀田善衛一家を筆頭にどれほどの日本人が世話になり、通過していったものか)とは三十代前半から死の時まで長い交友が続いた。この島を通じて私が住んでいたアンダルシアの村にサイドカー付きのスクーターで乗り込んできたのが戸嶋靖昌だ。その出で立ちはまるで神風特攻隊のようで、殺気に満ちた風姿と風貌を醸し出していた。模索する自らの芸術と血まみれな戦いを繰り返していたのだろう。そんな孤絶感と切迫感と存在感と、そして韜晦に隠された優しさが生き方にも絵にも漂っていた。
あの当時、スペインにいた日本人画家は生と死を賭して画業に励んでいたような気がする。
そして磯江毅、グスタボ(つよしとスペイン人が発音するのは難しいのでこう名乗ったそうな)・イソエ。その履歴を改めてみると、私がスペインから引き揚げた七四年に渡西している。……磯江の死に先立つ一年前に戸嶋が亡くなり、戸嶋のデスマスクを描いた磯江が死に、島真一までもが磯江の死の翌年に二人の友を追うようにして亡くなった。(……)
×人間とは、命よりも大切なものがあることによって成り立つ。それは、歴史と文化、家族、祖国、天職としての仕事に他ならない。
昨年暮れ、心に沁みる珠玉の言葉が並ぶ人生論『生くる』と詩歌随想集『友よ』を引っさげて彗星のように現れた。実業家としてビジネスの世界を生きながら、ここまで日本の歴史に深く根差した思索を続けてきたということ自体、ほとんど奇跡のように思える。「経済のあるところに赤心なし」思わざるをえないこの時代だから余計にそう思うのかもしれないが。
―『生くる』の冒頭に置かれた「わからぬがよろしい」という一文で「この人物は本物だ」と思い、あとはじっくり味わいながら一気に読了してしまいました。≪私は当たり前のことを当たり前にするのが、人生で最も大切だと考えるようになった。……それは当たり前と呼ばれるものが、人の努力の集積ででき上がり、歴史と文化の裏打ちがなされているからなのだ。……当たり前のことをきちっとやれば、人は誰でも確固たる自負心を持つことができる。≫これにはガツンときました。
執行 ありがとうございます。ここに書いたのは私の生き方そのものです。オーバーなことはひとつもないし、嘘もありません。本書が桑原さんの心に響いたとしたなら、それは桑原さんご自身がそのように生きているところがあるからでしょう。
―会社の経営をされながら、こういう考え方に辿り着いているということにも驚きました。悲しいけれど「経済のあるところに赤心はない」というのがグローバリズムにおかされた日本の現状じゃないですか。
執行 私はそうは思いません。私は創業したその日から「商売は誠の道」だと思っていました。そこから外れてお客様や従業員とつきあったことはありません。この本を私の家族、従業員、お客様も読んでいますが、みんなの感想は私そのものという意味の言葉ばかりです。誤解されるとちょっと困りますが、私はアメリカの企業家がする慈善事業的なものに抵抗があります。つまり、善のための善はどこかおかしいということですね。自分の仕事そのものが適正利潤を得ながら、国家や社会、人々の役に立たなければならないと私は考えています。
―確かにそれが理想だと思います。
執行 理想というより、そうすべきなんです。日本で言えば商道です。理屈は石田梅岩などによって示された「石門心学」によく表されています。また西洋で言えばカルヴァンを源流とするプロテスタンティズムを生み出した考え方ですね。この考え方は後に、マックス・ウェーバーによってわかり易く理論化されています。それらをそのまま「誠の道」としてやっていれば、別に慈善事業なんかする必要はありません。どんな商売も、本来、人の役に立つためにやるものです。役に立たないとしたらそれは自分の能力が足りないからです。
―本書には付箋を貼り出したらきりがないぐらい響く言葉が多かったんですよ。たとえば≪歌だけが日本では真心の発露となっていた≫という部分。
執行 「朝日歌壇」に載っているような今の歌はダメです。あれは語呂合わせですから。俳句で言えば生命観や自然観のない川柳もどきのものです。悪いとは言わないけれど標語にすぎません。歌というのは本来、歴史や天皇、自然、民族の源を讃える心から発するものです。だから讃歌以外のものはダメです。
―≪古代の日本で、歌は戦いの中から生まれてきた。戦いは、人間に赤心を呼び戻し、すべての理屈を乗り越えて人と人の間に共感をもたらす。崇高な献身の心だけが、人に戦いを強いることができる≫という指摘にも唸りました。大伴家持が「海行かば」をまとめることができたのは、彼が軍事氏族の出身であったことも大きかった。
執行 そうです。誠は命がけの生き方の中から生まれます。これは善し悪しではなく事実です。戦争を肯定するわけではありませんが、戦争になって初めて家族の愛情がわかり友情がわかる。価値あるものが見えてくるのです。
―その通りですね。
執行 日本を代表する歌も戦いから生まれています。たとえば『古事記』にある、神武天皇の東征のときに軍歌として歌われた「久米歌」です。そこで繰り返し歌われる「撃ちてし止まん」という叫びに、私は日本の歌の淵源を見ます。歌が戦いから生まれたということを忘れてしまうと、ただのお遊びになってしまう。『古今集』や『新古今集』は言葉遊びになっています。そして現代ではただの標語です。この対極にあるのが『万葉集』の防人の歌です。長く歴史に残るのは防人の歌だと私は思います。国を守るために家族と別れる、その悲しみを歌っているからです。そこには真心があり、涙があります。
―ところで、角川春樹さんの俳句をお読みになったことはありますか。
執行 いいえ。
―そうですか。これこそ広い意味での戦いの中から生まれた俳句だと私は思っています。他の言葉遊びの俳句とは全く次元が違います。
執行 それは良いことを聞きました。早速、角川さんの俳句を読んでみます。
―ぜひ。もし対談をされたら、とてつもなく深く面白い話が出てくると思います。
執行 角川春樹さんという人はいろんな物議を醸してきたけれども、非常におもしろいものを持っていますよね。あの生き方の中には、何ものかを貫いていることが見えます。
―ある種の狂気を常に抱えている方ですね。
執行 狂気と言われるものこそが、本気のものなのです。お父さんの源義さんと春樹さんの相克について、何かの記事で読んだことがありますが、私と父の関係に似ているんです。反発の出方が角川春樹さんと私は違いますが。
―それは興味深いですね。ぜひとも対談を実現したいものです。
―≪命が大切なのは当然だが、人間とは、命よりも大切なものがあることによって成り立つ≫。戦後の日本人が失ってしまった感覚です。
執行 しかし、「人道」とは突き詰めればそういうことです。
―戦後民主主義教育はこれを完全に否定してしまった。命が何よりも大切。
執行 「命は地球よりも重い」と言って、超法規的措置で過激派を解き放った首相もいました。そういう考え方がずっと罷り通ってきましたが、今では確実に時代が変わってきたと思います。
―確かに。
執行 命が大切なのは当たり前です。しかし、人間の歴史は、何かのために自分の命を投げ打ってきた人たちがつくってきました。学者だろうが芸術家だろうが、もちろん軍人だろうが自分の命よりも大切なものを持っていた。
―そうですね。
執行 そういう生き方が人道的人生なんですよ。
―それともつながってくるのですが、≪封建制の歴史は、人倫の道のごとく気高い生き方を、文化として人々の心に沁み込ませた≫という指摘も面白いと思いました。マックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で資本主義の土壌となった勤勉の習慣はプロテスタンティズムに負うと指摘しましたが、執行さんは封建制に負うと考えられている。
執行 私はそう思います。日本や西洋で資本主義が芽生えたのは、長い封建制の時代を経験したからです。プロテスタンティズムも封建制を経験したからこそ生まれたものだと私は考えています。日本にはキリスト教はありませんでしたが、精神構造的にその代わりになるものがありました。武士道です。
―なるほど。
執行 内村鑑三は、文明開化まもない明治初期にアメリカのアマースト大学を首席で出ています。それもポーンと留学して首席なんです。アマーストは、全米から秀才が集まってくるキリスト教教育の名門大学です。そこで首席となった理由について、内村鑑三は、自分は生まれたときからキリスト教漬けだったからだという主旨の発言をしています。武士の子でもあったにもかかわらず、新渡戸稲造もそう言っている。どういうことかと言いますと、武士道とは主君のために死ぬという道徳です。その主君を神に代えればそのままキリスト教だということです。つまり封建道徳です。封建道徳の精華が日本では武士道であり、西洋ではカトリックから分派して精神を大切にしようとしたプロテスタンティズムです。神のために働く勤勉な人たちが、自らは質素な暮らしをして、稼いだお金を社会に再投資することで資本主義が生まれた。長い封建制を経験してこなかった国では、資本主義は生まれようがありません。つまり、資本主義とは、商売が金もうけでしかない人々には、生み出すことができない思想なのです。
―そうですね。
執行 私が封建道徳でもっとも大事だと考えるのが「恩」という価値観です。恩を感知する感性がなければ人としての心は生まれてこないと思うからです。人生は恩に始まり、恩に終わると言っても過言ではありません。家族を中心として、国や仕事や世間から受ける恩を自覚すれば、必然的に自分の道は拓けてきます。
―≪現代の消費社会は、物質至上主義と歯止めのない似非民主主義に覆われている。その発展と共に、恩が人の心から薄れていくのを感じている≫と書かれていますが、それは個人の責任というよりも戦後教育が原因でしょうね。戦後教育は国を敵対するものとして措定し、国のために尽くすという発想を葬ってしまいました。特に歴史教育はひどすぎます。執行さんがこのような本を出版されても、いまなお続く戦前の日本はすべてダメだったという歴史教育を一刻も早く是正しないと、日本を愛せない日本人がどんどん再生産されてしまいます。
執行 その通りです。戦後の歴史教育は私流に言えば、親の否定です。自分の親を否定していい人生が送れるはずがありません。戦後の人は自分の親を否定しているということがわからない。私だって親は苦手ですが、苦手なのと否定は違いますから。
―自分が歴史にきちんとつながった存在であるということ、つまりいま自分がここにあるのは先人たちが守ってきた国があり親がいるからで、そのことに恩を感じるということが基本ではないかと思います。しかし、祖国のあらを探してこれを否定することが良心的である、というとんでもない勘違いから多くの人が抜け出せないままです。
執行 もう歪みきっています。そういう歴史教育を推進しているのが日本人自身だなんて、もう言葉がないですね。
―同感です。
執行 憲法もアメリカから押し付けられたものですが、アメリカ人だって日本人がこんなに憲法を遵守するとは思っていなかったでしょう。占領軍が引き揚げたら、日本人自身がさっさと帰るだろうと考え、一週間ぐらいで適当につくったものですから。それを日本人は六十年以上も遵守している。もちろんいい点もあります。それはわかっていますが、もう一度日本人自身が、いい点は残しながら日本的に練り直すのが当たり前だと思います。その議論さえ許されないのは異常です。私は小学生の時から、日本人自身の手で憲法をつくりかえるべきだと主張しているのですが、「右翼」と片付けられて相手にされませんでした(笑)。しかし、驚いたことにこの本はいろんな人が読んでくれています。耳を傾けてくれる人が徐々に増えてきたという実感はあります。
―アマゾンでは半年で八十件以上のレビューがつき、ほとんどが五点満点の五点をつけています。
執行 それほどの本じゃないんですが。でも、時代は確かに変わりつつありますね、私の本が評価されるということは。
―いや、それほどの本だと思います。本書を書くきっかけは社内報に連載された文章だったそうですね。
執行 そうです。お客様、社員、それから取引関係者の中に、私の生き方や考え方に関心を持つ人が結構いたんです。それで十数年前から社内報に、私はこういう生き方をし、こんなふうに考えているといった事柄を書き始めました。
私を知りたいという人たちは、この戦後民主主義の社会に対して違和感を覚えながらも、自分もそれに染まっておかしくなっているという自覚を持つ人が多かった。そういう人がそこから抜け出すには、歴史をきちんと学ぶことが大切だと考えて書き始めました。内々のことだったのですが、いろいろな方々の協力をいただいて、公の出版物となりました。
―執行さんの中に、歴史を垂直に貫く軸のあることを感じました。ここにも書かれていますが、≪価値のある人生観は、必ず歴史的な過去の英知と自己が結びつかない限り生まれない≫という一節は、フランス革命を批判し、「保守主義の父」と呼ばれる英国の哲学者、エドマンド・バークの思想に通じるところがありますね。
執行 そうですか。そう言われると心底嬉しいし、名誉を深く感じます。でも、少し照れちゃうなあ(笑)。
―三月十一日の大地震、大津波、原発事故で日本人の心は折れかかっています。どこに軸足を置いて立ち上がっていったらいいとお考えですか。
執行 もう消費文明を否定するしかないと思います。そもそも消費文明とは親の否定なんです。人々に物を蔑ろにさせて、次々に新しい物を消費させるには、親の世代の生き方や道徳を否定しなければなりません。戦後の日本は国策によって親を否定し、消費文明どっぷりの社会を築いてきました。日本はアメリカの物量にかなわず戦争に負けたという勘違いから起こったコンプレックスとその反省から、物質的豊かさの実現に向かって突き進むことになりました。政府は戦後に日本人を、日本の文化、伝統、家族から離反させ、ものがなければ生きられない人間に変えていきました。古い価値観を持つ親の言うことを聞かないで無駄遣いをする。昔でいう不良を国策として量産していったのです。昭和三十年代に入ってからはテレビが不良量産の任務を担い、そのため文学や映画をはじめとするあらゆる文化は衰退していきました。その結果、われわれが手にしたのは経済成長と電化製品です。
戦後の日本人は消費文明を豊かさだと勘違いしています。私は本にしても家具にしてもあらゆるものが明治時代のほうがよかったと思います。現代はゴミが増えただけで何も豊になっていません。戦後のコンプレックスが生み出した、似非民主主義などという、ろくでもないものをもたらした結果だと思っています。
―その通りです。
執行 もうゴミの捨て場書はありませんよ。そのことを誰もがわかっているのに、見て見ぬふりをしています。激しい言い方をすれば脳死状態ですよ。消費文明を諦めない限り日本だけでなく人類に未来はないと思います。繰り返します。消費文明というのは豊かさではありません。本当の豊かさとは、いいものを作って大事に使うことでしょう。当たり前のことなんです。そこに戻るしかないと思います。多くの人は、消費文明を捨てて経済成長が止まれば貧しくなると思い込んでいますが、それは思い込まされているだけなんです。消費文明以前の日本の社会を思い出してください。間違いなく現在より豊かです。渡辺京二さんの『逝きし世の面影』を読めば、昔の豊かさがよくわかるはずです。
―そうかもしれませんが、経済をはじめ、あらゆる分野が世界を覆う巨大なシステムに組み込まれている中で、日本が抜け出すことができるかは疑問です。
執行 それが洗脳による思い込みなのです。我々は美しい歴史を持つ国に生まれた日本人です。決意すればできます。その決意が覚悟にまで至っていれば、必ずできます。
―そしてもう一つの問題は、経済的な発展を望まない国の行き方で、やたらと膨張している隣国に軍事的に対抗することが可能かどうかという問題もあります。
執行 もちろん、対抗も可能です。
―可能ですか。
執行 細かいことを話せばいくらでもありますけども、これも決意次第です。戦争の歴史を見れば、小が大を打ち破った例が極めて多い。ほとんどがそれです。要は精神と、物質の運用の問題です。国民の勇気とやり方次第です。もっとも大切なのは国民の勇気です。もちろん、国を守るために命を投げ出すことは当然のことでしょう。そうしたくないと思わされているから無理なのです。いまの人には無理に見えるのでしょう。
―問題はそこです。
執行 これは教育しかありません。家族や国のために自分の人生や肉体を犠牲にするのは、道徳の根本ですから。
―教育は国家百年の大計といいますが、百年がかりでやっていくしかないでしょうね。
執行 やるしかありません。六十年かかってここまで崩したのですから、六十年かけて戻すしかありません。必ず戻ります。親不孝で恩知らずで茶髪でメチャクチャなことをしている青年だって、六十年前に国のために散華した特攻隊の青年と同じ純粋な魂を持っているんです。これは単に教育の違いなのです。戦後のすさんだ教育できれいな魂が発現できなくなっているだけだと思います。そういう意味では私は性善説に立っています。日本人は、いざとなれば自分のことよりも国や他人を思いやる素養が心の奥深くに今でもあると私は思っています。それは三・一一以後の被災地の人々の秩序正しい生き方を見ればわかるのではないでしょうか。日本人はやはり、今でも深く道徳的なものを蔵しているのです。
―話を消費文明の否定に戻します。教育が大前提となるでしょうが、ほかに何から手を付けていったらいいとお考えですか。
執行 できる人間が自分のできることから始めることでしょう。なかなか今の国家が変わらないのは、大掛かりに変えようとしているからだと思います。歴史というのは大掛かりには変わりません。「このままではだめだ、変わらなければ」という小集団があちこちに生まれ、それが集まって大きな力になっていく。今はマスメディアがあるために、これを利用して一気に変えてしまおうとする。だから変わらないんです。基本はできる人から始めることです。まず自分ですよ。
私は死ぬまで消費文明に対抗し、日本人の生き方に還ることを実践し、自分の周りの人間にも言い、機械があればものも書いて発言もしようと決意しています。それでどうなるかは自分にもわかりませんが、やり続けるしかない。要は、死ぬまでそうし続ける。
―原発についてはどうお考えですか。
執行 脱原発を決意すべきです。決意してできないことはないですよ。日本人が本気で太陽光や風力などの自然エネルギーの利用に取り組めば、どこの国にも負けないと思っています。なぜなら文明的に日本人には自然と共存する才能があるからです。
―確かにその通りですね。
執行 原発に至るエネルギー政策は、歴史的に見ればヨーロッパ人のものです。実は原子力の発想はキリスト教から来ています。ハルマゲドンの終末思想から生まれた物質科学です。元々、原子力とは、ヨーロッパ物質科学の頂点なのです。自然と共存しながら生きてきた日本人に原子力なんてわかるはずがない。またわからないことを恥じる必要もない。文明が違うのです。私は日本人は原子力をいじるべきではないと思っています。
反対にヨーロッパ人にわからないのが自然との共存です。だから日本人が命懸けで国を挙げて取り組めば、絶対に欧米に負けるはずがありません。そうすれば、今度はヨーロッパ人が日本文明を見習うようになるはずです。明治維新以降の日本はヨーロッパを見習ってここまできましたが、このままでは二流国のままで終わってしまいます。先生以上には絶対になれませんから。文明の源流には宗教が存在します。自然を人間の力で制御できるという発想はキリスト教のものであり、だから、日本人にはなじまないものです。原子力が猛威を振るったら、西洋人は本能的に抑えにかかるでしょう。つまり、文明的にその恐ろしさも知っているのです。しかし、日本人は本能的に逃げる。本質がわからなければ、そうなるのです。
そもそも日本の太陽光や風力など、自然エネルギーの研究は一九七〇年代には世界一進んでいたんですよ。それを電力は原子力に頼ればいいと日本は捨ててしまった。ご承知のように江戸時代の日本は世界に冠たるリサイクル社会でした。これは日本人の才能です。小さな島の中で自給自足するしかないという環境が日本人のリサイクルの才能を磨いたんでしょう。
―出ていくことができませんからね。だから住んでいる土地を大事にした。
執行 そうです。糞便に始まり、全ての使用済みのものやゴミを全部利用する社会なんて、日本列島に一万年暮らし続けてきた民族の叡智の結晶だと思います。すべてのリサイクルがシステム化されていたということに関して、ついに江戸時代には、日本は世界に冠たる文明と呼んでも差し支えないところまで行き着いていました。
だから、そういう遺伝子を自分たちも受けついでいることを誇りにすべきでしょう。このような一万年の歴史があるのだから、日本人が本気で取り組めば、新たなリサイクル文明を構築できるに決まっています。真の還元思想に基づく社会です。必ずできます。疑うことは何もありません。
著者は佐賀鍋島藩士の子孫で、祖父執行弘道は、帝国ホテル設計などで知られる米国人フランク・ロイド・ライトの親友だったという。実業に携わりながら芸術一般の造詣が深く、「生ききるために文学を友としてきた」(あとがき)。
“友”のうちから長年親しんだ詩歌45編を選び、思い出とともに紹介している。
取り上げた詩歌は、「言ふなかれ、君よ、わかれを、」で始まる大木惇夫の「戦友別盃の歌」から始まり、白楽天、英国のW・H・オーデン、大伴家持、長田弘、会津八一、藤村操など古今東西に及ぶ。欧文については著作が新たに訳を加えたと記している。
《講談社・2415円》
×若き日に小林秀雄や三島由紀夫の知遇を得た著者が「人生を共に生き哭いてきた、我が涙であり、骨肉である」と述べる四十五篇の詩歌を自らの思い出とともに綴った書。
ヘルマン・ヘッセや室生犀星、王陽明、T.S.エリオットら人口に膾炙した詩篇が多いが、著者の深い人生観が添えられていることによって、改めて心に染みてくるものがある。
選んだ詩歌が、本書を通じて読者の心の糧になってくれればと切に願う著者。人生の荒波を越えていくための珠玉の言葉ときっと出合えるはずだ。
×ところで、先般知人から執行草舟氏の『友よ』『生くる』といふ二冊の書籍(講談社、税込各二千四百十五円)を紹介された。一読して驚いた。氏は私と同世代で同じ戦後を生きてゐたのだが、二十歳前から小林秀雄氏や三島由紀夫氏の知遇を得て多くを学びながら古今東西の詩文を読み続け、それを力として起業し会社を経営しながら今日に至った方である。例えば左の如くである。
「現代人は物事を理解しわかろうとし過ぎる。人生や人の心、果ては、あの世から宇宙そして未来にまで及んでいる」(『生くる』)
自らの生き方を模索しながら詩文を読み、詩文に励まされながら生き抜いてきた著者の人生の軌跡が随所に記されてゐる。「心」を大切にしてゐるやうに見えながら、実際は「心」を見失ってゐる戦後的価値観とは無縁の好著である。二~三十歳代の諸兄にもぜひ一読をおすすめしたい。
(元福岡県立小郡高等学校長)国民同胞 社団法人 国民文化研究会
この春もまた、多くの若者が大学の門をくぐる。看護学教育に携わる私には看護職を志す学生との新たな出会いの時期である。彼らは大学で一体何を学ぶのだろう。
看護師は時に、笑顔を忘れないよう教えられる。確かに看護の根本は癒やしである。聖母マリアのようなほほ笑みは病める人の安らぎとなりうるだろう。しかし、その慈愛に満ちたほほ笑みは技術として習得するものでもなければ、教育によってつくられるものでもない。その人の心が感じ、自ら湧き上がることでしか表せないものだ。ならば、患者という一人の人に接する者の、その心の根底に必要な何かがあるに違いない。
それは一体何であろうか。これから人生を切り開いていこうとする若者たちに、この一大事を明確に、それも実践的に示す書物を紹介したい。執行草舟著の「友よ」である。著者は、自身の若き日の思い出とともにニーチェやヘッセ、王陽明、高村光太郎ら古今東西45編の詩歌を通し、人としての心や行動のあり方、つまり真心の本質を実にわかりやすく示してくれている。また、この本は、著者が知遇を得た小林秀雄、三島由紀夫、芥川比呂志、村松剛、ダライラマ14世までが生き生きとした姿で登場するという他に類をみない詩歌論だ。
一例を挙げよう。「人間五十年、下天の内をくらぶれば…」という一節をご存じだろうか。最近は歴女なる女性がいるのだから、信長を取り上げた作品で舞い謡われるこの「敦盛」を知る人も多いだろう。しかし、この舞いを時代劇で見ることはあっても、自ら舞い謡う若者は皆無であるに違いない。著者は、この敦盛に対してほれて恋する態度が大切だという。そうすれば、本当の自分の生が生きてくるのだと。実際、著者は若き日に小林氏の前で敦盛を舞い、敦盛に対する考えや、敦盛を舞い続けた信長の生き方を氏と語り合った。そして、著者の見解を絶賛した小林氏が著者に伝えた言葉もまた読者諸君の脳天を突き刺すのではないか。知性は勇気の下僕に過ぎない―。知の巨人と称される小林秀雄氏が口にされた言葉である。
この本で紹介されている詩歌たちは、これから青春を謳歌する大学生のみならず、老若男女の友となるものである。一人でも多くの方々に手に取っていただきたいと念じている。それぞれの魂に響く詩が必ずそこにある。そして、その響きは現代人が忘れかけている一番大切なものを呼び覚ましてくれるに違いない。
執行草舟著「友よ」は、講談社2,300円
執行草舟(しぎょう・そうしゅう)1950年生まれ。立教大法学部卒。実業家、著述家、歌人。戸嶋靖昌館館長。
渡辺久美 1971年倉敷市生まれ。東京大医学部保健学科卒。同大学院医学系研究科修士課程修了。岡山大医学部保健学科助手などを経て2008年から現職。医学博士。
×佐賀鍋島藩士の子孫で美術顧問として大正、昭和天皇にも仕えた執行弘道氏の孫にあたる執行草舟さん(60)=東京都=が、自身の人生を基につづった哲学書「生くる」「友よ」を、講談社から出版した。
執行氏は食品会社を経営する実業家で、十五年ほど前から自身の会社の季刊誌に書き続けた人生論や生命論などを全面的に改定してまとめた。「生くる」は、読書論や運命論などが人が生きていく上で、人生について考えさせられる事象を硬質な筆致でつづったエッセー集。「友よ」は、ニーチェや王陽明、大伴家持など、古今東西を問わず、執行氏がこれまで愛読してきた詩歌について、人生論を交えながら語っている。三島由紀夫や小林秀雄ら、執行氏が若いころに交流を持った著名人とのエピソードなども盛り込まれており、読み応えとともに、親しみやすい内容になっている。
執行氏の祖父にあたる弘道氏は、オックスフォード大に留学後、世界各地で日本美術の普及に貢献。建築家のフランク・ロイド・ライトとも親交があり、枢密顧問官としての天皇の美術顧問も務めた。執行氏自身は佐賀県内で生活したことはないというが、「佐賀に対する親近感は幼いころからずっと持っている。私にとって精神的な故郷」と、佐賀への思い入れは強い。さらに「佐賀藩士の家系ということで、自分の中には、葉隠の精神と誇りがある」とも。
執行氏が二冊の本で記した精神の中心にあるのは、陽明学と葉隠という。陽明学の中心思想となっている「知行合一」は、「知」と「行」の両方が一緒にならないと意味をなさないもので、武士道を説いた葉隠の精神にも通じると話す。「歴史に残っている人物は、人生を体当たりで生きてきた人。そんな人生を生きてきた人をたくさん知らないといけない。それをできるのが読書」と話す。
この二冊の本は、各方面で話題になっており、タレントで映画監督の北野武氏も、新潮社の「yom yom」に寄稿した「本が誘う、本は遊郭」の中で、最近読んだ本として「友よ」に触れ、「萩原朔太郎や室生犀星、オーデンやヘッセなど古今東西の詩歌を取り上げて、そこから紐解いて自分の思い出や人生観を綴っている。この本は実に面白かったなあ」と感想を述べている。
執行氏は「この二冊の本は、与えられた命をどう生きるかについて書いている。一回きりのこの命をどう燃焼させて生きるのか。それを考えるヒントになればいい」といい「『生くる』が人生の理論書として、『友よ』が実践編として読んでもらえれば」と話す。
◆『生くる』『友よ』は、ともに講談社判で各二千三百円(税別)
×本のタイトルもいささか文語調。事業家でアートコレクターの… などと肩書きを添えると、妙な先入観を与えそうだが、筆者は世代的には昭和25年生まれのバリバリの戦後世代のひと。俗っぽくいえば団塊世代に属する。それでいて、全二巻を貫く気骨のありかたはまるで明治の大人(たいじん)を思わすものがある。『生くる』のほうには筆者が今日まで生きてくるうえで心に刻んできた思い、信念を「科学とは、試論にすぎない」とか「自信をもてば、破滅が始まる」、「人生は累乗の産物である」など54の項目で語る。そこでは時に常識に反するような考え方も提示されるが、それはすべて筆者の体験に裏打ちされた信念なのである。まさに「生きる」ではなく「生くる」なのである。
『友よ』はこの『生くる』の信念を導く道程で出会い、魂を重ね合わせた先人たちの著書、なかでも詩作品の核心をとりあげたものである。その詩人の顔ぶれは白楽天や李白から、オーデン、エリオット、リルケ、ホイットマン、ゲーテ、更に中野重治、萩原朔太郎、高村光太郎、会津八一、そして現代の長田弘まで古今東西驚くほど幅広い。
日本で詩というと甘い抒情にもたれかかった詩句を思い浮かべがちだが、筆者が評価するのは「生くる」うえでの魂の絶唱ともいうべき厳しい表現をもつ作品群。詩とはかくも骨太で力強いものであったのか、目からウロコの落ちる思いになる。
×著者が“魂の友”“心の糧”としてきた古今東西を問はぬ四十五篇の詩歌を通しての人生論である。著者あとがきをそのまま引用させていただく。
私は、自分が生ききるために文学を友としてきた。特に詩の生命の中に、自己の燃ゆる思いを託して今日まで生きてきたのだ。辛い時には詩と共に哭き、楽しい時には詩と共にその嬉しさを実感してきた。詩を通して人生を謳歌し、詩に励まされて人生の哀しみと対面してきたのである。詩のゆえに、多くの友と交わり、また多くの者との別れを体験した。
我が魂の友と言うべき詩歌どもを、まだ目見えることのない、新たなる人々に知っていただく機会が訪れたことを、私は心の底から喜んでいる。私が本書で取り上げた詩歌どもは、すべて私の親友のような存在であり、人生の恩人とも言えるものしかない。私と人生を共に生きと共に哭いてきた、我が涙である。つまり私と一心同体の血であり、骨肉と呼んでもよい。
その詩歌どもが、本書を通じて新たなる友人たちの、心の糧になりたがっているのを私は感ずる。私が親友としてつき合ってきた詩歌どもが、読者とまた親友となっていただければ、私はこの上もない喜びを感ずる。そしてそれは、取りも直さず、私と読者とが心を通ずることに繋がり、また友情が芽生えることになるのではないか。私はこの書物の生が、そうなることを祈っている。
当然の如く御祭神乃木将軍の「山川草木」の詩も取り上げられてゐるが、詩を通して著者が語る乃木将軍は、数多の傳記よりも真の姿をあらはしてゐるやうに思ふ。ご一読をおすすめする。
発行所 ㈱講談社 販売部 03-5395-3622 ISBN978-4-06-215725-4
二、三〇〇円(税別)
佐賀鍋島藩士の子孫で美術顧問として大正、昭和天皇にも仕えた執行弘道氏の孫にあたる執行草舟氏(60)=東京都=が、自身の人生を基につづった哲学書『生くる』と『友よ』を出版した。
執行氏は食品会社を経営する実業家。15年ほど前から自身の会社の季刊誌に書き続けた人生論や生命論などを全面的に改訂してまとめた。
『生くる』は読書論や運命論など、人が生きていく上で、考えさせられる事象を硬質な筆致でつづったエッセー集。『友よ』はニーチェや王陽明、大伴家持など、古今東西を問わず、執行氏が愛読してきた詩歌について語っている。
三島由紀夫や小林英雄ら、執行氏が若いころに交流を持った著名人とのエピソードなども盛り込まれている。
執行氏は「佐賀に対する親近感は幼いころからずっと持っている。私の思想も中心にあるのは陽明学と葉隠」と話す。2冊の本についても「与えられた命は一回きり。この命をどう燃焼させて生きるのか。それを考えるヒントになればいい」といい、「『生くる』が人生の理論書で、『友よ』が実践篇と思って読んでもらえれば」と話す。
×「自分が生きるために文学を友にしてきた」。この大著は、若いときから心の糧としてきた古今東西45編の詩歌を、自らの思い出とともに論じている。
「お前は歌ふな/お前は赤まゝの花やとんぼの羽根を歌ふな」(中野重治「歌」)、「人間五十年、/下天の内をくらぶれば、/夢幻の如くなり。」(幸若太夫「敦盛」)、「危険の感覚を失わせてはならない/道は、かくもか細く、また険しい」(W. H. オーデン「見るまえに跳べ」)、「国破れて山河在り。/城春にして草木深し。」(杜甫「春望」)……。
驚くのは、著者の早熟さだ。16歳のときに八ヶ岳で三島由紀夫と知り合い、文学論をとうとうと述べて、三島から「私が次に進む勇気を与えてくれました」と言われたという。
大学生のときには小林秀雄と出会い、「知性は勇気の下僕にすぎない」という言葉やパーカーの万年筆を頂いた。「私の家に、父から譲り受けた戦前のSPレコードが山ほどあって、その縁で音楽好きの小林さんを知ったのです」
佐賀の鍋島藩で代々家老職を務めた祖先をもつ。祖父は建築家のフランク・ロイド・ライトの親友で、天皇の美術顧問だった。自身も異色の経営者だ。食品会社の社長だが、哲学、文学、美術、音楽の造詣を背景に豊かな感性と独自の美意識で「志の経営」を提唱してきた。安田靫彦や白隠などのコレクターとしても知られる。
「戦後民主主義や物質至上主義のもとで、益荒男や手弱女などの日本人の美風が滅びてしまった。武士道の精神や明治人の気概もすっかり失われた。私が『万葉集』の大伴家持や会津八一、釈迢空などの歌に魅了されるのは、真の日本人の心に触れたい、偉大な死者たちの魂と交流したいと思うからです」
×……気に入ったのは、執行草舟の『友よ』(講談社)。著者は鍋島藩士の家系で、お祖父さんはフランク・ロイド・ライトの親友で、天皇の美術顧問。本人も生命論研究者で、歌人で、実業家っていうなんだかすごい人らしい。萩原朔太郎や室生犀星、オーデンや、ヘッセなど古今東西の詩歌を取り上げて、そこから紐解いて自分の思い出や人生観を綴ってる。この本は実に面白かったなあ。……
×今どき珍しい実に古風な人生論だ。武士道こそ日本文化の背骨だと言い切るあたりも潔い。著者は実業家であり、歌人でもあるが、その人生から絞り出された言葉にはみじんの迷いもない。
内容は、読書論や学問論、芸術論といった一般的なテーマから、「習慣について」「便利について」など日常の細部にまで至る。その多彩な話題を貫いているのは「自らの生命を燃焼させることこそが生きること」という著者の人生哲学だ。
例えば恨みは一般的には醜い感情だと思われているが、著者はむしろ生命の発露だと言う。もちろん、恨みを暴力的報復によって晴らすことを勧めているわけではない。恨みによって生じたエネルギーをばねとして何かを成し遂げ、人を見返すことが大事なのだ。そのとき、恨みは自分の生命を燃焼させる力となる。なるほど。恨みは確かにすさまじい感情だから、うまくコントロールできれば、生きる上での大きな力となるだろう。
著者によれば「自分の生命を燃焼させる」ことは「恩の道を貫くこと」によってのみなし得る。恩に報いるために生きることこそが人生で、そのような生きざまを、真心を意味する「赤誠」という言葉で表現する。
ここまで読んで「何とも古くさい」と思われたかもしれない。でも、ちょっと待ってほしい。「生きる」とは、大きな視点で眺めれば、何かを他の誰かから受け取り、それを他の誰かに受け渡していくことだ。言葉、日常の習慣や価値観、仕事における技能、教養、芸事…私たちの人生を形作るものはすべて、自分より先んじて生きてきた他の誰かから受け取ったものだ。そしてそれをまた、他の誰かに受け渡す。
そうやって連綿と続いていくものこそ、人間の「生命」であり、生きることに他ならない。この命の連鎖を、本書は「恩」と呼んでいる。だとすれば、恩を感じ、それに報いるというのは、まさに人間の命の在り方そのものだ。一本筋の通った人生論。古くさいと思う前に読んでみてほしい。きっと目を開かされることがあるはずだ。(甲田純生=広島国際大准教授)※ 講談社・2415円
×スカパー!などで放映中の連続ドラマ「TOKYOコントロール東京航空交通管制部」に出演する一方、「まじで~」のパフォーマンスで各局のバラエティー番組を盛り上げる神田瀧夢。米国で活動してきたが、今後は拠点を日本に移し、日本文化を世界に発信したいと意気込む。
大阪府岸和田市出身。十九歳でイギリスに留学した際、現地の人がソニーの商品をイギリス製だと思い込んでいることにショックを受け、「日本文化を自分が伝えたい」と決心。
帰国後に能や日本舞踊、空手などの稽古に励み、三十五歳で渡米。俳優を目指すが、映画「ラスト サムライ」のオーディション落選を機にコメディーに転向した。
「もともと人を笑わせるのが好き。パーティーで会話が分からなくても輪に加わって、少しずつ発言するようにして鍛えた」
二〇〇八年に米ABC放送のバラエティー番組「I Survived A Japanese Game Show」で日本人初の司会に抜擢されてブレーク。番組は世界百五十カ国で放送された。
渡米直後は所属事務所が決まらずに、百六十に門前払いされた。そうした困難を乗り越えられたのは、食品会社を経営する実業家の執行草舟氏との出会いがあったからだという。
「志とは、自分の命よりも名も惜しむ武士の心。執行氏の教えを実行してきて今がある」と神田。
日本のスタッフと共に日本文化を伝えるテレビ番組や映画を制作し、世界に配給するのが目標。「アメリカ人に『日本、かっこいい』と思わせられたら最高」と語る。
×昨年、日本中に感動を巻き起こした小惑星探査機「はやぶさ」。幾多の苦難を乗り越え、最後に燃え尽きながらカプセルを落とす姿を人の一生に重ね合わせた人もいるだろう。では、一人の人間が完全燃焼するとはどういうことか?異色の人生論『生くる』と詩歌論集『友よ』には、そのヒントがありそうだ。
― はやぶさに感動するのは
「あれは生命だと感じるから。生命の燃焼というのは私の中心思想ですが、戦後の民主主義で忘れられている。生命とは食物であり、お金であり、年金であり、生活保障であり、社会保障だと思っているのが今の生命論。もちろん、肉体を持っているからしょうがない部分もあるが、そんなものは生命の本質論ではないということです」
≪6歳で大病し生死をさまよった経験から生ききった人間の言葉を詩や文学に求めるようになった。小学1年の時、家の本棚で最初に手にしたのは、「武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり」の一説で有名な『葉隠』≫
― 死を身近に感じてきた
「子供の頃から死ぬために生きていると思ってる。今の人は忘れているけどそれは本来、当たり前のこと。人生はどう死ぬかを考える時間なんです」
― 「殿様の馬前で討ち死にするのが武士道」とある。サラリーマンなら社長のために死ぬ覚悟がいるのか
「当然です。殿様だってバカ殿様からいろいろいるわけですから。そもそも目上に対して『この人のために死ねるか』なんて思うこと自体が自分の方が偉いという自我。それを捨てるのが武士道です。親のために命を捨てるのは親が優れてるとか偉いからではなく自分の親だから。武士道を家庭でやれば親孝行の道につながります」
― 難しいですね
「屁理屈が出てくるとこれほど難しいものはない。だって、理不尽じゃないですか。でも理不尽を受け入れるのが武士道であり生命論。元々いつ死ぬかわからず、混沌で暗くてどうなるかわからない中に生命のきらめきがある。それを認めなければ生命論は始まらないのです」
≪戦後民主主義と物質至上主義の西洋科学思想が日本人の歴史観に巣くっていることを憂う執行氏。親を慕うように日本という国が歩んできた「歴史」を愛することが真の愛国心だと語る≫
― 戦後民主主義を批判しているが日本を否定しているわけではない
「当たり前。アメリカかぶれのよくわかりもしない思想を振り回している日本を批判しているだけで日本を愛する力は人一倍。キリスト教社会から西洋人が生み出した民主主義は日本には必要ないし、定着すればわがまま主義になる。(政治体制も)日本人の血にない間違ったものを選択すれば民族は滅びます」
― 滅びるとは
「日本という主体や文化がなくなって、この列島の上に過去からは信じられない違う感性の生息動物が住んでいるという状態。例えば、日本の魂を歌った和歌を全員がわからなくなれば、それはもはや日本ではなくなるということ」
― それでも幕末のようにどん底から傑物が出てくるのでは
「幕末とは状況が違う。今も人材がいないとは思わないが、民主主義に合う人しか出てこられないシステムがある。民主主義は今のミーハー世相に合わせる人以外は認めない主義で人材とはそれに異議を唱える人。明治維新の時は武士という問題意識を抱えた階層がありました」
― 幕末の偉人といえば、昨年は坂本龍馬がブームになりました
「龍馬は大嫌い。なぜなら背負ってるものがないから。私はどんなに優れた人でも好き勝手にやってる人には魅力を感じない。幕末でも西郷隆盛などは藩を背負い家族を背負っていた。そういう“責任”が嫌いな今の人が龍馬に憧れるのは歴史的な必然。無責任な人の高尚な理想が『龍馬』で、下世話な例が『寅さん』。この構造が戦後日本人の潜在意識であり夢なんだと思います」
― 全てを断言する
「断言できないことはしゃべらないだけ。私の人生で他人に責任を持って言えることは30歳ぐらいまでのこと。それから30年、確信を持って生きてきて間違いがないと思うことを書いた。この2冊に価値があるとしたらそれだけです」
<詩は魂の雄叫びなのだ。詩は人生の涙なのである>
実業家の執行草舟さん(60)が、異色の詩歌論集『友よ』(講談社)を出版した。織田信長が愛した幸若舞「敦盛」、歌人の釈迢空、イギリスの詩人T. S. エリオットなどの45編を力強く論じる。
「人間は心に、詩を持たなければ生きていけない。この本から、読者に好きな詩が一つでもできたら」
帝国ホテルを設計した建築家フランク・ロイド・ライトと親交があった弘道を祖父に持つ。6歳のとき大病し「生き切った人間の言葉を文学に求めるようになった」と語る。文学少年となり、16歳で三島由紀夫、大学時代には小林秀雄と面会した。「小林さんはじかに接すると、人間の大きさに包み込まれるようでした」
現在は食品会社の社長業の傍ら、洋画家戸嶋靖昌の記念館館長も務める。
人生論を説く『生くる』(同)も同時に刊行。生と文学を語る硬質な言葉が、現代人に勇気を与えそうだ。
×詩や文学を心の糧にして生きるとはどういうことか。それがよく分かるエッセー。ニーチェ、ホイットマン、王陽明、大伴家持、西郷隆盛、長田弘など古今東西を問わずバラエティー豊かな全45篇の愛唱詩歌を紹介、それらにまつわる思い出が情感豊かに綴られている。
子供のころから詩や文学と深くつき合ってきた著者にとってそれは真に生きるためになくてはならない友であり、恩人でもあるという。
詩や文学には理屈を超越した所で心に作用する力があるようだ。実用書やビジネス書しか読まないという食わず嫌いの人にこそおすすめ。
三島由紀夫、小林秀雄、丸山真男、村松剛ら著者が若き日に交流した著名人たちとのエピソードも興味深い。22日に紹介した人生論『生くる』(講談社)と同時発売。
×巷にあふれる生き方指南書とは一線を画した重厚な人生論。とはいっても、堅苦しくなりすぎず、わかりやすいのがこの本のすごい所。実業家でもある著者は、とかく軽薄に陥りがちな消費社会の風潮に流されることなく、生命を燃焼させる生き方を貫いてきたという。自らの人生において直面した問題に真正面からぶつかり、真摯に立ち向かったからこそつかんだ人生論であることが、文面から伝わってくる。
「理解しようとするな、わからぬままに、突き進むのだ」「礼は科学である」「本物を求めてはならない」「自信を持てば破滅が始まる」など、現代人には意外な視点から切り込んだ指摘はとにかく新鮮。かつてない読み応えで目を開かされる。
×大磯で安田建一と雑談中、靫彦の日本画を蒐集するある人物のことが話題にのぼった。偶然にも知人だった。世の中はなんと狭いものか。コレクターは執行草舟といい、虎ノ門にある食品会社の創業者で、彼とは一人の洋画家を通じて知り合った。洋画家の名は戸嶋靖昌という。
戸嶋とは地元東京・吉祥寺の小さなギャラリーで出会った。二〇〇一(平成一三)年九月のことだった。日曜日、作陶展が開催されていたのでぶらりと寄った。芸術家らしい風貌をした男が四、五人、立ち話しをしていた。グラナダというスペインの町が話題となっていた。その中に長身瘦軀、白髪を肩までなびかせて鋭い眼光を放っている男がいた。圧倒されるような存在感だった。声をかけずにはいられない何かを私は感じた。
「失礼ですが、陶芸をやられているのですか?」
「画家だよ、俺は」
素っ気なく答えた。
「娘の作品展に同伴して来た」
粘土でできた素朴な人形があった。それがお嬢さんの作品だった。
「グラナダの話をされていましたね」
「ああ、長く住んでいたからな」
こんな調子で話しはじめた。興が乗ってきたのか戸嶋は、絵についての持論を展開した。自分のことをゴヤかゴッホのようにいう。口でならなんとでもいえる。私の反発を見てとったのか、鞄の中から美術雑誌を取り出し、附箋のついたページを突きつけた。
小さな図版ではあったが、雰囲気は摑めた。私の知っているいかなる肖像画とも異なっていた。男の胸のあたりが空洞となり、男は冥府でも宿しているようだった。重くて暗い絵ではあったが、心臓を鷲摑みされたように感じた。
「いいですね」
「そうか」
あいかわらずぶっきらぼうであった。
「モデルになった男ですが……」
「男じゃない、女だよ。アトリエの近くに住んでいた、バレリーという女性画家だ。男も女もない、人間だよ。俺は人間を描いているんだ」
人間を描く。いい言葉であった。図版ではなく、本物を見たいと思った。一週間後にアトリエを訪問する約束をしていた。
俳協に所属、声優をしている娘の英里と、出向先の会社の同僚、大類善啓を伴って、稲城市のマンションを訪れた。数多くの書籍やレコード、埃をかぶったカメラなど、物という物が足の踏み場もないほど溢れていた。廊下にもキャンバスが堆く積み上げられ、体を横向きにしないと通れなかった。まさに芸術家の塒だった。
別室に案内された。戸嶋が明かりを点けた瞬間、不思議なことが起きた。最近描いたものだと指さした絵の男に私は凝視された。見たのではなく、私は見られたのだ。こんな体験は初めてであった。
スプリングの甘くなったソファーに座らされ、ワインを振舞われた。『月刊美術』で見た絵を立てかけてもらった。その表情は怒りとも虚無とも苦悩とも違った、名状しがたい精気を孕んでいた。人間の根源を見つめた者にしか描けぬ絵であった。巨匠のゴヤ、レンブラント、デューラーとも比肩しうる絵だ。ヨーロッパの古城の壁面でこそ、この絵は生彩を放つ。狭隘な弧状列島の中では真価は発揮できまい。無性に私はうれしかった。こんな素晴らしい画家と出会えたということが。まさに人生に乾杯である。
戸嶋靖昌は一九三四(昭和九)年に栃木県で生まれ、秋田県の鷹ノ巣町で育った。一九五三(昭和二八)年、武蔵野美術学校油絵科に入学した。そこで麻生三郎や山口長男、山口薫の指導を受けた。麻生三郎は銀座で清澄画廊を経営する田中孝一に述懐した。「戸嶋君ほどの才能はめったにあるものではない。どのように育てるかは君たち画商の責任だ」と。
一九七四(昭和四九)年、戸嶋はスペインのグラナダに渡り、帰国したのは一九九八(平成一〇)年のことであった。
戸嶋は画風を変えることなく、ひたすら人間を描いた。魂に迫るものを描いた。売れようと売れまいとおかまいなしだった。画家を志していた時の若き理想がそのまま封印されていた。ワインは高価ではなかったが、魂はとびっきりのビンテージものだった。
「この絵をどう描いたのか、確かな記憶はない。神が描かせたとしか思えない。画家にはな、神が宿る瞬間がある。わかるか、君は」
酔ってきたのか、戸嶋は同じ台詞を何度も繰り返した。
アトリエを訪問してから三、四年経ったろうか、戸嶋から電話があった。
「スポンサーが見つかった。俺に肖像画を描いてくれと頼むのだ」
「戸嶋さんがですか?」
怪訝そうに問い返した。戸嶋が描くと、本人とは似ても似つかないものになる惧れがあったからだ。
「似ているなんてことは問題外だ。俺の魂を描いてくれと言う。俺は人から頼まれて描いたことはない。描きたいものしか描かなかった。でも今回は違う。描きたい男にやっと巡りあったんだ」
声が弾んでいた。
「似なくてもいいなんて、変わった人ですね」
「俺よりもっと個性的な男だ。会社にアトリエまで用意すると言われた」
クックッと鳩のように笑った。戸嶋の画は売れない。静物画は別だか、人物画は皆腰が引ける。どうやら拾う神が現れたようだ。
紹介された執行草舟と会った。経営者としての自信が全身にみなぎっていた。渋くて役者にしてもいいほどの男ぶりだった。
「どうして戸嶋さんを知ったのですか?」
「誰かに肖像画を描いてほしかったのです。偶然『月刊美術』を見て、この画家なら間違いないと直感、編集長から住所を聞き、電話をいれました。ところがいい返事をいただけなかった。戸嶋さんは断るつもりだったようです。そして某所でお会いすることになった」
「そこで意気投合されたのですね?」
「私は会社にアトリエを用意しました。彼のいる稲城まで通うわけにはいきませんからね。そんな熱意が通じたのでしょう」
「そうでしたか。あの雑誌を見なかったら、こうした出会いはなかったのですね」
小さな図版一枚、その感動が三人の縁を結ばせた。戸嶋を世に出そうと語りあったが、本人は有名になることなど露ほども望んでなかった。志を高く持つ、これこそ、戸嶋たる所以だった。
もし川端が存命中であれば、戸嶋の絵にどのように反応するのだろうか。一瞬、あの大きな眼が見開かれ、その場で釘付けになるのか。それとも一瞥しただけで首を振り去ってしまうのか、大いに気になるところである。
二〇〇六(平成一八)年七月、戸嶋は直腸癌に侵され、妻の日子のいる天国に召された。享年七二歳だった。絶筆となった肖像画は執行の会社にかかっている。
その一年後、長年戸嶋を支えた田中孝一は、秋田の大館郷土博物館で遺作展を開催、所蔵作品四五点を展示、記念の図録を刊行した。
また執行は戸嶋の画業顕彰のため、稲城にある戸嶋のマンションに、記念館(二〇〇八年秋完成予定)を設立すべく準備中である。これで七〇〇点の絵は劣化と散逸を免れ、後世に伝えることができる。一人でも多くの人に絵を見てもらいたい、これは戸嶋を愛する人たちの全員の願いでもある。
二〇〇八(平成二〇)年一月、安田靫彦コレクションを見せてもらおうと、虎ノ門の執行の会社を訪ねた。
「なぜ蒐集を思い立たれたのですか?」
「私の先祖は、遠く大伴家持に繋がるのです。七年前、奈良の万葉美術館に行き、初めて靫彦の描く家持像を見ました。その時、落雷に遭ったような衝撃を受けました。あまりに素晴らしかったからです」
執行は大きなため息をついた。
「どのような点ですか?」
「簡単に言葉にはできません。強いていえば、体験したことのない高雅、そして品位でしょうか……品位は芸術の生命である。気韻生動は洋の東西を問わず、すべての芸術の本願であり、芸術に無上の尊厳と悠久の生命を付与すると述べています」
執行はゆっくりと言葉を選びながら語った。彼の言葉から観念的、衒学的なものは微塵も感じられなかった。蒐集家として、靫彦への敬慕と深い愛情に裏打ちされていた。
「蒐集を思い立った私は、安田建一先生に連絡、挨拶に行ったのです」
「御子息のところへですね」
「ええ、《黄瀬川陣》や《卑弥呼》などの代表作は、東京国立近代美術館などに収まっていて、もう世に出ることもないでしょう。大作ではなくても、小品に目をつけました。靫彦の凄さは号数には関係がない。小さければ小さいほど、その真価を発揮します」
「ええ、品位は揺らぎません」
私は相槌を打ちながら、女流画家の小倉遊亀の逸話を思い出した。彼女が奈良の高等師範学校の生徒だった時のこと、絵の教師から「今、法隆寺の金堂壁画のように力強く、きれいな線の引ける画家は院展の靫彦しかいない」と教えられ、靫彦の名前を心に刻んだ。やがて遊亀は教師となり、横浜に赴任した。しかし画家への夢断ちがたく、大磯の靫彦の門を叩こうと決意した。一九二〇(大正九)年、遊亀、二五歳の時である。
新調の黒薩摩に白地の帯、腰巻まで一新した。もし入門を許されなかったら、小倉遊亀という絵描きは死ぬ、この日が私の命日だと悲壮な決意で臨んだ。いわば死に装束のつもりだった。
入門を熱望する遊亀に靫彦はこう答えた。
「絵の道には弟子も師匠もない。ただ先と後があるだけです。なんでも言える先輩としてなら、あなたを迎えましょう」
感激した遊亀はこう訴えた。
「先生、何を書いても同じようにしかならないのです」
「あなたの絵は強い。技法の上に、既にひとつの型ができている。生まれ変わりたいなら、型を破ることです。ただこれは容易ではありません。自分を出そうとしなくても、見た感じを逃さぬようにしてください。描き続けていれば、その都度違う表現となっていきます……、そうすれば、いつのまにか、一枚の葉が手に入ります。一枚の葉が手に入ったら、全宇宙が手に入れられるでしょう」
と道を示したという。絵に精進する者同士の身震いするような逸話である。
さて、執行コレクション丨
「まず、《大伴宿禰家持像》からお見せしましょう。これは昭和二三年、歌人の佐々木信綱の喜寿(七七歳)の祝いに描かれたものです」
総務部長の伏木裕美子が伸び上がり、軸装の画を壁にかけた。筆を持ち、歌を練る、たっぷりとした家持であった。運筆にいささかの迷いもない。
「見てください。この楠木正成。横山大観を始めとして正成を勇壮に描いたのは多い。しかしこうは描けていません。私は哀しさのある画が好きです。靫彦の人物画には憂愁が漂っています。靫彦は弱者の視点を持っています。無論、義経などの凛々しい若武者も良いのですが……」
私は執行をまじまじと見た。まさに武士のような風貌をしている。戸嶋靖昌があることを教えてくれた。執行家は代々九州鍋島藩の奉行職で、何度か家老も務めた。祖父の弘道は英国のオックスフォード大学に留学、帰国後、日本文化を世界に広める万博に関わった。晩年は枢密院に属し、美術顧問として、大正天皇や昭和天皇に講義した。しかし執行はそんなことを一切口にしない。
「どうですか、これ?」
「題は?」
「萩野です」
「これ、良寛が持っていた歌集『あきの野』から採っていますよ。良寛は万葉集を抜粋して自ら認めた、それをあきの野と呼ぶのです」
萩野を行くのは天平の公達だろうか。萩を手折って恋しい人に贈るのかもしれない。中国の墓の副葬品である俑からヒントを得た、《箕を持つ宮人》も佳品である。なんと明るく澄んだ色なのか。
話題は日本画の技法である白描に移った。ちなみに白描とは墨一色で描かれた絵に淡彩を施したものを指す。平安時代の大和絵に見られ、鎌倉時代には精緻な白描大和絵の絵巻が制作された。靫彦の特徴のひとつとされる。
「白描について、靫彦はこう言っています。白描は単なる輪郭などではない。そこには深い内容が裏づけられている。ある場合には色彩を施した作品よりもっと高いものだ。これは立派に完成された一個の本格的な芸術だと」
「なるほど、至言ですね」
話は尽きなかった。私は川端にも靫彦にも会ったことがない。おそらく執行草舟を通して、蒐集家なるものを見極めているのだろう。
作家の井上靖は知人にこんなことを語った。「私はペン一本で生きています。夜更けて一人、一字一字原稿の升目を埋めて、いくばくかの名声といくばくかの財を得ているわけですが、決して楽な仕事ではありません。そうして得た財で、私は美しいもの、第一級のものを手に入れたいのです。箱に入れておくのでは何の意味もありません。いつも眼に触れ手に触れられる身近に置いておきたいのです。それが、私の心の、創作の糧になるのです」
と。知人とは奈良県桜井市の観光課長・米田一郎のことである。米田のことは後述したい。
美術品の蒐集は趣味や道楽などではない。まさに座辺師友、身近にあり教え導かれる存在である。川端はいいものに出会うと命を拾った思いがすると述べたが、まさしくこのことであろう。執行と共有する時間は豊饒で、またたく間に過ぎていく。
「執行さん、コレクターとして、何か書いてください。この秋に本を出しますから」
「ああ、いいですよ」
快く了解してくれた。
後日、送られてきた原稿を見て仰天した。靫彦への灼熱のオマージュが火山のように噴出、まるっきり段落というものがなかった。文章を書く上での約束事など、たいした問題ではないのだろう。執行は絵の具ではなく、言葉で思いの丈を叩きつけた。表現の苛烈さにおいて、戸嶋と同様に執行も遜色はないのだ。