

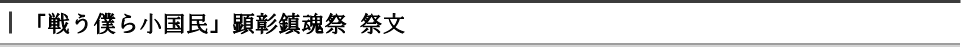
謹しみ畏みて、靖國神社の英霊の御前に奏上し奉ります。
思い出づる大東亜戦争最後の年、いまを去る七十七年前の今日この日、昭和二十年三月十日に、東京下町一帯は人類史上最大と言わるる米空軍の大爆撃によって潰滅せしめられました。その間、辛うじて生き延びた被災者の多くは既に世を去り、一つの真実が知られざるままに埋もれようとしております。いまここに、神々と英霊にこれを照覧いただくべく我ら一同会しております。
言辞を絶する爆撃の実態についてはこれまで詳細に検証され、被災者の凄惨なる体験も語り継がれ、慰霊祭も連綿と行われてきました。かたわら、犠牲者の遺骨を収める鎮魂碑は依然として立たず、一方、被害の補償を国に求めるごとき偏向した政治化さえ生ずるに至りました。
いかなる慰霊の形態でありましょうとも、そこには一つの共通の根本的認識があり、それは一貫して下町大空襲を「無辜の市民の犠牲」として捉えることでした。もちろん、これはまったくの真実であり、この爆撃が非戦闘員のジェノサイドだったことは一点の疑いをも容れません。しかし、そこには、歴史の蔭に掻き消された別のささやかな真実があり、それを私共は今日ここに喚起したいのであります。何かと申せば、大空襲下、当時、国民学校の生徒だった少年少女は、けっしてただむざむざと殺されたにあらず、「銃後の守り」の自覚と誇りを持った小戦士たちだったということであります。
かく申す自分自身、業火をかいくぐって九死に一生を得た国民学校六年生、十一歳の少年でした。この資格において、以下に素朴な証言を呈させていただきます。
思い起こせば、当時日本はアメリカ相手に太平洋上で三年有半にわたり死闘を続け、烈々の士気衰えることなきも、アッツ島の象徴的玉砕に始まって守勢となり、ついには絶対国防線をも突破され、敗北へと追いつめられていました。下町大空襲の前年秋には、すでに米・英・仏主体の連合軍は日本本土上陸作戦に乗りだし、これを察知した我が国大本営は焦土決戦をも辞せじと究極の国土防衛計画を遂行しようとする矢先にありました。強制的に疎開が押し進められ、都市の至るところに防空壕が掘られ、後に無謀な戦略の代名詞となる「竹槍訓練」までが住民にほどこされようとしていました。下町大空襲が起こったのは、さらに国民義勇隊が編成される直前のことでした。すなわち、国民学校卒業生から六十代老人に至るまでを総動員し、日本列島に上陸してくる敵を迎え撃つうえに最大三百万人の犠牲者の出ることをも想定して、一億総玉砕が叫ばれていたのです。沖縄戦に先立つ三ヶ月前のことでした。
後の世に如何に無謀、狂気と誹られようとも、しかし、そのような中にあっても、皇国日本が敗れると思った国民はなかったのです。それは国民学校の生徒たちにとっても同様でした。幼いながらも、いや、幼いからこそより純粋に最後まで日本の勝利を信じ、戦地の兵隊さんと一体になって僕たちわたしたちも戦っているのだとの自覚をもって、あらゆる困苦欠乏に耐えていたのであります。
B29による東京空襲は前年の十一月から始まっていました。それまで「戦線・銃後」と呼ばれていた区分けは、もはやありません。戦線は東京の上空にまで移ってきていたからです。巷には「ここも戦場だ」とのポスターがひるがえり、私たち生徒は「勝ち抜く僕ら小国民」、あるいは「戦う僕ら小国民」の呼称を胸に、それを誇りと思っていました。学校の校庭で、たすき掛けで一斉に薙刀を振るっていた女生徒たちの健気な姿が思い浮かびます。僕ら男子生徒の手には、いつしか剣道の竹刀に代わって竹槍が握られていました。「鬼畜米英」に見立てた藁人形に向かって小さな叫びを上げて突っこんでいくのです。手榴弾投げも習いました。一、二,三の三秒で投げなければ自分が死ぬぞと指導され、食糧不足でやせこけた体で煉瓦を投げるのに必死でした。
狂気の沙汰には違いありません。「軍国主義」の行き過ぎかもしれません。しかし、往古、わずか三百騎でペルシアの大軍に抗して全滅したスパルタのテルモピレーの戦い以来、国敗れんとするや、いずこでも、いかに弱小なりとも、そのように人々は祖国防衛に命を賭してきたのではないでしょうか。のちにヴェトナム戦争が起こったときに世界は、小国といえども挙国一致の真価を知るでありましょう。そのかみ、蒙古来襲にさいしてこれに屈せず撃退したのはアジアで日本とヴェトナムの二国のみであった史実を思わずにいられません。
過去の事例ばかりではありません。東欧の一国、ウクライナが、まさにこの数日前から核大国ロシアの侵略を受け、大統領の呼びかけで六十歳までの男性が踏み止まり、挙国一致で応戦しつつあるではありませんか。
隅田川を挟んで、本所・深川・向島から日本橋・江戸川にかけて、七歳から十一、二歳までの生徒たちが一身を捧げる覚悟をもって苦難を耐え抜き、そのほとんどが猛火に命を奪われたことは、無惨ではありましたが、だからといって、いたずらに哀れとのみ嘆くのみではその魂は浮かばれない、むしろ、よく耐え抜いたと讃えるべきではありますまいか。
そして「戦う僕ら小国民」の顕彰鎮魂を行いうる唯一の場こそは、ここ靖國の宮居なのであります。
何となれば、かくも苛酷な運命を小さな肩に耐えさせたものこそは、「戦地の兵隊さん」を思う一体感にあったからにほかなりません。しかして、戦地は列島に迫りつつあり、それは上空から始まっていました。名にし負う「帝都防空戦」なる戦闘機隊が三鷹から千葉に至る空域に侵入しくる敵爆撃機群を何度も迎撃し、わけても特攻隊員十三烈士は「三月十日」に先立つ空爆激化の三ヶ月間に集中して、体当たり、散華しておられるのです。
私たち下町の住人もそうした光景を目撃したことがありました。それは、忘れもしない昭和十九年十二月二十九日真昼のことでした。壮絶な空の戦いを、私共はみな防空壕から這い出て見つめていました。すると、高高度で飛来するB29の編隊の一機に、針のように鋭い光が走ったと見るや、敵機は真っ二つに切断され、驚くほどの巨体と翼を落下させていったのです。それは私が生涯で只一度目にした「体当たり」の瞬間でした。何が起こったのかを知ったのは、ずっと後のことでしたが。逆落としの必殺技で見事大敵を仕留めたのは、特攻隊員ならぬ若干二十歳の少年飛行兵、熊谷兼一軍曹だったと判明しました。しかも若武者は、深川森下町の私共の真上の上空から、猛火につつまれた愛機をあやつって亀戸まで落下し、人家を避けて沼の泥土ふかくに没しさったのです。同地の人々の感動がいかばかりであったか、後にその地に立てられた石碑が雄渾に物語るとおりであります。
このような壮絶なる天空の捨身の光景をまざまざと見て、ただ歯がみするばかりであった地上の私共住民は如何に感動に打ちふるえ、我もまた神州を死守せんとの一層の気概に燃え立ったことでしょうか。
「バトル・オブ・東京」は、かくのごとく天と地、軍民一体となって繰りひろげられていたのです。
ちなみに「三月十日」の大爆撃で命を奪われた無慮十万の人々は、けっして我が方が無反撃であったのではなく、果敢に反撃して少なからぬ戦果を挙げた事実を知って御霊を安んぜられんことを。
この空襲は、B29約三百機が二時間半にわたって狭いエリアを低空で舐めつくすように徹底的に焼きつくした殺戮行為でしたが、ただちに出撃した我が方の防空戦闘機と高射砲により撃墜十五機、撃破五十機の戦果を挙げたことが後に判明したからであります。
「三月十日」大空襲により東京の東部は潰滅し、日本全土の大半の都市は炎上し、五ヶ月後に原爆投下、ポツダム宣言受諾へと日本は追いつめられ、戦後さらに戦勝国側によって日本の大義、聖戦は悪として断罪されるに至りました。しかしながら、歴史の裁判の是非をこえて私たち日本人は、明日なき、あの暗い日々の中にあってさえ、戦線銃後がかくも一致団結して国難に立ち向かった事実を忘るべきではなく、むしろ誇りをもって思いかえすべきであろうと信ずる次第であります。
わけても、「戦う僕ら小国民」があったという事実を――。
私自身、その一員でした。江戸の浮世絵師、歌川広重描くところの名画、「大橋 あたけの夕立」、いまの新大橋のたもとの八名川国民学校で、卒業式一週間前で爆撃に遭いました。「海ゆかば」の作曲家、信時潔の作った校歌を斉唱するこの学校で、私は、深川出身の戦地の兵隊さんへ慰問文を出したことから交流が生じ、満州国から支那、台湾を経てスマトラに至るまでの大勢の出征兵士の方々と三年間にわたって緊密な手紙のやりとりを続けました。私の十歳前後のことでした。わが生涯において、これほどの熱い思いを交わしたことはありません。文字どおり「戦線銃後の別なく」互いに死線をこえて励まし合ったのです。そのうち八名の方々の軍事郵便二十二通が手元に残っております。その中の五方が戦死者として祀られております。日本が勝利したあかつきには晴れて私たちは相会し、名乗り合えたものを、往年の軍国少年は言うべき言葉もありません。
ただ、思うのです。
護国の英霊二百四十六万余柱に、何のかんばせあって私共は相見えることができようか、と。
戦死者だけではありません。玉音放送を聞いて無窮の皇道に殉じた大東塾十四士から真正日本の覚醒のため義挙に立った三島由紀夫・森田必勝の両烈士に至るまで、壮絶なる自刃をとげた英雄たちの魂魄に真向かっても、我ら生者は何を言いうるでありましょうか。
国士三浦義一の挽歌が甦ってまいります。
かかる日に 逢ふと誰かは おもひけむ
死にて悲しゑ 生きてかなしゑ
死することに劣らず苦しい生くる道を選んだこれら先人の努力によって戦後日本は奇蹟の復活を遂げ、世界を驚嘆させましたが、経済優先の繁栄の蔭に尚武の気質は失われ、新たなる近隣覇権国家の脅威に対して毅然たる姿勢を取りえない現状へと至りました。平和は防人の血によって贖われたにもかかわらず、崇敬の念は薄れ、靖國の神苑にぬかづく宰相の影は途絶えました。さる年の八月十五日に昭和天皇の詠まれた、
この年の この日にもまた 靖國の
みやしろのことに うれひはふかし
との御製に流るる慷慨が、ソロモンの神殿に詣でることのかなわぬ身を嘆いた預言者エレミヤの悲歌をどうして喚起せずにいるでしょうか。
かくして亡びたユダ王国がイスラエルとして復活するまでに実に二千五百年あまりの歳月を要し、その間、ヘブライの民は「さまよえるユダヤ人」として世界中に四散の運命を辿ったのでした。
聖書は、史上最も残酷といわれたアッシリアをさして「北より一つの国が攻め来たり、この地を荒廃させた」と誌しています。悪はつねに北より来たるとの根源的ヴィジョンが、以後、失われたことはありません。アッシリアにもまさる残酷が、現にユーラシア大陸の覇権国家によって周辺弱小民族に対して行われつつあり、その暴虐ぶりは、そもそも人類の進歩とは何ぞやとの根本疑念を起こさせずにはいません。
このような疑念、無力感に、いまや世界の民主主義陣営は囚われているかに見えます。
しかしながら、我が国は、フランスの人権宣言以後たかだか二百三十年を数えるにすぎない西洋の近世民主主義に較べて、神武創成のみぎりより独自の民本主義を宣明した国であり、ここから発祥した武士道は、西洋の騎士道が短命で終わったのにひきくらべて倍以上も長く存続し、しかも皇室あるゆえに今後もなお常にその復興の可能性を保持しています。特攻は、その誇るべき一つの例証にほかなりません。かかる復興を懼れるがゆえに敵性勢力は「武士道があるのになぜ残虐行為をやったのか」と卑劣な反日悪宣伝に汲々としてきましたが、それとても日本側研究者の精緻なる歴史検証によって完膚なきまでに論破され、やがて朝の幽霊のごとく消えゆかんとしています。
いまや日本は、伝家の宝刀を手に、剣太刀いよよ研ぐべき時に至りました。敗北を嘆く時代は去り、尊い皇軍の犠牲によってアジア・アフリカ諸国を独立させ、世界史を一変させた奇蹟を誇るべき時であります。
思えば、アジアにおいては、ガンジーとネールのインドは、非暴力主義を貫いて非道なるイギリスの植民者たちを一掃し、「正義の手段をもって正義の国家をつくる」範を示して世界から称賛されましたが、ネール首相はロシアを破った武士道の日本に発憤して回天の偉業を達成したことが想起されます。
「北より一つの国が攻め来たり」エルサレムを破壊した神話的悪夢がよみがえりつつあります。
その根底とする唯物主義イデオロギーを打ち破る強固な思想を見いだせずに自由世界はたじろいでいます。
しかし、日本には、まさに武士道があるではありませんか。
あの絶望的日々のなかでさえ、「戦う僕ら小国民」は、日本が世界最初に「人種差別撤廃」を国際場裡で宣言した国であることを誇りとして、死をも恐れず、聖戦を戦い抜くことを誓い合っていたのです。
その多くを焼き亡ぼした猛火の中から、猛火よりも強く、いま、彼らの殉国の歌声が聞こえてきます。
神とまします英霊に願い上げ奉ります――
たとえ戦死者と呼ばるること適わぬとも、
せめて今日、
ここ九段の大鳥居の空に、
「戦う僕ら小国民」の精霊を迎え、
親しく照覧したまわらんことを!
令和四年三月十日 斎主 竹本忠雄