

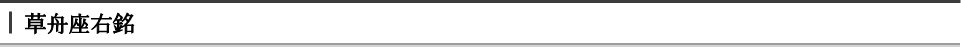
執行草舟が愛する偉人たちの言葉を「草舟座右銘」とし、一つひとつの言葉との出会い、想い、情緒を、書き下ろします。いままで著作のなかで触れた言葉もありますが、改めて各偉人に対して感じることや、その言葉をどのように精神的支柱としてきたか、草舟が定期的にみなさまへご紹介します。ウェブサイトで初めて公開する座右銘も登場します。
この世は、悲しみに満ちた街道に過ぎない。
《 This world nys but a thurghfare ful of wo. 》
『カンタベリー物語』を読んだときの感慨を、忘れることはないだろう。その書き出しからして、実に信仰的で敬虔に満ちている。何か近代の洗礼を受けてしまった我々が、失ってしまったものを感ずるのだ。人生の目的というか、そういう根源的なものがすでに違っている。無心に、あの大伽藍を創り続けた純心に出会う清々しさがある。恐ろしい話にも、愛くるしさが漂っている。それは根底の命の問題に違いない。自分自身の命が、どういうものなのかという認識の差異だ。
中世人は、自分たちを神の分身だと信じていた。そしてこの世を、神の国へ行くための修行の場と考えていたのだ。中世の根本哲学である「死を想え」(メメント・モリ)を思い返すこともないだろう。その中世人の生に、我々は人間の豊かさを見ている。その悲しみを湛えた人生に、我々は人間の生まれて来た本質を感じているのだ。それはアナール派の歴史家たちを持ち出すまでもなく、いまの歴史観の常識となりつつある。人間の心に神が生きていて、人生の時間は限り無くゆったりと流れる。
生きることを、本当に味わい尽くしている人生をそこに感ずるのは、私だけではあるまい。人生を味わう人々は、この人生の悲哀を抱き締めていた。自分の命のはかなさを深く知っていたのだ。それが愛を生み憎しみもまた生み出した。そこに本当の生の躍動があった。自分たちを、旅人と感じていた。この世を苦しみと悲しみの旅と思っていたのだ。しかし、それが偉大な中世の文化を創り上げたのである。ヨーロッパでも日本でも、現代の我々が享受する文化の豊かさは、すべてその根を中世に負っているのだ。
2021年1月18日
