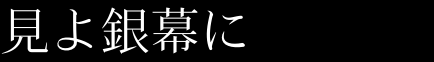
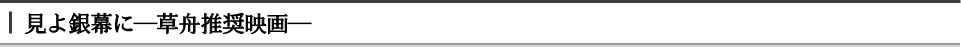
著作『見よ銀幕に―草舟推奨映画―』は多くの方にご愛読いただいておりますが、草舟私見を読むことができ、推奨映画を検索できるページができました。最新の推奨映画もタイムリーにお知らせでき、またご興味に合わせて膨大な映画の中から、ワード検索し抽出することができます(例:ルイ・ジューヴェ、愛、陸軍、フランス、母など)。映画のあらすじは本のみの掲載になりますので、ぜひお手元の本と合わせてご活用ください。
(※書籍『見よ銀幕に―草舟推奨映画―』(734本の推奨映画収録)の情報はこちら)
最新の草舟私見の一覧)
「蜩(ひぐらし)ノ記」(2025年8月25日追加)
「四万十川」(2025年8月18日追加)
「朝を呼ぶ口笛」(2025年8月18日追加)
「夕笛」(2025年8月18日追加)
「紀ノ川」(2025年8月17日追加)
「越前竹人形」(2025年8月17日追加)
「日輪の遺産」(2025年5月20日追加)
「ベルファスト」(2025年1月28日追加)
「復活の日」(2023年12月19日追加)
「1950 第一部 鋼の第7中隊 第二部 水門橋決戦」(2023年10月24日追加)
(1959年、大映) 90分/カラー
(1966年、大映) 121分/カラー
(1974年、東映) 199分/カラー
(1965年、大映) 87分/白黒
(1967年、東映) 102分/白黒
(1968年、東映) 104分/白黒
(1960年、大映) 95分/カラー
(1979年、新日本映画) 154分/カラー
(1968年、東映) 103分/白黒
(1969年、大映) 100分/カラー
(1988年、仏) 204分/カラー
(2015年、米) 97分/カラー
(1989年、東宝) 114分/カラー
(1963年、日活) 100分/カラー
(1970年、ソ連=伊) 150分/カラー
(2015-2017年、カナダ) 269分/カラー
(1975年、米) 114分/カラー
(1949年、英) 98分/白黒
(1965年、黒澤プロ) 185分/白黒
(1972年、西独) 93分/カラー
(1960年、松竹) 128分/カラー
(1988年、仏) 116分/カラー
(1978年、東映) 159分/カラー
(1967年、日活) 91分/カラー
(1960年、日活) 106分/カラー
(2016年、仏) 117分/カラー
(1955年、東宝) 109分/白黒
(1969年、米) 111分/カラー
(1995年、伊) 115分/カラー
(1964年、東映) 103分/白黒
(1988年、タキエンタープライズ) 114分/カラー
(1999年、中国) 106分/カラー
(1948年、米) 123分/白黒
(1951年、米=英) 105分/カラー
(1995年、フジテレビ=松竹) 94分/カラー
(2006年、米) 138分/カラー
(2019年、米) 93分/カラー・白黒
(1995年、米) 140分/カラー
(2000年、「雨あがる」製作実行委員会) 91分/カラー
(1961年、米) 121分/白黒
(1977年、東京映画) 141分/カラー
(2006年、スペイン) 139分/カラー
(1960年、米) 155分/カラー
(2001年、米) 157分/カラー
(1938年、ソ連) 108分/白黒
(1973年、仏=伊) 95分/カラー
(1984年、豪) 183分/カラー
(1959~1963年、米) 合計3870分/白黒
(1995年、オランダ=ベルギー=英) 102分/カラー
(1967年、ソ連) 182分/パートカラー
(2008年、米) 177分/カラー
(1959年、米) 150分/白黒
(1996年、TBS) 94分/カラー
(2018年、仏) 109分/カラー
(1949年、米) 109分/白黒
(1940年、米) 130分/白黒
(1993年、米) 127分/カラー
(2011年、テレビ朝日) 120分/カラー
(1983年、東宝) 125分/カラー
(1974年、東宝=ホリプロ) 82分/カラー
(1987年、こぶしプロ) 117分/カラー
(2018年、チェコ=ウクライナ) 169分/白黒
(2021年、中国) 合計324分/カラー
(1992年、米=仏=スペイン) 156分/カラー
(1963年、日活) 89分/カラー
(2019年、英=米) 119分/カラー
(1967年、伊=仏) 104分/カラー
(2014年、米) 115分/カラー
(1995年、伊) 109分/カラー
(1944~1946年、ソ連) 209分/白黒・パートカラー
(2009年、米=独) 153分/カラー
(2014年、米=英) 169分/カラー
(1997年、米) 103分/カラー
(2011年、米) 111分/カラー
(1988年、英=米=西独) 106分/カラー
(2009年、フジテレビ・他) 114分/カラー
(2001年、米) 134分/カラー
(1995年、英) 96分/カラー
(2016・2018年、米) 合計1257分/カラー
(1986年、電通=毎日放送) 140分/カラー
(2003年、米) 110分/カラー
(1996年、フィンランド) 96分/カラー
(1966年、米) 96分/カラー
(1967年、松竹) 100分/白黒
(1974年、讀賣テレビ=オフィス・アカデミー) 全650分/カラー
(1986年、「海と毒薬」製作委員会) 123分/白黒
(1999年、米=伊) 125分/カラー
(2018年、英=仏=米)112分 カラー
(1965年、TBS) 104分/白黒
(1971年、米) 109分/カラー
(1960年、米) 208分/カラー
(1992年、NHK) 150分/白黒(パートカラー)
(映像の世紀:1995~1996年、新・映像の世紀:2015~2016年、NHK) 合計1175分/カラー
(2000年、米) 127分/カラー
(2011年、スペイン) 95分/カラー
(1981年、東宝) 132分/カラー
(1939年、米) 92分/白黒
(2015年、英) 108分/カラー
(2014年、米=英)150分/カラー
(1956年、英) 123分/白黒
(1963年、大映) 102分/モノクロ
(1991年、フジテレビ=東映) 114分/カラー
(1998年、英) 123分/カラー
(2007年、英) 115分/カラー
(1989年、英) 94分/カラー
(1987年、スペイン=仏=伊) 150分/カラー
(1980年、米=英) 123分/白黒
(1953年、新東宝) 108分/白黒
(1962年、東映) 92分/白黒
(1997年、イラン) 98分/カラー
(1975年、米) 123分/カラー
(2000年、ベルギー=仏=独) 114分/カラー
(1976年、米) 98分/カラー
(1960年、東宝) 95分/白黒
(1960年、東映) 90分/カラー
(1937年、米) 84分/白黒
(1976年、東宝) 102分/カラー
(2005年、「ALWAYS 三丁目の夕日」製作委員会) 133分/カラー
(1990年、東映=テレビ朝日=モスフィルム、他) 123分/カラー
(1974年、東宝) 93分/カラー
(1965年、英) 165分/カラー
(2004年、テレビ朝日) 合計453分/カラー
(1976~82年、NHK) 合計1000分/カラー
(2005年、「男たちの大和」製作委員会) 143分/カラー
(1996年、NHK) 合計240分/カラー
演出・構成:波田野紘一郎/音楽・出演:デヴァカント/語り:蟹江敬三/ドキュメンタリー(1998年、伊) 95分/カラー
劇場版(1995年、松竹=フジテレビ) 104分/カラー
テレビシリーズ(1989~2006年、松竹=フジテレビ) 各話約50分(スペシャルは70~90分)/カラー
(2016年、韓国) 110分/カラー
(1938年、独) 212分/白黒
(1967年、米) 105分/カラー
(1992年、大映=電通) 123分/カラー
(2001年、「かあちゃん」製作委員会) 96分/カラー
(1985年、東映) 135分/カラー
(1982年、東宝) 142分/カラー
(2007年、NHK) 222分/カラー
(1972年、東宝) 128分/カラー
(1954年、米) 91分/カラー
(1936年、米) 87分/白黒
(2007年、仏) 109分/カラー
(1996年、NHK) 120分/カラー
(1995年、米=南ア) 106分/カラー
(1980年、東宝) 179分/カラー
(1978年、NHK) 合計510分/カラー
演出: 斎藤暁、村上佑二、江口浩之、門脇正美、三井章/原作:司馬遼太郎/音楽:林光(2002年、米) 120分/カラー
(2013年、スタジオジブリ) 126分/カラー
(1976年、NHK) 各話45分・合計2340分/カラー
(1939年、米) 232分/カラー
(1975年、米) 113分/カラー
(2008年、フジテレビ) 合計532分/カラー
(1984年、徳間書店=博報堂=東映) 116分/カラー
(2007年、NHK) 合計344分/カラー
(1999年、イラン) 118分/カラー
(1970年、松竹) 107分/カラー
(1974年、伊=仏) 130分/カラー
(1990年、日本テレビ) 313分/カラー
(2007年、ポーランド) 123分/カラー
(2009年、「火天の城」製作委員会) 140分/カラー
(1944年、東宝) 89分/白黒
(2017年、NHK) 60分/カラー
(2011-2012年、NHK) 合計2265分/カラー
(2022年、NHK) 2190分/カラー
(1982年、松竹=角川春樹事務所) 109分/カラー
(2013年、NHK) 合計196分/カラー
(2007年、伊=仏=スペイン=独) 209分/カラー
(1968年、ソ連) 228分/カラー
(2015年、米) 114分/カラー
(1951年、松竹) 86分/カラー
(1974年、芸苑社) 211分/カラー
(1974年、米) 144分/カラー
(1965年、米) 139分/カラー
(1957年、米=西独) 98分/カラー
(1982年、英=印) 188分/カラー
(1998年、今村プロ=東映=東北新社=角川書店) 129分/カラー
(2001年、TBS) 96分/カラー
(1949年、米) 103分/カラー
(1995年、東映=バンダイ) 130分/カラー
(2010年、TBS) 118分/カラー
(1956年、米) 114分/白黒
(1964年、大映) 152分/白黒
(2015年、英) 108分/カラー
(1962年、米) 107分/白黒
(1999年、米) 95分/カラー
(1984年、東映=俳優座映画放送) 124分/カラー
(1938年、仏) 98分/白黒
(1986年、松竹) 135分/カラー
(1966年、松竹) 173分/カラー
(1989年、日本テレビ) 310分/カラー
(1959年、米) 115分/カラー
(1995年、君を忘れない製作委員会) 116分/カラー
(2000年、米) 144分/カラー
(2013年、キャプテンハーロック製作委員会) 115分/カラー
(1999年、仏=ネパール=英=スイス) 108分/カラー
(2002年、米=伊)/167分/カラー
(2000年、キューバ=仏) 97分/カラー
(1953年、仏=メキシコ) 99分/白黒
(1952年、仏) 147分/白黒
(1992年、英=ポーランド=デンマーク) 97分/カラー
(1988年、ギリシャ=仏) 125分/カラー
(1982年、東映=俳優座映画放送) 146分/カラー
(1976年、ATG) 109分/カラー
(1979年、東映) 128分/カラー
(1975年、大映) 155分/カラー
(2005年、米=スペイン=英=独) 145分/カラー
(1951年、仏) 82分/白黒
(1993年、伊=仏=独) 118分/カラー
(2000年、米=独=英) 124分/カラー
(1984年、東映=全真言宗青年連盟映画製作本部) 169分/カラー
(1969年、英) 127分/カラー
(1979年、NHK) 合計400分/カラー
(2000年、「郡上一揆」製作委員会) 112分/カラー
(1984年、米) 93分/カラー
(1964年、佐野芸術プロ) 92分/カラー
(1978年、松竹=俳優座) 160分/カラー
(1953年、重宗プロ=新世紀映画) 100分/白黒
(1957年、松竹) 105分/白黒
(1995年、東映=松プロ) 130分/カラー
(2000年、米) 155分/カラー
(1988年、仏) 168分/カラー
(1968年、米) 133分/カラー
(1999年、米) 188分/カラー
(1999年、仏) 115分/カラー
(1993年、カナダ) 94分/カラー
(1989年、今村プロ=林原グループ) 123分/白黒
(1959年、仏=ブラジル) 107分/カラー
(1987年、伊) 113分/カラー
(1989年、米) 122分/カラー
(1968年、三船プロ=石原プロ) 195分/カラー
(1970年、米) 139分/カラー
(1972年、東宝=新星映画) 96分/カラー
(1956年、新東宝) 101分/白黒
(2009年、テレビ朝日) 229分/カラー
(2002年、米) 137分/カラー
(1985年、米) 113分/カラー
(1992年、テレビ朝日=松竹=荒戸源次郎事務所) 50分/カラー
(1955年、スペイン) 87分/白黒
(1961年、英) 99分/白黒
(1957年、西独) 107分/白黒
(1956年、英) 136分/白黒
(1970年、東宝) 134分/カラー
(1971年、東宝) 149分/カラー
(1993年、仕事) 111分/カラー
(1965年、大映) 83分/カラー
(1977年、米) 110分/カラー
攻殻機動隊(1995年、講談社=バンダイ) 84分/カラー
続・攻殻機動隊(2004年、徳間書店=電通・他) 99分/カラー
(2006年、NHK) 各話44分・合計2188分/カラー
(1946年、米) 97分/白黒
(1960年、米) 128分/カラー
(1964年、伊=西独=スペイン) 97分/カラー
黄落(1997年、テレビ東京) 119分/カラー
(1996年、カザフスタン=露) 95分/カラー
(2004年、米) 136分/カラー
(1970年、仏=伊) 134分/カラー
(1981年、米) 108分/カラー
(2013年、NHK) 合計360分
(1999年、英) 104分/カラー
(2011年、NHK) 合計98分/カラー
(2016年、スペイン) 126分/カラー
(1972年、米) 175分/カラー
(1974年、米) 200分/カラー
(1982年、米) 121分/カラー
(1938年、日活) 71分/白黒
(1961年、大映) 119分/白黒
(1993年、斑目力曠) 98分/カラー
(2004年、仏) 100分/カラー
(1988年、日本テレビ) 290分/カラー
(1990年、ポーランド=西独) 118分/白黒
(2019年、「コンフィデンスマンJP」製作委員会) 124分/カラー
(2000年、米) 145分/カラー
(2011年、仏) 113分/カラー
(2021年、英=米) 133分/カラー
(1970年、米) 126分/カラー
(1995年、日=豪) 90分/カラー
(1957年、日活) 81分/白黒
(1970年、東映) 122分/白黒
(2011年、仏=伊=アルジェリア) 105分/カラー
監督:ジャンニ・アメリオ/原作:アルベール・カミュ/音楽:フランコ・ピエルサンティ/受賞:ヴェネチア映画祭 外国人記者協会賞(1980年、米) 114分/カラー(一部白黒)
(1965年、米) 175分/カラー
(1994年、映画「さくら」製作委員会) 109分/カラー
(1991年、独=仏=カナダ) 106分/カラー
(2010年、「桜田門外ノ変」製作委員会) 137分/カラー
(2014・2015年、中国) 合計255分/カラー
(1950年、新東宝) 141分/白黒
(2001年、米) 129分/カラー
(1999年、英) 95分/カラー
(2016年、NHK) 各話44分・合計2253分/カラー
(1981年、米=リビア) 175分/カラー
(2002年、米=英) 132分/カラー
(1968年、東宝) 97分/カラー
(1999年、仏=スペイン) 100分/カラー
(1986年、米) 122分/カラー
(2010年、中国) 合計4085分/カラー
(1947年、米) 96分/白黒
(1999年、仏) 108分/カラー
(1962年、松竹) 112分/カラー
(2000年、近代映画協会) 126分/カラー
(2018年、米) 101分/カラー
(1965年、米) 105分/カラー
(1993年、仏) 160分/カラー
(1993年、米) 114分/カラー
(2022年、米) 587分/カラー
(1998年、日=中国=仏=米) 168分/カラー
(1969年、伊=西独) 155分/カラー
(1951年、米) 114分/カラー
(1979年、米) 153分/カラー
(1994年、東宝=日本テレビ=サントリー) 129分/カラー
(1962年、米) 178分/白黒
(1952年、米) 129分/カラー
(1949年、大映) 94分/白黒
(2016年、英=ベルギー) 125分/カラー
(1954年、東宝) 207分/白黒
(1955年、米) 105分/カラー
(1956年、米) 222分/カラー
(2001年、米) 128分/カラー
(2002年、中国) 97分/カラー
(1984~1994年、英) 各102~104分/カラー
(1991年、日本へラルド映画) 111分/カラー
(1964年、米) 155分/カラー
(2017年、英) 90分/カラー
(1972年、米) 142分/カラー
(1999年、米) 158分/カラー
(1991年、米=香港) 115分/カラー
(1984年、松竹=セゾングループ=シネマセゾン、他) 121分/カラー
(1964年、東映) 97分/白黒
(2012年、若松プロ) 120分/カラー
(1966年、英=仏) 138分/カラー
(1942年、日活) 90分/白黒
(1983年、フィルムリンク・インターナショナル) 132分/カラー・白黒
(2001年、NHK) 180分/カラー
(2002年、NHK) 合計240分/カラー
(2014年、BS朝日) 45分/カラー
(1994年、米) 143分/カラー
(2000年、米) 121分/カラー
(1984年、東映) 139分/カラー
(1993年、米) 101分/カラー
(1966年、大映) 150分/白黒
(1978年、フジテレビ) 合計1426(各話46分、全31話)/カラー
(2009年、オーストリア=独=仏=伊) 144分/白黒
(1987年、西武セゾンクループ=学研=キネマ東京=荒木事務所) 110分/カラー
(1989年、米) 107分/カラー
(1962年、日活) 102分/白黒
(2004年、テレビ東京) 120分/カラー
演出:高橋一郎/原作:高橋団吉/音楽:渡辺貞夫(1953年、米) 92分/カラー
(2006年、NHK) 合計174分/カラー
(1970年、三船プロ) 122分/カラー
(1965~66年、東映=テレビ朝日) 合計1300分/カラー
(1993年、米) 195分/白黒(パートカラー)
(1972年、NHK) 191分/カラー
(1983年、米) 170分
(2015年、「杉原千畝」製作委員会) 139分/カラー
(1971年、英) 103分/カラー
(1949年、米) 133分/白黒
(1984年、米) 114分/カラー
(1993年、独=米) 138分/カラー
(2001年、米=独=英=アイルランド) 131分/カラー
(1973年、米) 129分/カラー
(1999年、米) 111分/カラー
(1964年、勅使河原プロ) 124分/白黒
(1974年、松竹) 143分/カラー
(2003年、「スパイ・ゾルゲ」製作委員会) 182分/カラー
(1960年、米) 186分/カラー
(1963年、米) 120分/カラー
(2006年、米) 117分/カラー
(2019年、NHK) 119分/カラー
(1996年、ポーランド=独=仏) 97分/カラー
(1993年、NHK) 合計830分/カラー
(2018年、ニュージーランド=英) 99分/カラー・白黒
(1981年、東映) 140分/カラー
(1999年、米) 119分/カラー
(1982年、東映) 142分/カラー
(1930年、米) 103分/カラー
(1987年、東映=今村プロ) 124分/カラー
(1954年、ポーランド) 88分/白黒
(1984年、YOUの会=ヘラルド・エース) 140分/カラー
(2003年、NHK) 合計301分/カラー
(2013年、米=英) 91分/カラー
(1962年、日活) 110分/カラー
(1984年、東宝) 128分/カラー
(1966年、東宝) 92分/白黒
(1977年、伊=仏=西独) 116分/カラー
(1956年、英) 119分/カラー
(1962年、米) 176分/カラー
(1925年、ソ連) 75分/白黒・無声
(1976年、伊=仏=西独) 303分/カラー
(1984年、英) 110分/カラー
(1957年、英) 163分/カラー
(1989年、英) 102分/カラー
(1987年、英) 110分/カラー
(1983年、シネベンチャー・プロ=大島渚プロ、他) 123分/カラー
(2006年、フジテレビ) 108分/カラー
(1959年、東宝) 104分/白黒
(1954年、新東宝) 82分/白黒
(1970~73年、日活) 合計593分/カラー
(1965~67年、ソ連) 424分/カラー
(1972年、英) 141分/カラー
(1983年、米) 合計450分/カラー
(1977年、米) 128分/カラー
(1998年、ブラジル) 110分/カラー
(1989年、松竹) 123分/カラー
(1964年、松竹) 94分/カラー
(1989年、松竹) 103分/カラー
(1964年、米=ギリシャ) 142分/白黒
(2015年、米) 101分/カラー
(1970年、米) 115分/カラー
(1981年、テレビ東京) 合計585分/カラー
(2013年、米=英) 134分/カラー
(1997年、NHK) 合計270分/カラー
(2011年、英=米) 113分/カラー
(1959年、近代映画協会=新世紀映画) 115分/白黒
(1949年、英) 120分/白黒
(1965年、米) 121分/カラー
(1953年、米) 98分/白黒
(2001年、米) 114分/カラー
(2012年、米=英) 99分/カラー
(2010年、米=英) 106分/カラー
(1995年、英=独=スペイン) 110分/カラー
(1982年、東映) 181分/カラー
(1993年、伊丹フィルムズ) 116分/カラー
(1965年、東宝) 95分/白黒
(1960年、米) 116分/白黒
(1951年、米) 98分/カラー
(1960年、新東宝) 90分/白黒
(1960年、東宝) 118分/カラー
(1963年、東宝) 101分/カラー
(1953年、東宝) 119分/白黒
大魔神 (1966年、大映) 84分/カラー
(1953年、米) 105分/カラー
(1960年、仏=伊) 119分/カラー
(1995年、英=仏=ベルギー) 112分/カラー
(1999年、カナダ=ハンガリー) 181分/カラー
(1987年、米) 152分/カラー
(1953年、米) 102分/白黒
(1999年、イラン) 90分/カラー
(2010~2015年、2019年、英) 合計3181分/カラー
(2008年、デンマーク=チェコ=独) 136分/カラー
(1942年、米) 127分/白黒
(2002年、松竹=日本テレビ=住友商事、他) 129分/カラー
(1987年、日本テレビ) 330分/カラー
(1939年、仏) 100分/白黒
(1993年、女子パウロ会) 25分/カラー
(1974年、米) 158分/カラー
(1964年、仏) 124分/カラー
(1992年、仏) 88分/カラー
(1990年、米) 178分/カラー
(1964年、米) 117分/カラー
(1982年、仏=ポーランド) 139分/カラー
(1962年、東映) 170分/カラー
(1970年、英) 140分/カラー
(2008年、スペイン=仏=米) 132分/カラー
(2008年、スペイン=仏=米) 133分/カラー
(1978年、仏) 120分/カラー
(2019年、米) 合計320分/カラー
(1959年、ソ連) 87分/白黒
(1957年、ポーランド) 97分/白黒
(1977年、近代映画協会=ジャン・ジャン) 125分/カラー
(1970年、米) 101分/カラー
(1970年、米) 112分/カラー
(1993年、米) 133分/カラー
(2002年、仏) 115分/カラー
(1969年、米) 156分/カラー
(1965年、東宝=三船プロ) 131分/白黒
(2004年、「血と骨」製作委員会) 144分/カラー
(1960年、東宝) 125分/カラー
(2002年、英=米) 97分/カラー
(2001年、フジテレビ) 143分/カラー
(2022年11月22日~2023年1月8日、NHK) 150分/カラー
(1981年、表現社=マコ・インターナショナル) 132分/カラー
(1983年、伊) 89分/カラー
(1975年、仏) 101分/カラー
(1989年、デンマーク) 88分/カラー
(1971年、英) 102分/カラー
(1939年、日活) 120分/白黒
(1957年、米) 135分/カラー
(1970年、ソ連) 208分/白黒
(1978年、米) 183分/カラー
(2015年、米) 105分/カラー
(1957年、大映) 86分/白黒
(1998年、米) 132分/カラー
(1981年、櫂の会) 115分/カラー
(1956年、伊) 115分/白黒
(1977年、英) 100分/カラー
(1975年、ソ連) 141分/カラー
(1984年、東映) 133分/カラー
(2008年、英=スペイン) 112分/カラー
(1991年、NHK) 45分/カラー
ドキュメンタリー(2007年、テレビ朝日) 234分/カラー
(1990年、「天と地と」委員会) 119分/カラー
(1980年、「天平の甍」製作委員会) 152分/カラー
(1996~98年、ピクニック) 合計505分/カラー・白黒
(1965年、東京オリンピック映画協会) 170分/カラー
(1957年、東宝) 61分/白黒
(1953年、松竹) 135分/白黒
(1991年、トーメン) 122分/カラー
(1961年、日活) 97分/カラー
(1980年、東映=シナノ企画) 150分/カラー
(2011年、米) 110分/カラー
(1999年、米) 107分/カラー
(1992年、東急グループ=テレビ朝日=松竹) 118分/カラー
(1977年、英=米) 175分/カラー
(1965年、東映) 143分/カラー
(1983年、NHK) 各話45分・合計2288分/カラー
(1980年、東映) 139分/カラー
(2002年、NHK) 各話45分・合計2235分/カラー
(1991年、米) 123分/カラー
(1965年、米=伊) 201分/カラー
(2010年、仏=伊) 106分/カラー
(1974年、喜八プロ=ATG) 93分/カラー
(1957年、米) 88分/白黒
(1990年、NHK) 各話45分・合計2160分/カラー
(1980年、米) 98分/カラー
(1987年、イラン) 83分/カラー
(1989年、米) 99分/カラー
(1970年、米) 147分/カラー
(1974年、イラン) 72分/カラー
(2016年、米) 126分/カラー
(1988年、映画「敦煌」委員会) 143分/カラー
(1936年、仏) 95分/白黒
(1966~68年、TBS) 各話約50分/白黒
(1963年、米) 120分/カラー
(1954年、米) 131分/カラー
(1950年、松竹) 94分/白黒
(2000年、東映=「長崎ぶらぶら節」製作委員会) 115分/カラー
(2001年、NHK) 70分/カラー
(1959年、米) 107分/カラー
(1961年、米) 144分/カラー
(1959年、仏) 123分/カラー
(2014年、仏) 101分/カラー
(1961年、東京映画) 112分/白黒
(1983年、東映=今村プロ) 130分/カラー
(1948年、英) 110分/カラー
(1945年、米) 92分/白黒
(1959年、日活) 101分/白黒
(2011年、ハンガリー=仏=スイス=独) 154分/カラー
(1989年、フィーチャーフィルムエンタープライズ) 114分/カラー
(1959年、全国農村映画協会) 144分/白黒
(1954年、松竹) 162分/白黒
(2006年、フジテレビ) 107分/カラー
(2009年、米=カナダ) 158分/カラー
(2011年、角川映画) 134分/カラー
(1979年、永田プロ) 141分/カラー
(1964年、東宝) 93分/カラー
(1965年、東宝) 95分/カラー
(1980年、東映) 181分/カラー
(1969年、東宝) 128分/カラー
(1983年、東映) 131分/カラー
(1967年、東宝) 158分/白黒
(2000年、日活) 119分/カラー
日本の首領・やくざ戦争(1977年、東映) 132分/カラー
日本の首領・野望篇(1977年、東映) 141分/カラー
日本の首領・完結篇(1978年、東映) 131分/カラー
(2005年、日本テレビ) 106分/カラー
(1971年、東映) 99分/カラー
(1954年、新東宝) 102分/白黒
(1989年、伊) 124分/カラー
(1955年、新東宝) 106分/白黒
(1956年、日活) 84分/白黒
(1978年、「人間の骨」映画プロダクション) 104分/カラー
(2014年、米)138分/カラー
(1994年、仏=英=独=ルーマニア) 120分/カラー
(1992年、NHK) 各話45分・合計2205分/カラー
(2004年、米) 89分/カラー
(2000年、米) 124分/カラー
(2001年、米) 183分/カラー
(2016年、露) 137分/カラー
(1958年、ポーランド) 104分/白黒
(2018年、米) 107分/カラー
(1989年、伊) 86分/カラー
(1959年、西独) 86分/カラー
(2015年、米) 122分/カラー
(1970年、中村プロ) 121分/カラー
(1951年、大映) 114分/白黒
(2003年、映画HAZAN製作委員会) 108分/カラー
(1998年、仏) 92分/白黒
(1987年、英) 103分/カラー
(1961年、米) 135分/白黒
(1987年、東急グループ=三井物産=松竹) 107分/カラー
(1956年、米) 169分/カラー
(1992年、米) 111分/カラー
(2000年、中国=米) 89分/カラー
(1977年、橋本プロ=東宝=シナノ企画) 171分/カラー
(2004年、米) 127分/カラー
(1969年、米) 171分/カラー
(1985年、米) 146分/カラー
(2000年、米) 165分/カラー
(2013年、仏=独) 121分/カラー
(1967年、大映) 100分/白黒
(2005年、NHK) 合計260分/カラー
(1973年、松竹) 165分/カラー
(1970年、日活) 95分/カラー
(1988年、東映) 139分/カラー
(1978年、近代映画協会) 80分/カラー
(1995年、NHK) 合計225分/カラー
構成:片島紀男/ドキュメンタリー(1988年、松竹=ビッグバン=キネマ東京) 75分/カラー
(1973年、仏=米) 151分/カラー
(2008年、米=仏=英) 101分/カラー
(2010年、「はやぶさ」大型映像製作委員会) 64分/カラー
(2001~2011年、英=米) 合計1180分/カラー
(1975年、米) 185分/カラー
(1958年、松竹) 116分/白黒
(1981年、英) 112分/カラー
(1966年、仏=米) 173分/白黒
(2002年、NHK) 合計258分/カラー
(1980年、松竹=日本シネセル=アビプロ) 134分/カラー
(1965年、米) 156分/カラー
(2006年、「バルトの楽園」製作委員会) 134分/カラー
(1991年、アイスランド=独=ノルウェー) 85分/カラー
(2005年、「春の雪」製作委員会) 151分/カラー
(1977年、米) 127分/カラー
(1992年、英=日) 143分/カラー
(1942年、東宝) 115分/白黒
(1977年、ハンガリー) 110分/カラー
(1954年、新東宝) 115分/白黒
(2001年、テレビ朝日) 217分/カラー
(1958年、松竹) 118分/カラー
(2014年、東宝) 129分/カラー
(1960年、米) 98分/白黒
(1969年、フジテレビ=勝プロ) 140分/カラー
(1977年、西独) 155分/白黒(パートカラー)
(2004年、独) 155分/カラー
(2006年、独=オーストリア) 96分/カラー
(1978年、東宝) 137分/カラー
(1993年、米) 134分/カラー
(1980年、シネマハウト=ATG) 126分/カラー
(1999年、米) 127分/カラー
(1970年、伊) 107分/カラー
(1986年、日本テレビ) 288分/カラー
(1974年、JMP) 120分/カラー
(1973年、米) 106分/カラー
(1956年、日活) 116分/白黒
(1973~74年、THAMESテレビ、他) 合計1317分/カラー・白黒
(1975年、米) 126分/カラー
(2018年、米) 141分/カラー
(1983年、米) 96分/カラー
(2016年、米) 112分/カラー
(1959年、東映) 95分/カラー
(1969年、東宝=三船プロ) 166分/カラー
(1997年、英) 98分/カラー
(2005年、ハンガリー=独=英=イスラエル) 140分/カラー
(1999年、独=米=仏=キューバ) 105分/カラー
(1984年、仏) 182分/カラー
(1995年、「深い河」製作委員会=仕事) 134分/カラー
(1958年、米) 93分/白黒
(2007年、スペイン=独=伊) 122分/カラー
(1979年、松竹=今村プロ) 140分/カラー
(1961年、ソ連) 161分/白黒
(2016年、米) 107分/カラー
(1980年、東宝) 156分/カラー
(2006年、ルートピクチャーズ) 119分/カラー
(1994年、米) 120分/カラー
(1976年、芸苑社) 181分/カラー
(2014年、米=英) 135分/カラー
(1962年、仏) 102分/白黒
(1998年、東京映像制作=東映) 161分/カラー
(1991年、米) 130分/カラー
(1998年、米) 169分/カラー
(2004年、韓国) 148分/カラー
(1986年、米) 119分/カラー
(1987年、仏) 108分/カラー
(1988年、米) 96分/カラー
(1978年、東宝) 133分/カラー
(1966年、米) 154分/カラー
(1983年、こぶしプロ) 106分/カラー
(1945年、米) 129分/白黒
(1971年、西独) 102分/白黒
(1987年、米) 117分/カラー
(1984年、米) 112分/カラー
(1995年、米) 178分/カラー
(1990年、仏) 111分/カラー
(1991年、仏) 99分/カラー
(1993年、米) 121分/カラー
(1973年、米) 102分/白黒
(1963年、米) 150分/カラー
(1971年、伊=仏) 130分/カラー
(2021年 アイルランド・英) 98分/モノクロ(一部カラー)
(2020年、ドイツ=オランダ=カナダ) 183分/カラー
(1987年、デンマーク=スウェーデン) 151分/カラー
(1995年、米) 110分/カラー
(2007年、NHK) 108分/カラー
(1966年、米) 180分/カラー
(2005年、NHK) 89分/カラー
(2005年、米) 105分/カラー
(1959年、米) 137分/カラー
(2010年、米:Pioneer Productions) 44分/カラー
(1972年、米) 117分/カラー
(1999年、「鉄道員(ぽっぽや)」製作委員会) 112分/カラー
(2002年、テレビ朝日) 119分/カラー
(1981年、英) 119分/カラー
(1989年、西友) 107分/カラー
(2000年、松竹) 105分/カラー
監督・原作:山城新伍/音楽:坂田晃一(2014年、米=加=独) 105分/カラー
(1993年、大映=電通=黒澤プロ) 134分/カラー
(1971年、英) 100分/カラー
(1996年、米) 132分/カラー
(2017年、ブラジル) 117分/カラー
(1989年、ヘラルド・エース=テレビ朝日、他) 123分/カラー
(2015年、米) 95分/カラー
(2018年、英=米) 120分/カラー
(1971年、米) 140分/カラー
(2012年、NHK) 合計365分/カラー
(2003年、伊=英) 116分/カラー
(2001年、米) 153分/カラー
(2019年、映画「マスカレード・ホテル」製作委員会) 133分/カラー
(2014~2015年、英:BBC) 合計1060分/カラー
(2003年、米) 139分/カラー
(1981年、青銅プロ) 104分/カラー
(1977年、米) 129分/カラー
(1999~2003年、米) 合計403分/カラー
(2021年、米) 合計148分/カラー
(2019年、インド) 148分/カラー
(1952年、米) 84分/白黒
(2016年、独=仏=ベルギー) 118分/カラー
(2000年、伊=米) 92分/カラー
(2022年12月29日、30日NHK二夜連続ドラマ) 150分/カラー
(1933年、独=オーストリア) 89分/白黒
(1982年、「未完の対局」製作委員会=東光徳間) 133分/カラー
(2015年、英=米) 104分/カラー
(1954年、伊) 107分/白黒
(1990年、米) 102分/カラー
(1986年、英) 126分/カラー
(1976年、米) 131分/カラー
(1942年、米) 134分/白黒
テレビ版(2002年、テレビ東京) 合計498分/カラー
劇場版(2003年、松竹=テレビ東京=テレビ大阪=電通、他) 137分/カラー
(2000年、英=仏) 97分/カラー
(2005年、米) 163分/カラー
(1990年、伊=仏) 127分/カラー
(1994年、仏=ベルギー=独) 94分/カラー
(1958年、東宝) 105分/カラー
(2004年、TBS) 94分/カラー
(2004年、「村の写真集」製作委員会) 111分/カラー
(2001年、東京映像制作) 122分/カラー
(1957年、新東宝) 114分/カラー
(1958年、新東宝) 121分/カラー
(1959年、新東宝) 104分/カラー
(1989~2013年、英) 短編50分・長編100分/カラー
(2000年、英=カナダ) 121分/カラー
(1958年、米) 128分/カラー
(1964年、米) 139分/カラー
(1990年、米) 107分/カラー
(1966年、松竹) 91分/白黒
(1970年、東映=テレビ朝日) 合計1300分/カラー
(2004年、英=米) 126分/カラー
(1998年、仏) 394分/カラー
(2013年、NHK) 各話44分・合計2246分/カラー
(1978年、東映) 130分/カラー
(1974~77年、三船プロ=東映) 各47分/カラー
(1964年、日活) 95分/カラー
(1973年、東映) 102分/カラー
(1974年、東映) 96分/カラー
(1985年、キネマ東京=ザ・ワールド企画、他) 101分/カラー
(1963年、伊) 162分/カラー
(1999年、中国) 93分/カラー
(1969年、米) 128分/カラー
(1975年、米) 107分/カラー
(1966年、三島由紀夫) 28分/白黒
(2000年、米) 116分/カラー
(1965年、伊=スペイン) 127分/カラー
監督・原作:セルジオ・レオーネ/音楽:エンニオ・モリコーネ(1967年、日活) 91分/カラー
(1981年、西独) 135分/カラー
(1991年、米) 115分/カラー
(1992年、米) 131分/カラー
(1941年、米) 129分/白黒
(1991年、伊=仏=ベルギー) 89分/カラー
(2005年、NHK) 各話44分・合計2209分/カラー
(1987年、米) 72分/カラー
(1957年、松竹) 160分/カラー
(1986年、松竹=東京放送=博報堂) 130分/カラー
(1944年、東宝) 95分/白黒
(2003年、米) 109分/カラー
(1992年、米) 112分/カラー
(1976年、米) 99分/カラー
(1996年、米) 101分/カラー
(1987年、伊) 127分/カラー
(1999年、米) 116分/カラー
(1974年、襤褸の旗製作委員会) 112分/白黒
(2009年、NHK) 87分/カラー
(1950年、米) 105分/白黒
(1989年、勅使河原プロ=伊藤忠商事=博報堂=松竹) 135分/カラー
(2013年、東映) 123分/カラー
陸軍中野学校(1966年、大映) 96分/白黒
雲一号指令(1966年、大映) 81分/白黒
竜三号指令(1967年、大映) 88分/白黒
密命(1967年、大映) 88分/白黒
開戦前夜(1968年、大映) 89分/白黒
(1973年、仏=伊) 103分/カラー
(1996年、米) 109分/カラー
(1988年、ブルガリア) 164分/カラー
(1982年、テレビ東京) 合計590分/カラー
(1987年、アルマンス企画) 109分/カラー
(2016年、仏) 115分/カラー
(1977年、米) 合計570分/カラー
(1972年、伊=西独=仏) 240分/カラー
(1975年、仏) 109分/カラー
(2003年、テレビ朝日) 261分/カラー
(2004年、米) 152分/カラー
(2015年、米) 156分/カラー
(1972年、伊=仏=スペイン) 合計225分/カラー
(1996年、米) 133分/カラー
(2007年、米) 108分/カラー
(1994年、米) 132分/カラー
(1990年、米) 135分/カラー
(1993年、独=ベルギー) 188分/カラー
(1969年、米) 117分/カラー
(1957年、仏=伊) 186分/カラー
(2019年、仏) 104分/カラー
(1981年、東宝) 145分/カラー
(1968年、東宝) 131分/カラー
(1977年、オランダ) 110分/カラー
(1999年、スペイン) 98分/カラー
(2008年、テレビ朝日) 106分/カラー
(2010年、米=英) 156分/カラー
(1995年、米) 139分/カラー
(1997年、スペイン=米) 114分/カラー
(1992年、米) 135分/カラー
(1970年、伊=ソ連) 127分/カラー
(1994年、米) 191分/カラー
(1972年、米) 103分/カラー
(1993年、東映=日本テレビ) 125分/カラー
(1966年、米=英) 118分/カラー
(1990年、米) 127分/カラー
(1941年、米) 118分/白黒
(1960年、スウェーデン) 117分/白黒
(2019年、トルコ)/126分/カラー
(2012年、松竹) 118分/カラー
(1972年、ソ連) 168分/カラー
(1992年、ポーランド=英=独=仏) 110分/カラー
(1976年、英=米) 131分/カラー
(1959年、東宝) 113分/白黒
(2010年、英)/104分/カラー
(2011年、米)110分/カラー
(2003年、フジテレビ) 95分/カラー
演出:林宏樹/音楽:本多俊之(1988年、仏=米) 112分/カラー
(2003年、NHK) 75分/カラー
(1950年、大映) 106分/白黒
(2002年、米) 138分/カラー