

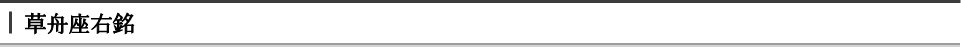
執行草舟が愛する偉人たちの言葉を「草舟座右銘」とし、一つひとつの言葉との出会い、想い、情緒を、書き下ろします。いままで著作のなかで触れた言葉もありますが、改めて各偉人に対して感じることや、その言葉をどのように精神的支柱としてきたか、草舟が定期的にみなさまへご紹介します。ウェブサイトで初めて公開する座右銘も登場します。
海と私、ほかには誰ひとりいない。―― そんな気がする。
チェーホフの演劇が湛える哀愁を、私はずっと愛し続けて来た。その劇には、「巨大な孤独」とも呼ぶべきものが横たわっているのだ。ロシア的な、ゆったりとした寂しさとでも言ったらいいだろう。その高く悲しい高貴性が、劇中に展開される下世話なものを昇華していた。巨大な孤独性が、その文学を貫く生命的リアリズムを際立たせているに違いない。チェーホフの生命は、日常と非日常を同時に呑み込んでしまう。その神秘がもつ孤高の激しさに、私は打たれ続けた。
チェーホフは「何ものか」と対峙し続けていたのだろう。多分、それは人間の生命がもつ暗黒のような深淵だったのではないだろうか。私はそう考えていた。そしてその『手帖』を読んでいたとき、この言葉に出会ったのである。私は、長年考え続けていたチェーホフの神秘を垣間見たように感じたのだ。生命の神秘と、唯一人で対面する男の姿がそこにはあった。この断章の中に、チェーホフの魂の淵源を私は見出したのだ。真の孤独を表わす、歴史的な恩寵がここにはある。
私は孤独の中を生き抜いて来た。私の武士道が、それを命じていたのだ。人間の魂がもつ宇宙的使命のことだけを考えていた。だから、神と自己の関係性を重んじていたと思っている。マルチン・ブーバーの言う「我と汝」こそが、私の人生そのものだった。そこに、このチェーホフの大思想が付け加わったのだ。それは激しく生命的な孤独だった。広く深い孤独と、熱く柔らかい孤独を私にもたらしてくれたのだ。ユーラシアの荒涼が、私の魂の奥深くへ固着していくのを感じていた。
2022年2月12日
